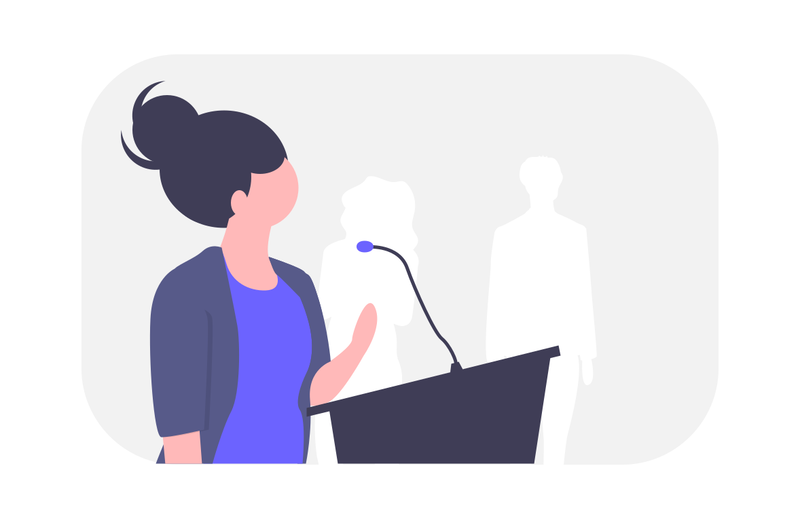
山口慎太郎ゼミ
経済学部ゼミ
労働経済
教育経済
計量経済学
労働経済学、教育経済学などについて、計量経済学の見地も踏まえて扱う。
目次
基本情報
| 執行代 | 新歓活動は原則3年が行う。ゼミ長を中心に、先生と意見交流をしながら学生主体で運営される。 |
|---|---|
| 人数 | 各学年10〜15人 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 卒業論文 | あり |
| ゼミ論 | なし |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
16単位 |
| 公式X | |
| 公式メアド |
sy.semi.ut[a]gmail.com
([a]を@にしてメールを送信してください) |
概要
〈内容〉
実証ミクロ経済学。データ分析の手法を学び、実社会のデータに応用することで社会問題の理解と解決を目指す。主な応用分野は「教育」「子育て」「労働」等の政策評価や市場分析などであるが、特に限定はしない。
〈授業計画〉
Sセメスターでは例年学術論文の紹介とディスカッションを行っている。特定のテーマに沿ってトップジャーナルから英語論文を数本選び、その内容について紹介する。経済学研究が何をどこまで明らかにしたのか理解し、その知見を日本社会における問題解決に応用することを目指す。昨年度は、「アメリカにおける教育政策の効果」や「女性の社会進出と離婚率の関係」、「試験における男女のパフォーマンス差」などを扱った。
今年度は因果推論に関する教科書の輪読を行う予定。因果推論の手法や理論だけではなく、それが労働経済学や教育経済学でどのような研究に用いられているのかを学ぶことができる。
Aセメスターでは自分たちでテーマを設定し、実社会のデータを用いて記述的分析や政策評価などの実証分析を行う。昨年度は、「雇用形態が結婚行動に与える影響」「男性による家事育児を促進する施策」などのテーマに取り組んだ。
毎回のゼミでグループ発表を行う。発表に対しては、他のゼミ生や教員から質問・コメントを頂き、それに対して回答し議論を行うことで、問題への理解を深めることを目指す。グループは3-4人で構成され、3年生も4年生も交えたものとなるのが通常。準備などを通じて、学年を超えた交流が可能。
〈テキストについて(参考資料)〉
山口先生から指示された計量経済学に関連するもの。
昨年度は 西山・新谷・川口・奥井『計量経済学』(有斐閣)
〈サブゼミについて〉
昨年度は、計量経済学の道具として、統計ソフトRの基礎的な操作を学んだ。
※サブゼミ:ゼミの前後に行われる補習時間のこと。経済学部的にはプロアクティブラーニングセミナー(プロアク)とされる。サブゼミが、プロアクとゼミに認定された場合は単位が認められ、そうではなければ認められない。事前に特定のメンバーが監督者(4年生または院生)となり、受講者の名前・学生証番号も全て登録しておく。
〈山口慎太郎先生について〉
労働経済学、教育経済学、家族の経済学等にご関心をお持ちの先生。
東京大学経済学研究科教授。内閣府・男女共同参画会議議員、朝日新聞論壇委員、日本経済新聞コラムニストなども務める。1999年慶應義塾大学商学部卒業。2001年同大学大学院商学研究科修士課程修了。2006年アメリカ・ウィスコンシン大学経済学博士号(Ph.D.)取得。カナダ・マクマスター大学助教授、准教授、東京大学准教授を経て2019年より現職。専門は労働市場を分析する「労働経済学」と結婚・出産・子育てなどを経済学的手法で研究する「家族の経済学」。『「家族の幸せ」の経済学』(光文社新書)で第41回サントリー学芸賞を受賞し、ダイヤモンド社 ベスト経済書に選出。『子育て支援の経済学』(日本評論社)は第64回 日経・経済図書文化賞受賞。(公式ページから引用)
Twitterでも多彩な情報発信をなさっている。
〈他ゼミ比較〉
ダブゼミしているゼミ生は例年それほど多くはない。兼ゼミ先は松井(ミクロ理論)、渡辺努(マクロ)、林(財政)、山本(経済史)など様々で、一貫した傾向はない。
メンバー構成
- 人数:3年生11名、4年生16名。女子学生率は全体で4割程度。男女比率の調整等は行われない。
- 属性:原則、経済学部の3・4年生。運動会からノンサーまで様々。他学部や1・2年生で参加したい方は、山口先生に直接コンタクトを。
- 性格:労働経済や教育経済、政策評価を扱うため、社会科学的な関心が高いメンバーが多い。比較的真面目でほんわかした人が多い印象。
- 就職先:かつてはコンサルやシンクタンクなどが多かったが、近年は多様化している。院進は毎年2~3名程度。
活動頻度
火曜4限※延長は一切なし
Sセメでは連続して5限にサブゼミを行った。今年度も開講予定だが、開講時限はゼミ生で話し合って決める予定。
募集
3年・4年いずれも募集している。
選考の際はエントリーシートを提出する。
内容は
・氏名や学部などの基本情報
・簡単な自己紹介
・いま興味を持っている社会・経済現象
・将来のキャリアプラン
・参加希望の理由
・その他伝えたいこと、アピールしたいこと(自由に)
「いま興味を持っている社会・経済現象」という課題が課されるが、そこまで仰々しいものではない。あくまで自分の学問的な興味について軽く述べる程度。
年間予定
両セメスター通じて火曜4限に開講。
長期休み中のゼミ活動は原則なし。
内部のホンネ
○魅力
・山口先生のちょっとした愚痴が聞けたりする。
・朗らかな雰囲気
・ゼミ中は真面目な雰囲気。扱う論文やその背景知識についての十分な理解やゼミ内の発表に向けた入念な準備などには抜け目なく取り組む学生が多い。また山口先生もそういった学生を求めているとのこと。
・発表や出席などは全て学生主体で、学生どうしで忙しさを調整し合うことができるので、就活や部活などの融通も利く。
・授業の延長は一切なし。
△大変なところ
・輪読で扱う教科書のレベルは山口先生が「これ一冊で大学院の基礎レベルをカバーできる」とおっしゃっていた。計量経済学における基礎的な数学のチカラは必要。
(駒場の統計Ⅰ・統計Ⅱのレベルで十分)
・2024年度入ゼミ生からは、卒論執筆が課される。
新歓日程詳細
経友会主催ゼミ説明会を基本とする。
個別に質疑等があればTwitterのDMもしくは質問箱へ。
Twitter https://twitter.com/sy_semi
質問箱 https://peing.net/ja/sy_semi
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
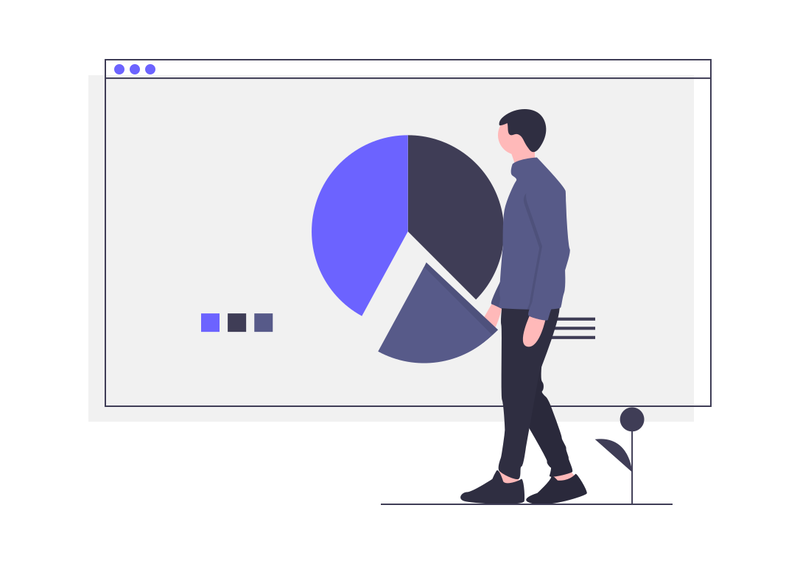
新井ゼミ
コーポレートファイナンス・バリュエーションを学ぶ経済学部の自主ゼミ。
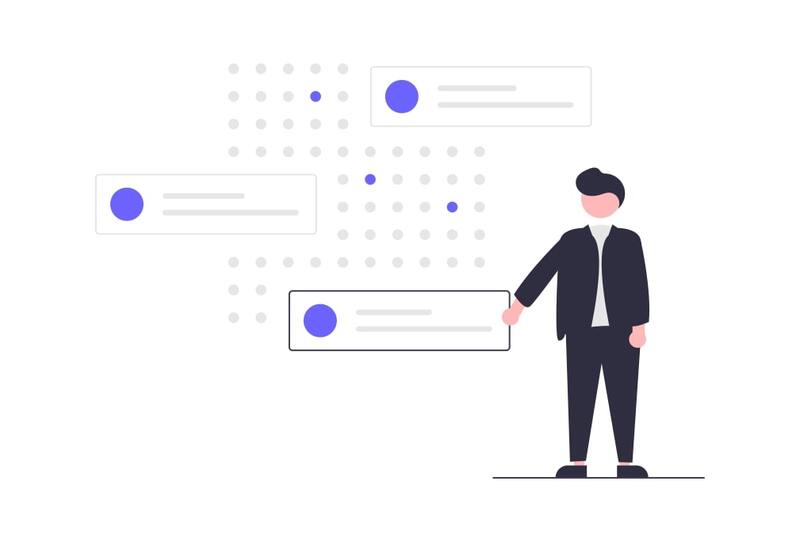
大木ゼミ
国際経営を学ぶ経済学部のゼミ。

大橋ゼミ
産業組織論(応用ミクロ)を学ぶ経済学部のゼミ。

伊藤元重ゼミ
国際経済/経済政策などの時事経済を扱う経済学部の自主ゼミ。




