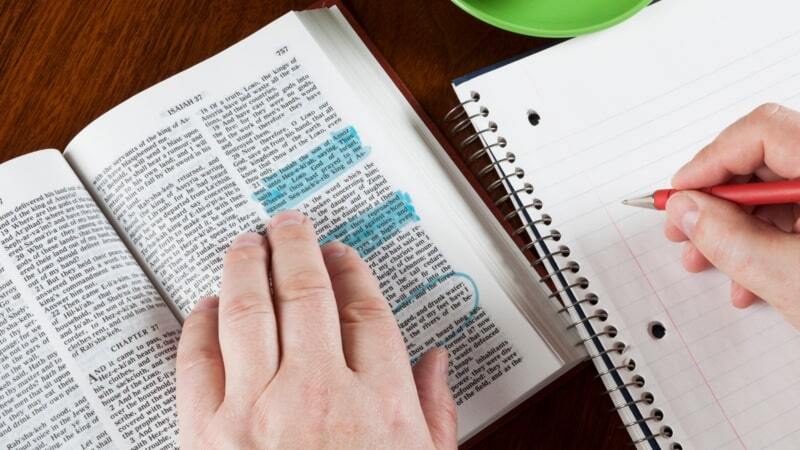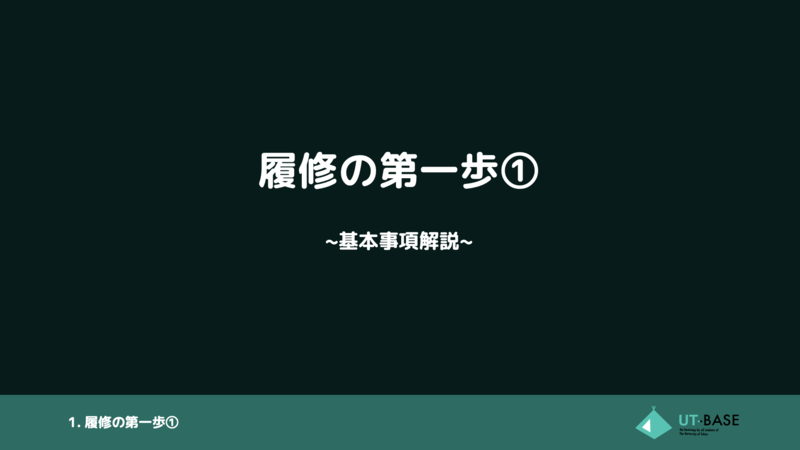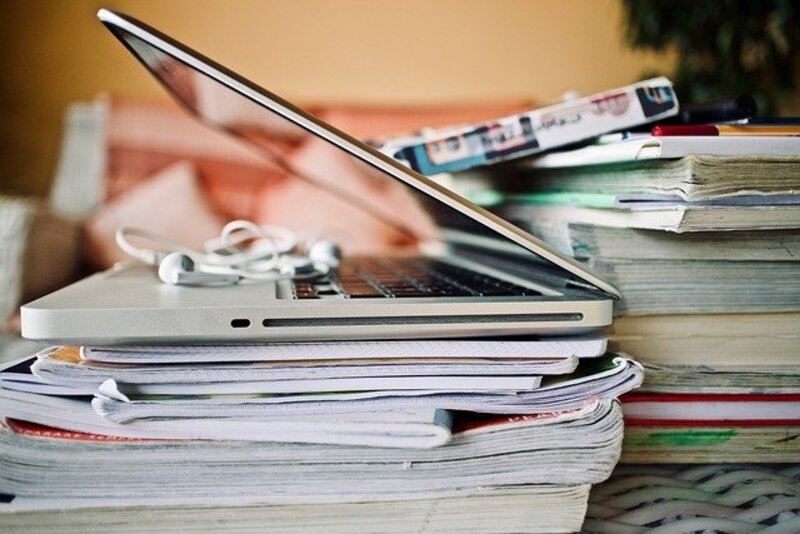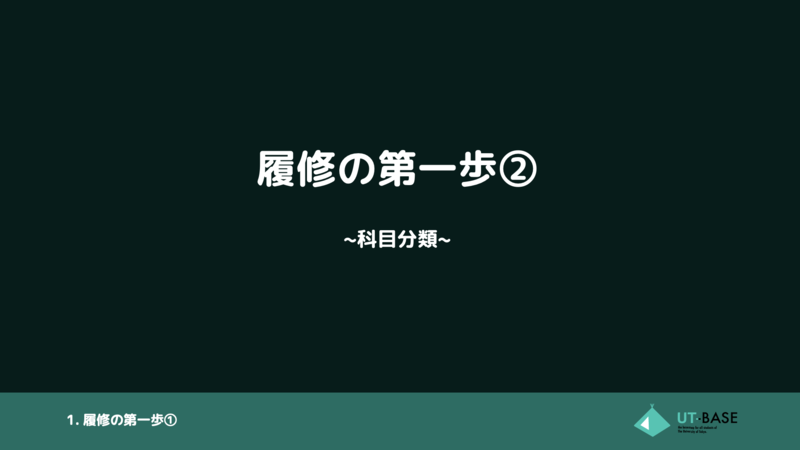目次
前回で1Sの履修を組み終えました。
しかし、前期課程の終わりには「進学選択」が存在します。そのため、進学選択がどのような仕組みになっているのかを理解し、1Sでどのような履修を組むべきか逆算する必要があります。
そこで、今回は、前期課程から後期課程に進学するための2つのチェックポイント、そして進学選択で用いる点数の計算方法について解説します。
第1節 前回までの復習
まずは、今まで何回も登場したこれらのキーワードを改めて確認しておきましょう。
《🔑キーワード》----------------------------
前期課程:東大で過ごすうち、前半2年間の課程。1,2年生全員が教養学部に所属して、教養教育を受ける。
後期課程:東大で過ごすうち、後半2年間の課程。各学科に分かれ、専門教育を受ける。
進学:前期課程で必要な単位を揃えて、後期課程に進むこと。
進学選択:各自が進みたい後期課程の学部・学科を決め、2Sまでの成績(平均点)に応じて志望先へ進学を決定すること。進振り。
内定:進学選択の結果、翌年度から各学部学科に所属する権利を獲得すること。2A末時点で、前期課程を修了する条件等を全て満たせば、自動的に翌年から内定を得ている進学先に進学できる。なお、文科生が一部の理系学部への進学(理転)を希望する際に最低限必要となる知識を補うための科目である「要求科目」は、通常の「進学選択が可能となる条件」に加えて満たさなければならないものである。
------------------------------------
これを見て、鋭い方は次の点にお気づきになったかもしれません。
「進学選択は2Sまでの成績で行なわれるのに、実際の進学の判定は2Aまでの成績で行なう。なぜかこれらはタイミングがずれている」「2Aは何をするのだろうか」
この問題は、前回保留をしてしまったものでもあります。
このタイミングのずれについての疑問を解消するのが、第2節の目的です。
(ちなみに:「鋭い方は」のような表現を、大学では何回も目にするでしょう。大丈夫です。ほとんどの人は気付きません。気付かない方が普通です。)
第2節 2つのチェックポイントの意味と内容
ここからの説明は、前回も登場した以下の図を見ながらお読みください。
(0)1S→1A→2S
入学後、2年生Sセメスター(2S)までは、休学等しない限りは誰しもが進むことができます。1年生から2年生に進級する際の条件もありません。
よって、2Sまでは自由に過ごすことができますが、あまりゆっくりしてはいられません。次をご覧ください。
(1)2S→2A
2Sから2Aに進む段階で、初めてチェックポイントが登場します。詳しく見ていきましょう。
2S末の成績で進学選択が実施されるのは、これまで何度も言及してきました。
しかし、誰もが無条件に進学選択に参加できるわけではありません。
極端な例を考えてみましょう。2単位(1科目)しか取ってないが、これが100点で、「自分の成績の平均点は100点です!」という人が居たとします。進学選択は平均点での勝負なので、この人は進学選択で最強です。これでは、律儀に単位を集めてきた学生にとっては迷惑
な話です。
よって、進学選択に参加するにも、その前提となる条件がいくつか設けられています。これを、「進学選択が可能となる条件」(『履修の手引き』8頁)といいます。
では、この条件を満たせば、自動的に2Aに進めるのでしょうか。
答えはNoです。
実は、もう一つ条件があります。
それは、「内定を得ること」です。逆に言えば、内定がない状態では2Aに進むことができません。
進学選択が可能となる条件を満たさなかった場合、または進学選択に参加できても内定を得られなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、2Aに進む代わりに1Aに逆戻りします。
つまり、1S→1A→2S→1A→2S…と時が進んでいくということです。
このように、2Sから1Aに進むことを、「降年」といいます。
(進学選択で使用する「2S末の成績」が実際のところどのように決まるのかは、後で説明します。)
では、以下に、各科類の進学選択が可能となる条件を示します。ただし、細かい条件は省きます。詳細は、『履修の手引き』8頁をご参照ください。
【全員共通】
・英語:「一列①」「一列②」「二列W(ALESA,ALESS)」「二列S(FLOW)」の平均点が40点以上
・二外:「一列①」「一列②」「二列」の平均点が40点以上
・初ゼミ:単位取得済であること
【文系】
・社会科学:4単位以上取得済(文一・二)、2単位以上取得済(文三)
・人文科学:2単位以上取得済(全員共通)
・総合科目:11単位以上取得済(文一・二)、13単位以上取得済(文三)
・総取得単位数:46単位以上(全員共通)
【理系】
・基礎実験:3単位の取得(全員共通)
・数理科学:6単位の取得(理一)、5単位の取得(理二・三)
・物質科学:「力学」「熱力学」「物性化学」の単位取得(理一)、「力学」「化学熱力学」「物性化学」の単位取得(理二・三)
・生命科学:「生命科学」の単位取得(理一)、「生命科学Ⅰ」の単位取得(理二・三)
・総合科目:8単位以上取得済(全員共通)
・総取得単位数:53単位以上(全員共通)
《🔑キーワード》----------------------------
進学選択が可能となる条件:この条件を満たさなければ、進学選択に参加すらできず、自動的に降年となる。
降年:2Sの次に2Aではなく1Aに進むこと。進学選択が可能となる条件を満たせなかった、進学選択に参加しても内定できなかった、進学選択への参加を辞退したなどの理由で、2A開始前に内定を持っていない場合に発生する。
------------------------------------
(2)2A→3S
いよいよ、前期課程を修了する時です。2Aの段階では内定を持っているだけで、あくまでも前期課程に所属する学生という扱いでした。所属学部が変わるのは、2Aが終わり3Sになるタイミングです。
後期課程に進学するにも条件を満たす必要があります。このチェックポイントで立ちはだかる要件は、「前期課程修了要件」(『履修の手引き』頁)です。
前期課程で身につけるべき知識や技能をきちんと身につけたかが、必要な単位を取得したかにより判定されます。
具体的にどのような要件が設けられているのかは、第4章で詳しく解説しましたので、そちらをご参照ください。
前期課程修了要件を満たさなかった場合は「留年」になります。つまり、3Sに進むことはできず、2Aの次は2Sに戻り、2年生をやり直すことになります。
なお、留年した場合、内定は取消となり、再度進学選択に参加することになります。
《🔑キーワード》----------------------------
前期課程修了要件:この条件を満たさなければ、後期課程に進学できず、留年となる。
留年:次の学年に進めず、同じ学年をもう一度繰り返すこと。
------------------------------------
(3)2つの条件の関係
これまでの説明を読んだ皆さんはきっと、「2Sまでに進学選択が可能となる条件を満たして、そのあと、2Aまでに前期課程修了要件を満たせばいいんだな!!」とお思いになることでしょう。しかし、残念ながらそれは間違いです。
2Sまでに「前期課程修了要件」を満たしてしまうのが通常です。なお、「進学選択が可能となる条件」は「前期課程修了要件」を満たせば、自動的に満たされるようになっています。
なぜ「前期課程修了要件」を2Aではなく2S末までに満たさなければならないのか、その理由は大きく2つあります。
1つ目は「2Aは後期課程の授業を受けなければならないから」
2つ目は「進学選択で用いる成績は前期課程修了要件をもとに計算されるから」
です。
次の(4)では1つ目の理由を詳しく見ていきましょう。
(4)2Aの過ごし方
2Aは、所属学部こそ前期教養学部ですが、内定を得た先の学部・学科が開講する授業を受けることが中心となります。
これらの前期課程の学生が履修可能な後期課程の科目は「持ち出し科目」と呼ばれます。
各学部・学科は、進学後の学びの基礎となる科目を持ち出し科目として開講しており、進学後の学修を円滑に進めるためにはこれらの科目の履修は必須です。実際、必修の持ち出し科目も多く開講されています。
2Aでは時間割の多くが持ち出し科目で埋まります。2Aの時点で「前期課程修了要件」を満たしていなければ、持ち出し科目に加えて前期課程の授業も履修しなければならず大変です。しかも、持ち出し科目と前期課程の授業の開講曜限が重なることもあります。その結果、必修の持ち出し科目が履修できない場合もあります。
このような事態を防ぎ、2Aは後期課程の持ち出し科目に集中するためにも、2S末時点で前期課程修了要件を満たしておくのが望ましいのです。自分の行きたい学部の持ち出し科目については、UT-BASEの学部学科紹介をご参照ください!
第3節 平均点の算出方法
前期課程修了要件は2S末までに満たす必要があります。その理由の2つ目が、この平均点の算出方法にあります。平均点の計算のやり方を順を追って説明しつつ、理由の2つ目を探ってみましょう。
(1)平均点計算の基本
第1章で、前期課程の成績は100点満点で計算されることを説明しました。進学選択ではこの点数が使われることになります。
進学選択で使用する成績は、簡単に言えば、履修した全科目の平均点です。ただし、気を付けてほしいのは、その平均点は履修した科目数ではなく履修した単位数を基準に考えるということです。
進学選択では、点数に単位数をかけた平均点を計算します。計算手順は、(ある科目の点数にその科目の単位数を掛けたものの総和)÷(単位数の総和)です。
【計算上の注意】
・点数が出ず、「合格」「不合格」だけで成績が表される科目(理系の初年次ゼミナールなど)は計算に含めません。
・逆に、点数が出る科目はすべて計算に含めます。50点未満(不可)の科目も含みます。
・上記計算は実はまだ正式な平均点ではありません。後程説明する「重率」というものを掛ける必要があります。
(2)必修、選択必修で取得していない単位がある場合
続いて、次のような事例を見ていきましょう。
科目a、b、c が全て必修だったとします。
また、科目X、科目Y、科目Z(各2単位)の中から4単位が選択必修だったとします。
そして、以下のような結果だったとします。
科目a 2単位:70点
科目b 2単位:60点
科目c 2単位:未履修
科目X 2単位:80点
科目Y 2単位:未履修
科目Z 2単位:未履修
このとき、平均点は以下のように計算します。
このように、必修で取得していない単位、選択必修の不足分は、0点として扱われ、平均点が計算されます。(「0点算入」と呼ばれています。)
(3)「基本平均点」と「重率」
これまでに平均点の求め方を説明してきましたが、実際の進学選択で使用される平均点は「基本平均点」(『履修の手引き』56ページ)と呼ばれていて、これまで説明してきた平均点に「重率」というものを掛け合わせる必要があります。
【重率とは】
平均点を計算するうえで、その科目をどの程度重視するかを表す指数です。重要度が普通なら重率は1、低い重要度なら0.1に設定されています。
例えば、必修の科目は重要なので重率1、それ以外の科目はそこまで重要ではないので重率0.1のようになります。
【基本平均点の計算方法】
進学選択で使用される基本平均点は、「(ある科目の点数×その科目の単位数×その科目の重率)÷(単位数×重率の総和)」で求められます。
重率はどのように決定されているのでしょうか?
前回、「必修」と説明した科目は全て重率1となります。また、「〇〇から〇単位」というように表記した選択必修も、点数が上位の科目から指定の単位数分だけ重率1となります。
そして、ここに含まれない科目は全て重率0.1です。
※一部科目はこれとは異なる重率が設定されている場合があります。詳しくは『履修の手引き』を熟読してください。
ここで、前期課程修了要件を2S末に満たしておくべき理由が明らかになります。
この重率1が適用される「必修」「選択必修」の範囲は、本来2A末時点で問題となる「前期課程修了要件」におけるものです。「進学選択が可能となる条件」はその一部にすぎません。
これらの科目に不足があれば、先ほどの「0点算入」が発生します。つまり、問答無用で重率1で0点が算入されるため、平均点を大きく引き下げる原因となってしまうのです。
(4)基本平均点の応用:「追い出し」
これまでは重率が1になる状況を説明してきました。次に、重率が0.1になる場面を見てみましょう。
仮に、あなたがとある科目で低い点数をとってしまったとします。もしそれが重率=重要度1で基本平均点に算入されてしまったら平均点が低くなってしまいます。とても悲しいですね。
そこで、重率=重要度を下げることはできないか?という考えになるのですが、その、重率を下げる操作のことを慣例的に「追い出し」と呼んでいます。
【追い出しとは】
選択必修として合計で〇単位必要な科目群Xにおいて、その科目群に含まれる科目を必要単位数より多く単位取得することで、成績順に並べたときに〇単位を超過する部分の重率を0.1にすること。
なお、追い出しは先ほどの図で説明すると次のような位置付けになります。
【追い出しの例】
簡単な例を用いて追い出しを含む平均点計算の練習をしましょう。
最初に追い出しを含まない確認問題を解いたのち、追い出しを含む練習問題を見ます。
各2単位の科目群d~fの中から4単位の選択必修だったとします。
現在の成績は、以下の通りです。
科目d 2単位:80点
科目e 2単位:50点
科目f 2単位:未履修
この時、科目群d~fの平均点を求めよ。
((点数単位数重率)の総和) / ((単位数*重率)の総和)
を計算します。
新たに科目fを履修し、次のような成績になったとします。
科目d 2単位:80点
科目e 2単位:50点
科目f 2単位:90点
この時、科目群d~fの平均点を求めよ。
科目群d~fは計4単位が選択必修=重率1なので、全部で6単位取得したときは、成績上位4単位が重率1になり、成績下位2単位が追い出されて重率0.1になります。
今、成績が一番低いのは「科目e」なので、この重率が0.1になります。
こうなると、平均点の計算は次のようになります。
最下位の科目が重率0.1に追い込まれたことで、追い出す前に比べて全体の平均点が上がりました。
このような作業を「追い出し」といいます。
以上のように、必修・選択必修の範囲内の科目に重率1、その他の科目に重率0.1をかけて計算した平均点を「基本平均点」と呼びます。
「基本」ということは、基本ではない平均点も存在します。学部ごとに重率が少し変わることもあるので、調べてみましょう!発展的内容となるので、ここでは省略します。
《🔑キーワード》----------------------------
重率:科目の重要度を表す指数。得点、単位数などに乗算して反映させる。
基本平均点:必修・選択必修の枠内か否かを考慮して、各科目に重率をかけて計算される平均点。
追い出し:ある選択必修の枠内において、追加的に科目を履修し、高得点を取ることで、点数の低い科目を重率0.1に落とすこと。低得点科目の平均点への影響が下がり、基本平均点が上昇する。
------------------------------------
第4節 最低限覚えておくべきこと
かなり込み入った話に触れてしまいました。混乱している方もいらっしゃるでしょう。
最低限、以下の四点だけ頭に入れておいていただければ十分です。
①進学選択では、2S→2A、2A→3Sという2つのチェックポイントが存在し、それぞれに「進学選択に参加する条件」と「前期課程修了要件」という異なる通過条件が設定されていること。
②「進学選択に参加する条件」は「前期課程修了要件」の一部であること。
③進学選択で用いる点数は「前期課程修了要件」に準拠して計算するため、「進学選択に参加する条件」を満たしていれば良い2S末の段階で「前期課程修了要件」も満たしておくのが望ましいこと。
④必修科目の成績は一律で重率1となり、平均点に大きな影響を与えること。
このように考えると、「進学選択に参加する条件」を単体として考える意義は薄く、もっぱら「前期課程修了要件」を満たすことを目標に履修を組めば十分ということになります。
さらに、必修科目は成績が即時確定し重率1となる一方、選択必修科目は成績が悪くても重率0.1に「追い出し」て平均点に占める比重を下げる余地があるため、成績のことを考えるならば必修科目に力を入れるべきであることも分かるでしょう。
ーーーー
結び
履修に関して、最低限誰もが1S開始前に理解しておくべきことは、ここまでです。
第1章から読んでくださった皆さまは、もう1Sの履修のことを心配する必要はありません。
ここで、改めて『履修の手引き』を開いてみましょう。
受け取った当初は何も理解できなかった冊子が、ここまでの説明を踏まえれば理解できるものになっているはずです。
今後、履修について疑問点が生じたときは、必ず「履修の手引き」を開いてみてください。答えは必ずその冊子の中にあります。
もちろん、自分で探してみても分からなかったことは、UT-BASEの質問箱までお寄せください。お待ちしています!
ここまで長きにわたりお読みいただき、ありがとうございました。
皆様が自分自身にとって最高の履修を組み、大学生活を充実させることを、心から応援しています!