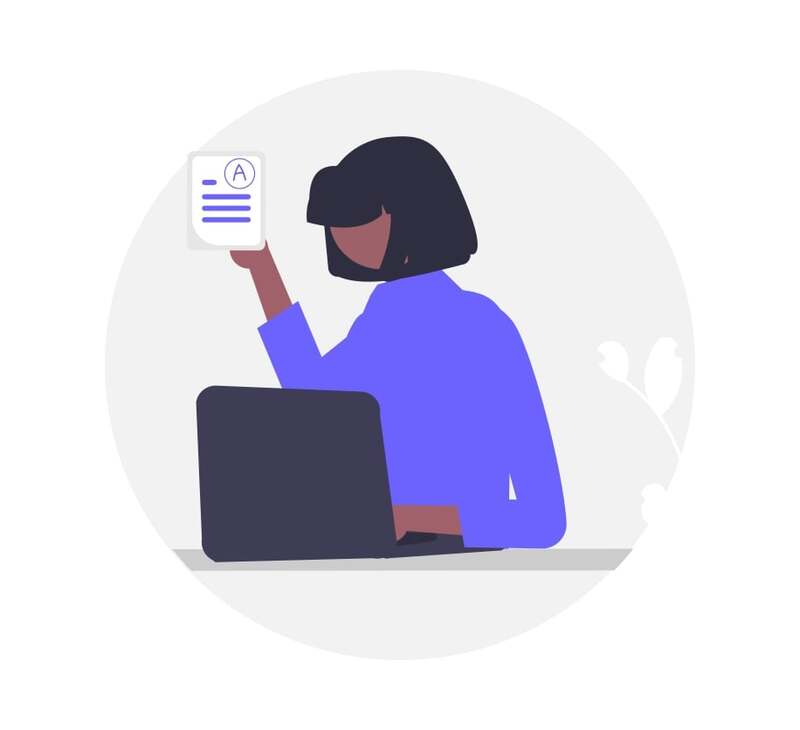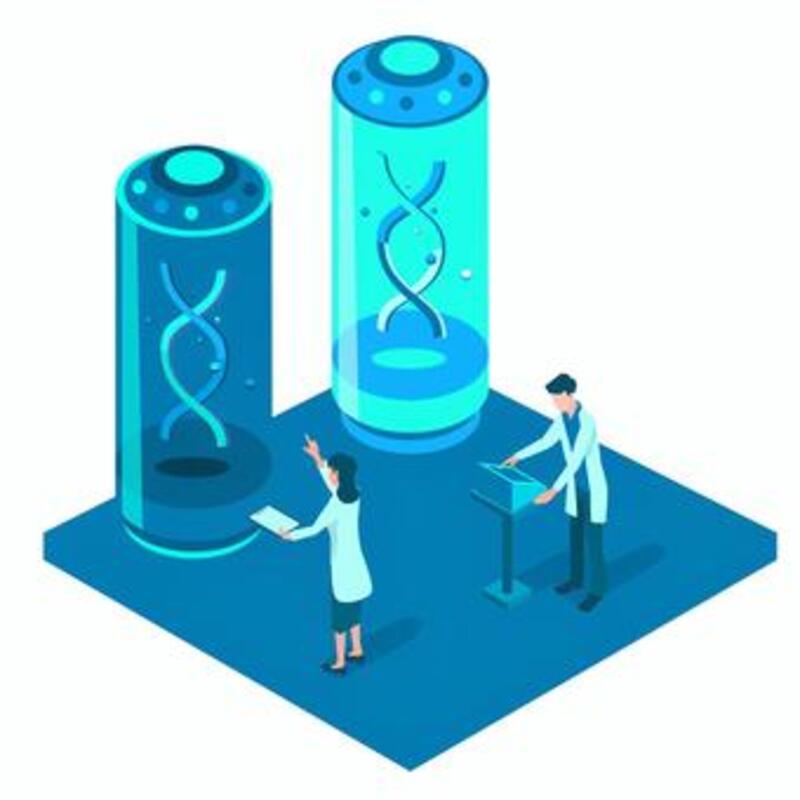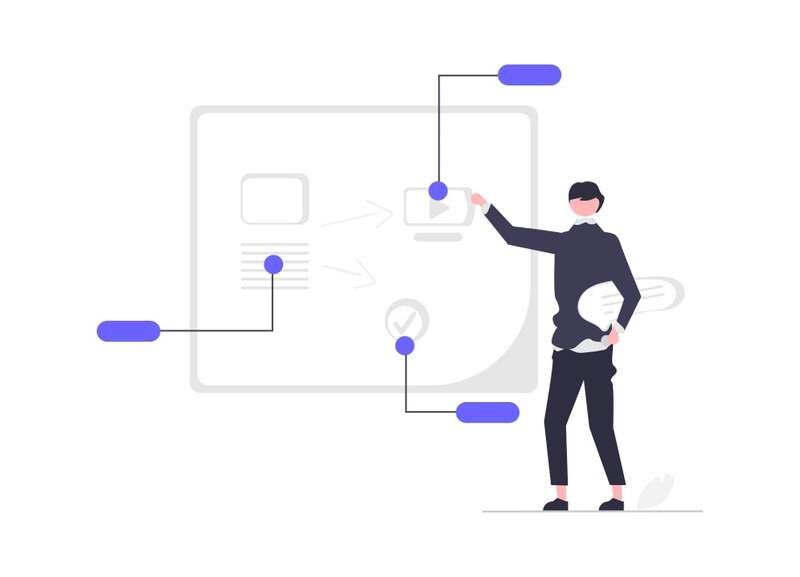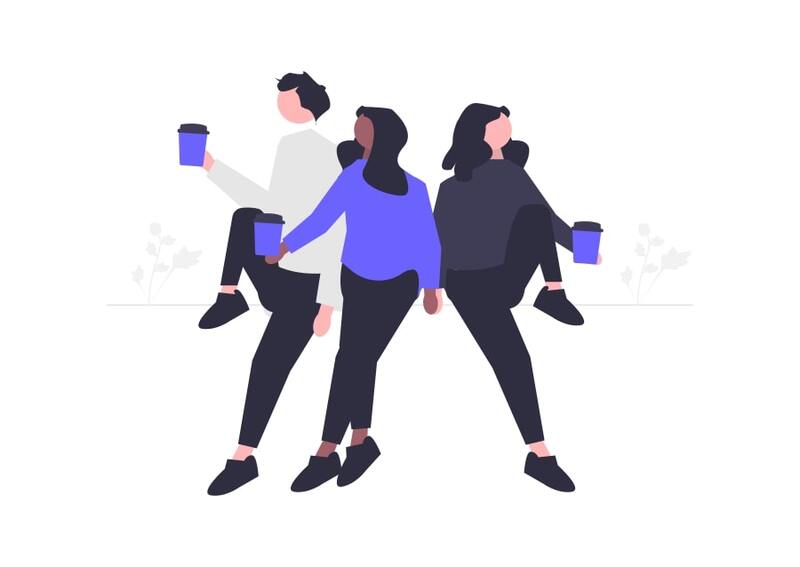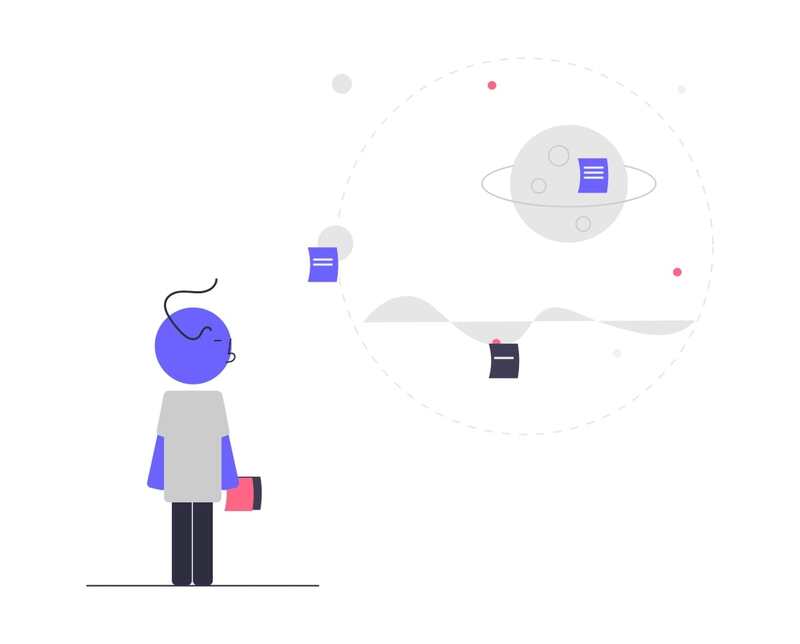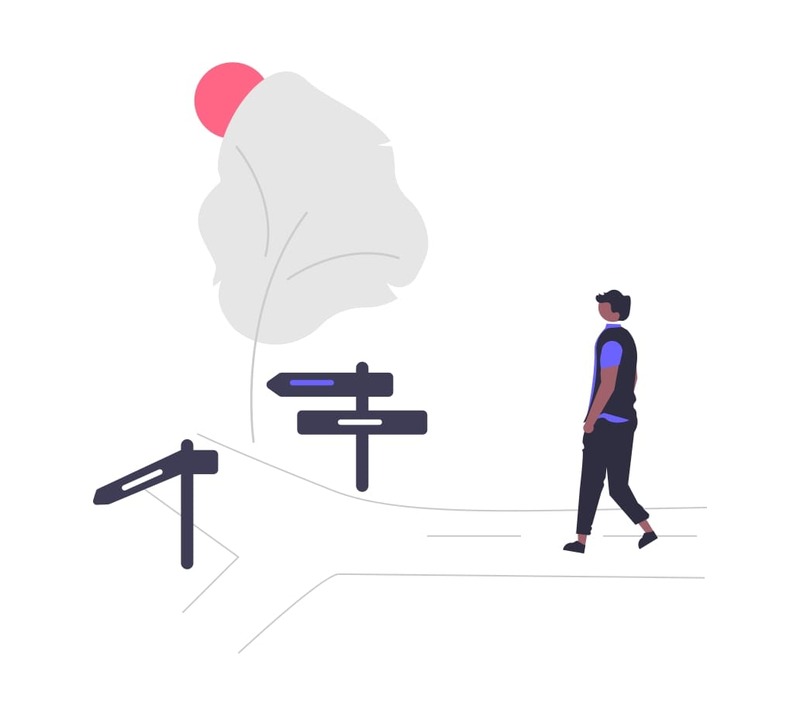初めに
今回訪問したのは、教育学部/大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター特任准教授 飯野由里子さんです。
飯野さんの情報はこちらから!!
メンバー:フェミニズムとクィア理論を中心に勉強しており、研究者としてのキャリアを考えています。飯野さんのご著書を読んで障害のある女性や在日コリアン女性など、たくさんの人の状況を自分が無視してきた事実に衝撃を受けました。
飯野さんは研究・執筆活動は勿論のこと、ふぇみ・ゼミやバリアフリー教育開発研究センターなど学問外の実践活動も両立されています。差別を取り扱う分野に関して研究や運動をすることは、ときに痛みや自己嫌悪を伴います。あまりメジャーではないこれらの分野で研究者としての職を安定して得ることもとても大変だと聞いています。
今回のインタビューでは、それでも研究者としてずっと活動を続けて来られた飯野さんの想いを伺うことで、
・これらの研究分野の魅力
・研究者として活動することの魅力
を見つけられればと思っています!
それでは、よろしくお願いいたします!
フェミニズムと障害学の出会い
メンバー: 現在はフェミニズム、クィア・スタディーズ、障害学など多岐にわたって研究されていますが、最初からそのような幅広い研究関心を持っていたのでしょうか?
飯野さん: 元々はフェミニズムが専門で、博士課程では、日本のレズビアン運動に焦点を当てた研究をしました。
その後、障害学に出会ってからは、障害学とフェミニズムを架橋することに焦点を当ててきました。
関心が移り変わっているようにも見えますが、一貫して「フェミニズムをどう豊かにしていくか」を考えています。女性の中でもマイノリティ性を持つ人たちーーレズビアン女性や、障害のある女性たちーーの運動の視点から、異性愛者で障害がなく人種的・民族的にマジョリティの女性たちによって担われてきたメインストリームのフェミニズム運動を問い直すことに関心があります。
メンバー:障害学に興味を持ったきっかけは何でしたか?
飯野さん:2002年に博士課程の単位を取得した後、非常勤講師として働いたことがきっかけでした。200人や400人といった大規模授業で、ジェンダー論を教えていました。シラバスを作って、スライドを作って、授業に行ったんですね。そして学生の前に立って初めて、400人のクラスの中に、弱視の学生がいるって気づいたんです。どうして気づいたかというと、単眼鏡を使って一生懸命スライドを見ていたからです。その後200人のクラスに行ったら、難聴の学生がいたんです。なぜ気づいたかといえば、補聴器をつけていたからです。
今思えば、目に見える印があったからこそ気づけただけで、見えない障害を持った学生さんもきっとあの場にいたんだろうな、と思います。でも、授業を準備している時に、そういうさまざまな障害をもつ学生さんの存在が私の意識からすっかり抜け落ちてしまっていた。学部生の時も、大学院生の時も障害のある学生と一緒に勉強していて、障害のある学生がいることを知っていたはずだったのに。そのとき自分に失望したっていうか、このまま私は大学の教員としてやっていっていいのだろうか、と反省したし悩みました。
メンバー:ここから学問としての障害学にはどのようにつながっていったのでしょうか?
飯野さん:悩んでいた時に偶然、障害のある研究者の支援者の仕事が入ってきたんです。最初は1年だけ障害について勉強するつもりで始めたのですが、これがその後もずっと障害学を勉強し続けるきっかけになりました。
その時に支援を担当したのが星加良司さんで、のちに『障害とは何か』という本として出版される博士論文を書いていました。その中で「障害の社会モデル」と出会い、フェミニズムが主張してきたことをもっとシンプルにモデル化している!と衝撃を受けました。
メンバー:「障害の社会モデル」について詳しく伺えますか?
飯野さん:障害の社会モデルというのは1960-70年代、主にイギリスの障害者運動の中で提唱された考え方です。
従来は、障害は障害者の心身の状況にあり、リハビリや治療で「治す」か地域の療養施設で管理されて生きていくしかない、と障害者自身も周囲の人も考えてきました。それに対し社会モデルでは、障害者の生きづらさの原因は、個人の身体ではなく社会の作られ方にあるのだと考えます。非障害者を中心に作られたこの社会は、障害者が他の人たちと同じように社会に参加できないような仕組みになっている、というわけです。
メンバー:この考え方がどのようにフェミニズムと結びついたのでしょうか?
飯野さん:私の中では、「個人的なことは政治的なこと」という第二波フェミニズムのスローガンと重なりました。私が「自分の性格が弱いせいだ」などと悩んでいた時に、フェミニズムはそれは社会構造の問題だ、社会構造によって自分がやりたいことをうまく追求できないのだ、と教えてくれました。これをもっとシンプルに言ったのが障害の社会モデルだ、と感じました。
この時は私自身フェミニストとしてのアイデンティティの方が強かったので、障害の社会モデルをフェミニズムにも浸透させたい、フェミニズムと障害学を繋げたい、と思うようになりました。
研究を社会へ開く、実践に移す
メンバー:「障害の社会モデル」は研究以外の領域でどのように役に立っていますか?
飯野さん:この10年、企業や行政、学校などの人たちと連携しながら「社会モデル」の考え方を広めるための活動をしてきました。当初は自分自身の研究活動とそうした実践の間に大きな距離を感じていましたが、活動を継続する中で、企業や行政、学校にいる人たちが直面している問題を、自分の研究関心に関連させて考えられるようになってきたと思います。
メンバー:教育分野での活動について詳しく伺えますか?
飯野さん:活動の一環として、「障害の社会モデル」の考え方に基づく教材の開発を行っています。この教材を使って、学校の先生に子供と一緒に社会モデルについて考える授業を実践してもらってもいます。2020年から実践しているので、長いところだと3〜4年、授業をしてくれている学校もあります。

※上は実際に作られたハンドブックの写真。
メンバー:その活動の効果にはどのようなものがありましたか?
飯野さん:生徒と先生、両方に考え方の変化が見られました。
生徒たちの変化としては、学級会の運営方法の変化が印象的でした。例えば、体育会でドッジボールがしたいとなったときに多数決で決めるのではなく、不安や心配の声がないかを確認するようになったクラスもありました。
先生側の変化としては、もめごとがあった時、片方だけを一方的に悪いとみなすのではなく、両当事者の話をよく聞き、衝突が起きやすい環境になかったかを考えるようになったそうです。
特別支援学級の生徒に対する担任の接し方に関して、小学校四年生の人が「差別だ」と校長に直談判したこともあったようです。
メンバー:なるほど。「障害の社会モデル」というと、段差の有無など物理的なものを想像しがちでしたが、制度など目に見えない部分にも大きな変化をもたらせる考えなんですね。
研究と実践
メンバー:活動をしている中で感じている課題や、研究との衝突・葛藤はありますか?
飯野さん:社会モデルはシンプルかつ汎用性の高い考え方であるため、既存の価値観に大きく抵触しない範囲で解釈できてしまう可能性があるとも感じています。
学校の事例でいうと、日本の学校では、みんなで同じことを同じタイミングで行うことを「平等」と捉え、重視する価値観があります。この意味での「平等」を実現する目的で、社会モデルの考え方を積極的に利用しようという教職員はたくさんいます。他方、そうした限定的な意味での「平等」という価値観自体がバリアになり得るということに気づいてもらうのは難しいです。
メンバー:この問題について、これからどのように取り組んでいくご予定ですか?
飯野さん:ここからが研究者の仕事だと思っています。私たち研究者は、企業や行政や学校に知見提供をしたり、一緒に考えたりしながら、インクルーシブな環境を実現していくお手伝いをしているわけですが、特定の企業や学校の利益追求のためにそうしているわけではありません。
今のやり方に限界はないだろうか、この方法で新たに抑圧される人はいないだろうかと、良かれと思ってやっている事柄に対してこそ、批判的な目線を向けることが必要です。この時に研究という手法はとても有効だと思います。
研究者として働くことの魅力
メンバー:社会問題に取り組むときに、研究者以外としての関わり方はたくさんあると思います。研究者としてのポジションにはどのようなメリットがありますか?
飯野さん:私は学ぶことが好きなので、好きなことを追求していたら研究者になったという感じです。ただ、資本主義社会の中で研究者として生活していくことは大変で、給料が少なすぎて、借金をしながら働いていたこともありました。
私にとって研究者でいることの一番のメリットは、いろいろなプロジェクトに関わる中で、自分の興味・関心だけで勉強していたら見落としてしまうものに気づけることです。最近だと、『ホワイト・フェミニズムを解体する インターセクショナル・フェミニズムによる対抗史』という本の監訳に携わらせてもらうことで、先住民女性の運動を自分が見落としてきたことに気がつきました。
将来の展望
メンバー:自分の関心の外にあったものと出会うために、意識して行っていることはありますか?
飯野さん:ひとつはふぇみ・ゼミ&カフェでの活動です。ふぇみ・ゼミ&カフェのメンバーと出会ったことで、在日コリアンの女性たちの運動など、マイノリティ女性のフェミニズムとの関係が変わりました。
それと、毎日論文を1本読むようにしています。有名な本やジャーナルだけでなく、マイナーと思われている紀要論文なども意識して読むようにしています。世の中には、地道に研究している人がいて、自分ひとりで勉強していたら出会えないものを文字にしてくれている人がたくさんいます。そのことへのリスペクトを大事にしたいと思っています。
メンバー:素敵ですね。今後のご研究やご活動の展望について教えて下さい。
飯野さん:自分が何かしたいというより、若手の研究者にバトンタッチしていきたいと思っています。ここ数年は大学院生を積極的に雇用し、プロジェクトに参加してもらったりしています。ただ、私がいろいろ教えるのではなく、共にプロジェクトに関わる中で、その人にとって大事だと思うものを拾ってもらえたらいいなという感じです。すごく前に「種を拾う」というエッセイで書いたのですが、私は社会モデルや障害学という新しい領域と出会って、そこで拾った種をフェミニズムの方に植えていこうという気持ちで続けてきました。それぞれが好きな種を拾い、こことは違う別のところに植えてもらえたら嬉しいです。
メンバー:飯野さん、ありがとうございました!教育現場の声を聞き、小さな論文の声も拾い、新たな出会いを大切にしながらマイノリティ女性の経験から社会を問い直していく姿勢に、研究者としての飯野さんの真摯さを感じました。改めて、今回は素敵なお話をありがとうございました!