農学部
農業·資源経済学専修
2023.8.30
【環境資源科学課程】通称「農経(のうけい)」
目次
基本情報
| 人数 |
30~35名(3割が文系出身) |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ2割程度 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
院進は15%前後で、2~6名程度/大多数は就職 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
農学部農業・資源経済学専修は経済学をベースにして、歴史的・政策的・経営的視点も踏まえながら、日本と世界の食料・農業・農村問題を解明することを目指す。通称、「農経」と呼ばれている。
農学の理論を学ぶ授業として、必修の農業史概論や農業経済学汎論、その他社会学・経営学系の授業がある一方で、農学の実践を学ぶ場として地域経済フィールドワーク実習や農作業実習がある。
2年次後期~3年次にかけては、必修の座学や演習(ゼミ)を受けつつ地域の現場に足を運ぶ授業が展開される。それらを参考にしながら3年次2月に自分の興味のあるテーマを扱っている研究室を選ぶ。4年次には、経済学・農業経営学・農政学・食料資源経済学・農村開発金融・農業史のいずれかの研究室に所属し、卒論を執筆する。ちなみに、どの研究室に配属されても、自分のやりたいテーマで卒論が書けるとは言われている。なお、研究室訪問は基本的に無いので、2Aからのゼミの雰囲気や各教授・研究室のタイプ、先輩の卒論、自分の興味に応じて研究室を選ぶことになる。
出身科類は理二が5~6割を占める一方、3割が文系出身となっている。文理融合の雰囲気は強く、実験がほぼ無いことや、経済学部の授業を聴講する学生が多いことにもその特質が表れている。
経済学部との大きな違いは、経済学部が理論に寄る一方で農経は現場も重視していることである。
■農経の諸制度
卒業に必要な単位は76単位。その内訳は下表の通りとなっており、それぞれの区分から必要単位以上を取得しなければ卒業できないため、きちんと計算して履修を組む必要がある。
・卒業に必要な単位数
| 区分 | 必要単位数 | 内容 |
|---|---|---|
| ①農学総合科目 | 4単位以上 | ②と併せて16単位以上取得。20単位まで算入可 |
| ②農学基礎科目 | 6単位以上 | 必修3科目6単位(農業・資源経済学汎論/農業史概論/ミクロ経済学)を含む |
| ③環境資源科学課程専門科目 | 20単位以上 | 選択必修を含む |
| ④農学共通科目 | 3単位以上 | 必修1科目2単位(農学リテラシー)+選択必修1単位(○○倫理) |
| ⑤専修専門科目 | 16単位以上 | 必修6科目(農村調査概論/農業・資源経済学専修Ⅰ~Ⅲ/農作業実習/卒業論文)を含む |
| ⑥他課程・他専修専門科目/農学展開科目/課程共通科目/他学部科目 | 合わせて21単位まで算入可 | 農学展開科目は2単位まで/経済学部以外の他学部科目は承認が必要 |
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
・週15コマ前後が一般的。
・2Aは大教室での選択必修が多い。結構多めに単位数を修得しておく必要がある。
・必修は3つ、「農業史概論」「農業経済学汎論」「演習(※)」がある。
※演習(ゼミ):2A~3Aの3セメスターで開講される。先生が選んだ本・論文を輪読し、毎週1,2名が発表を行う。教員が4名おり、志望ゼミを登録したうえで抽選で決定される。学科ガイダンスの際に希望調査~抽選まで行われる。セメスターごとにゼミ変更可能。「ゼミの先生は、2Aセメスターは教授、3S・3Aセメスターは准教授が担当していた印象がある」とのこと。
3年生Sセメスター
・週10コマ前後が一般的。
・必修は「演習」に加えて農作業実習がある。6月の最初の土曜日に、田無の農場に行って田植えをする。
・S2タームの代わりに「SPターム」があり、その期間は集中形式の講義が多い。
・必修に加え、選択必修※の座学「農業経済学」「農政学」「農業経営学」などを必要単位数と勘案して履修する。
※「選択」とついているが、相応の数を選択しないと必要単位数に満たない。
・地域経済フィールドワーク実習(略して地域経済FW実習)という授業がある。全体の1/3程度の学生が参加。夏休みを使って地方の農村にフィールドワークに行き、現地の実態を調査する。Sセメではその調査票を作り、Aセメでは夏休みの現地調査で得られたデータを整理して論文を書く。「これに参加しないと、農経に来た意味が無いと言われています!」
(理二→農経)
3年生Aセメスター
・週10コマ以内が一般的。
・必修は「演習」に加えて、農作業実習がある。毎週1回田無に通い、圃場の整備や果樹の収穫、稲刈り等を体験する。
・2月に4年次に所属する研究室を選ぶ。
・1月中旬の卒論ゼミガイダンスにて、教員が各研究室の紹介を行い、その際に志望票が配布される。志望票は卒論報告会(例年2月10日前後)以降に提出し、それに基づいて研究室の配属が決定される。面接などの選考は無いが、希望多数の場合は所属ゼミの分野に応じて多少優先順位に差が付けられるという噂。
4年生Sセメスター
・必修は卒論のみ。
・卒業単位を取り切っていない学生は、卒業チャレンジに挑む。
・研究室に配属される。
4年生Aセメスター
・必修は卒論のみ。
・卒業単位を取り切っていない学生は、卒業チャレンジに挑む。
入る前の想像と実際
・「想定していたよりも統計や経済学が重要な分野だった。経済学の理論や統計の基礎知識は身につけておいた方が良い。」
・「とはいえ、文系から進学する学生も多いので、学部に入ってから頑張って勉強すれば十分ついていける。心配する必要は無い。」
・「2Aは学科合同で大教室の授業が多いので、学科の人と仲良くなる場としてゼミがあったのはありがたかった。」
(談:理二→農経)
選んだ理由/迷った学科
・「食べるのが好きだったので農家になろうと思っていた。その後留学して、食糧問題に関心を拡げた。品種改良等のアプローチ(農2(※)など)にも興味があったが、フードロス等、余剰と飢餓が同時発生している「非効率な分配構造」に取り組めるのが農経だと感じた。」
・「前期課程では自由研究ゼミナール『農作物を知る』で品種改良に関する授業も受けた。それはそれで楽しかったが、先輩の話も聞き、国際機関へのキャリアに関心があることもあって、農経への進学を決めた。」
(理二→農経)
※農2:農学部の生命化学・工学専修のこと。平成18年以前の進学振り分け制度で両専修が「農学部2類」と呼ばれていたことから、現在もそう言われることが多い。
コミュニティとしての機能
・30名という規模感から、親睦はある程度深い。ただ、密にコミュニケーションを取っている人はそれほど多くない。
・全体のコンパは1回あった。
・LINEグループがある。
・先輩後輩の繋がりはそれほどない。
・毎年7月中旬に農水省の人と懇談するイベントが行われる。農水省志望の学生含め、3,4年生が数多く参加する。
・農業に強い関心を持つ学生もいれば、点数が足りなかったり必修が少なくて楽だったりという理由で来る学生(特に理系)もいる。
・学部生用の専修室がある。
・4月・9月には歓迎会等のイベントが行われる。
授業スタイル
・出席を取る授業が多い。出席の確認方法は紙が配られることが多い印象(ただし、Covid-19によるオンライン授業移行前の話)。
・実験はほぼ無い。実習かゼミか、あるいは座学。
・試験がもともと多い学科だが、近年は弥生キャンパスの改築の影響で、レポートに切り替える科目も多くなってきた。
研究室・資料
農学部公式の「教員カタログ」はこちら
(各教員の研究内容が平易に書かれているだけでなく、目指す教育内容や研究室の人材輩出実績など進学選択の意思決定に役立つ情報が盛りだくさん。)
・農業経営学研究室
・農政学研究室
・農業史研究室
・経済学研究室
・食料・資源経済学研究室
・農村開発金融研究室
・専修紹介(教員作成)
・専修紹介(学部生作成)
特別な制度・その他
・One Earth Guardians 育成プログラム (略称OEGs):農学部の学部生・院生向けプログラム。「100年後の地球に貢献する科学者」を育てることを目指している。OEGs候補生は、企画立案から実行まで行う「実学研修」と「認定科目」とをそれぞれ履修。学部3年生から博士課程まで、様々な学年
・専修の学生が参加している。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

農学部
諸科学に関する世界水準の教育・研究を進め、食料・環境をめぐる多様な課題に取り組む専門性豊かな人材を養成する学部
関連記事

水圏生物科学専修
【応用生物科学課程】通称「水圏(すいけん)」

動物生命システム科学専修
【応用生命科学課程】通称「動シス(どうしす)」
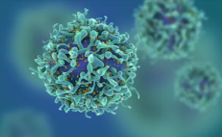
応用生物学専修
【応用生命科学課程】通称「応生(おうせい)」

国際開発農学専修
【環境資源科学課程】通称「国農(こくのう)」




