工学部
システム創成学科B(SDM)
2023.4.15
システムデザイン&マネジメント
目次
基本情報
| 人数 |
35名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ1割程度 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
就職:院進=7:3 |
| 公式サイト |
学科概要
■システム創成学科共通の特徴
・工学部システム創成学科(略して「シス創」)はA~Cの3部門に分かれている。社会系、物理系、情報系の授業がバランスよく存在している。
・限定選択(※)に経済学や経営学を扱う授業があるように工学部の中でも文系寄りで、扱う内容の幅も広い。一般的に第一ターム(S1/A1)に開講科目が固まっていることが多く、2,3回の欠席で落単してしまう科目もあるので要注意。
・2Aから4Sにかけて〇〇プロジェクトと名付けられた、似通ったテーマを持つ人で少人数グループを作り、調査、プレゼン、ディベート等を行う実践学習形式の授業がある。テーマは、プログラミングによるシミュレーションなど。次第に各コースごとに専門性が高まっていき、全コース合同のプロジェクトは2年次のA2タームだけである。
※ 限定選択とは、工学部一般に用いられる用語で、要は選択必修のこと。
■Bコースの特徴
・工学とプログラミングの学習をベースに、メインテーマのシミュレーション技術やレジリエンス工学を集中的に学んでいく。
※なお、コース名の末尾に付されるSDMとは、System Design Managementの頭文字である。
■当コースの諸制度
卒業に必要な履修単位数は90単位。うち必修科目が20単位(うち卒論が10単位)、限定選択科目(※)が40単位以上となっている。
■時間割
2年生Aセメスター
※ ページ内の汎用にもあるが、当学科全コース科目は(創成)、Aコース科目は(E&E)、Cコース科目は(PSE)となり、Bコース科目は(SDM)と記載されている。内容は最新版とは限らないので注意。
3, 4年生
※ 必修科目、限定選択科目、その他がまとめて書いてある。そのため、各セメスター紹介でも一部紹介するとはいえ、原則として詳細はシラバスや学科便覧で確認すること。
■進振りの時に気を付けること
・第一段階は一般的な学科コース(工学部)同様、工学部平均を用いて進学振り分けが成されるが、第二段階に注意。第二段階では、工学部平均と単位数を掛け合わせた値を基準に進学振り分けを行う。そのため、平均が少し低くても単位数を多く取る方が優位になる。(「システム創成学科 第二段階指定平均点」 = 「工学部指定平均点」× 取得単位数(上限90単位)) (2020年度の場合。次年度以降は変わる可能性あり。)
■進学後の内実は?
・ターム制講義が多い。特に3S/4Sはそれぞれ必修科目の「基礎プロジェクト」、「領域プロジェクト」が第一ターム(S1/A1)に入るので、第一タームは比較的忙しいが、第二ターム(S2/A2)は必修に囚われず様々な履修ないし課外活動に取り組むことができる。
・3Aセメスター末から4Sセメスターのはじめにかけて研究室振り分け(研振り)が行われる。各研究室ごとに選考基準や配属されるタイミングはバラバラで、学部(2A~3A)の成績順の研究室もあれば、2人枠のうち1人は成績もう1人は面接、というところもある。進振りのように仮調査が行われて各研究室ごとの志望人数が出たのち、それを参考に第一希望の研究室へ正式に申込をする。
・卒業論文/卒業研究は4年生の1年間で取り組む。
卒業論文タイトル(2019年)
卒業論文タイトル(2018年)
卒業論文タイトル(2019年)
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【相対的に授業が多い2A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 動機付けプロジェクト | 必修 | 火曜3-5限 |
・A1、A2合計で平均20コマ前後が一般的。
・2Aは限定選択科目の割合が多く、ここで多数履修しておくのが一般的。
・社会、環境、エネルギーなど人間社会の課題を解決するための俯瞰的な工学を扱う、コース共通の講義が限定選択科目に多く存在する。
・週3コマ(火曜3-5限)、セメスター開講科目の「動機付けプロジェクト」が必修、合計で2.5単位。当セメスターのみ、プロジェクトのテーマは全コース共通。
・コース共通 「数理手法」では、この学科のテーマの1つである数理最適化を扱う。
・コース共通 「プログラミング基礎」では、プロジェクト系の授業で用いる物理シミュレーションのためのプログラミング技術を学ぶ。
・単位数を稼ぐため、比較的単位が取りやすい経済学部の授業を取る人や、コマ数を埋めるために他学科/他学部の授業を受ける人が多い。
3年生Sセメスター
■【S1が忙しい3S】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 基礎プロジェクトB | 必修(S1のみ) | 月/木3-5限 |
・平均20コマ前後が一般的。
・週6コマ(月曜/木曜3-5限)、S1ターム開講の「基礎プロジェクト」が必修で合計2.5単位。
・コース共通の授業に、「経済学基礎」や「金融レジリエンス情報学」等。
・2, 3割の学生は学部就職するが、外資コンサル・投資銀行を狙う場合、この時期に就活を始める人が多い。その他日系大手なども、夏休みにかけてサマーインターンに応募していく。
3年生Aセメスター
■【研振りを控える3A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 応用プロジェクトB | 必修 | 木3-5限 |
・平均20コマ前後が一般的。
・研究室振り分け前に点数を稼いでおく最後のチャンス。
・週3コマ(木曜3-5限)、セメスター開講の「応用プロジェクト」が行われる。合計2.5単位。2019年度の場合、A1タームでは英語の学術論文、発表のコツを教わり、A2タームでは校舎の構造をCADで再現し、耐震強度をシミュレーションにより検証した。
・3A末から4Sのはじめにかけて、研振りが行われる。(詳細は上部「学科概要」の欄に記載)
・学部就職については、外資系企業や一部日系大手は内定(内々定)が出始め、終活(就活終了)する人も。官公庁の教養区分はこの時期で、官僚志望の学生は少数だが受ける人も。
4年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 領域プロジェクトB | 必修 | 火/金3-5限 |
・平均10コマ前後が一般的。
・週6コマ(火曜/金曜3-5限)、S1ターム開講の「領域プロジェクト」が行われる。合計2.5単位。 最後のプロジェクト系授業ということもあり、Bコースならではの専門的なテーマ(※)を扱う。
・S2タームからは殆どの時間を卒業研究、卒業論文執筆に充てる。
・学部就職については、6月前後で民間企業勢はほぼ終活し、官庁訪問を経て官公庁志望も夏には内定先が決まる。
・7割程度が院進するが、院試は夏休みに行われるのが一般的。夏休みに向けて志望進学先の勉強に励む学生が多い。
※先端コンピューティング、金融市場の数理と情報、生命知コンピューティング等。
4年生Aセメスター
■【引き続き卒論に勤しむ4A】
・殆どの時間を卒業研究、卒業論文の執筆に充てる。
入る前の想像と実際
・多様な分野の教授が集まっているため広い視点を持って学べる事に魅力を感じ進学したが、実際にそうだった。選択肢が多いので、自分に合った講義選択ができた。
(理I → シス創B)
選んだ理由/迷った学科
・情報系や建築系など、目的が明確に決まっている人は専門の学科に行く中、学びたい科目があまり定まっていなかったため、扱う内容の幅も広いこのコースを選んだ。プロジェクト系の授業などを通じて分野を決めた。
(理I → シス創B)
・内容に若干の被りがある経済、精密工学と比較検討してこの学部に入る人が多い。
・松尾研等で人気のCコースと比べ底点が低く入りやすい。
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 【2】 |
| LINE | 無 |
| Slack | 有(※1) |
| 学科ドライブ | 有(※2) |
| オフラインでのつながり | 無 |
| 上下のつながり | 有 |
※1:Bコースでの重要事項の連絡の際に使用するが、あまり活発ではない。
※2:学年間で過去問共有などを行う(シケタイ制度、パ長制度はなし)
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 40~60名前後(※1) |
| 成績評価 | 出席+レポート |
■成績評価
基本的には座学の出席重視、2,3度の欠席で落単してしまう科目もあるので要注意。評価はコロナ禍以前より殆どが出席+レポートで、一部出席+テストの科目がある。出席はITC-LMSでとる授業が多く、一部紙を回して氏名を書く形式の授業もある。
研究室・資料
・システム創成学科Bコース公式サイト
・システム創成学科Bコースカリキュラム
・システム創成学科Bコース教員紹介
◆原子力国際専攻
山口 彰教授(コース長): 原子力安全、熱流体工学
長谷川 秀一教授: 光子・同位体利用工学
高橋 浩之教授: 放射線測定
笠原 直人教授: 高温構造システム
石川 顕一教授: 原子・分子・量子エレクトロニクス
阿部 弘亨教授: 材料科学、原子炉材料学
関村 直人教授: システム保全学
◆システム創成学専攻
吉村 忍教授: システム創成学
越塚 誠一教授: 数値流体力学・物理ベースCG
大澤 幸生教授: システムデザイン、知識工学
和泉 潔教授: 金融・経済データ解析
◆人間環境学専攻
陳 昱教授: 複雑物理系と複雑適応系
奥田 洋司教授: 計算力学
◆レジリエンス工学研究センター
古田 一雄教授: 認知システム工学
・ビッグデータの解析を行う、和泉潔教授の研究室の人気が高い。(参考 和泉・坂地研究室)
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
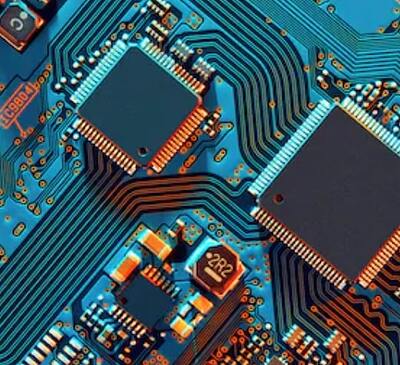
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

化学生命工学科
化学生命工学

総合 国際関係論コース
教養学科 総合社会科学分科

生命化学・工学専修
【応用生命科学課程】通称「農二(のうに)」
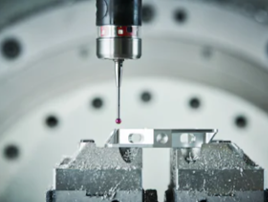
精密工学科
知的機械・バイオメディカル・生産科学




