工学部
機械工学科(機械A)
2024.1.7
デザイン・エネルギー・ダイナミクス
目次
基本情報
| 人数 |
90-100名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性は1割程度 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
大多数が院進/就職は1割と言われる。 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
機械工学科は、従来にない新しい「もの」を作ることに興味のある学生に向いている。研究分野は基礎的な科学研究から実用的な研究まで多岐にわたり、自分の関心に合わせた選択ができる。機械の設計・製作ができるようになることを目標に学ぶ。
兄弟学科の機械情報工学科とともに機械系2学科を構成し、機械工学科は「機械A」や「機械工」、機械情報工学科は「機械B」や「機情」と呼ばれることが多い(以下「機械A」「機械B」と表記)。2A~3Sセメスターは両学科一緒に同じ授業を受けることが多い。2学科合わせて130名程度の学生がいるが、うち機械Aは90~100名程度。
進学定数は、理科一類から88名(第一段階57名+第二段階31名)、理科二・三類から2名、全科類枠で2名となっている。
機械Bの方が機械Aよりも進振り点が高い傾向にある。機械Bを志望していたが点が足りず、カリキュラムが似ていると言う理由で機械Aに入る学生も存在する。この場合、ゼミ演習は機械A,Bで合同だが研究室は分かれているので要注意。
2Aセメスターは機械工学と情報工学の基礎を学ぶ、機械Bとの共通カリキュラム。工学系4力学:「熱力学」「流学」「機械力学」「材料力学」や、制御工学、情報工学を学ぶ。3Sセメスターでは2Aセメスターを発展させた内容を扱い、座学より演習の授業が増える。3Aセメスターは機械Bとは異なる授業が大半となり、少人数ゼミでは各研究室で実習を行う。4年生になると4月に研究室に配属され、卒業論文に向けた研究が中心となる。
■学科の諸制度
卒業に必要な単位は95単位。必修は23.5単位(うち卒論10単位)、限定選択(※)は47.5単位以上の修得が必要。
(※)限定選択とは工学部一般に用いられる用語で、選択必修のこと。
2020年度A1A2機械系時間割原表(学部)
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 機械工学総合演習第一 | 必修 | 金曜1,2限 |
・週20コマ前後が一般的。「演習第一」(2単位)のみが必修で、残りは限定選択を16個程度、30単位近く修得する。座学が中心。
・授業はほぼ全て本郷。水曜日のみ駒場。
・駒場開講の科目は、「ソフトウェア第一」と「数学1B」。
・大部分の授業が機械Bと合同。
・座学中心だが、演習の時間も。必修科目の「演習第一」に加えて、「機械数学演習」「機械ソフトウェア演習」が1単位ずつ。
・「演習第一」は、8名ずつのチームに分かれて課題をこなしていく。班ごとに動くので、他班とは同授業回でも実験内容が違う。よって課題をやる際は、チームの絆が大切。
・この時期にパ長・シケ長も決める。後に触れるが、セメスターやターム終わりごとに飲み会をやる代も。授業ごとにシケタイが割り振られる。
3年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 機械工学総合演習第二(※1) | 必修 | 月火水金の3,4限 |
(※1)週8コマ、4-5名の班に分かれてスターリングエンジンの設計を行う。各実験室に5-6名の教員・TAがおり、2学科を挙げた授業。電子回路を組む演習、プログラミング演習(C,Python)、CADの練習(SOLIDWORKS)など、学びが多い。(以下「演習第二」とする)
・週20コマ程度。「演習第二」(6単位)のみが必修で、残りは限定選択を10個程度、計30単位近く修得する。座学中心の2Aセメスターよりも実習の比重が増え、コマ数は座学と実習がほぼ同数になる。
・2020年度の「演習第二」は、新型コロナウイルスの影響で、材料の切り出しや組合せなどの対面必須の内容だけは夏休み以降に持ち越しとなった。
・限定選択の授業などで少しずつ機械Bとの合同授業が減っていく。
・「数学2B」の演習も負担がかなり大きい。複素数解析やマクローリン展開を扱う。水曜2限に講義があり、3限に演習がある。時間割によると演習は15時までだが、14時前後に終わる回が多い。また、当授業は機械A・機械B・航空宇宙工学科(以下「航空宇宙」とする)とで3学科合同だが、演習では機械Aで1教室、機械Bと航空宇宙で1教室と、2教室に分かれる。内容は先生の趣向次第とも。
3年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 創造設計演習 | 必修 | 月木,3-4限,金1-4限(例年は金3-4限) |
・週20コマ前後が一般的。「創造設計演習」が必修で、水曜4限の「機械工学少人数ゼミ」を通じて研究室選びの準備を行う。
・この時期には機械Bと授業がほぼ分かれる。
・「創造設計演習」では、11月下旬までは全員同じ規定課題(電子回路を組んだり工作したりシミュレーションしたり)をこなす。その後はガイダンスの際の希望調査に基づき、メカトロ演習、IoT演習、シミュレーション&ヴィジュアライゼーション演習の3つに分かれる。「面白いおもちゃを作る」というコンセプトで、4人1組のグループになり作業する。最終的には動画やスライドを用意して発表する。
・4年次研究室選びの準備段階に当たるのが、3Aにある「少人数ゼミ」である。ガイダンスの時に、研究室・研究内容一覧等の基本的情報を提供され、そこからどのゼミにするか選ぶ。定員があるとはいえ、基本的に志望から漏れた人はあまり見かけられない。
4年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 技術者倫理 | 必修 | 火曜5限 |
| 卒業論文 | 必修 | ____ |
・3年までに単位を取り切り、4Aは少数の必修を取りつつ、卒業研究にリソースの多くを割くべきと言われている。
・研究室選びは、学科公式ページの一覧を参考にして決める。
・研究室によって活動量の多寡は様々。
・院試の勉強もすれば卒論もする。
4年生Aセメスター
・実質的に卒業研究のみ。
入る前の想像と実際
・ハードウェアや機械工学を学ぶと思っていたが、その通りだった。進学後に、2Aセメスターで微分積分などを初歩から教えてもらえたので安心した。
・思ったよりもプログラミング関連のスキルを伸ばす機会に恵まれていた印象がある。
・教室内の空気が悪い。工学部2号館221教室で授業を受け続けるのだが、換気がされておらず淀んでおり、眠気を催す学生も。(コロナ以前)
・2020年度のオンライン授業では、授業録画を公開してくれる先生はあまりいなかった。白抜きのスライドを手書きで埋めるという授業も。
(理一→機械A)
選んだ理由/迷った学科
・工作や、ハードウェアによって物体の運動を制御する機構などが好きだった。ソフトウェア的解決のみを目指すより、ハードウェアで解決できる課題はハードウェアで解決したいと考えていた。
・迷った学科として機械Bを挙げる学生が多い。点数が足りないから機械Aに入り、限定選択や少人数ゼミで機械Bに関する科目を取る人も存在する。ヒューマノイドに興味がないため機械Aにする人もいる(が、機械Bでもヒューマノイドばかりをやっているわけでは無い)。
(理一→機械A)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
オフライン:5-6、オンライン:3 |
| LINE | 有(※1) |
| Slack | 有 |
| オフラインでのつながり | 有(※2) |
| 上下のつながり | 個人的関係にとどまる(※3) |
(※1)Slackに入るために使われた程度。
(※2)試験終わりやターム終わりに飲み会をやっていたイメージ。パ長の社交性次第。2学科合同のコンパが3回程あったが、徐々に参加者は減少していた。
(※3)過去問の共有はシケ長同士で行うことが通例。
・学科内(機械系2学科合同)のSlackはある。課題相談などの事務的な内容が多い。今期から個人チャンネルができたが、これは年度によって異なりそう。
・Slackの中で機械A/機械Bにはっきり分かれている訳ではない。オンライン授業の影響もあってか、2学科が明確に分かれるのは授業の時ぐらいだと言う声も。
・全員の名前を知っていたり飲み会を主催したりする人もいれば、そうでない人も。一般的には実験などを通じてコミュニティを構築していくイメージ。
・RoboTechの人、女子、やや勉強へのモチベーションが低い人など、似た属性の人同士でまとまりやすい。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 授業により異なる(※1) |
| 成績評価 | ほぼ試験(+出席) (オンラインによりレポートがやや増) |
(※1)2Aは140人程度、実験は8人、少人数ゼミは2~6人、その他演習は平均4人、その他授業は70~200人
・多くの場合には試験で評価が行われるが、小テストのみで評価する科目があったり、レポートが課される科目もある。
・シケタイ制度もある。前年度の過去問を貰って回答を作るといった具合で、他学科や前期教養でもあるようなオーソドックスなスタイル。
・大体の授業で出席点を付けるので、出席率は9割以上。
・機械系の学科は「学生を見捨てない」と明言しており、単位取得という点で言えば、出席点のような救済措置が用意されている授業が多い。
研究室・資料
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
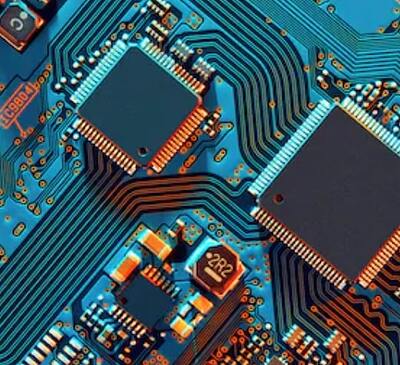
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

システム創成学科B(SDM)
システムデザイン&マネジメント
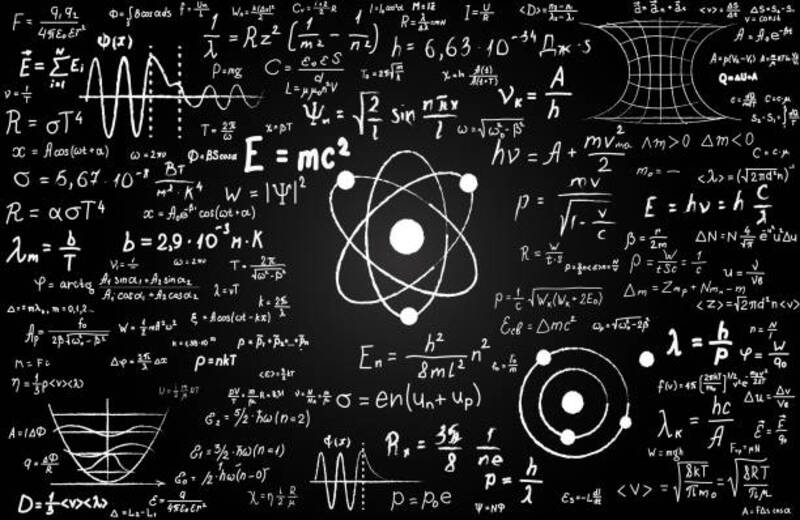
物理工学科
物性物理・量子情報

マテリアル工学科
A,B,Cをまとめて掲載

システム創成学科A(E&E)
環境・エネルギーシステム




