工学部
社会基盤学科
2023.12.30
A,B,Cまとめて掲載
目次
基本情報
| 人数 |
Aコース21名、Bコース20名、Cコース10名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女子は1~2割 |
| 要求/要望科目 |
要望科目 |
| 就活or院進 |
9割以上が院進する |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学科?
社会基盤学科(以下「社基」)では、基盤技術を中心に、水環境や生態系・都市問題・防災・地域や国土の計画・社会資本政策やプロジェクトマネジメント・国際協力など、ひとつの学科にまとまるとは思えないほどのフィールドの広さをカバーしている。人間・自然環境の再生と創造を実現するために必要な、基盤技術・デザイン・政策決定・マネジメントなどに関する研究・開発・実践を行うことが社会基盤学の目的としている。
進学選択では、Aコース(設計・技術戦略)、Bコース(政策・計画)、Cコース(国際プロジェクト)の3つのコース単位で募集されるが、優先的に配属される研究室が異なるだけで基本的に授業は共通。どのコースからでも興味のある研究室に行くことができる。
授業は2Aのうちは座学が多く、3Sからは実習や実験が増える。座学は材料力学、水理学などの物理の授業と、ディスカッションやグループワークの授業がある。卒論以外で唯一の必修であるフィールド演習は河口湖にある東大の施設でおこない、同級生、先生との仲がぐんとよくなる。ほとんどの単位を3Aまでに取り切り、4Sからは卒論に取り組む。研究室には留学生も多く、ゼミを英語でやる研究室も多い。
学部卒でも就職する人は何人かいるが、ほとんどは修士課程に進んで研究をする。卒業後の進路は多岐にわたる。鉄道、エネルギー、デベロッパーを始めとして、官公庁、コンサル、銀行、マスコミなど文系就職も多い。
■社会基盤学科の卒業単位数
| 科目 | 必修科目 | 必要単位 |
|---|---|---|
| フィールド演習 | 必修 | 2単位 |
| 卒業研究 | 必修 | 10単位 |
| 限定選択科目 | 62単位以上 | |
| 標準選択科目 | 限定選択科目と合わせて68単位以上 | |
| 卒業に必要な単位 | 95単位以上 |
・社基の必修は12単位で、フィールド演習と呼ばれる河口湖での実習(3年)と卒論(4年)のみ。
・同一の授業でも、A、B、Cコースで選択科目の区分が違うことがある。たとえば、「公共経営学」はBコースでは限定選択科目であるが、A、Cコースでは標準選択科目として扱われる。
・コース関係なくほとんど全員が同じ授業を受けるため、選択科目を意識することは少ない。
・卒業に必要な単位をとるために、農学部や都市工の授業を受ける人もいる。
・大学院(社基の大学院の授業は全て英語で実施)と共通の授業もある。
■進学定数は?
Aコース
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理Ⅰ(指定科類) | 12 | 7 |
| 理II、III(指定科類) | 1 | |
| 全科類 | 1 |
Bコース
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理Ⅰ(指定科類) | 11 | 6 |
| 全科類 | 3 |
Cコース
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理Ⅰ(指定科類) | 4 | 3 |
| 全科類 | 3 |
・B、Cコースの人気が高くなることが多い。
・全科類を利用して、文系からの進学者も一定数いる。
■内実は?
<授業>
・数学や物理をガッツリと扱う座学と、グループワーク型の授業、座学で学んだことを実際に活かすことができる演習がバランスよく用意されている。
・履修の自由度はかなり高く、他学部の授業も受けたりしながら自分の興味を広げたり追求することができる。
・3Sから実際に現場に行く機会が増える。授業の一環でまちを歩いたり、海で波の観測を行ったりする他、シールドマシンの掘削工事や渋谷駅改良工事など、実際の現場を見学できる現場見学会が企画される。また、各研究室の主催で4名程度の学生を募集する少人数型のセミナーが授業とは別に開催され、授業から一歩踏み込んだ実験や、現地調査をすることができる。
<コミュニティ>
・インフラやまちづくりに何かしらの興味を持っている人が集まってきている。
・運動部は一定数いる。サークル活動も参加している人が大半。
・2Aでは学科全体で橋の模型をつくる導入プロジェクトという授業があり、そこで同期の人と交流することができる。3Sではグループワークが基本となる基礎プロジェクトが開講される。かなり大変な演習であるが、そのぶんチームメイトと深い繋がりをつくることができる。その他、夏休みには3日間かけて行う測量実習や、河口湖での3泊4日のフィールド演習など、グループワークが多くあり同期と仲良くなりやすい。グループワークの授業が多いものの、フィールド演習以外は必修ではないので、グループワークの授業をどの程度とるかは自分で選択できる。
■進学前の注意点は?
・要求科目はないものの、大学の基礎的な数学や物理は授業内では扱わないことも多いため、文系から進学する場合は自分で補う必要があるが、先生に質問すれば丁寧に教えてもらえるし、同期内で理系科目が得意な人に教えてもらうことなどもしやすい環境である。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【数学や物理の授業に苦しむ2A】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 基礎流体力学 | 限定選択科目 | A1月、火曜2限 |
| 基盤技術設計論Ⅰ,Ⅱ | 限定選択科目 | A月、火曜3限 |
| 社会基盤学序論 | 限定選択科目 | A月曜5限 |
| 国際プロジェクト序論 | 限定選択科目 | A水曜3限 |
| 数学1E | 限定選択科目 | A水曜4限 |
| 導入プロジェクト | 限定選択科目 | A1金曜3,4,5限 |
| 社会技術論 | 限定選択科目 | A2金曜3,4,5限 |
(※1):微分方程式やベクトル解析の基礎を学ぶ。
(※2):学科全員で橋の模型をつくる。実際に使用された橋の設計図のみ渡されて、設計図の読み取り方から模型の作成方法、スケジューリングなどはすべて学生にまかされるので大変ではあるがここで仲良くなることができる。
(※3):アイデアを生み出す発想法を学び、実践する授業。扱うテーマはインフラだけではなく、バラバラだった。
・週平均は17~18コマ。
・座学がほとんどであり、A1とA2で授業が分かれているものもある。
・毎回コンスタントに課題が出ることは少ないが、レポートやテストが重い。
3年生Sセメスター
■【実習や実験を通じてさらに仲が深まる】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| フィールド演習 | 必修 | 集中 |
| 都市学 | 限定選択科目 | S1火、金曜2限 |
| 海岸工学 | 限定選択科目 | S1火、金曜4限 |
| 基礎プロジェクトI | 限定選択科目 | S水曜4,5限 |
| 基礎プロジェクトII | 限定選択科目 | S2月曜3,4限 |
| 国際コミュニケーションの基礎 | 標準選択科目 | S2月、木曜1限 |
(※1):河口湖で演習を行う。23年度は「社会基盤学のあり方」という抽象度の高い議題を同期や先生とひたすら議論した。毎晩親睦会があり、学生、教員ともに賑やかな雰囲気でおしゃべりをする。終わった後にレポートで評価がつく。
(※2):23年度は品川の再開発の現場見学などが開催された。
(※3):交通系の研究室が受け持っている授業。チームごとに担当する敷地が割り当てられ、現地調査を踏まえて空間計画、都市計画を作成する。演習室に泊まり込む人が出るほど大変な授業であるが、都市のあり方について考える初めての授業であり、チームや学科の同期と議論した時間は貴重な経験となる。
(※4)コンクリート研究室が受け持っている授業。学生は小グループに分かれて受注会社、教員側が受注者となる。受注者から要求されるコンクリートの材料費、比率などを自分たちで調査して、受注者に提案する。
(※5)英語で行われる授業。プレゼンテーションのスキルを学んだり、ブックレポートを書いたりする。
・週平均で20コマほど。3Sでも4Sでも取れる授業がほとんどであるが、3Sで取り切る人が多い。朝から晩まで授業が詰まっている。
・基礎プロジェクトでは、それぞれの研究室が行っている研究を体験することができる。
・授業によって大変さに波がある。暗記で乗り切れる科目もあれば、深夜遅くまで準備に時間がかかる科目もある。
3年生Aセメスター
■【研究室を考え始める】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 景観学 | 限定選択科目 | A1月、木曜2限 |
| シビルエンジニアの活躍する世界 | 標準選択科目 | A金曜2限 |
| 地球環境学 | 限定選択科目 | A木曜4限 |
| 計算地震工学 | 標準選択科目 | A2月、木曜3限 |
・週平均は20コマほど。
・「応用プロジェクト」と呼ばれる、基礎プロジェクトの延長のような授業がある。より研究室の内容に近づいたものを体験できる。
・授業が終わった1月くらいに研究室が決まる。研究室には大きく分けて水圏環境、基盤技術と設計、都市と交通、景観とデザイン、マネジメント、国際プロジェクトの6つグループに分かれている。研究室の決まり方は成績、面接など研究室によって条件が違う。
4年生Sセメスター
■【研究に打ち込む日々】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業研究 | 必修 | 集中 |
・4Sは授業を取らないか、取っても集中講義など。
・研究スタイルは研究室によっても大きく違う。国際プロジェクト研究室では在宅でもデータを集められるため、あまり研究室に出向くことはなかった。
・本来であれば、海外に行ったり、観測に行ったりしてリサーチを進める。
・夏頃に中間発表がある。
・大学院入試も8月の下旬にあるため、その準備も並行して行う。
4年生Aセメスター
■【研究に打ち込む日々】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業研究 | 必修 | 集中 |
・研究の発表会は2月の上旬ごろ。
入る前の想像と実際
・勉強は確かに大変だが、思ったよりも力学系は少なかった。また、試験の際にノート等の持ち込みがokな科目もあるのでそこまで恐れる必要はない。
・授業が大変でも、優しく助けてくれる人が多い。
・真面目な人が多いと思っていたが、面白い人もいる。
・インフラマニアや旅行好きは多い。内定してすぐに食事会や旅行の計画が立ったほど、同級生同士の距離が近い。
・授業の種類が幅広い。工学部の中でも、土木は公共政策や経済と密接に関わっていて文理横断的な分野なので、興味が広がる。
・「公共」が学科全体を貫くキーワードである。
・「社会基盤学とは何か」は教員によっても多様な考え方があり、授業やフィールド演習を通して議論し考え続けることになる。
・地盤や河川など自然を相手にした工学技術を学ぶことをベースにしながらも、都市計画やデザインを考えられる機会は多い。
選んだ理由/迷った学科
■【選んだ理由】
・「もともと環境問題について学びたかった。色々な分野から勉強することができると思ったが、大きなスケールで扱いたかった。また、フィールドワークの多い授業や、海外研修も積極的に応援してくれる環境も魅力的だった。」(理二→社基A)
・「対象範囲が広く、分野横断的に学べそうと思ったのと、学科の雰囲気が良さそうだったから」(理一→社基B)
・「社会のことについて幅広く学ぶことができ、ハードも開発もやっていて色々なことが聞けると思ったから。社基系の授業は取っていなかったが、1年生の時から視野に入っていた。」(文三→社基C)
■【迷った学科】
・「迷っていたのは社基C。社基は第二段階では理一からしか行けず、コースに関係なく希望の研究室にいけるのであれば、確実に通りそうなAで出した。」(理二→社基A)
・「経済、社基C、情報系で迷った。経済は就活が中心になりそう、社基Cは国際プロジェクトにはひかれたが、やっていることが漠然としていてわからなかった。また、情報系は、数学があまり得意ではない自分にとっては授業が大変そうだと思った。」(理一→社基B)
・「迷ったのは都市工学と教養の国際関係など。しかし、日本と世界の両方をフィールドにできる点や、ハードについて学べる点に魅力を感じ社基にした」(文三→社基C)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 9 |
| LINE | 有 |
| Slack | 学年による |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
(※1)
・2Aの導入プロジェクトがあるため、かなり早い段階から仲がよくなる。コロナでオンライン授業になってもディスカッションやグループワークを積極的に授業で取り入れているので、必然的に交流する機会が増える。
・試験前はZoomが毎日のように開かれて、試験対策をしている。
・学科部屋は存在しないが、演習室でお喋りをしたり、演習室の前の休憩所のようなところで雑談したりすることはよくあった。
・毎年五月祭に企画を出して、研究の成果を発表する。
(※2)
・一週間に一度は動いている。どうでもいい話から連絡、確認事項まで色々なことを話している。(2017年入学)
・事務連絡で使っている。(2019年入学)
・日々の連絡から試験前の教え合いなどに使われているほか、「社基の日常」というアルバムが作られていて日々学科の写真が集められていたりする。(2021年入学)
(※3)
・ほぼ動いていない。(2017年入学)
・授業ごとのチャンネルがあり、資料をアップしたり連絡事項を流したりしている。また、雑談をするチャンネルもよく動いている。(2019年入学)
(※4)
授業やそれ以外の場面でも学科内で交流する機会は多い。
(※5)
内定が決まってすぐに、3年生が学科の説明会を開催する。基礎プロジェクトや少人数セミナーでTAとして先輩が参加するのでそこで交流することができる。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 授業により異なる |
| 成績評価 | ほぼ試験(+出席) (オンラインによりレポートがやや増) |
・2Aではほぼ座学だが、学年が上がるごとに実習や実験が増える。
・座学では出席を取られることもあり、救済措置として機能する。評価方法は、レポートや試験など科目により異なる。試験は持ち込みが可能な場合もある。
研究室・資料
特別な制度・その他
・有名な教授が多くいらっしゃるが、国連大学の教授を兼任されている沖先生は特に有名。
・留学・国際インターンシッププログラム
社会基盤学科・専攻は、昨今のインフラ市場の国際化・グローバル化や日本企業の積極的な海外展開に対応するため、国際的に活躍するリーダーとなる人材の育成に力を入れている。
以下のようなプログラムが提供されている。
・TSAプログラム:ソウル国立大学、台湾国立大学、東京大学の3つの大学の社会基盤学分野の学生が集まり、共同でプロジェクトに取り組む短期の学生交流プログラム
・海外実習プログラム:海外の大学、研究所、公的機関や企業における1~2ヶ月間の海外実習プログラム
・ADBインターンシッププログラム:社会基盤学専攻とADB(アジア開発銀行)との間で作られた独自の長期インターンシッププログラム
・フランスENPCとの大学院修士課程共同プログラム:東京大学大学院工学系研究科とフランスのグランゼコールの1つであるENPCとの協力による修士課程のダブルディグリープログラム
他にも、世界銀行や米州開発銀行でのインターンシップ(いずれも米国・ワシントンDC)や、当学科・専攻の教員主催による新興国(ベトナム、インドネシアなど)でのインフラ建設現場見学会が行われている。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
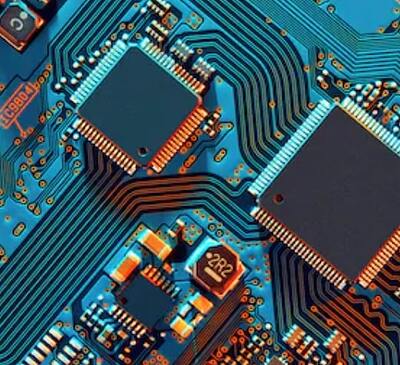
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

国際開発農学専修
【環境資源科学課程】通称「国農(こくのう)」

機械工学科(機械A)
デザイン・エネルギー・ダイナミクス

経済学部各学科
各学科まとめて説明

化学システム工学科
環境・エネルギー・医療




