工学部
マテリアル工学科
2023.4.15
A,B,Cをまとめて掲載
目次
基本情報
| 人数 |
3コース合計で80人程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ1割程度 |
| 要求/要望科目 |
特になし |
| 就活or院進 |
院:就職 = 9:1程度 |
| 公式サイト |
学科概要
■当学科の特徴
・当学科はバイオマテリアルコース、環境・基盤マテリアルコース、ナノ・機能マテリアルコースの3つに分かれているが、別のコースの授業も全て履修可能で、コースで分かれて授業が行われることはない。
・ターム制、週2コマの授業が多い。
・実験が週4コマ行われる3年生Sセメスター、A1タームは相対的に忙しくなる。
・有機材料、半導体材料などを含む材料全般を扱う学科だが、金属工学をルーツとすることもあり、学科図書館のラインナップが金属系に偏っている。
・同じ内容が違う講義で異なる視点から説明されることが多く、多角的な考え方が身に付きやすい。
■各コースの特徴
各コースの指針に従い履修した場合の目標、学習内容は以下の通り。
・「バイオマテリアルコース」では、人工臓器や人工ウイルスなどの新しいバイオマテリアルの創製を目標に、材料学や生命科学を学ぶ。
・「環境・基盤マテリアルコース」では、鉄鋼材料から半導体まで幅広い材料の安全で持続可能な活用を目標に、材料学や設計方法を学ぶ。
・「ナノ・機能マテリアルコース」では、現在あらゆる高機能デバイスに導入されている、原子・分子スケールで設計、制御された”ナノマテリアル”の創製を目標に、材料学や量子力学を学ぶ。
■当学科の諸制度
・2年生Aセメスター以降研究室配属(3年生Aセメスター終了時)までに54単位、必修および限定選択(※)科目で38単位(卒論の12単位を含む)が必要。卒業には95単位必要。
・「マテリアル開講」と題された授業はマテリアル工学科が開講する限定選択(※)の授業のことで、マテリアル工学科のほぼ全員が履修する。
※ 限定選択:工学部一般に用いられる用語。選択必修のこと。
■時間割
マテリアル工学科時間割
※2022年度の必修科目と限定選択科目が、ターム別に記載されている。年度により変更する可能性があるので、シラバスや学科便覧での確認が必須。
■進振りの時に気を付けること
前述の通り、各コースの授業内容や形式に大きな差がなく、コースを跨いで自由に履修できるため、進振りの段階でもコース分けの重要度は高くない。
■進学後の内実は?
学習内容は、材料全般。金属、セラミック、ゲル、半導体など様々な材料を学ぶことができるため、材料分野に漠然と興味がある人だけでなく、やりたいことが決まっていない人にもおすすめの学科となっている。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【材料学の基礎を固める2A】
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 基礎熱力学I | 必修(A2タームのみ) | 火/水2限 |
・週15コマ前後の履修が一般的。
・2Aセメスターでは、各コースごとの授業は存在しない。
・必修「基礎熱力学I」では、1年生Sセメスターの必修「熱力学」の復習を行う。
・他にマテリアル開講(※)の授業が10科目、当学科が推奨する工学部共通の限定選択の授業が3科目ある。
・マテリアル開講の中でも「材料結晶学」「材料統計力学」は講義内容の難易度が高く入念な対策が必要。
・マテリアル開講「マテリアル工学概論」では、コースを跨ぎ、バイオ、環境、ナノに関する問題に焦点を当てた講義が行われる。
・マテリアル開講「マテリアル工学自由研究」は、少人数のゼミ形式で、特定のテーマに対する解決策を議論し、最後に発表を行う。
※”当学科の諸制度”を参照
3年生Sセメスター
■【相対的に授業が多い3S】
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| マテリアル工学実験I | 必修 | 月/木3-4限 |
・週20コマ前後の履修が一般的。
・必修「マテリアル工学実験I」は名物授業で、週2回、4コマの授業で1つの単元を扱う。実験は7人程度の班ごとに行う。レポート提出と全ての出席が必須。走査型電子顕微鏡の使用方法を習得し、持ち寄った試料を観察・プレゼンするコンテストが期末に開催される。
・他にマテリアル開講(※)の授業が13科目、当学科が推奨する工学部共通の限定選択の授業が1科目ある。
・マテリアル開講のうち、「高分子科学I」はバイオコース、「金属材料学」は環境・基盤コース開催の授業。これらの授業も所属するコースと関係なく履修可能。
・マテリアル開講「マテリアルシミュレーションI」では、Pythonの文法の学習や、回帰分析や機械学習の基礎の演習を行う。
・マテリアル開講「マテリアル環境工学概論」では、環境ビジネスや政策など幅広い内容のオムニバス形式の講義が行われる。
・「マテリアル工学実地演習第一」と題された、1単位が取得できる工場見学が夏季に行われる。(コロナ禍では開催中止)2泊3日で参加費用は2万円前後。授業で扱ったプロセスを実際に観察できることに加え、学科内の交流が深められる貴重な機会でもある。
・就活を行う人は1割程度だが、その多くが3年生の夏季休暇に就職活動に励む。
3年生Aセメスター
■【研振りを行う3A】
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| マテリアル工学実験II | 必修(A1タームのみ) | 月/木3-4限 |
・週12コマ前後の履修が一般的。
・必修「マテリアル工学実験II」は、3年生Sセメスターの「マテリアル工学実験I」と同様の形式で行われるが、「II」はA1タームのみで開講される。
・マテリアル開講のうち、「高分子科学II」「分子細胞生物学」はバイオコース、「セラミック材料学」「生産プロセス工学」は環境・基盤コース、「デバイス材料工学」「薄膜プロセス工学」はナノ・機能コース開催の授業。これらの授業も所属するコースと関係なく履修可能。
・A2ターム終了後に研究室振り分けが行われる。研究室振り分けは4Sセメスター開始直前(4月頭)。冬季休業期間(Wセメスター)にほとんどの研究室で見学会が行われる。
・「マテリアル工学実地演習第二」と題された、1単位が取得できる工場見学が春季に行われる。(コロナ禍では開催中止)3年生Sセメスターの「第一」と同様に、2泊3日で参加費用は2万円前後。
4年生Sセメスター
■【院試を控える4S】
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| マテリアル工学卒業論文輪講 | 必修(A1タームのみ) | 3-4限 |
・当セメスターでは、卒業研究、及び卒業論文の執筆と院試対策を主に行う。授業については、3年生までで単位を取りきれなかった場合にいくつか履修する程度。
・必修「マテリアル工学卒業論文輪講」では、卒業論文に関連する内容の論文3本を要約する。
・マテリアル開講「マテリアル工学基礎及び演習」では、院試の過去問演習とその解説が行われる。これに加え、各研究室の過去問のデータも使い演習を行うことが推奨される。
・授業以外では、院試対策に多くの時間を費やすため、就活をこのセメスターに行う人は少ない。
4年生Aセメスター
■【卒論執筆に勤しむ4A】
・殆どの時間を卒業研究、卒業論文の執筆に充てる。卒業論文は12単位分。卒論の提出期限は2月前後。
入る前の想像と実際
・進学前は、材料力学の学習しかできないと考えていたが、実際には材料力学だけでなく、環境問題や生物、計測、安全など様々な内容の学習ができた。また、重要事項は複数の講義で扱うため、定着しやすかった。(理I → マテ工環境)
・材料全般を学べると想像していたが、実際には無機の割合が高い印象を受けた。(理II → マテ工バイオ)
・材料学全般について基礎的な事項を学ぶことができた反面、一つの分野を掘り下げて学習するという機会は少なかった。(文I → マテ工ナノ)
選んだ理由/迷った学科
・金属材料に興味があったのと、有機化学が好きだったため当学科を選択した。(理I → マテ工環境)
・カーボン、半導体に興味があり、工学部化学生命科と迷っていたが、最終的には進振り点の関係で当学科を選択した。(理II → マテ工バイオ)
・元々文系で、1年生Aセメスターの「物理化学」をきっかけに物理系の学科に興味を持った。工学部の物理工学科、電気電子工学科とマテリアル工学科の3つで迷ったが、要求、要望科目の関係から、当学科を選んだ。(文I → マテ工ナノ)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 【6】 |
| LINE | 有 |
| Slack | 有 |
| 学科ドライブ | 有 |
| オフラインでのつながり(※1) | 有 |
| 上下のつながり(※2) | 有 |
※1 コロナ禍以前における授業以外の交流を指す。
※2 過去問の共有等。
・LINEはあまり活発ではなく、授業での資料配布の有無等を確認する程度。
・Slackでは課題や資料のPDFのアップロードや、説明会の情報のリマインドがされる。
・少人数のゼミや実験、工場見学など交流の機会は多い。
・コロナ禍では実験の控え室が主な対面の交流機会。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 80名前後(※) |
| 成績評価 | 出席+テスト |
※ 3コース合同で受講する時の人数。
・3年生Sセメスター、A1タームの実験以外は基本的に座学の形式。
・救済措置としてほぼ全ての授業で出席が取られる。
■成績評価
・成績評価は出席の比重が高い。
・ターム制の授業が多いことからターム末毎に多くのテストがある。過去問を利用した入念な対策が求められる。
研究室・資料
特別な制度・その他
・マテリアル工学科の制度として、マサチューセッツ工科大学(MIT)との交換留学制度(UT-MIT)や、3年生の3月にイギリス、スイスなどの大学のマテリアル工学科を訪問し、学生交流や講義の聴講をするプログラムがある。
・他、東京大学としての海外大学との連携制度については、マテリアル工学科 海外大学との連携を参照。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
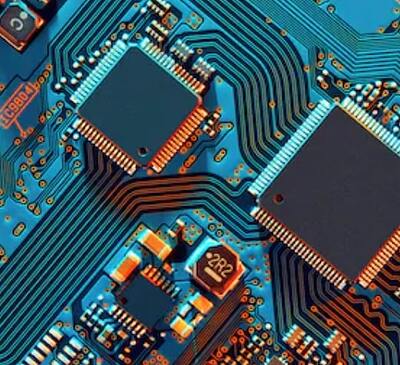
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

水圏生物科学専修
【応用生物科学課程】通称「水圏(すいけん)」

地球惑星環境学科

化学システム工学科
環境・エネルギー・医療

フィールド科学専修
【環境資源科学課程】通称「フィ科(ふぃか)」




