医学部
医学科
2023.4.15
医学科
目次
基本情報
| 人数 |
110名前後 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ1-2割程度 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
他の学部学科と違って後期課程は4年間。 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
医学部の目的は生命科学・医学・医療の分野の発展に寄与し、国際的指導者になる人材を育成すること。医学部は医学科と健康総合学科に分かれており、その中でも医学科は医学知識と臨床技能を修得し、プロフェッショナリズムとコミュニケーション能力を培い、社会的視点を持つ人材を目指す。
授業は主に講義と実習にわかれ、4年生のSセメスターから実習が本格化する。
卒業後は勿論医師として働く人が多いが、中には医療系ベンチャーを立ち上げる人もおり、他大の医学部に比べてキャリアの多様性が見られる。
■医学科の諸制度
・学年の呼ばれ方
2年生はM0、3年生はM1、4年生はM2、5年生はM3、6年生はM4と呼ばれる。
・各学年の進級条件
・教養学部A1、A2、Wタームの専門科目とM1の基礎科目全てを履修し合格すること、M1の実習に合格することがM2の進級条件。(そのうち二科目はM2までに合格すれば可)
・M1、2の必修科目(基礎科目、臨床各科系統講義科目)全て履修し合格し、M2で実施されるOSCE(4Aセメスターにて説明)とCBT(4Aセメスターにて説明)に合格することがM3の進級条件。
・M2、3のクリニカルクラークシップ(※1)、臨床統合講義(※2)、公衆衛生学実習に合格すること、平均概略評価が2.0以上であることがM4の進級条件。
※1 クリニカルクラークシップ:学生が医療チームの一員として実際の診療に参加する、実践的な臨床能力を身に付ける臨床参加型実習。
※2 臨床統合講義:2004年度より行われている本学医学部医学科伝統の特別講義。各日が学生の要望をもとに設定されたテーマについての集中講義の形を取り、最先端の知見に触れ医学の多面的な理解を図る。
M3になるとM2の1月から始まっている実習の続きに入り、M4になると学内・学外の病院で実習を受け、医師国家試験を受験して卒業となる。
卒論はない。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理科Ⅲ(指定科類) | 67 | 33 |
| 理科Ⅱ(指定科類) | 6 | 2 |
| 全科類 | 1 | 1 |
■内実は?
・理3からそのまま進学した学生がほとんど。病院見学や初期研修などを通じて希望の診療科が変わる学生もいる。
・4年生までは必修の講義が大半なので自由にゼミなどを履修できないという声も。
・良くも悪くも万能と思われがち。実際、数学オリンピックの強者や学生起業家、スポーツの全国大会出場者、コンテスト優勝者など、医学以外の何かに秀でている人もいる。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【細胞学と生化学に追われる2Aセメスター】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 統計学 | 集中講義 | 木曜3、4限 |
| 生化学 | 集中講義 | 月曜1、2限 |
| 医学序論 | 集中講義 | 木曜5、6限 |
・組織学の授業では人間の臓器一つ一つをよりミクロに観察する。2Aセメスターの中でも時間的拘束が大きい。
・この授業では、顕微鏡でプレパラートを見てスケッチしていく。細胞の細かな構造を写すにあたりどこまで実際の様子に忠実に描くかという点で画力が求められる。授業後にそのスケッチを先生に提出し、試験日に改めてスケッチブックを持参することが受験資格となる。
・それに比べ、生化学の授業は駒場で開講される「生命科学」の延長というイメージ。代謝や遺伝子の仕組みなどについて幅広く扱う。物化選択は少し苦労するとも言われる。
3年生Sセメスター
■【解剖実習が始まる3Sセメスター】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 微生物学 | 必修 | 火曜1〜3限 |
| 解剖 | 必修 | 火曜4〜6限 |
| 免疫 | 必修 | 水曜1〜3限 |
| 生理学 | 必修 | 木曜1〜3限 |
解剖実習
・3年生の初めから約2ヶ月間行われる。
・毎日午後、日によっては一日中行われる。
・4、5人ごとに班に分かれ、「実習の手引き」と呼ばれるテキストの手順に沿って作業する。
・神経・血管・筋肉がそれぞれどこから発しどこへ向かうのか、互いにどう連携しているのかを表したイラストやフローチャートを用いながら学習する。
・この授業で初めてご遺体を扱うことになるが、組織の中から神経などを丁寧に掘り出していくようなミクロな作業が中心なので、そこまで大きな衝撃を受けるような学生は少ないそう。
・微生物学では細菌やウイルスが人体内にどう侵入するのか、どんな治療法があるのかと言ったことを学んでいく。
3年生Aセメスター
■【生理学に圧倒される3Aセメスター】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 生理学 | 必修 | 月曜1〜6限 |
| 薬理学 | 必修 | 火曜1〜6限 |
| 生理学実習 | 必修 | 水曜1〜6限 |
| 薬理学実習 | 必修 | 木曜1〜6限 |
・Aセメスターに入ると、生理学が重くのしかかる。体内の恒常性といった分野を多様な視点から捉える本講義は内容の広さゆえ苦労する学生も多い。
・学期末の試験では8:30 〜12:30の計4時間、全記述の問題に取り組む。
4年生Sセメスター
■【臨床科目が始まる4Sセメスター】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 外科 | 必修 | 月曜1〜6限 |
| 消化器内科 | 必修 | 金曜1〜6限 |
・今年は全授業オンラインで開講された。
・臨床科目の講義(外科、内科、小児科、耳鼻科、泌尿器科、産婦人科、皮膚科、整形外科、精神科など)の授業が本格的に始まる。
・毎時限ごとに授業をする先生は変わるが、1日中特定臨床科目を教わるという形態が増える。
4年生Aセメスター
■【二つの試験が待ち構える4Aセメスター】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 小児科 | 必修 | 火曜1〜3限 |
| 形成外科 | 必修 | 水曜1〜3限 |
| 耳鼻科 | 必修 | 木曜1〜3限 |
| 眼科 | 必修 | 水曜1〜5限 |
| 放射線科 | 必修 | 火曜1〜6限 |
| 公衆衛生 | 必修 | 木曜1〜3限 |
| 医療情報 | 必修 | 木曜4〜6限 |
Sセメスターに引き続き、臨床科目の講義がほとんどを占める。OSCEが10月、CBTが11月に実施されるため、秋からは本格的なテスト対策に取り組む学生が多い。
※OSCE:「客観的臨床能力試験」。ペーパーテストによる知識重視の教育ではなく、判断力・技術力・マナーなど実際の現場で必要とされる臨床技能(医療診断や身体診察など)の習得を評価する試験。
※CBT:臨床実習に必要な「知識」を問われる試験。毎年コンピューター上で行われる。
上記二つに合格しないと5年から始まる臨床実習に参加できない。
■【実習を通して実践的に学ぶ5年生】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 臨床実習 |
臨床実習(クリニカルクラークシップ)が始まる。小人数(6~7人)単位に分かれ、1~3週間の期間、それぞれの臨床科に配置される。病棟で入院患者を受け持ち、診察や診断、あるいは外科手術も含めた治療法を診療チームの一員として体験する。
■【国家資格試験を控えた6年生】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 臨床実習 |
・5年6年の間に最低2ヶ月間、エレクティブクラークシップと呼ばれる自由選択期間がある。学生の希望によっては外部病院あるいは海外の病院で行うこともできる。
・卒業前の2月上旬には医師国家試験がある。
入る前の想像と実際
・工学部のように課題やレポートが沢山出るわけでもなく、周りに言われるほど大変でもない
・暗記メインの勉強なので受験勉強の延長と捉えてひたすらやるしかない
・4Sまでは想像以上に実習と比べて講義(座学)が多い
選んだ理由/迷った学科
・数学が好きだったので理学部に進学することも考えたが、進振り点と将来のキャリアを考えてやはり王道の医学部を選んだ。(理3→医学部)
・入学した際は、薬学部で創薬研究をしたいと思っていた。駒場で薬学部や医学部主催の授業を受けていく中で、創薬の中の薬を創る方よりも、もっと病気の根本的なところを研究していく方に興味を持ち、そこで初めて医学部進学を検討し始める。最後まで薬学部と医学部とどちらに出すか迷ったが、医学部に出すだけ出してダメだったら薬学部というくらいの気持ちで進振りに臨み、無事内定を獲得した。
(理2→医学部)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
4 |
| LINE | 有 |
| Slack | 有 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
・学科LINEは機能している。シケプリ等の情報共有、何かしらの宣伝が多い。
・学科Slackは存在するが、ほぼ機能していない。
・オフラインでは、医学部のコンパが数回開催されたことはある。
ただ、人数が多いこともあって全体で集まることは稀。
・オンラインでは、Among Us(流行りのゲーム)をするためのLINEグループが作られるなど、むしろ以前より交流が増えたかもしれない。
・部活内での結束はどこもある程度強い。医学部医学科の3分の1程度が鉄門に在籍。上下関係はそこまで厳しくない。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 100名前後 |
| 成績評価 | 出席はほぼ取らず、期末試験とレポートで決まる |
・優秀なしけたい、膨大な量の過去問や資料を集めたデータベースが存在する。
・過去問対策をすれば容易に点を取れる科目もあれば、毎年予測できない科目も。
・基礎医学は臨床医学に比べて良い成績を取りにくい。
・1講義あたりの学生数が多いため、授業内で教授と学生が交流する機会はあまり多くない。
・学科全員で受ける授業がほとんど。他学部合同や、自由選択の講義はあまりない
研究室・資料
特別な制度・その他
・MD研究者育成プログラム:6年間の学部教育を修了してから研究生活(大学院)に入ると研究のスタートが遅れるとの懸念から、学部生の時から最先端の研究現場に身を置いて、研究者の考え方を身につけようというプログラム。M1の時期から基礎研究室の一員として研究に参加し、実験方法や研究姿勢を習得したり、英語での論文作成やディスカッション・スキルの訓練などを通して、基礎医学研究者としての姿勢の獲得を目標とする。通常の6年間の医学教育と並行して進められる。
・臨床医学者育成プログラム:臨床医学領域での研究についてその重要性を学んでもらうことを目的とし、MD研究者育成プログラムと並行して運営されるプログラムの一つ。 現在はレクチャーシリーズと臨床研究個別プロジェクトコースが用意され、レクチャーコースは毎週定期的に開催され、臨床研究個別プロジェクトコースはそれぞれの研究領域を推進している複数の臨床科や講座の教員で構成するコンソーシアムで運営される。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

医学部
生命科学・医学・医療の分野の発展に寄与し、国際的指導者になる人材を育成する学部
関連記事
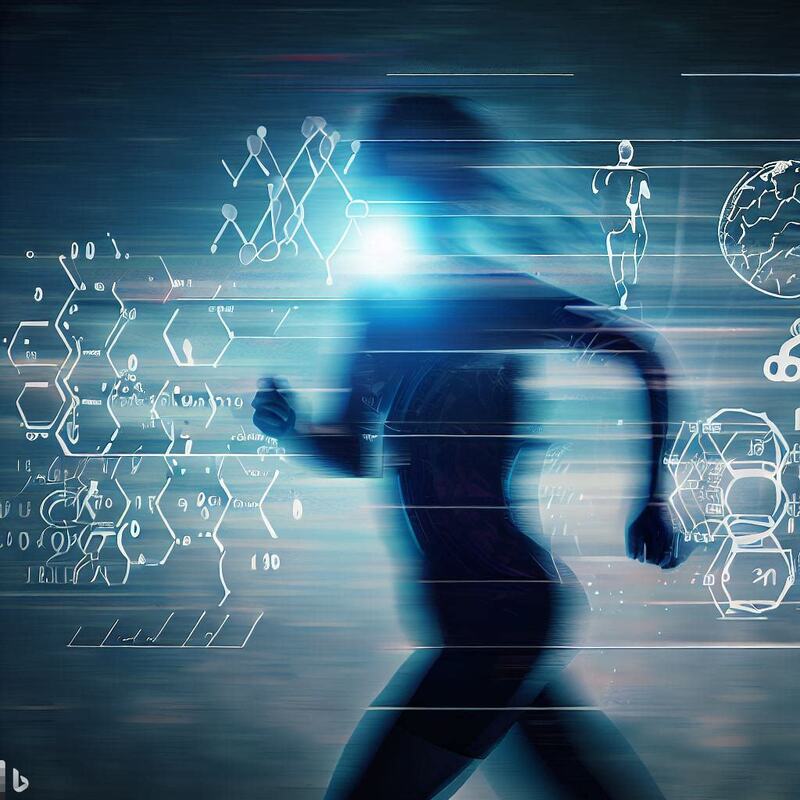
統合 スポーツ科学コース
2023年度の進学選択より正規コースとなった統合自然科学科スポーツ科学コース

薬科学科 薬学科(両学科)
"くすり"を中心に、「物質」「生物」「医療」の観点から生命科学の教育・研究を行っている学部。

健康総合科学科
環境生命科学専修・公共健康科学専修・看護科学専修




