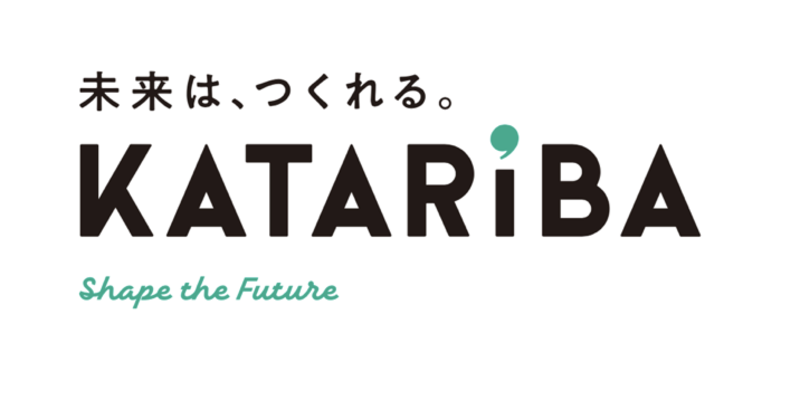■企画概要
東日本大震災と福島第一原子力発電所事故から14年が経ちました。原発事故により長期避難を余儀なくされた福島県双葉郡は、社会経済基盤に大きな打撃を受けました。かつてメディアで報じられた、廃墟のようになった街並みの記憶が残っている方も多いかもしれません。
その後、除染や生活基盤の再建が進む中で、新たな産業の創出を目指したさまざまなプロジェクトも展開され、地域の「復興」に向けた取り組みは着実に進められてきました。
一方で、人々の暮らしや生業の「復興」は、依然として道半ばです。人口の回復が進まないほか、医療・介護・福祉、買い物、教育といった日常生活に欠かせない環境にも、多くの課題が残されています。
福島の復興は、その規模の大きさや複雑さゆえに、外からはなかなか見えにくい側面があります。廃炉やALPS処理水といった大きな話題に注目が集まる一方で、地域で暮らす人々の葛藤や日々の積み重ねは見えづらくなっているのが現状です。
本プログラムでは、現在も帰還困難区域が残る浪江町、双葉町、大熊町、富岡町を訪れ、自治体、住民の方々、地域の事業者への聞き取りや参加者同士の議論を通じて、この地域における復興の過程をあらためて捉え直すことを目指します。
「復興」とは何か。その現場では、どのような歩みが続けられ、そこにどのような願いや想いが重ねられているのか。地域で暮らす人々の言葉や行動に直接触れながら、地域の課題や可能性を探究します。
■プログラム構成
・浪江町、双葉町、大熊町、富岡町の4町を対象に、現地視察および現地の方々へのヒアリング調査を実施
・上記をもとに、参加者同士で議論を行う
・議論の成果を自治体の方々などにフィードバックする