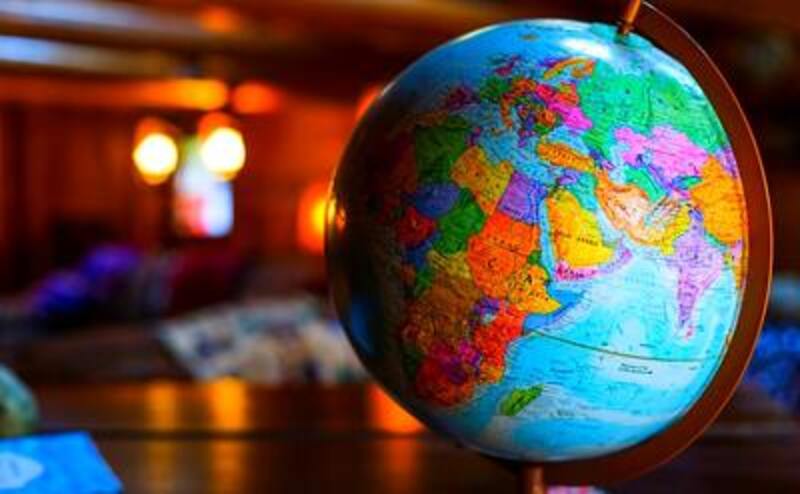日露学生会議
#ロシア
#ソ連
#国際交流
#JRSC
2023.4.18
「日露の架け橋たらん」をモットーに、毎年夏に日露の学生会議を主催する。
目次
基本情報
| 執行代 | 特に決まっていない |
|---|---|
| 人数 | 日本人学生約15名、ロシア人学生約15名 |
| 参加学年 | 学部生+院生 |
| 選考情報 | 選考あり |
| 年会費 | 13500円(本会議がオンライン開催の場合。ロシアに渡航する場合は変更する可能性も) |
| 活動頻度 | 夏休みの期間に、2週間に本会議(概要を参照)を開催。本会議に向け事前勉強会やフィールドワークも。 |
| 公式サイト |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
民間交流の先駆けとなる、「日露の架け橋たらん」を大きなテーマに掲げている。また、日本人のロシアに対するイメージは良いものばかりではないが、それが必ずしも正しいとは限らないのではないかという問題意識を持っている。ロシアに対し、正しい見方が広まるような活動をしていくために、学生という立場から、文化交流だけでなくロシア人と議論を深めることも大切にしている。
■活動内容 ※2022年度の情報
《ビフォーコロナ》
1年に1回夏休み、日本人とロシア人の学生の議論、交流の場である「本会議」を2週間かけて行なっていた。本会議における議論の内容は毎年変わり、3つの分科会ごとにテーマが決められる。例えば、領土問題を扱う「政治経済」やジェンダーを扱う「カルチャー」などがテーマとして存在した。なお、この際のやり取りは全て英語で行われる。
本会議後、まず次年度の運営委員を参加者から選出する。広報や渉外活動を進めつつ、5月ごろには次年度の参加者の募集を開始。参加者が確定した後は、週に1回の勉強会を開催。本会議で話したいテーマについての本を読むなどして、ゼミに近い活動を行う。コロナ前は対面開催だったので、隔年でロシアと日本が交互にホストを務めていた。また、コロナ前は、シベリア抑留者の方にお話を聞いたり、国立環境研究所を訪問したりする対面でのフィールドワークや合宿も行っていた。
《アフターコロナ》
今年は初のオンライン開催であり、日本側がホストとなった。対面ではフィールドワークなどの観光、お楽しみの要素が例年あったため、今年は日本側が観光名所を撮影してロシア側に見てもらう「バーチャル観光」を催したり、アイスブレイクに力を入れたりと工夫した。また、2020年度は環境分科会があり、SDGsに関するテーマで開催したという点も環境問題の話題性を反映していると言える。
■OBOGの進路/活動
〈進路〉
省庁や商社など進路は多様。外務省にOBOGがいて、講演などをしてもらうことも。なお、日露学生会議に参加するロシアの学生は外交官やジャーナリストをはじめとした日本とも関わることが多い国際的なエリートになる傾向にある。
メンバー構成
人数
参加者、実行委員含め、定員は日本側からは15名。実行委員と参加者の壁はなく、実行委員も参加者として参加する。
学年
年によって変動あり。
執行代
バラバラ
ジェンダーバランス
女性はおよそ5割
加入時期
参加者募集:2月ごろ〜4月ごろ
属性
・ロシア語を専攻する学生もいる一方で、ロシアやロシア語に馴染みのない、医学部、理系の学生なども参加。
・東大、上智、早慶など大学も多様。
・メンバーの活動は多様。体育会やオーケストラなどの活動をしている人もおり、両立はできる。むしろ、他の団体に入っている人の方が多い。
離脱率
基本的に0(入会時に1年間所属するのが原則と伝えられる。)
活動実態
活動頻度
広報や渉外活動を行う時期は週に1回1時間会議を行う。本会議までの期間は、運営メンバーと参加者が一体となって分科会ごとに勉強会が週に1回実施される。これに加えて参加者は、本会議だけでなく、月に1回ほどのフィールドワークにも参加する。
年間予定
12月~3月 本会議企画・広報活動
1月~2月 参加者募集・応募期間
2月~3月 選考会
3月頃 参加者決定
5月~7月 勉強会
8月頃 本会議
10月頃 報告会(協賛する財団向け)
募集情報
選考あり/選考なし
考あり
募集対象:
大学生・大学院生・専門学生
実際に入会する人:
東大・早慶・上智・外語大等の学部生がメイン。
今年は中央大・法政大の参加者も。稀に大学院生も参加。
入会手続き内容:
公式LINEに登録して、説明会に参加。興味のある人はエントリーシートをその後提出(1次選考)し、面接選考(2次選考)を通過すれば参加者として内定する。
内部のホンネ
○魅力
・団体が小規模であるため、様々な仕事に関わることができる。またそれゆえに、自分の得意なこと、能力を活かし、柔軟性を持って仕事を行うことができる。
・様々な所属の友人ができ良い刺激を受けられる。
△大変なところ
・ロシア人と連絡を取り調整を行うところから、年間の活動の締めである報告会まで一貫して活動を行うという点は大変ではある。
・コロナ禍において、ロシア側とオンラインミーティングだけで意志疎通し認識を合わせて進めていかねばならず、文字でのやりとりが大半を占めるので互いの認識に齟齬が生じる場合がある。
・活動支援金を頂いている財団へ明確に企画を提示する必要がある。他者に納得してお金を出してもらうために、どう説明すればいいのかは、腕の見せどころでもある。
新歓日程詳細
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル

KIP 知日派国際人育成プログラム
「『日本知らずの国際人』から『知日派の国際人』へ」を掲げ、学生・若手社会人で討論を行う会員制グループ。

茶話日和
多様な人々との交流・対話を通じて、東アジアの人・生活・文化を伝えるメディア。
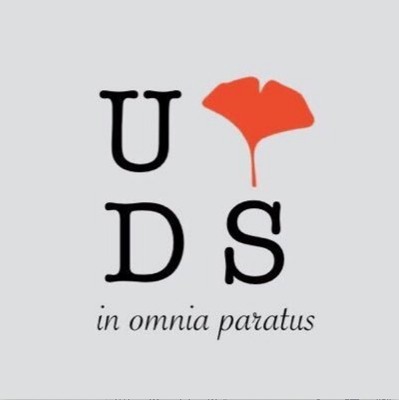
UTDS(東京大学英語ディベート部)
普段の練習や大会参加を通じて英語即興ディベートに取り組む。

東京大学 E.S.S.
東京大学の学生によるサークルで、主に駒場で英語を使った活動をしている団体。