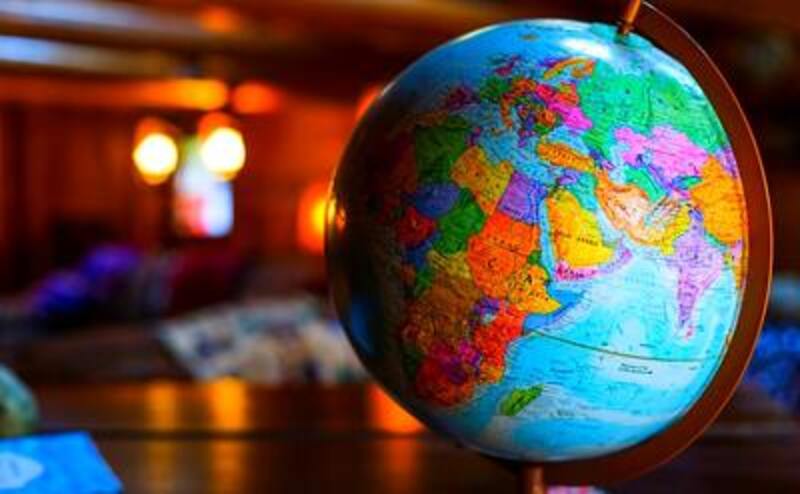AFPLA
国際交流
日中韓台交流
政治
東京大会
議論
国際問題
経済
2025.12.6
東アジア(日中韓台)の学生が集まり、社会問題を議論する国際会議を年1回開催する学生団体。
目次
基本情報
| 執行代 | 2年生がやることが多いが、3,4年生が運営に参加する年も |
|---|---|
| 人数 | 25名が一般的 |
| 参加学年 | 学部生のみ |
| 選考情報 | あり |
| 年会費 | なし ※別途渡航費、宿泊費等が自己負担。一部補助がある可能性があり。オンライン開催の場合はなし。詳しくはお問い合わせください |
| 活動頻度 | 週1回のペースで分科会ごとに勉強会 |
| LINE | |
| 公式メアド |
afpla.utokyo[a]gmail.com
([a]を@にしてメールを送信してください) |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
AFPLAは、東アジア日中韓台の5大学(東京大学、北京大学、復旦大学、ソウル大学校、国立台湾大学)の学生が毎年夏一堂に会する国際会議を開催する団体。 2007年に北京大学とソウル大学によって設立され、第4回大会の開催された2011年以降、東大が正式に参加して現在に至っている。
会議では歴史や社会など東アジア共通の様々な議題を扱い、夏の会議まで各大学で勉強会を開いて準備する。学生同士だからこそ自由で熱い議論ができ、議論の外では将来の東アジアを担う青年間の繋がりを築けることがAFPLAの魅力。2020年、2021年は新型コロナウイルスの影響を鑑み会議はオンライン開催とした。2022年度は2021年に引き続きオンライン開催。コロナ禍を乗り越え、2023年は上海、2024年はソウル、2025年は東京で開催した。
■活動内容
主な活動は、8月に行われる国際会議の本大会とそれに向けて5月から7月にかけて行われる準備である。
準備期間には、週1回程度分科会ごとに勉強会を開き、各自リサーチを進めたり英語ディスカッションを開催したりしている。6月には東大内で中間報告会を行い、進捗を報告し合う。そして、本大会では各大学の分科会ごとに調査・議論した内容を元に、5大学の学生によるセッションが複数回実施され、最終的な議論の内容を形作っていく。また、本大会中には大学間のメンバーが横断的に交流する機会も設けられている。本大会終了後から次の年の4月にかけては、本大会の報告書の執筆、打ち上げ、そして運営に携わりたい人は来年度の大会の準備と新歓期の準備を始める。
2023年夏は、復旦大学主催で上海での開催となり、実は4年ぶりの対面開催のAFPLAとなった。本大会では、各大学の分科会メンバーが自分の成果を報告し、自由に議論をすることがメインイベント。他にも、culture nightというイベントがあり、各大学が自国の文化を代表するようなパフォーマンスを行う。本大会では英語の議論と発表がメインとなり、多少疲れを感じる人もいるが、culture nightや他大学のメンバーと飲みに行くことなどを通じ、リラックスすることができるとともに、他大学のメンバーとの交流がより密になった。
■OBOGの進路/活動
外資、政府系機関に就職する人は多い。院進する人も一定数いる
メンバー構成
人数
・例年は5人×5分科=25名が平均的
学年
・1、2年が多い。
・2、3、4年で加入するメンバーが他の国際系サークルと比べ多い。選考において、学年に応じて重みづけ(1年生有利)は行わず、フラットに行う。
・引退という概念はなく、毎年の本大会ごとにメンバーが集うイメージ。1年間のイベントごとに「期」で数えて表記している(例:2018年~2019年に参加し、2020年も大会に参加する学生は、AFPLA12期であり、13期であり、14期でもある)。なお、一度加入したら次年度に再度選考を受ける必要はない。
執行代
立候補制をとっており、様々な学年のメンバーが役職を担っている。原則2年生だが、一部の役職を3,4年生が行う場合もある。
体制
代表・副代表、分科会リーダー5名に加えて、渉外・会計・新歓担当を設置。後者3つの担当者は分科会リーダーとの兼任が可能である。
ジェンダーバランス
女性はおよそ5割
加入時期
新1年生の加入が多いが、2年生以上の入会もある。新歓は春のみ行う。
属性
・文一・二が多い。
・文三も在籍。
・理系は現状少ないが、文理問わず大歓迎。
・法学部3類の演習の一環としてサークル化した経緯もあり、政治系に関心を持つ学生が多い。それ以外の分野に強い関心を持つ学生も。
・国際関係論コースに進む学生が最近多め。
・運動会に入っている人(少林寺拳法、応援部など)も在籍。
・国際系サークルとの兼サーは多い(HCAP,京論壇,TGIFなど)。
※ 他サークルや部活をやっている人でも両立できるところは推しの一つ。
離脱率
10〜20%。8月の本大会まではしっかりとコミットする人がほとんどだが、それ以降の活動については人による。1年生から3年生までは続ける人が多い印象。
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
およそ10%~20%
メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?
多少はある
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
多少在籍している
活動頻度
通常活動
・週1回のペースで分科会ごとに勉強会。
・プレゼンや議論を進めるために中間報告会や英語ディスカッションを開催。
・本大会終了~翌年4月にかけては、本大会の報告書の執筆、そして運営に携わりたい人は来年度の大会の準備と新歓の準備を進めていく。
コンテスト/イベント前後の期間
本大会直前期(8月上中旬頃)は準備の為忙しくなる。
年間予定
4月:春新歓
4月末:選考→合格通知
5月上旬:分科会メンバー初顔合わせ、勉強会開始※1
5月:他大学との事前交流会(予定)
6月中旬:中間報告会
7月:他大学との事前交流会(予定)
8月10日-16日:本大会※2
9月:執行引き継ぎ
2月:リーダーズミーティング
Aセメは特に予定はなし。次年度に向けて運営準備等
※1 中間報告会・本大会に向けて、プロポーザルに対してどのように議論していくか準備をしていく。中間報告会はその中間報告を行うもの。
※2 本大会では、5大学での懇親会も開催。
4〜7月の勉強会は対面中心の予定。一部オンラインイベントの可能性もあり
8月の本大会については韓国での開催予定。
募集情報
選考あり/選考なし
あり
募集対象:
全学年
実際に入会する人:
全学年
入会手続き内容:
・選考方法:4月くらいまでに応募フォームを記入し、4月下旬までに面接を行う。
・面接は4月下旬。例年は4月末までに合格通知が送られる。
・人数等を考慮しつつ、AFPLAの求める選考基準に照らして選考を行う。
選考結果がメールで通知された後、合格者はその後全体の顔合わせに参加することになっている。
内部のホンネ
○魅力
・あったかい人が多い(治安の良さについては東大一の自信)(先輩後輩の垣根が低い、中の人間関係が非常に極み)、いろんな進路の人がいる。
・みんな寛容でat homeな雰囲気。
・みんな優秀、国際系の交流とかが初めての子もいるけれど、頑張っている。
・日中韓台の5大学、大規模、特に台湾とのチャネルを持っている団体はこの団体のみ。
・日中韓台の5大学の優秀な学生と交流を深めることで、新たな視点を得、自らの価値観を相対化できる。簡単に言えばめっちゃ刺激になる。
・学術的な交流だけでなく、文化面でも交流が盛んである。
・同世代の学生だからこそ、共通の話題で自由な議論を楽しめる。
・なんだかんだ英語できる人が多い上、英語力強化も図ることが可能である。
・留学生が一定数入ってくる。
・自分の努力次第で成長度合いも大きくなる。
△大変なところ
・取り扱うトピックは単純ではなく、ある程度しっかりと勉強会にむけて準備をする必要がある。
・帰国子女も多く、英語のディスカッションに慣れる必要がある。
・みんな忙しく、勉強会等の予定が合わない(他で活動している学生が多い、バイトとか兼サー先とかインターン先とか起業とか留学生帰省とか)。
・海外の他大学と議論の進め方を調整するのが難しい。
新歓日程詳細
春(サーオリやut-baseの新歓イベントなどに参加する予定)
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル
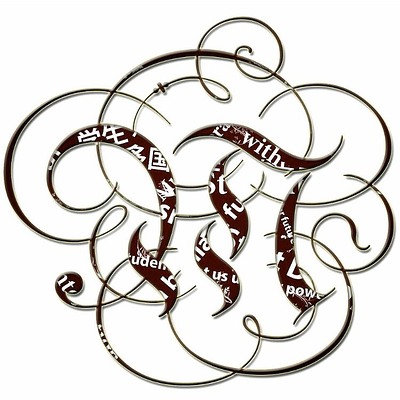
MIS
日本・ASEANの学生が集まり社会問題を議論する国際会議と現地プロジェクトの実施を行うNPO法人。
東京大学SDGs協創学生アライアンス(UT-SCSA)
SDGsに関連する異なる分野を扱う5つの学生団体の集合体。
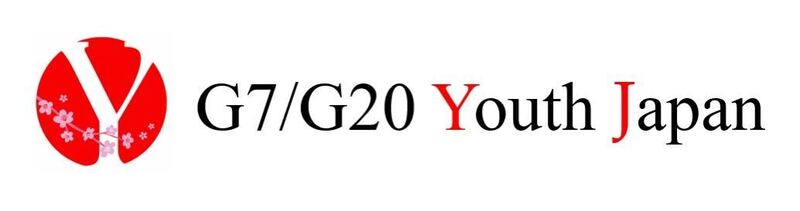
G7/G20 Youth Japan
G7/G20サミットの30代以下の若者を対象とした公式関連会議「Y7/Y20サミット」の運営や、官公庁/企業との協業を行う団体。

日米学生会議
日本最古の国際的な学生交流団体。日米の学生が共同生活を送り、英語で議論をする。