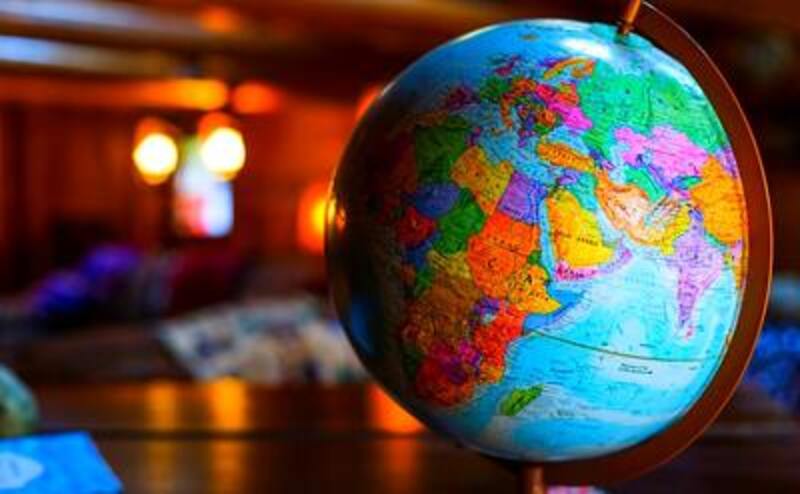日米学生会議
学生会議
日米関係
日本最古の学生団体
英語
共同生活
jasc
インカレ
議論
国際交流
海外研修
2024.12.2
日本最古の国際的な学生交流団体。日米の学生が共同生活を送り、英語で議論をする。
目次
基本情報
| 執行代 | 過年度の参加者から運営は選出 |
|---|---|
| 人数 | 参加者側は28名。 運営側は8名 |
| 選考情報 | あり |
| 年会費 | ・無し ・活動がオフラインの場合、アメリカ開催の時は30万円ほど。日本開催の場合、18万円ほど。宿泊費や実地体験などは大学や自治体が一部負担。これらの金額には、夏の3週間の本会議だけでなく、春合宿の費用も含まれる。 |
| 活動頻度 | 週1回で分科会ごとにオンラインミーティング |
| 公式サイト | |
| 公式メアド |
広報:jasc77.promotion[a]gmail.com 選考:jasc77.selection[a]gmail.com 全体:jasc77.official[a]gmail.com
([a]を@にしてメールを送信してください) |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
日米学生会議は、日本初の国際的学生交流プログラム。「世界の平和は太平洋にあり、太平洋の平和は日米間の平和にある。その一翼を学生も担うべきである」という理念の下、1934年に発足した。本会議では、日米両国から同数の学生が約一ヶ月にわたって共同生活を送りながら議論や活動を行う。会議全体を通して、日米両国の参加者間の相互理解を深めていくことを目的としている。参加者には、会議で得た成果を長期的に社会還元していくことを期待する。※詳細は日米学生会議公式HPを参照。
■活動内容
参加者側は、2~3月に選考を受け、そののちに春合宿や様々な研修を経たのち、夏の本会議(例年7月後半~8月中旬のどこかの期間)に参加。本会議では、日本側36名、米国側36名、合計72名の学生が約1ヶ月間に亘って寝食を共にしながら、それぞれのテーマに関する議論を深める。
分科会における議論、本会議でのフィールドトリップ、文化体験並びに講演会や現地学生との討論、各サイトでのフォーラムを通じて、各々のトピックについて、また日米関係について考える。2023年度は日本(京都、長崎、東京)、2024年度はアメリカ(ロサンゼルス、ニューオーリンズ、ワシントンDC)で開催。2025年度は日本(京都、大阪、熊本、東京)で開催予定。
■OBOGの進路/活動
〈進路〉
外交官、金融、コンサル、商社、裁判官、大学教授、メディア、医師、航空会社。海外志向は強め。
〈諸活動例〉
HLABという教育系ベンチャーは、10年前の日米学生会議でその構想が生まれた。
OBOGとの交流の場は年に5回ある。OBOGの講演会がしばしば開かれたり、毎年春合宿でOBOGとの交流の場が設けられたりするなど、同窓会組織が強い。
メンバー構成
人数
参加者側は28名。
運営側は8名
学年
年によって構成は変わる。学年・年齢が違うメンバーどうしの関係もフラット。
執行代
1年目の後半から2年目の前半にかけて執行代を担当。基本は1年間務めた後、引退する。
本会議中に参加者の中から次の実行委員が選出される。参加者が実行委員として活動を続けるかどうかは基本的に立候補。候補者が多ければ、選挙となる。
体制
実行委員長、副実行委員長=向こう側のそれと情報交換。
主役職:財務担当と選考担当と広報担当
副役職:春合宿担当ほか行事ごとに担当をもつ。
主催団体が一般財団法人、事務局の人と渉外を行う。実行委員長が基本同行。
ジェンダーバランス
女性はおよそ5割。特に選考で調整はしない。
加入時期
3月。加入する学年は学部1年生〜院生までバラバラ。
属性
・帰国子女⇔非帰国:4:6。
・本校生徒の参加経験あり。
そのほか早慶や関東圏の大学、それに限らず京大、名大、北大、九大等北海道から九州まで日本全国から学生が集まっている。
・OBOGの著名人には、宮澤喜一、茂木健一郎、橋本徹、キッシンジャー、大宮透、原田曜平 岩澤 雄司 高田修太など。
・就職先は大企業が一般的。
・60回(2020年度が72回)以降のOBOGではベンチャーで起業している人もいる。
※年によって変わるので参考程度までに
※注意点
・運営側は、学生会議中に、日米それぞれ8名が執行代として選出。
→立候補者がエッセイやスピーチをしたのち、選出に関わる質問がなされる。
・2年以上参加者として参加することはできない。
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
0%
メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?
ほとんどない
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
全くいない
活動頻度
通常活動
・週1回で分科会ごとにオンラインミーティング。分科会は4名ずつ。
・春合宿には参加必須(自主研修・勉強会・安全保障研修は任意参加)。
コンテスト/イベント前後の期間
基本毎日。
年間予定
通年はこのようなスケジュールで行われる。申込年度では異なる場合があるので、参考程度に参照のこと。
12月~2月:応募、一次選考(書類選考)
3月:二次選考(個人面接・教養試験)※オンラインで実施
4月上旬:合格発表、28名が選出。
4月~7月:7つの分科会に分かれて、週1回のオンラインMTGや勉強会によって本会議に向けた準備をする。
5月上旬:春合宿(2泊3日)(東京のオリンピックセンターにて開催)
6月上旬:防衛大学校研修
7月上旬:自主研修(2023年度は台湾、2024年度は韓国)
8月:本会議(2024年度は8/3-24、運営側の選出も行われる)
募集情報
選考あり/選考なし
選考あり。
2024年度11月時点で大学・大学院・短期大学・専門学校に在籍する学生(正規留学生可)を募集。加入メンバーは1,2年生が過半数を占める。年によって構成は大きく変わる。
募集対象:
全国の学生全般。学年も大学も問わない。
実際に入会する人:
学部2年生が多め。大学がばらばら。
入会手続き内容:
一次選考(書類選考)(2月上旬までにES提出)。
→二次選考(個人面接・教養試験(英語も有))(3月上旬に東京・京都で開催)。
→4月上旬に合格通知。
※各種英語能力試験も一次選考の参考資料とするので、スコア提出が原則必須。未受験者は、大学教授による推薦状と授業成績の提出など特別措置を行うため選考担当メールアドレスに要連絡。なお、TOEIC満点など非常に高い英語能力が必須というわけではない。
※運営側は、7月下旬~8月上旬の本会議の後半に設けられたタイミングで立候補。
内部のホンネ
○魅力
・普段は簡単に流すような話題を真剣に話す環境。
・分科会には専門的な知識の有無に全く拘らず議論に参加しやすい雰囲気。
・自分の意見を英語で伝える能力が身につく。
・OBOG(アラムナイ)との縦の繋がりが強い。アラムナイコミュニティの集まりは「サロン」と呼ばれる。春合宿に参加するアラムナイも。
・自分がいるコミュニティ以外で、普段とはまったく違う刺激を得ることができる。
・防衛大学校研修では、防衛大学校生との会話を通じて、安全保障について身近に感じることができる。また、安全保障と教育とジェンダー観について、自分たちとは異なった意見を持つ人が多く、それらの問題について問い直すきっかけになる。個性を重視した教育が歓迎される世の中に対し、集団教育の防衛大学校の風土を見て、さまざまなことを考えさせられることもあった。
△大変なところ
・参加者自身がすでに忙しい場合、キャパってしまう人も。
・3週間ずっと英語で話し続ける環境をハードに感じる人も。
・分科会の配置においては、分野に対する様々な意見に触れ、新しい気づきを得ることを重視しているため、必ずしも分科会の分野に明るい人のみというわけではない。
新歓日程詳細
2024年度の新歓活動は終了。例年の新歓時期は11月〜12月頃。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル

GNLF
約10カ国30名規模の国際会議を企画・運営し、議論や文化交流を通じて国際交流を行うサークル。
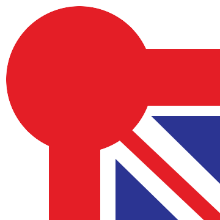
日英学生会議
日本・英国の学生が集まり社会課題について議論を行う会議を開催する学生団体。
東京大学SDGs協創学生アライアンス(UT-SCSA)
SDGsに関連する異なる分野を扱う5つの学生団体の集合体。

FSF (Friends without borders)
留学生と一般学生の交流を当たり前にすることを目指し、イベント開催やコミュニティ運営を行う学生団体。