
東京大学語学愛好会
言語
言語学
語学
2024.3.28
言語に興味のある人が自主的に集まり学ぶサークル
目次
基本情報
| 執行代 | 特に定まっておらず、やりたい人が自主的になる |
|---|---|
| 人数 | 20−30名 |
| 参加学年 | 学部生+院生 |
| 選考情報 | なし |
| 年会費 | 無料 |
| 活動頻度 | ゼミによるが、基本的には週1回 |
https://www.instagram.com/ut.glossophilia?igsh=MWR6czRjdGZhMmIycg== |
|
| 公式サイト |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
去年までは活動が凍結していたが、2023年度から活動が再開。参加者が自分の興味あるテーマでゼミを立ち上げ、そのゼミに参加する他の参加者とともに自主的に勉強を進めていく。このようなゼミのまとめとして立ち上げられた、コミュニティの様なサークル。
■活動内容
ゼミ活動
基本的にはゼミ単位で活動しており、誰でも新たなゼミを立ち上げ可能。テーマ、形式、頻度は全て自由に決められる。学期中だけなく、休み中にだけ集中的に行うゼミもある。ゼミを立ち上げるにあたってのガイドラインはあるが、規則ではなくあくまで参考資料として活用されている。言語に関わっているものならテーマは自由。アンケートでゼミのテーマを募集することもある。
2024年3月20日時点で実施されているゼミの例:
特殊相対論原論文ゼミ
アイシュタインの論文をドイツ語で読み、文法についても触れるゼミ。担当者を割り振って予習して発表する形で進める。成果が保存され、ドイツ語だけでなく物理学の知識も身につく。参加者にはドイツ語未習の人や文系の人もいて、自分の読み方を他人の読み方で客観視できる。週1の頻度で、駒場キャンパスにて対面で行われる。
日葡辞書・日本大文典ゼミ
1603年長崎にて初めて出版された、初めての日本語ポルトガル語辞典を読むゼミ。日本大文典は、その翌年に出版された文法集である。
中には日本語の単語の意味がポルトガル語で解説されているものもあり、安土桃山時代の日本語を知る上で貴重な資料となっている。例えば、「あばけもの」など、当時使われていた言葉や発音がわかる。読解を通して古い時代の資料を原典のまま解読できるようになり、文字が消えたり綴りが違ったりすることにも慣れる。隔週の木曜6限に対面で開催された。
伝奇集ゼミ
スペイン語で書かれた小説集『伝奇集』を読む。全てオンライン行われる。文章の全体的な構造を読み解き、全訳、単語注などを書き込みながら進む。
印欧祖語ゼミ:印欧祖語(英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、ヒンディー語などヨーロッパからインドまで広い範囲に分布する多くの言語の共通祖先の言語)についての言語学の英語の教科書を輪読する
古典ギリシャ語ゼミ:古典ギリシャ語を基礎から学ぶ
韓国語小説購読ゼミ
過去に行われたゼミ:
・旧約聖書原文を読むゼミ
・ドイツ語ゼミ:ドイツ語を基礎から勉強する
・自然言語処理ゼミ:自然言語処理(自然言語の文をコンピュータで解析する技術)についての教科書を輪読する)
・JOLのための勉強会:毎年12月に開催される日本言語学オリンピック[注:20歳以上・大学生以上もオープン枠で参加可能]に備えて集まって過去問を解いて説明し合う勉強会 ※2024年冬も実施するかもしれません
これから実施予定のゼミ:
・低地ドイツ語初級ゼミ
・アイヌ語ゼミ
定例会
具体的なテーマがあるゼミではどうしても似たような興味(言語や分野)を持っている人としか知り合えないことが多い。そのため、異なる興味を持つ人たちとも交流できる機会として設けられている。一、二ヶ月に一度の頻度で基本的に対面。前半はサークル運営、学祭などについての話し合いで後半は雑談。
様々な国からのお土産を分け合うこともある。
公式ウェブサイトにてメンバーが書いた言語学・語学に関する記事(おすすめの勉強法、好きな言語の紹介など)を掲載する、言語学・語学活動を広めていく活動を行なっている。**
学祭
駒場祭・五月祭では、メンバーの書いた記事を集積した会誌を販売する。記事は誰でも書くことができ、掲載もできる。
2023年の駒場祭では言語解読企画を行った。
総じて言えば、参加が必須の活動はなく、メンバーそれぞれが自分自身の興味に合わせて活動に参加しているため、かなり自由度が高い。*
メンバー構成
■メンバー構成
人数
Discordには約170人が入会しているが、アクティブメンバーは20-30名前後。
学年
学部1年生から博士課程の院生まで在籍している。また、高校生メンバーも少数ながら在籍している。
執行代
ゼミや学祭での企画を出したい人が自主的に担当する。
ジェンダーバランス
女性は約2割
加入時期
年間を通して募集している
属性
言語学の知識がなくても入ることができる。
初心者大歓迎なので、知らない言語でも0から勉強できる。
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
離脱する人はあまりいない。
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
語学に興味があって積極的に活動しているので、普段から活動に参加しているメンバーがほとんど。
活動頻度
通常活動
活動頻度はかなり自由度が高く、全員参加必須の活動はない。
ゼミは基本的に週1の頻度で行われるが、具体的な頻度と曜日はゼミごとに決まっている。参加条件はなく、途中からの参加や一回だけの見学や、複数のゼミへの同時参加は可。
加えて、言語について楽しく語り合う定例会は月1の頻度で行われる。
コンテスト/イベント前後の期間
駒場祭、五月祭の前後は出展の準備のため多少忙しくなる。
年間予定
募集情報
選考あり/選考なし:
なし
募集対象:
言語・語学に興味があれば誰でも参加可能
実際に入会する人:
東大生だけでなく他大生も。
アクティブメンバーに理系が多い。
様々な言語を学んでいるメンバーが多い。
入会手続き内容:
Xやインスタグラムで入会希望のDMを送ってDiscordに入る。
内部のホンネ
○魅力
・普段勉強できないような言語を自由に学べる
・好きな言語の勉強ができ、かつそれを他の人と共有できる
・語学のモチベにもつながる
・いろんな学年の学生や社会人と語学を通して関われる
△大変なところ
強いて言えば、ゼミを担当する人や駒場祭は少し忙しくなるかもしれない。
新歓日程詳細
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連カテゴリー
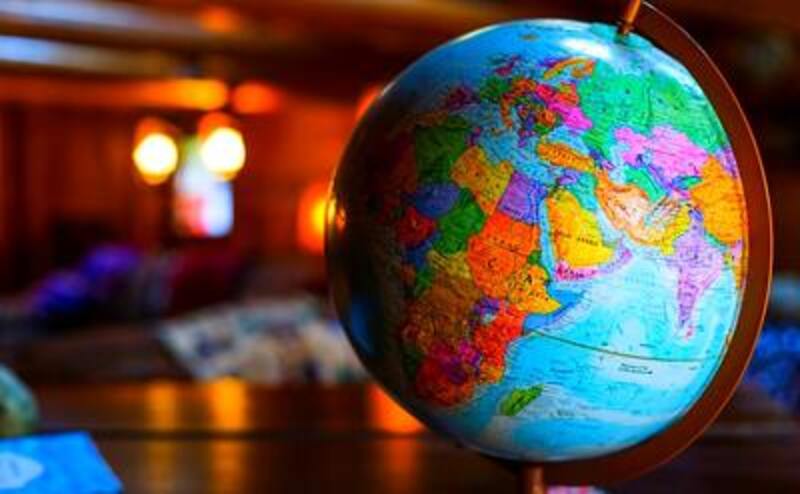
国際交流・語学
東大生に対して海外大生や国外での交流や体験活動を提供する団体。

人文科学(教育・文学・芸術)
教育・文学・芸術など「人文科学」を活動の軸として、研究やイベントの開催を行う団体。
関連サークル

アイセック 東京大学委員会
海外インターンシップの運営を主幹事業とする、世界最大の学生団体の東大支部。
東京大学SDGs協創学生アライアンス(UT-SCSA)
SDGsに関連する異なる分野を扱う5つの学生団体の集合体。
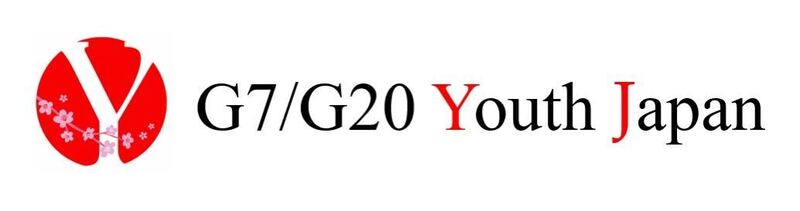
G7/G20 Youth Japan
G7/G20サミットの30代以下の若者を対象とした公式関連会議「Y7/Y20サミット」の運営や、官公庁/企業との協業を行う団体。

東京大学 E.S.S.
東京大学の学生によるサークルで、主に駒場で英語を使った活動をしている団体。




