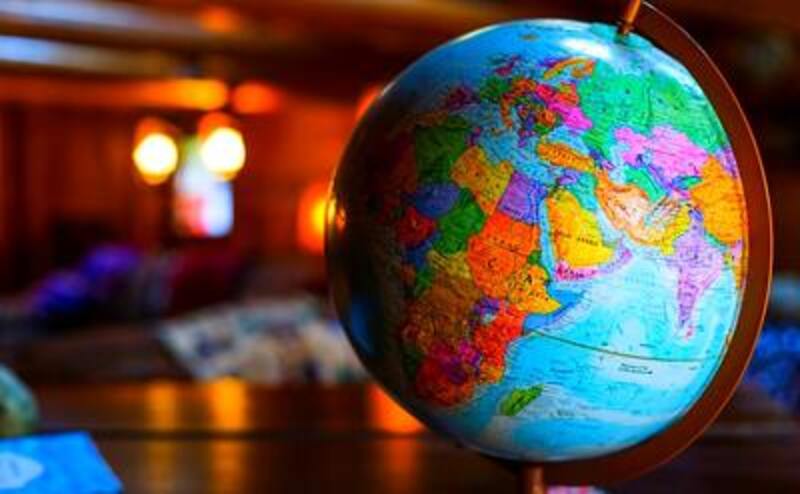GNLF
国際交流
国際フォーラム
国内実施
イベント実施
インカレ
2025.3.12
約10カ国30名規模の国際会議を企画・運営し、議論や文化交流を通じて国際交流を行うサークル。
目次
基本情報
| 執行代 | 1年目10月〜2年目9月 |
|---|---|
| 人数 | 10名弱 |
| 選考情報 | あり |
| 年会費 | なし |
| 活動頻度 | 週1回 対面(駒場・渋谷・カイザー邸)or オンラインでの対面 |
https://www.instagram.com/gnlf2025?igsh=MWptbXB1a285YzlkMA%3D%3D&utm_source=qr」 |
|
| 公式サイト |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
Global Next Leaders Forumの略。2010年度設立。2011年9月、第1回本会議開催。
理念:将来の世界を担う可能性と意思を持つ大学生が一堂に会する国際会議を「起点」として、数年~数十年の長きにわたりプログラムへ関与することを通じて一人ひとりがグローバル・リーダーへと自律的に成長できるような場を、そして彼らが人間的な絆を深めてゆくことのできるような場を創造する。
設立趣意全文は公式ページ「[設立趣意[(http://www.g-nextleaders.net/wp/gnlf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/%e8%a8%ad%e7%ab%8b%e8%b6%a3%e6%84%8f/)」から。
■活動内容
《ビフォーコロナ》
一年に一度、10日間程度の国際会議である「本会議」を開催し、その企画から運営まですべてを担う。本会議には、世界中(アジア、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパ)の約10ヵ国から計30名程度が集う(日本人参加者3〜5名を含む)。参加者の内訳の特色として、大国に限らず、日本との関係が表立って注目されないような国からも学生を招いている点が挙げられる。2月後半に行われる本会議では、テーマに沿ったディスカッションやフィールドワークなどのプログラムを行うほか、文化交流イベントや観光などを通じて国際交流を行う。テーマは各年の執行代が決定する。
《アフターコロナ》
定例ミーティングだけでなく、本会議自体もすべてオンラインで行われたが、フォーラムの前から参加者とzoomで話す機会があるなど、オンラインならではのメリットもあった。宿泊費なども不要になり、会議参加の障壁も下がった。2021年度のフォーラムには、日本の大学に通う約20名の運営メンバーに加え、7つの国と地域(スロバキア、オーストリア、チュニジア、日本、パキスタン、ハンガリー、メキシコ)から30名を超える参加者が集まり、「教育」をテーマに議論したほか、文化交流のイベントも行った。2022年度は3年ぶりの対面開催が実現し、海外から20名以上の参加者が集まった。2023年度以降も継続して年1回の本会議を対面で行っており、コロナの影響も薄まってきている。
■OBOGの進路/活動
〈進路〉
省庁、院進、外資、銀行など。
〈諸活動例〉
あまり団体の活動から派生したOBの活動は無い。ただし、本会議で知り合った友人のいる国へ個人旅行に行くことはある。
メンバー構成
人数
10人
学年
1年生〜3年生
執行代
・1年目10月〜2年目9月にかけて執行代を担当する
ジェンダーバランス
男:女=2:1
加入時期
1年生の入会が多いが、他学年からの入会者も毎年いる。
属性
・東大生が6,7割程度を占め、他に慶應大・東京外大・青山学院大・東京農大・ICUなど様々な大学のメンバーがいる。
・文系と理系は半数ずつ程度。
・文化系サークルだけでなく、運動系のサークルと掛け持ちしている人もいる。
・他サークル等の活動と両立を容認・奨励しており、他団体で得た知見も生かしてほしい。
離脱率
およそ10-25%
メンバー間のコミット量の差はどのくらいあるか
それなりにある
打ち上げにしか来ないメンバーも在籍していますか?
まったくいない
活動実態
執行代
・1年目の10月~2年目の9月にかけて執行代を担当する。
・2年目の人は、執行代の役職から降りるものの、団体に籍を置いたまま、執行代にアドバイスをするなど、後ろからのサポートを行う。
・秋にその翌年度の本会議を運営する執行代の代表(次期代表)が決まる
体制
・代表
・財務:財団とのやり取りを行う。
・渉外:参加者とのやり取り(各大学とのやり取り)を行う。
・プログラム担当:ディスカッションをコーディネートする。
・総務:財団以外との交渉+その他諸々の仕事を行う。
・広報:ホームページの更新、SNSでの発信を担当。
支援して下さる財団の方とのやり取りが本会議の1年半程度前から始まり、それが1年目のメンバーにとっての初仕事となる。各幹部役職は2年目のメンバーが担当する。
活動頻度
通常活動
・週1回のミーティングでプログラム作りや勉強会(プログラムの内容に関連することについて)を行っている。
・試験期間は原則活動していない。ただし、フォーラム直前(Aセメスターの終盤)は試験期間でも自主的に集まって話し合いを行うことがある。
コンテスト/イベント前後の期間
・フォーラム直前は、定例ミーティング以外にも、自主的に集まって作業や話し合いをすることがある。
・各セッション担当者が、そこでどういう議論をするか話し合ったり、本会議用の資料を作ったりするのがメイン。
・オフライン開催の場合は、本会議参加者が宿泊する場所や、空港に送迎する車の手配も行う。
年間予定
1年間(試験期間を除く)を通して継続して行うこと
・本会議のテーマに基づいたプログラムづくり(5月完成めど)
・勉強会
・フィードバック会
※毎週のミーティングが中心
その他のイベント
4月:新歓
5月:選考(面談)・参加者確定
6月~7月:メンバー交流会・本会議準備
8月:本会議
9月:財団への実施報告書作成
10~12月:来年度助成金申請
1~3月:新歓準備・来年度本会議テーマ決め
募集情報
選考あり/選考なし
選考あり
募集対象
学年制限なし。明文化された規定はないが、基本的には国内の大学に所属する学生を募集対象としている。
実際に入会する人
入会する1年生は毎年10名前後。他学年や大学院から入会する人もいる。
入会手続き内容
新歓イベントなどの際に、募集用のGoogleフォームを配布。フォーム提出者は、選考面談を受けたのちに入会。基本的には春の新歓期に採用を行っている。
内部のホンネ
○魅力
・コミュニティとして小規模なため、各メンバーの繋がりが強い。
・スロバキア、パキスタンなど交流の機会が少ない国の人と、ディスカッションや共同生活を通じて親しくなることができる。
・国際会議を日本でやる「受け入れ事業」だから渡航費がかからない。
・ミーティングが週1なので負担は少なめで、掛け持ちもしやすい。
・プログラムを一から設計できるので、興味や関心に応じて創造力を発揮できる。
△大変なところ
・人数が少ないので、一人当たりの仕事は決して少なくない(やりがいはあるから魅力でもある)。
・英語でのコミュニケーションに苦労することもある。
・8月の試験後から本会議直前までは結構忙しい。
新歓日程詳細
調整中
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル

東京大学メルボルン交友会(UTMEA)
日本とオーストラリアを結ぶコミュニティ
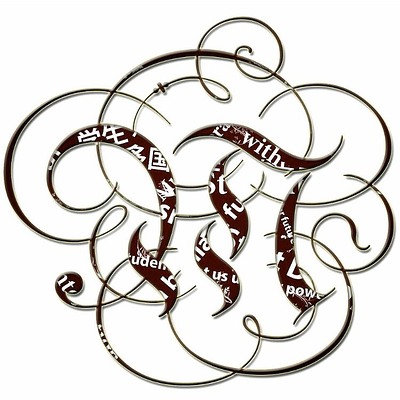
MIS
日本・ASEANの学生が集まり社会問題を議論する国際会議と現地プロジェクトの実施を行うNPO法人。

東京大学Diligent
「現場で学ぶ・社会を知る・仲間と成長する」をミッションに、世界的なリーダーの育成を目指す学生団体。

東京大学語学愛好会
言語に興味のある人が自主的に集まり学ぶサークル