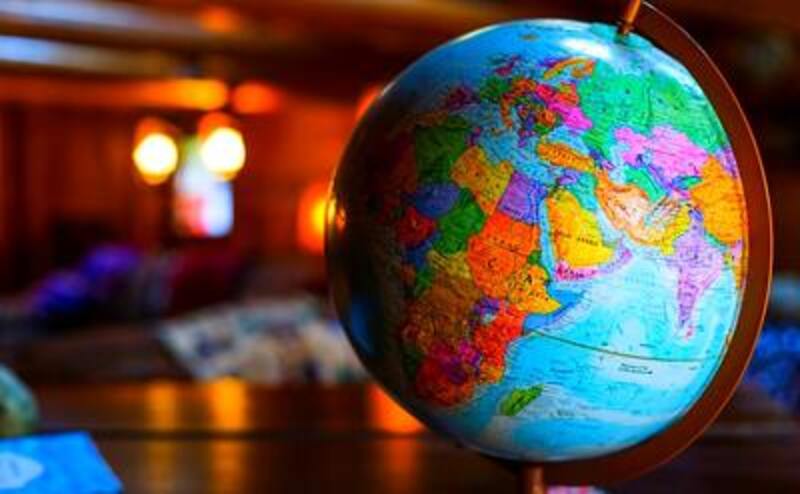MPJ Youth
アフリカ
国際交流
勉強会
アフリカ研修
インカレ
2025.4.7
アフリカを学び、発信する日本最大級の学生アフリカプラットフォーム。
目次
基本情報
| 執行代 | 2A〜3S |
|---|---|
| 人数 | 在籍: 100名超 アクティブメンバー: 50名程度 |
| 参加学年 | 学部生+院生 |
| 選考情報 | なし |
| 年会費 | あり:入会費1000円、年会費3000円 ※アフリカ研修参加(希望者)は別途約20万円程度(2週間分の宿泊・移動・食費、航空券代を含む) |
| 活動頻度 | 週に1回程度、勉強会の班・部局・その他不定期イベント企画の担当ごとにミーティング |
| LINE | |
| 公式サイト | |
| 公式メアド |
mpjyouth23[a]gmail.com
([a]を@にしてメールを送信してください) |
活動の様子




概要
■理念/指針・沿革
MPJ Youth (ミレニアム・プロミス・ジャパン・ユースの会)は「アフリカを学び、発信する」をコンセプトに、アフリカに興味のある学生が集まり、様々な分野の知見からアフリカを学び、議論するとともにその情報を団体内外に発信する団体である。アフリカの貧困削減を支援し、日本におけるアフリカの広報活動を行うN P O法人ミレニアム・プロミス・ジャパン(MPJ)(現在はSDGs Promise Japan)のユース団体として、2009年に東京大学の学生有志らが設立した。MPJ Youthでの活動を通して、社会の諸問題にタフに取り組む姿勢とアフリカについての幅広い知見を持ったグローバル・リーダーを育成するとともに、日本におけるアフリカに対する理解、関心の向上をめざす。
■活動内容
勉強会・講演会・機関訪問などアカデミックな物から、アフリカご飯会・料理会・ボドケ会・映画会などポップな物まで目白押し。春には2週間のアフリカ研修があり、1年間訪問先の国について学んでから現地へ渡航する。様々な興味を持った仲間と学び合うことで、1人ではたどり着くことのできない視座からアフリカ、そして世界を見つめることができるのが魅力。
<アフリカ研修>
実際にアフリカを肌で経験し学ぶ機会として年に1度行われ、選考で選ばれたメンバーが実際にアフリカに2週間ほど渡航する(今までの渡航先はマラウイ、ルワンダ、ガーナ、タンザニア、ジンバブエ、セネガルなど、今年度はナミビアを予定)。研修に向けて各自がテーマを設定し、現地で政府機関や企業などの訪問、現地の方との生活や現地でしかできない様々な方法を通して学びを深める。研修後は報告会を行うとともに、研修報告書を作成し、内外に発信する。
<勉強会>
前期(4~7月)は新入生が班ごとに分かれ、先輩と少人数で月に2~4回勉強会を行う。内容は班によって様々。メンバーの関心のあるテーマに沿った文献を輪読(本を章ごとに区切ってみんなで読む)するのが主だが、そのほかにも班でアフリカ料理を食べにいったり、アフリカクイズを行うなど楽しい要素を含む班も多い。
後期(10~1月)にも個人の興味に合わせて勉強会が開かれる。昨年度はアフリカの歴史や経済などについて本の輪読を行ったり、ガーナ大に留学している先輩からサヘルと呼ばれる地域に関する講義を受け、その中で現地ならではのお話を伺ったりした。参加頻度は自由で、一部の固定メンバーを除けば好きな時に参加していた。
<各種イベント>
その他にも月に3~4回程度、任意参加のイベントが開かれる。
JICAや大使館などの機関訪問や、アフリカの研究者や大使、アフリカで活躍される企業の方々などによるイベント・講演会を主催している。
ポップなイベントとしてはアフリカご飯会・料理会・ボドケ会・映画会。音楽会など、本や資料だけでなく、料理や文化などを通じてアフリカ文化に対する理解を深める企画が開かれる。
■OBOGの進路/活動
〈進路〉
民間(商社)、官公庁、大学院進学など多種多様な就職先。
JICAや外務省など国際系に進む人も多い。
アフリカに渡航経験がある人材は多くはないため、就職では強いアピールポイントとなる。
〈諸活動例〉
アフリカ各国へ留学するのはさることながら、夏季休暇中や休学中に長期インターンを行って現場で働くメンバーもいる。また、MPJ Youthの勉強会等を通じて得た知識を大学のレポートや発表に活かす人も多い。
メンバー構成
人数
在籍: 100名超 アクティブメンバー: 50名程度
学年
4年生 20名程度
3年生 30名程度
2年生 50名程度
院生等 数名
ジェンダーバランス
男性:女性=6:4
加入時期
春新歓で加入する新入生が多い。入会締め切りは5月上旬予定。加入自体は通年で全学年受け付けており、秋新歓で入会する人も例年数名いる。
属性
・語学力: 研修の際には英語が必要だが、語学力は全く問わない。
・インカレ。東京外国語大学アフリカ地域専攻の学生が多く所属(全体の3~4割ほど)。それ以外にも、様々な大学(東大、御茶ノ水、千葉、早慶上智ICU、MARCH、横国、名古屋外大、大正、清泉女子、東京女子など)の学生が参加している。
・アフリカの特定分野に強い興味を持っている人が多い印象。それ以外には、国際協力分野や国際機関などに興味があり参加する学生もいる。
・穏やかで優しい人が多く、優秀だが謙虚なメンバーが多い。
・兼サー率はかなり高い。運動系サークルとの掛け持ちも多い。
運動会の部との掛け持ちも数人所属(軟式野球部、ヨット部、ラクロス部、応援部等)。
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
50%
メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?
それなりにある
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
多少在籍している
活動頻度
勉強会は班によって月1~4回程度。
その他の各種イベントは月に3~4回程度。
研修メンバーはこれらに加え、8月以降は勉強会が週1回ある。
年間予定
4月~5月:新歓期間
5月:五月祭企画実施
5月~8月:新入生勉強会(通常の勉強会と並行して実施)
8月:夏の自由研究
9月以降:部門横断のプロジェクト実施
11月:駒場祭企画実施
10月~12月:後期勉強会
2月中旬~3月上旬:アフリカ研修(2024年度はセネガル)
募集情報
選考あり/選考なし
なし(ただし研修の参加には選考あり)
募集対象:
全学年の学生が入会可能。
実際に入会する人:
1年生に加えて、毎年度5〜10名程度、2年生以上も新規入会している。
入会手続き内容:
新歓説明会または新歓イベントに参加することを推奨。
4月末(GW前) から5月初旬にかけて、Googleフォーム(MPJ新歓用LINEオープンチャットに添付) を通じて入会を受け付ける。
内部のホンネ
○魅力
・東大においてアフリカを学べる場が少ない中で、アフリカに幅広い興味を持つメンバーから、非常に多岐に渡る視点・分野からアフリカを学ぶことができる。
・アフリカ研修では、単独渡航より安全かつ安価にアフリカに渡航することができる。
・普段の活動、研修などで、各国大使館やJICAへの訪問、国際協力に関わる会議やイベントへ参加する貴重な機会がある。
・他のメンバーの発表、情報交換、リサーチを通してアフリカに対して自分が抱くイメージが、日々改められる面白さがある。
・議論好きな人が多く、活動以外でも様々なトピックの議論で盛り上がる。
・穏やかな人が多く、アットホームな雰囲気がある。
・時期に合わせてコミット率の調整が可能であり、先輩も優しいのですぐに馴染むことができる。
△大変なところ
・勉強会の準備はそれなりに大変。ただ班員や上級生のサポートは充実。また、勉強会についてもコミット率は各自で調整可能。
・アフリカ研修の渡航費は自費負担。ただし、各種助成金がある為、個人で渡航するよりは遥かに安く抑えることができる。
新歓日程詳細
対面新歓
最新の情報は各種SNSをご確認ください。
4月13日(日)日中
アフリカ留学生交流イベント
場所:武蔵の森公園(外大近く)
4月24日(木)19時〜
企画名:アフリカンレストランご飯会
場所:Yinega@渋谷
4月25日(金)19時〜
企画名:アフリカンレストランご飯会
場所:Padi‘s Tokyo@六本木
4月26日(土)日中
企画名:上智ASANTE、ウガンダ野球、ルワンダ学生会議と合同新歓
場所:未定
4月27日(日)日中
企画名:アフリカ料理ボドゲ音楽会(マンカラ大会/賞品あり)
場所:新宿付近のレンタルスペース
オンライン新歓
4月7日(月)21時〜
4月15日(火)21時〜
4月22日(火)21時〜
5月1日(木)21時〜
5月13日(火)21時〜
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル

日仏学生フォーラム (FFJE)
日仏の文化・政治・経済の観点から国際交流を行う学生団体。

ERIFF 東アジア国際和解映画祭
東アジアの「和解」を目指して毎年映画祭を実施。
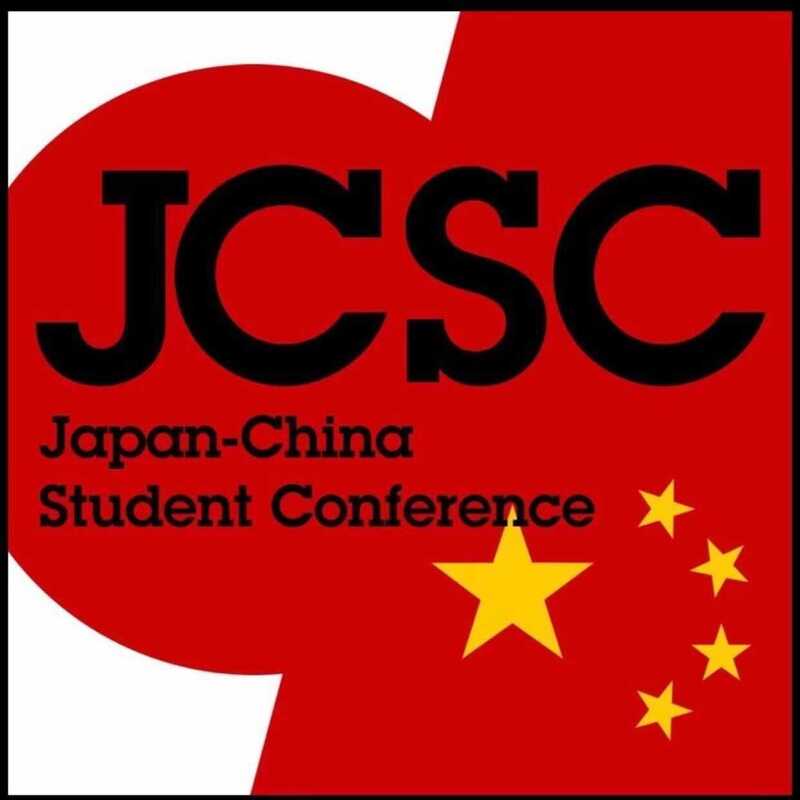
日中学生会議
毎年8月に英語・中国語・日本語を使用し、3週間本会議(合宿)を行う。

HUAP Tokyo
討論・文化交流によるカンファレンスへの参加と企画・運営を通じてハーバード大学生と交流する学生団体。