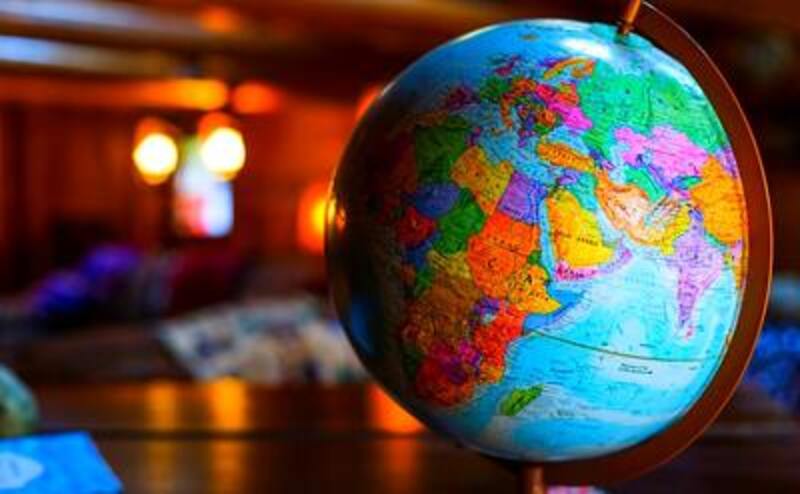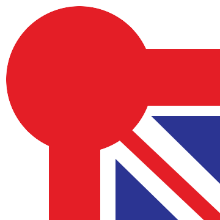
日英学生会議
イギリス
学生会議
英語
夏休み
2024.4.21
日本・英国の学生が集まり社会課題について議論を行う会議を開催する学生団体。
目次
基本情報
| 執行代 | 日本・英国の大学生 |
|---|---|
| 人数 | 30-40名 |
| 選考情報 | あり |
| 年会費 | 年会費はなし。本会議参加費として7万円(会議中の宿泊費・食費込み。複数の財団からのご支援によって参加費は大幅に減額されている。今後変動の可能性あり)。 |
| 活動頻度 | 会議参加者と実行委員で活動頻度が異なる。参加者は、毎年7〜8月の事前学習と8月の本会議(一週間)。実行委員は時期にもよるが約週一回でオンラインミーティング。 |
| 公式サイト |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
理念/指針
日本と英国の将来の担い手である学生同士の交流と議論の場を提供することで、両国の学生が社会で活躍する際に礎となる人脈形成を支え、日英間の交流を活性化させることを目標とする。また、異なるバックグラウンドを持つ学生同士が議論することを通じて、潜在意識に眠る自分の先入観や偏見を問い、多角的なアプローチに気づく、という体験を重視する。自由闊達にとことん語り合うというこの風土を、会議期間・会議場内に終わらせず、是非とも学生各人に自国のコミュニティーに持ち帰ってもらい、こうした「気づき」の体験を日英学生会議の外に伝えていきたいと考える。
沿革
2016年にBizjapanの1つのプロジェクトから独立して結成された。
■活動内容
2020年度、日英学生会議は「英国における日本文化季間認定事業」として在英国日本国大使館から認定された。
2022年から対面での開催を再開した。昨年2023年度のテーマは「ナショナル・アイデンティティ」で、東京で一週間程度開催された。登壇者(大学教授が多い)の方を世界中からお呼びし、ナショナル・アイデンティティと教育や政治などの多岐にわたるトピックを結んだレクチャーを通して学んだのち、ワークショップやグループワークを経て、政策立案を行った。東大生含め、日英の18の大学から学年も国籍もバックグラウンドも異なる多様な学生が集まった。(詳しくは2023年次報告書)
■OBOGの進路/活動
〈進路〉
オックスフォードに進学、駐米日本大使館で勤務など多様。
メンバー構成
人数
2023年度の本会議は実行委員7名(うち日本3名)、参加者28名(うち日本14名)
学年
実行委員:学部2年から既卒まで様々
参加者:foundation courseから院生まで様々
執行代
・一度大会に参加してみて興味を持てば、実行委員になるため、学年などは関係しない。なお、University College London (UCL), University of Oxford, University of Cambridge, 東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学等の学生が執行代を務める。
・一年目の後半(大会後)から実行委員を担当。残りたければ、自由に何年間も実行委員として残ることができる。
・代替わりは毎年9月。
体制
president(代表):1人。全体の業務をとりまとめる。代表は1年間続ける場合も2年間続ける場合もある。
finance兼logistics:3人。協賛の企業との渉外(資金調達)。宿泊施設の手配。
social media marketing:2人。SNS運用。新歓の告知。
academic:4人。講演者の決定。選考過程の問題を決定。
実行委員を担当している以上の10名の中には、イギリスの学生も含まれており、日英両国の学生が協働しながら大会の運営を行う。
男女比
実行委員の男女比は1:9。例年女子学生の方が多い。
参加者の男女比は1:1。例年女子学生の方が多い。
加入時期
4月、5月の新歓時期のみ。
夏に本会議があり、実行委員になるか(執行代に入るか)どうかを決めるのは9月。
実行委員になる過程で選考が行われる。(エッセイなどを書く)
属性
実行委員、参加者ともに東大含む様々な大学から参加している。
参加大学:
・実行委員:UCL、ケンブリッジ、inmperial college、エディンバラ、オックスフォード、上智、南山
・参加者:キングス・カレッジロンドン、慶應、ケント大学、オックスフォード、ウォーリック、ケンブリッジ、インペリアルカレッジロンドン、エクセター大学、東京外国語大学、九州大学、法政大学、早稲田大学、一橋大学、ロンドンスクールオブエコノミックス、南山、同志社、東大、上智、東海大学、エディンバラ、イギリスの高校生。
2020年度はオンライン開催のため、日英ともに地方の大学の参加者が増えた。
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
ほぼなし
メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?
多少はある
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
全くいない
活動頻度
通常活動
会議参加者と実行委員で活動頻度が異なる。参加者は、毎年7〜8月の事前学習と8月の本会議(一週間)。実行委員は時期にもよるが約週一回でオンラインミーティング。
コンテスト/イベント前後の期間
・ミーティングは基本的に絶対参加ではない。
・基本的には全体ミーティングだが、部署ごとのミーティングもある。
・実行委員は、イベント前後はミーティングの頻度が上がる。
年間予定
3月:ロンドン/東京にて、前年度会議報告と新歓を兼ねたイベント(対面/オンライン)を行う。
3月下旬(予定)から5月下旬:第一次書類選考(小論文)
6月上旬:第二次面接選考(実行委員と1対1で英語による面接)
7月:事前学習会
8月19日~27日(予定):本会議(ロンドン開催予定)
9月以降はReunionやUKxJP Alumni meet-upを通じて参加者同士交流しています!
募集情報
選考あり/選考なし
選考あり
例年4-6月にかけ、参加募集。
1次選考:書類選考。テーマに関する小論文(英語・日本語)を3つほど。
2次選考:英語Web面接。提出された小論文や、テーマに関連した質問をもとに、面接担当の実行委員と30~60分の議論。
→合格連絡
募集対象:
イギリスまたは日本の学生。
実際に入会する人:
大学生・大学院生。
入会手続き内容:
合格連絡があれば参加費を払って入会。
内部のホンネ
○魅力
・日英の学生と社会問題について自由闊達な議論・対話ができる。
・英国トップ大の教授の講義や、最先端で活動するNGOの方々のお話を聴き、直接質問できる。
・多様なバックグラウンドを持つ日英の大学生と仲良くなれる。
・議論や政策立案を通して、英語のアウトプット能力が高まる。
・運営視点では、若い団体なので伝統やしがらみがなく、自分次第で色々実現可能。
△大変なところ
・たくさん英語の学術論文や図書を読むこと。特に自分にとって初めての分野だと専門用語に慣れるまで努力が必要。
・現地開催の場合、開催地までの渡航費用がかかる(現地での費用はほぼ全額補助!)
・団体の成長期にあり、実行委員の役割は流動的(だからこそやりたいことができる)
・イギリス側との摺合せを英語で行うのが難しい。物事の捉え方や、国ごとのバックグラウンドの相違から、意思疎通や合意に難儀することもあった。
新歓日程詳細
2024年度の新歓日程については随時更新予定。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル
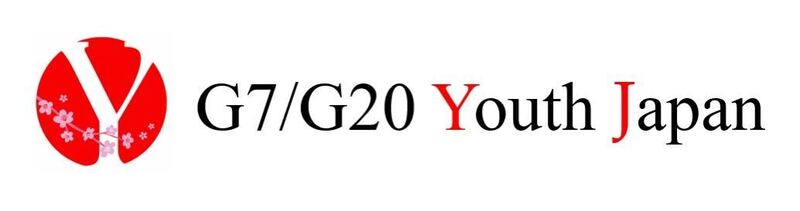
G7/G20 Youth Japan
G7/G20サミットの30代以下の若者を対象とした公式関連会議「Y7/Y20サミット」の運営や、官公庁/企業との協業を行う団体。

IDYF(International Development Youth Forum)
国際開発に関心を持つ若者が増える中で、交流やネットワークを構築し、国際開発について若者が学び、意見交換する場を作る団体です。
東京大学SDGs協創学生アライアンス(UT-SCSA)
SDGsに関連する異なる分野を扱う5つの学生団体の集合体。

OVAL JAPAN
東アジア最大級の国際ビジネスコンテストを日中韓の大学生で開催する学生団体。