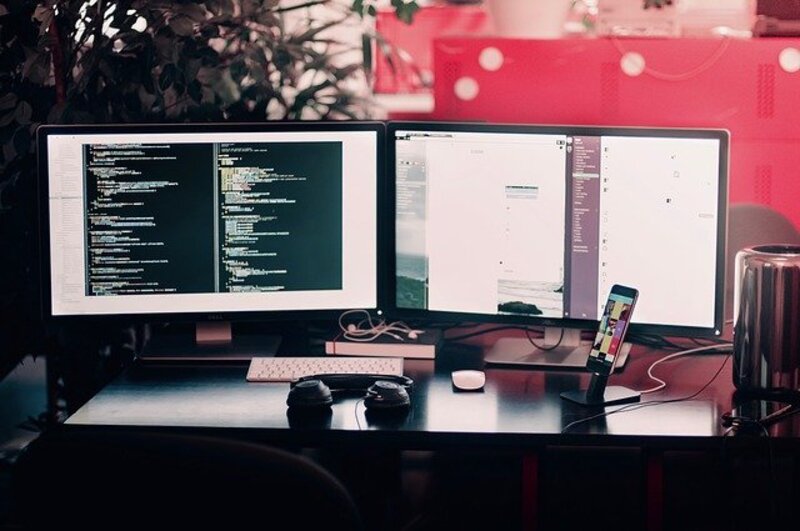UTokyo Football Lab.
2025.3.27
2023年に東京大学ア式蹴球部(サッカー部)エンジニアリングユニットとして発足した団体。
目次
基本情報
| 執行代 | 特になし |
|---|---|
| 人数 | 20名 |
| 参加学年 | 学部生+院生 |
| 選考情報 | あり |
| 年会費 | なし |
| 活動頻度 | プロジェクトごとに週1回にオンラインの定例ミーティング、毎週火曜日20時~21時にオンライン勉強会、2ヶ月に1回対面での全体会 |
| 公式サイト | https://sites.google.com/view/ut-ashiki-engineer/home?authuser=0 |
概要
■理念/指針・沿革
2023年に東京大学ア式蹴球部(サッカー部)エンジニアリングユニットとして発足し、プロチームとの関わりが増えた後に独立して一般社団法人となった。
Mission
テクノロジーの力で世界一のサッカーチームを作る
Vision
世界一のサッカー研究機関として、インパクトある事例を生み出し続ける
Value
・Creativity :
技術の遊び場として、シーズを生み出す
・Pragmatism:
現場に立脚し、実用的な活動を行う
・Open Innovation:
知識をオープンにし、革新をもたらす
UTokyo Football Lab.は、以上のMission、Vision、Valueを掲げて、データ革命の潮流の中で、様々な研究機関・チームと連携しながら、日本サッカー界にデータ革命を起こす挑戦を行なっている。
■活動内容
基本的には各メンバーがそれぞれのプロジェクトに所属し、プロジェクトごとに活動を行なっている。
2025年3月現在には、以下のようなプロジェクトが存在している。
ア式蹴球部のデータ分析:PassやShotなどのイベントデータとGPSデータをもとに、ア式蹴球部の強化につながるデータ分析を行う
筋骨格プロジェクト:映像から筋肉や関節にかかる力をシミュレーションすることで、けが予防などを目指す(本郷テックガレージSFP採択)
画像認識:試合の放送映像から各選手の位置や姿勢を取得する
その他、プロチームとの提携プロジェクト複数
また、以上のプロジェクトの他、過去のプロジェクトも含め、本郷テックガレージSFPには4件、未踏ITに1件採択されている。
全体としての活動は、毎週火曜日20時から21時のオンライン勉強会、2カ月に一回程度の対面の全体会、不定期の対面会がある。
メンバー構成
■メンバー構成
人数
20名
学年
学部1年から博士課程まで
執行代
特になし
ジェンダーバランス
→「回答はメンバー個人の情報流出につながる旨の注意喚起を行い、その上でノンバイナリーの存在を明記することや、項目自体の削除も可能」な旨を口頭で伝える
男:女 6:1
加入時期
通年
属性
・ア式蹴球部の部員や卒業生が多いが、外部のメンバーも増えている。
・理系が殆どであるが、物理学から言語学まで専門分野は幅広い。
・留学に行くメンバーが多い
・サッカーへの興味、もしくは技術への興味があって参加する人が多い。
活動実態
活動頻度
通常活動
各プロジェクトの進捗報告を兼ねたオンラインでの定例ミーティングが週1程度で行われる。
また、毎週火曜日に勉強会があり、サッカーに関することや技術に関する話題が提供されている。2カ月に一度程度対面での全体会が開催され、各プロジェクトの進捗報告やメンバーの交流の時間がある。これら以外に、日本代表の試合観戦会や忘年会など不定期のイベントも存在する。
コンテスト/イベント前後の期間
コンペに出るようなプロジェクトの場合は毎日進捗報告ミーティングが開かれる場合もある。
年間予定
プロジェクト次第
募集情報
選考あり/選考なし:
あり
応募者に対しては面談を実施し、選考を行う場合もある。
募集対象:
学部生・大学院生・他大学生・社会人
実際に入会する人はどのような人が多いか:
ア式蹴球部の部員・卒業生や、既存メンバーの友人や学科同期が多いが、応募フォーム経由で入会するメンバーも増えてきている。
入会手続き内容:
この問い合わせフォームからご連絡下さい。
入会において、メンバーとの面接を経てからの加入となる。
また、プロジェクト毎に応募する場合もある。
内部のホンネ
○魅力
・優秀なエンジニアと共同開発の経験を積める
・最新の技術を知れる
・コンペやプログラムに出るタイプのプロジェクトだと、実績になる
△大変なところ
・エンジニア歴が浅い場合、教育プログラムは特にないため、自分で勉強しながら進めることになる
新歓日程詳細
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル

東大AI研究会
AI人材の拡大を目指して活動する学生団体。
アイデアを形にするモノづくり体験~ロボットから家電まで~(ものゼミ)
「micro:bit」を活用しながら「楽しい」をモットーに活動する短期集中型のゼミ。

ut.code();
2019年度に発足した開発系のプログラミングサークル。

Littermate
「二面性をもつ生物学のカルチャーを発信する」ことがモットーの東大院生中心のアパレルブランド。