
すずかんゼミ
(学藝饗宴)
学藝饗宴
議論
少数精鋭
ゼミ
アート
芸術
議論
少数精鋭
哲学
2024.10.14
学術を俯瞰するために、藝術との饗宴を図るゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | 前年度からの継続生が執行部 |
|---|---|
| 人数 | 15名~20名、参加学年:学部生+院生→1,2年生(他大学も受け入れている) |
| 参加学年 | 学部生+院生 |
| 選考情報 | あり |
| 年会費 | なし |
| 活動頻度 | 火曜日の19時~(対面とオンラインを併用)→火曜日の19時~対面@主にKOMAD |
| 公式サイト | |
| 公式メアド |
minerva.komaba2019[a]gmail.com
([a]を@にしてメールを送信してください) |
活動の様子
概要
■理念/指針・沿革
爛熟期を迎えた19世紀末フランスのサロン、とりわけ詩人マラルメの「火曜会」を範とするこのゼミは、文部科学副大臣も務めた東京大学公共政策大学院教授の鈴木寛(すずかん)主催のもと、『学藝饗宴』と題して学術と藝術を綜合する教養教育を目指すものである。「すずかんゼミ」として四半世紀に亘り開講されてきた歴史を持ち、2017年度より新たに『学藝饗宴』の名の下で開講されている。学術を俯瞰しながら、藝術というものを考えてみようというところから『学藝饗宴』と題されたため、一般的に東大生が得意であるとされる論理的思考能力や言語化能力では太刀打ちできない問いと出逢い、新たな視点から学問を再考することができる。
■活動内容
ゼミの活動は、ゲスト回、学生回、中間報告発表からなる火曜の夜の「火曜会」と、読書会、最終制作を行う合宿を主軸とする。
セメスター毎に3回ほど設けられるゲスト回では、講義・質疑応答・制作体験など、特定分野のプロフェッショナルによる講義が展開される。2023Aセメスターでは詩人の高橋睦郎氏を、2024Sセメスターでは、詩人・小説家の松浦寿輝氏をお招きして創作における考えをお聞きし、ゼミ生各々が持つ問いを深める貴重な機会となった。その他、過去にお招きしたゲストの一部についてはTwitter、およびFacebookに掲載するので確認してほしい。受講生によりプロデュースされる学生回では、学生各々の関心ある分野や、その期のテーマにについての勉強会やワークショップが開かれる。専門・興味の異なる学生間の等身大の議論からは、新たな展望が拓かれることだろう。
セメスターの中間に行われる中間報告では、各々が思考の現在地をA4一枚にて報告する。
また、他大学の学生との交流会が設けられることもある。2019年度は、慶應大学の学生とコラボレーション授業を行った。
火曜の夜以外に行われる読書会では、各期のテーマに沿って設定された課題図書を読む。一人で読むのには晦渋な文章にゼミ生全員で向き合うことで学びを深める。
セメスター末に行うゼミ合宿では、普段火曜会を行ってきた場から離れた合宿地にて、各ゼミ生が学習の成果を「最終制作」として結実させる。
求める学生象
『学藝饗宴』の講義は、特定の問題についての答えを与えるものではない。むしろ、関心のある領域をそれぞれが見出し、頭から離れなくなるような問いを得ることを目的とする。問いに際して、論理や経験から答えを導こうとするだけではなく、個々人が自らの真善美を追求し、感性を磨きあげることに重きをおく。分からないものの分からなさに好奇心を抱き、それを自らの血肉としてゆっくりと結実させようと試みるような学生を歓迎する。また、単に知識を深めるだけではなく、学んだ知識をいかにして実際の「活動」へと集約させていくのかということに興味のある学生に参加してほしい。
メンバー構成
■メンバー構成
人数
2023年度はSセメスター12名、Aセメスター13名
学年
学年
主に1,2年生
ジェンダーバランス
女性はおよそ5割
加入時期
Sセメスターが4月、Aセメスターが10月
属性
・兼サー率は高く、ジャンルは多様である。中には、他のゼミや運動会に所属している者も見受けられた。
・文一から法学部という進路を取る人と、美術や哲学系に進む人が多い。
・理系の学生も多く在籍している。
・海外の大学など、他大学からの受講生が在籍することもある。
・映画や演劇好きの人が多く、実際にゼミ生で一緒に観に行くことも多い。
・ゼミ生は本好きで、哲学書の読書会を自主的に行うことも。
活動実態
1年間でどのくらいのメンバーが活動から離脱してしまう?
ほとんどない
メンバー間でコミット量の差はどのくらいある?
ほとんどない
遊びや打ち上げにしか来ないメンバーもいる?
全くいない
活動頻度
・週1回。火曜日の19時以降(5限後)に行われる。
・活動は主に駒場東大前駅近くにあるKOMADというコワーキングスペースで行われることが多い。
・毎回の活動後にゼミ生が作った夕食が振る舞われる。
・その他、有志によるスピンオフ企画も設けられる。毎年恒例になっているものとして、夜の長さの特異点である夏至と冬至付近の火曜日に、火曜会終了後から夜明けまで語らいながら夜通し歩き続ける「夏至夜行」「冬至夜行」などがある。他にも、KOMADでの映画観賞会、美術館の展覧会鑑賞回など、セメスターによってさまざまなスピンオフ企画が催される。
年間予定
4月:ガイダンス及び選考試験
5月~7月:ゼミ活動
8月~9月:ゼミ合宿
(以下、Aセメスター)
10月:ガイダンス及び選考試験
10月~1月:ゼミ活動
2~3月:ゼミ
※ゼミ合宿の場所及び日程はセメスター毎に定められ、今期も2泊3日ほどを予定している。
※最終制作発表はゼミ合宿において行われる。
募集情報
選考あり
募集対象:
1,2年生
実際に入会する人:
1,2年生。OB、OGとして3年生以上が参加することもある。
入会手続き内容:
・セメスターの授業初週日にオンライン上でガイダンス、2週目にオンラインにて選考を行う。
・試験の受験登録はSNSを通じて掲載されるフォームへの回答が必要。従って、入会希望者はSNSを随時参照すると良い。
・過去問はFacebookおよびTwitterに掲載される。
・選考の数日後には合否の通知をする予定。(受験規模によっては、若干の前後あり。)
内部のホンネ
○魅力
・全学自由研究ゼミナールとして登録されており、単位を取得できる。また、GLP対象科目にもなっている。→文理融合ゼミナールとして登録されており、1年生のAセメスターからは単位を取得できる。
△大変なところ
△大変なところ
・2024Aセメスターから主題科目という区分で開講される都合上、1年生のSセメスターにおいての履修は聴講という形しか認められず、単位を認定することができない。(文章の追加をお願いします。)
・二つ目にある読書会についての文で、「昨年度」を「過去には、」に変更をお願いします。
新歓日程詳細
未定ですので、後ほどご連絡させていただければと思います
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連サークル

ミライエコール
中高生の学校生活において、学生自身の声を反映させることを目指す学生団体。

FOS
主に中高生の進路・教育支援を行うNPO。教育や進路に関してさまざまな格差をテーマに包括的な支援活動をしている東大最大級の教育団体。

東京大学語学愛好会
言語に興味のある人が自主的に集まり学ぶサークル
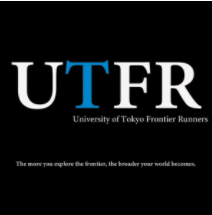
UTFR
東大受験への情報・環境格差打破を目指す、非進学校出身東大生のコミュニティ。






