
柳川ゼミ
経済学部ゼミ
ミクロ
ゲーム理論
金融
起業
ビジネスエコノミクスを学ぶ経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長は3A~4S。 OBOG係や合宿係について3年生が行い、4年生はサポートに回る。 ゼミ長については夏休みのゼミ合宿にて、3年生間で話し合って決める。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生15名、4年生14名 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週木曜4限(15〜18時) |
| 卒業論文 | なし |
| ゼミ論 | あり |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
12単位 |
| 公式X | |
| 公式Instagram | |
| 公式メアド |
yanagawa.87semi[a]gmail.com
([a]を@にしてメールを送信してください) |
概要
〈内容〉
「ビジネスエコノミクス」というゲーム理論やミクロ経済学の理論を用いて実際の企業/組織における行動の分析を行う。具体的には「ある企業の戦略(価格戦略など)が市場構造や産業全体に対してどのような影響を与えるのか」についてミクロ経済学の手法を用いるイメージ。
〈授業計画〉
両学年ミックスで活動する。両セメスターで輪読とディスカッションを行う。
輪読については、本の選定を先生が学生と相談し行う。2024年度はSセメスターでは活かすゲーム理論』を扱っている。
ディスカッションについては、ゼミ3回で1トピックについて扱う。2024年度はSセメスターでは楽天グループの成長戦略、Aセメスターでは、銀行/証券/地銀の収益向上施策等を扱った。
また、サブゼミ(※)が行われ、単位認定も行われる。そちらでも輪読を行う。。3,4年生ともにほぼ全員参加。
※サブゼミ:ゼミの前後に行われる補習時間のこと。経済学部的にはプロアクティブラーニングセミナー(プロアク)とされる。サブゼミが、プロアクとゼミに認定された場合は単位が認められ、そうではなければ認められない。事前に特定のメンバーが監督者(4年生または院生)となり、受講者の名前・学生証番号も全て登録しておく。
〈柳川範之先生について〉
1988年、慶應義塾大学経済学部卒業。
東京大学大学院経済学研究科博士課程で学び、慶應大学経済学部専任講師、東京大学大学院経済学研究科助教授、准教授を経て、同大学院経済学研究科教授に。
NRA総合研究開発機構理事、法と経済学会理事、事業再生実務者協会常務理事、経済財政諮問会議民間議員などを歴任。
〈他ゼミ比較〉
経営系の稲水ゼミ、桑嶋ゼミ等と検討して入ってきた学生は多い。
メンバー構成
人数:3年生14名、4年生13名。女性は4割程度。先生自身が多様性を重視する先生なので、応募者の母集団よりは女子率が上がる傾向。
属性:全員が経済学部生。兼ゼミは毎年5割前後。所属コミュニティとしては、スポ愛、ダンス、運動会、五月祭/駒場祭実行委員会、学生団体/ゼミ系も一定数おり、多様である。
性格:明るく外向的な一方で、学ぶ時はしっかり学び議論する学生が多く、オンオフの切り替えがうまい学生が多い(Play hard, work hard.)。オフライン活動時はエアビーを借りてパーティーしたりドライブしたり、ディズニー行ったりとキラキラしている側面も。
兼ゼミ先:自主ゼミ(元重/片平)との兼ゼミが非常に多い。単位付きゼミと兼ねている学生はほぼいない。
就職先:日系大手や外銀外コンが多い。稀に起業やベンチャー等に就職する人もいる。
活動頻度
毎週木曜4限(15:00~18:00)。
Sセメはサブゼミも毎週開講され、単位認定も行われる。
募集
原則、経済学部の3年生を新規で受け入れており、4年生の募集は無い。例年一次募集で終わってしまうことが多い。選考は経済学部のスケジュールに準じて行う。
応募に際しては、エントリーシートの提出が必要。自己紹介、本郷で勉強したいこと等を含めて3000字程度でまとめる。
エントリーシート提出者は、その後グループディスカッション(グループワークというよりはグループ面接に近い)に参加する。テーマは時事を絡めた経済トピックが多く、当日先生が口頭で提示し、挙手制で自分の意見を述べていく形式が多いらしい。
その後先生との1対1の個人面談が数分行われ、2問程度質問がなされる。
募集人数は毎年15名程度。選考は先生が行っている。倍率はならして3倍前後。
年間予定
両セメスター共に毎週木曜日の4限にゼミを行う。
4月:新入生歓迎会
5月:BBQ
7月 経済学部フットサル大会
8月:ゼミ合宿
日中は事前に与えられたテーマ(ここ数年は起業のアイデア発表など)に関するプレゼンとそれに対する質疑応答などがメインで勉強中心。夜は先生も交えたコンパが開催される。
12月:インゼミ
慶應大学の久保ゼミ、法政大学の大木ゼミと合同で行う。事前に決められたテーマに関して各大学からそれぞれ発表を行い、それを踏まえたディスカッションを行う。インゼミ終了後は親睦会も開かれる。
1月:OBOG会
歴代の先輩方が一堂に会する一大イベント。年の離れた先輩方とも仲良くなる貴重な機会になっている。(2023年度は1期生から26期生の参加)
3月:追いコン
内部のホンネ
○魅力
・留学に挑戦する人や起業経験者など「強い」人もいて刺激を受けられる。
・知的好奇心が旺盛で活発に議論をする雰囲気がある。
・グループワーク等のゼミ活動や、OBOG含めて参加する飲み会があるなど、ゼミ内の縦横の繋がりが実感できる。
・ノリのいい人が多く、オフライン時はディズニーに行ったりドライブに行ったり、とイベントが盛りだくさん。
・学ぶときは集中して勉強、遊ぶ時は思いっきり楽しむ、などオンオフの切り替えが上手い要領の良い人が多い。
・先生がとても優しい。ゼミ生と積極的にコミュニケーションを取ってくださり、よく理解してくださっている。
△大変なところ
・小グループでのディスカッションの時間が多く設けられており、自分の意見を持つことが求められる。「受け身」でゼミに参加するのではなく、常に自分の意見を考えること、相手に分かりやすく伝えることが求められる。
新歓日程詳細
応募受付期間や提出方法は経済学部規定に従う。
説明会や選考会などの最新情報は随時SNSにて告知。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
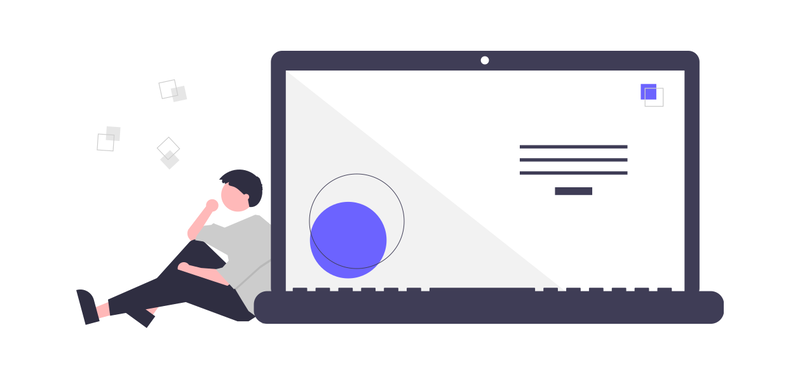
佐藤整尚ゼミ
プログラミング言語Pythonを使ってのデータ分析やデータマイニングを行う経済学部のゼミ。
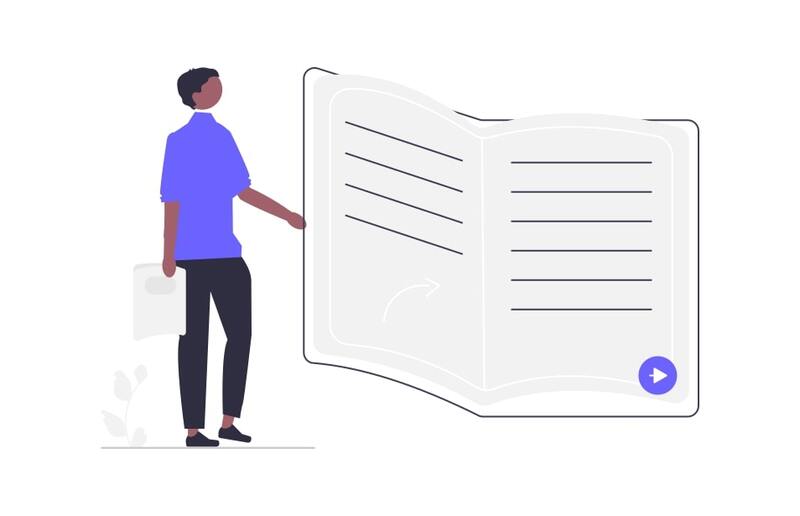
山本ゼミ
日本語・英語での文献講読や議論を通じて資本主義の歴史を探究するゼミ

古澤ゼミ
英語で国際経済学を学ぶ経済学部のゼミ。

市村ゼミ
計量経済学の理論を基礎から発展まで学ぶ自主ゼミ。




