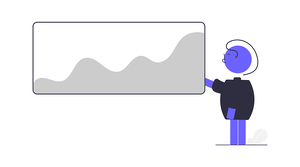
林ゼミ
経済学部ゼミ
財政学
社会保障
租税
租税や社会保障などの財政分野を取り扱うゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長を始めとして各係を3A~4Sで務める。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生10名、4年生10名。 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週月曜4限 |
| 卒業論文 | なし |
| ゼミ論 | あり |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
12単位 |
| 公式X |
概要
〈内容〉
税や社会保障を中心に財政について経済学的観点から学ぶ。先生が民間シンクタンクの出身で現実の政策に直接携わっていらっしゃったこともあり、日本の財政の諸制度について詳しい知識を得ることができる。専門科目の財政の講義では理論的な説明が中心となる一方、林ゼミでは実際の運用の観点により重きを置いて議論することが特徴的。
〈授業計画〉
Sセメスターでは財政学についての書籍の輪読を行い、基礎知識を固める。合わせて、サブゼミで基本的な計量経済学と統計ソフトRについて学ぶ。Aセメスターでは、12月のインゼミに向けてグループで実証分析や論文発表を行い、期末にゼミ論を作成する。
輪読:2023年度は『はじめての社会保障』(椋野・田中、有斐閣)、『財政学をつかむ』(畑農ほか、有斐閣)、『日本の財政を考える』(馬場ら、有斐閣)を扱った。各章毎に担当者を決め、ゼミ中にスライドを使って発表をし、質疑応答や先生からのコメントを通して知識を深めていく。書籍の輪読は原則として3年生が担当し、4年生は関連する論文の発表を行う。
インゼミ:例年12月に、慶應大学土居ゼミや山田ゼミと合同で、それぞれのゼミの研究発表と討論を行う場を設けている。3年生が中心となってグループ別に実証分析を行い、研究成果を報告する。財政のゼミではあるがテーマ選択の自由度は高い。昨年度は「生活保護被保護率の都道府県格差の要因分析」「北陸新幹線の地域経済効果」の2つ。
サブゼミ:実証分析に必要な計量経済学の理論的基礎を輪読形式で学ぶとともに、実際に統計ソフトRを用いた実証分析の手法を習得する。昨年度はS2〜A2の月曜5限に実施。教科書は『計量経済学の第一歩』(田中、有斐閣)を使用した。
※サブゼミとは、ゼミの前後に行われる補習時間のこと。事前に特定のメンバー(4年生または院生)が監督者となり、受講者の名前・学生証番号も全て登録しておく。履修上はプロアクティブラーニングセミナー(プロアク)として単位が認められる。林ゼミの場合はA1A2の2単位。
〈林正義先生について〉
東京大学経済学研究科教授。民間シンクタンクや財務省財務総合政策研究所での勤務を経て2014年より現職。日本財政学会代表理事、日本応用経済学会理事、政府財政調査会特別委員、地方財政審議会特別委員等を歴任。専門は地方財政や社会保障に関する実証分析。
(以下、経済学研究科の教員紹介ページより)
今までは、地域・市町村単位データを用いて、主に政府間財政や社会保障にかかるトピック(課税競争、市町村合併、地方交付税、社会資本、生活保護、介護保険)について実証分析を行う一方、世帯単位の個票データを利用して個人所得税や社会保障給付にかかるトピック(労働の賃金弾力性、公的資金の限界費用、配偶者控除、消費の等価尺度)についても実証分析も行ってきた。最近は、税や社会資本にかかる研究を継続すると共に、生活保護に関する実証分析に、地域データと個票データの双方を活用しながら再度、注力している。
〈他ゼミ比較〉
現在、財政学を扱うゼミは林ゼミのみ。
メンバー構成
・人数:3年生10名、4年生10名。女子は若干名。
・特徴:真面目過ぎず、不真面目過ぎずといった印象。他のゼミと比べても個々人の負担はかなり軽いため、運動部や兼ゼミも多い。
・兼ゼミ先:山口ゼミ、佐藤(泰)ゼミ、新井ゼミ、松井ゼミなど。
・就職先:官公庁や政府系金融が比較的多めだが、民間金融機関、シンクタンク、商社、交通、通信、メディア、デベロッパーなど様々な業種にわたる。(例:総務省、金融庁、日本政策投資銀行、農林中金、SMBC日興証券、東京海上日動、日本総研、伊藤忠、JR東海など)
活動頻度
毎週月曜4限。サブゼミが月曜5限に開講され、A1A2は単位も認定される。
募集
経済学部の3・4年生を10名程度募集。例年、2次募集まで行われることが多い。
提出書類:志望動機書(A4)1枚
年間予定
4〜7月 教科書の輪読、計量経済学とプログラミングの学習
9月 執行代の交代
9〜11月頃 実証分析、論文発表
12月 インゼミ
12〜2月 ゼミ論執筆、論文発表
内部のホンネ
○魅力
・先生が学生の質問には快く答えてくださる方なので、財政制度等に興味を持っている方には最高のゼミ。
・課題がそれほど重くないため、他にやりたいことがある人や兼ゼミしたい人にはちょうどいい。
・飲み会も適度に開催されるため、ゼミで交友関係を広げることもできる。
・インゼミのためのグループワークを通して、班員と仲良くなれる。
・ゼミ内での発表に対して、質問や意見が盛んに出されるため、議論を深めることができる。
△大変なところ
・インゼミで初めて実証分析に触れる人が多いと思うので、その点は戸惑うところが多いかもしれない。
・しばしばゼミが延長される。
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウントにて告知。
例年は、12月に駒場で、また3月末~4月頭に本郷でゼミ説明会が行われる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事

稲水ゼミ
経営組織論・組織行動論・経営科学を学ぶ経済学部のゼミ。
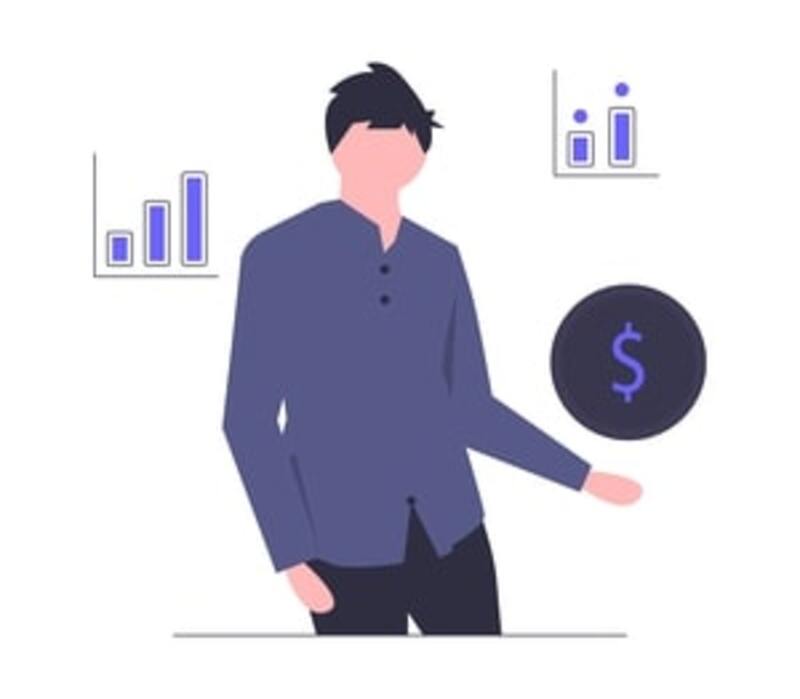
田中万里ゼミ
計量経済学について学ぶ経済学部のゼミ。
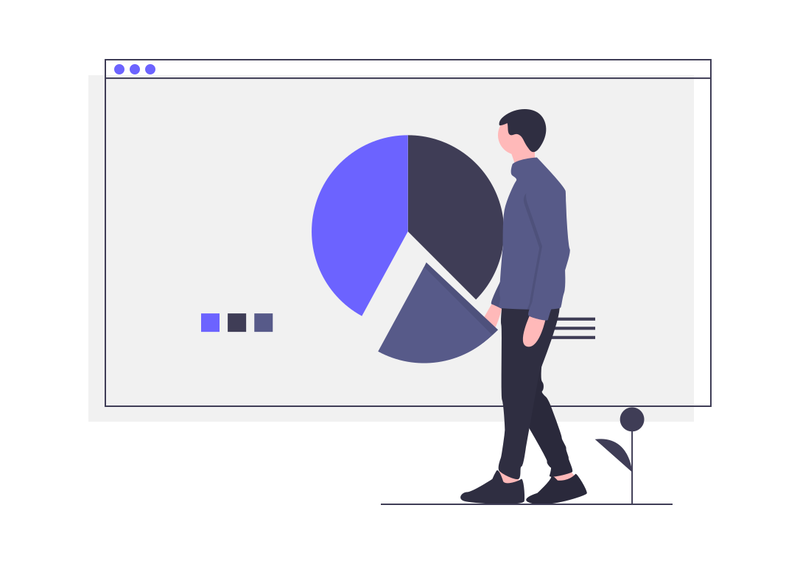
新井ゼミ
コーポレートファイナンス・バリュエーションを学ぶ経済学部の自主ゼミ。

植田ゼミ
マクロ経済・国際金融を扱う経済学部のゼミ。




