
西村ゼミ
経済学部ゼミ
自主ゼミ
他学部OK
マクロ金融
日銀
OBOGとのつながり
金融市場・金融政策を扱う経済学部の自主ゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長;3Aの10〜11月から1年間。 先輩からの推薦で選出される。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生15名、4年生15名 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 【隔週】火曜5限 |
| 卒業論文 | なし |
| ゼミ論 | なし |
| サブゼミ | なし |
|
2年間の
合計単位数 |
0単位 |
| 公式X |
概要
〈内容〉
元日銀副総裁を勤められた西村教授の下で、金融政策・金融市場について学ぶ。金融政策・金融市場に関する輪読と時事トピックに関する自由発表が基本であり、2020年度はコロナ禍の各国の金融政策の分析や、デジタル通貨、アベノミクスの効果検証やアメリカ大統領選挙の動向などのトピックを扱い、ディスカッションを行った。
〈授業計画〉
Sセメスターは3,4年ミックス、1グループ4,5名で発表活動を行う。2回に1回は、輪読書籍の章ごとの発表とディスカッション、もう1回は先生から頂いた論文・資料をまとめた発表とディスカッションとなり、それが繰り返される。つまり、月1回は輪読に関する発表、もう1回は先生から頂いた論文に関する発表である。1セメスターで1回発表があり、発表日は自身の都合に合わせて希望できる。
2020年度Sセメスターの輪読書籍は「中央銀行(白川方明)」で、毎年度金融系の書籍を読むのが通例。
Aセメスターも3,4年ミックス、1グループ4,5名で発表活動を行う。2回に1回は、Sセメスター同様に輪読書籍の章ごとの発表とディスカッション、もう1回はSセメスターとは異なり、各グループで自由テーマを設定した発表とディスカッションとなり、それが繰り返される。つまり、月1回は輪読、もう1回は自由発表であるSセメスター同様、1セメスターで1回発表があり、発表日は自身の都合に合わせて希望できる。
グループはSセメスターとメンバーは入れ替わる。
2020年度Aセメスターの輪読書籍は「デジタル化すると世界と金融(山岡浩巳)」である。自由発表のテーマは各グループの裁量に委ねられ、結果的に時事経済トピックが多くなる。2020年度Aセメスターは、アメリカの大統領選挙が経済面に与える影響、GOTOの効果検証(日本の観光政策について)、アベノミクスの効果検証など。
〈西村清彦先生について〉
1953年生まれ。東京大学経済学部卒。東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。米イェール大学経済学部大学院 Ph.D.取得。政策研究大学院大学教授、東京大学名誉教授。専門は理論経済学・経済統計・金融政策。2008〜2013年にかけて、日本銀行副総裁を務めた他、元クックパッド株式会社取締役としてビジネスの領域でも活躍。
〈他ゼミ比較〉
・自主ゼミかつ金融系、またコミュニティとしての側面が強いことから、伊藤元重ゼミと比較されることが多い。活動頻度が隔週である点(⇔伊藤元重ゼミは毎週)は異なる。
・分野は金融系なので、新井ゼミ、福田ゼミ、別所ゼミ等と比較されることが多い。違いとしては、活動頻度が隔週であり単位がつかない点が大きい。また、新井ゼミはコーポレートファイナンスを扱い、福田ゼミや別所ゼミは財政学を扱っている点で、金融政策を扱う西村ゼミとは異なる。
メンバー構成
・人数:3年生15名、4年生15名。女性は4割程度。
・属性:ほぼ全員が経済学部生で、他学部の学生も一定数いることが多い(2020年度は後期教養学部3名)。文一・三や理科出身など、学生間のバックグラウンドも多様。多くのゼミ生が兼ゼミしている(自主ゼミで単位がつかないことが大きいか)。所属コミュニティは多様で、運動会(フットサル、躰道など)や運動系・文化系サークルとそれぞれ一定数在籍。
・性格:(自主ゼミのため)卒論執筆が無い。穏やかで明るい性格の学生が多い。みんなで集まって話すのが好きな学生が多いイベント好きな人も多く、ゼミ旅行やコンパなども開催される。
・兼ゼミ先:大橋ゼミや柳川ゼミが多く、福田ゼミや松井ゼミなども。
・就職先:外銀・外コンから、政府系機関(日銀・DBJ・省庁)や総合デベロッパーなど、就職先は多様。
活動頻度
隔週火曜5限。延長などはほぼ無く、基本的には定時で終わる。コロナ禍ではオンラインと対面を併用している。
募集
原則、経済学部(他学部でも可)の3年生を受け入れており、4年生も若干名募集予定である。例年二次募集まで行う。選考は自主ゼミのため、経済学部のスケジュールに準ずるとは限らない(2020年度は4月中旬に独自で開催した)。
応募に際してエントリーシートの提出が求められる。昨年の内容は、「自己紹介・志望動機(400字)」、また3つのテーマから1つを選んで600字程度で記述する形式だった。3つのテーマとは、「2Aの駒場の経済学部専門科目の中で興味を持ったものについて」「最近の経済ニュースの中で興味を持ったトピックについて」「今まで勉強した経済学について」。
エントリーシート提出者に対して、ゼミ生数名による面接が行われる予定である。面接内容は、エントリーシートに書いた内容に基づいて行われる。
募集人数は毎年12〜15名。選考は原則として学生が行っている。
年間予定
例年の年間予定
4月-7月:授業→輪読(指定図書or西村先生指定の論文)
8月:ゼミ合宿
9月-1月:授業→輪読(指定図書or西村先生指定の論文)・自由発表
11月:OBOG会
3月:追い出しコンパ
※この他、任意参加のアフターやゼミ生同士で出かけることも!
内部のホンネ
○魅力
・リアルタイムの金融政策・金融市場について、過去に副総裁を務めた西村先生の視点から、ご意見をいただける。
・Aセメでは自主的にテーマを選び、発表をする会があり、自身の興味関心のあるテーマについてディスカッションできる。
・西村先生の教養に溢れたお話を聞ける。
・隔週のためダブゼミ、トリゼミも比較的しやすい。
・先生も積極的なコミュニティとしての活用を望んでいることもあり、イベントも多い。
・ゼミ生同士の仲が非常に良い。同期だけでなく先輩・後輩同士でも仲良くなれる。
・西村ゼミのことを「サークル」って間違えて言って呼んでしまうほどの楽しさ。
・先生の偉大さ、ゼミ生同士の距離の近さ、扱う内容の自由度。
・負担が比較的軽いものの、ゼミ生同士の繋がりが強い。
△大変なところ
・西村先生からのツッコミが厳しいため、しっかりとした準備・理解が求められる。
・先生が2回に1回しか来られないため、お話するのがなかなか難しい。
・負担が他のゼミに比べ大きくないうえ自主ゼミなので自分を律することができないと学びを得るのは難しい。
・発表回の準備は少し大変ですが、先輩も手伝ってくれますし回数も他ゼミに比べ少ないので心配せずに!
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウントにて告知します!
アカウントはhttps://twitter.com/nishimura2022
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
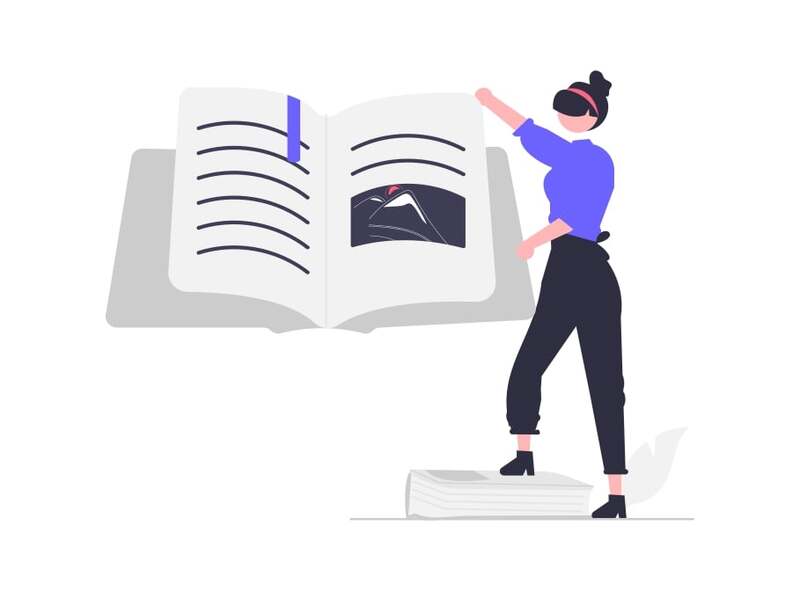
神取ゼミ
ゲーム理論・メカニズムデザイン・情報の経済学などについて学ぶ経済学部のゼミ。

柳川ゼミ
ビジネスエコノミクスを学ぶ経済学部のゼミ。
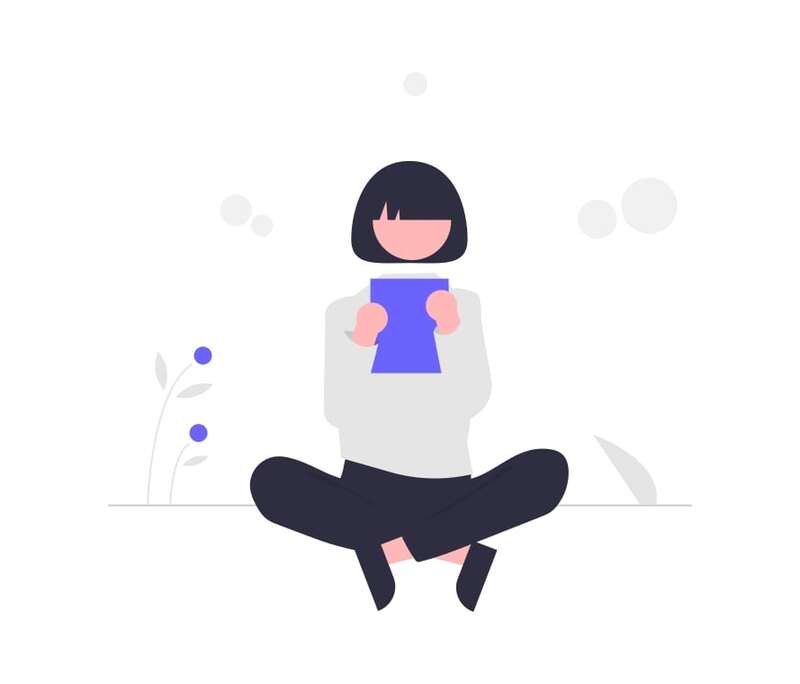
石原ゼミ
家族やジェンダーといった視点を取り入れつつ社会保障について考えるゼミ。主な活動は輪読と個人研究。

青木ゼミ
マクロ経済学に基づいて身近な現象を分析する力を養う経済学部のゼミ。




