
高橋伸夫ゼミ
経済学部ゼミ
経営論
組織論
経営・組織・意思決定論を学ぶ経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長・パ長は3A~4S。 両役職は先輩からの推薦で選出される。9~10月に行われるゼミ合宿にて発表される。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生10名、4年生10名 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週火曜4限 |
| 卒業論文 | なし |
| ゼミ論 | なし |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
12単位 |
| 公式X |
概要
〈内容〉
経営・組織・意思決定に関する知識を習得しながら、コミュニケーション力の習得を最も重視するゼミである。3つの目標を設定し、日々の活動を行なっている。①プレゼンテーション能力②基本的な経営学の知識の習得③他人に呼んでもらえるような卒論の執筆、である。①については、的確なレジュメを用いながら、人前で自分の考えを要領よく話す能力を身につけることを目的としている。②では、基本的な知識を前提に、効果的な議論に参加することを目指す。先生は、周囲の人間と難局を乗り越える経験を積み重ね、「またあいつと仕事をしたい」と言われるような人間になってはじめて一人前になる、それこそが真の評価だと考えている。そのため、高度な知識の習得のみを目的とするのでなく、社会人となって活躍していくためのプレゼンスキルやコミュニケーション能力を習得することを最大の目的としている。
活動内容の詳細はこちら(https://www.bizsci.net/seminar/index.html )を参照。
〈授業計画〉
両セメスター・両学年ともに輪読・精読を行う。なお、Sセメスターの最初には、論文の書き方についても簡単に学ぶ。
輪読については、本の選定を先生が行う。Sセメスターは経営学関係の標準的な大学テキストが中心で、2020年度Sセメスターは「コアテキスト 経営学」を読んだ。Aセメスターは経営・組織・意思決定に関する古典的な学術書を扱うことが多く、2020年度Aセメスターは「経営行動」を読んだ。週ごとの担当者が担当箇所を要約して発表し、発表後、それに関するテーマでディスカッションを行う。
〈高橋伸夫先生について〉
1980年、小樽商科大学商学部管理科学科卒業。
筑波大学大学院博士課程社会工学研究科で学び、学術博士を同大学で取得。1994年より東京大学経済学部助教授となり、同大学院経済学研究科助教授を経て、1998年より同教授を務める。研究分野は経営学、経営組織論。
国家公務員採用Ⅰ種試験(経済)試験専門委員、会計検査院特別研究官、特定非営利活動法人
グローバルビジネスリサーチセンター(GBRC)理事長(現)、日本経営品質賞判定委員長(現)などを歴任。
(詳細:https://nobuta.bizsci.net/index.html )
〈他ゼミ比較〉
・人気が高いゼミという観点では、柳川ゼミと比較されることが多い。
・経営系ゼミという観点では、桑嶋ゼミ(経営戦略とイノベーション)、片平ゼミ(ブランドマーケティング)、新宅ゼミ(経営戦略)、稲水ゼミ(組織戦略)等と比較されることが多い。高橋伸夫ゼミは、稲水ゼミと同じく、組織戦略を主に扱う。
メンバー構成
・人数:3年生10名、4年生10名。女性は4割程度。応募者の母集団もそれくらいになりがち。
・属性:全員が経済学部生。兼ゼミは毎年1割前後。所属コミュニティとしては、4大テニサーやスポ愛が多い。
・性格:卒論執筆が任意で(実際に書く学生はそれほど多くない)、学業に熱を入れたい学生がそれほど多くは無い。アクティブで明るく外向的な学生が多い。お酒を飲むのが好きな学生も少なくない(オフライン開催時は、毎週ゼミ後に、池袋などに飲み会に行く)。イベント好きな人も多く、ゼミ旅行なども頻繁に開催される。
・兼ゼミ先:兼ゼミしている人がそもそも少ない。
・就職先:商社・不動産・金融系が多い傾向だが、官僚やコンサル、事業会社などもおり、多種多様である。
活動頻度
毎週火曜4限。延長などはほぼ無く、基本的には定時で終わる。サブゼミ(※)も存在し、「プロアク」として単位認定されている。ただ特定の曜限に集まって作業をするというよりは、各自で好きな時間にこなすことが多い。
※サブゼミ:ゼミの後に行われる補習時間のこと。経済学部的にはプロアクティブラーニングセミナー(プロアク)とされる。サブゼミが、プロアクとゼミに認定された場合は単位が認められ、そうではなければ認められない。事前に特定のメンバーが監督者(4年生または院生)となり、受講者の名前・学生証番号も全て登録しておく。ゼミによるが、3年生のみの所が多い。サブゼミが設置されている場合、受ける人がほとんどである。
募集
原則、経済学部の3年生を新規で受け入れており、4年生の募集は無い。例年一次募集で終わってしまうことが多い。選考は経済学部のスケジュールに準じて行う。
応募に際してエッセーの提出が求められる。テーマは「ボランティアでもやりたいこと」(5000字程度)。エッセー提出者は、その後先生&ゼミ生数名による10分程度の面接に参加する。質問その他発言は、基本的にゼミ生主体で行う。
経済学の知識に関する質問は一切なく、「最近のお酒の失敗エピソード」等、日々の生活に即して、その人の人柄がわかるような質問が殆どである。合格するために取り繕うのではなく、ありのままの自分で受け答えした方が印象が良いと思われる。
募集人数は毎年10名。選考は原則として学生が行っている。倍率は3倍前後。
年間予定
3月:説明会・春新歓
4月:加入メンバー決定・ゼミ開講
9月:ゼミ合宿
10月:フットサル大会
1月:OBOG会
3月:卒ゼミ会
※ゼミ旅行、BBQなど不定期開催のイベントが多数あり
内部のホンネ
○魅力
・週一で飲み会をやるなど、ゼミ生の仲が非常に良い。
・先輩後輩の垣根も低く、コミュニティの輪を広げることが多い。
・ゼミ旅行やコンパ等、ゼミの時間以外でもゼミ生と交流する機会が多い。
・歴史が古いゼミでもあり、OBOGとの交流も多く、就職活動に役立てやすい。
・先生はフレンドリーに接してくださり、飲み会にもいらっしゃる。先生とも仲良くなれる。
△大変なところ
・他ゼミと比較してディスカッションが多いことから、自分で考えて伝える力が必要となる。
・飲み会の機会が多いため、飲み会の雰囲気やお酒が苦手な学生は、ややフィットしづらいかもしれない。
・学業・研究活動のみを追求したり、ゼミ生同士の交流を好まなかったりする学生は、ややその雰囲気に合わないかもしれない。
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウントにて告知。(3月頃から稼働開始か)
例年は、12月に駒場で、また3月末~4月頭に本郷でゼミ説明会が行われる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事

植田ゼミ
マクロ経済・国際金融を扱う経済学部のゼミ。

藤井ゼミ
数理ファイナンス(金融工学)に関連した分野を扱う経済学部のゼミ

奥井ゼミ
実験経済学を学ぶ経済学部のゼミ
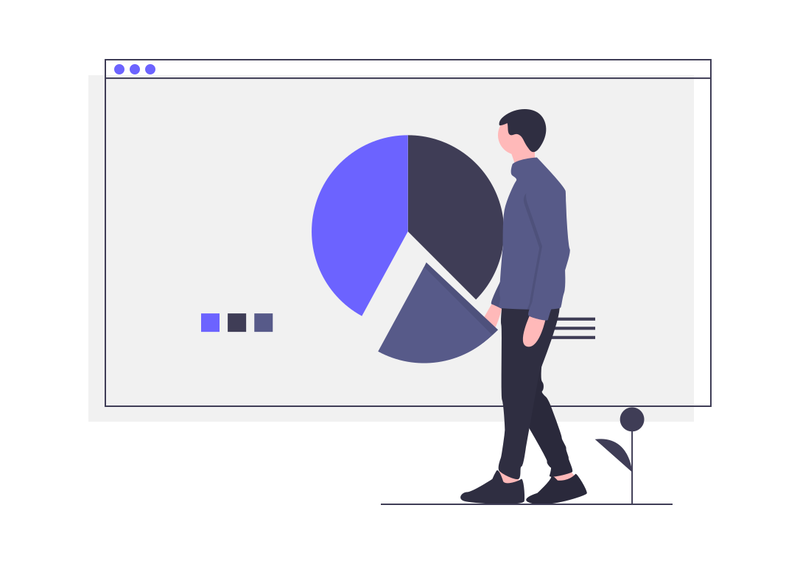
新井ゼミ
コーポレートファイナンス・バリュエーションを学ぶ経済学部の自主ゼミ。




