
澤田ゼミ
経済学部ゼミ
開発経済学
データサイエンス
政策の因果分析
留学
院進
開発経済学を学ぶ経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ執行代は3A-4S。ゼミ長は立候補のうえ話し合いで決める。 |
|---|---|
| 人数 | 4年生10名、3年生14名(2023年度) |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 本ゼミ毎週金曜4-5限(15時-18時)+サブゼミ週1回 |
| 卒業論文 | あり |
| ゼミ論 | あり |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
16単位 |
| 公式X | |
| 公式サイト |
概要
〈内容〉
澤田ゼミは経済学部で唯一開発経済学を専門にするゼミである。開発経済学とは、どうすれば現在の途上国が発展するかを考える学問だ。しかし、「発展」といっても、所得、雇用、健康、教育、環境、農業生産、工業技術、ジェンダー、政治、財政、心理など幅広い分野を対象とする。世界では途上国の発展のためにさまざまな政策が多額の費用をかけて実施されている。しかし、どの政策が発展のために効果的なのだろうか?それぞれの政策はどのような効果をもたらすのだろうか?澤田ゼミは、この問題に理論面、実証面双方から挑む。理論では、ミクロ経済学・マクロ経済学をはじめとしたあらゆる経済学のモデルから、発展のメカニズムを考察する。実証では、ランダム化比較試験(RCT)をはじめとした統計的因果推論とよばれる最先端の計量経済学的な手法を用いて、途上国の発展を目的にした政策にどの程度効果があるのかをデータに基づいて徹底的に議論する。
澤田ゼミは教室での「お勉強」で決して終わらない。ゼミ生同士の議論を通じて問いを立て、その問いを検証するために東南アジアへフィールドワークに出かけて自らデータを収集する。そして、持ち帰ったデータをRやStata、Pythonといった統計ソフトで分析し、論文にまとめる。その論文を基にして11月に行われる日韓の大学の合同発表会でプレゼンテーションする。その過程で、研究における問いの立て方、先行研究の探し方、データサイエンスの手法、論理的な文章の構成方法、簡潔にアイデアを伝えるプレゼンテーションの技法など、卒業後どんな進路においても間違いなく役に立つ力を身につけることができる。
〈授業計画〉
2022年度はSセメスター、Aセメスター通じて毎週金曜5,6限に10分プレゼン、計量経済学の学習、開発経済学に関する実証研究論文の輪読を行っている。これらの活動は本ゼミと呼ばれる。
10分プレゼンでは、担当者が興味のある経済現象や研究について10分間発表する。担当者は、コーヒー市場の価格変動やプロ野球のチケット販売方法など、自分の趣味や日々の発見に基づいた独創的な発表をしている。
計量経済学の学習では、教科書の輪読を通じて、データから政策の効果を検証するための統計的手法を身につける。2022年度のSセメスターは、『「原因と結果」の経済学:データから真実を見抜く思考法』や『Wonderful R 5 統計的因果推論の理論と実装』を読み、因果推論の基本からR(コンピュータ言語)による分析実装まで学んだ。Aセメスターは、“Impact Evaluation in International Development: Theory, Methods, and Practice”を読み、開発経済学に特化して政策効果の評価方法や実際の研究での応用例を学んでいる。
実証研究論文の輪読では、開発経済学の論文を毎週1本読んでいる。セメスター開始前にゼミ生は自分の興味分野を先生に伝え、各々の興味分野に沿った論文を要約・解説する。担当者による発表の後には、ゼミ生・先生との質疑応答を行うだけでなく、論文の手法に対する批判や考えられる研究の応用可能性について議論が交わされる。たとえば、Aセメスターの初回は、フィリピンでのフィールドワークを通じてスラム住宅街に興味をもったゼミ生が“There Is No Free House: Ethnic Patronage in a Kenyan Slum”という論文について発表した。この論文は、スラム住宅街において住人、家主、仲介者という3者の民族構成が家賃や家の改築状況にどのような影響を与えるのかを分析している。ゼミ時間内では、家の改築状況を示す指標に関して、論文における測定方法が適切であるかなどを議論した。
学生は発表担当者に限らず全員が予習として毎週ゼミまでに計量経済学の教科書と実証論文を読んでくる。ゼミ生は卒業までに計量経済学の教科書を4冊近く読み込むため、基本的なデータ分析手法を徹底的に叩き込むことができる。実証論文は年25回ほどの授業で毎回1本ずつ読む。すなわち、澤田ゼミ生は本ゼミだけでも学部時代に50本以上読むことになる。計量経済学の教科書で学習した統計的手法の応用例を知れるのはもちろんのこと、短時間でどのように論文のエッセンスを読み取れるようになる。
澤田ゼミには金曜の本ゼミに加えてサブゼミと呼ばれる活動もある。サブゼミでは、ゼミ生が協力して1本の論文を書き上げる。Sセメスターは、ゼミ生の興味分野を掘り下げて行き、1つのリサーチクエスチョンを練り上げ、その問いに答えるための研究計画を立てる。夏休みは、東南アジアで1-2週間フィールドワークを行い、データを収集する。Aセメスターは、収集したデータを統計的に解析し、論文を執筆する。ゼミ生は11月に開かれる日韓の合同発表会に向けて論文を書き上げる。発表会には、澤田ゼミだけでなく古澤ゼミや一橋大学、ソウル大学などの約10個のゼミがそれぞれ執筆した経済学の論文について、各ゼミ20分間プレゼンする。論文・発表・質疑応答はすべて英語である。2022年度はフィリピンのフィールド実験を通じて、tricycle(日本でいうタクシー)の価格決定メカニズムを明らかにした。
〈澤田康幸先生〉
東京大学大学院経済学研究科教授。専門は開発経済学。スタンフォード大学大学院経済学博士課程修了。2017年から2020年までアジア開発銀行(Asian Development Bank)のチーフエコノミストと経済調査・地域統合局長を務めた。詳細は、ホームページ参照。
〈他ゼミとの比較〉
・開発経済学を専門にするゼミは東大経済学部ではただひとつ。
・政策の因果分析を扱うゼミは他にもある。しかし、実際に海外までフィールドワークに出向いてデータを自ら集め、論文を書き上げるゼミは澤田ゼミのみ。
・開発経済学は「総合格闘技」であり、他ゼミで扱う経済学のあらゆる分野を網羅する。
メンバー構成
・人数:3年生14名、4年生10名。女性はおよそ3~4割程度。
・属性:9割ほどが経済学部生。文(言語)・後期教養(国関)、工(シス創)など他学部の学生も毎年参加しているが、聴講扱いで単位は出ない。
・性格:学業に熱を入れる学生はとても多い。海外志向・留学志向の学生も多い(2023年度の3年生は5名留学中)。ゼミの時間内はとても真面目で白熱した議論が交わされる。真面目一辺倒ではなく、毎週ゼミ後に先生と学生で飲み会に行く。先生も学生も非常に仲が良い。
・兼ゼミ先:青木、神取、北尾、首藤、別所、松井、植田、伊藤ゼミ。経済理論・実証・会計・経営など多様。
・就職先:民間企業(コンサル、銀行、証券、メーカー)、官庁など。特徴的なのは、JICAや開発系コンサルなど、開発経済学に関連した職に就く学生が一定数いることである。大学院に進学する学生は例年2-4名いる
活動頻度
週1回の本ゼミと週1回のサブゼミからなる。2022年度の本ゼミは毎週金曜5,6限(17-20時)に「少人数講義」として開催している。2023年度は毎週金曜4,5限に「演習」として開講する予定。週1回サブゼミも開講され、4単位認定される。サブゼミはゼミ生同士で日程調整して曜日・時間帯を決める。
募集
原則、経済学部の3年生を新規で募集している。他学部学生も参加可能だが、単位が出ない。選考スケジュールは経済学部に従う。2023年度は1次募集で募集終了。
入ゼミ希望者には選考課題が課される。2023年度は、志望理由書に加え、開発経済学に関するプレゼンテーション動画の視聴が求められた。選考面接では、志望理由や興味分野に加えて、動画の感想を問われた。面接では、澤田先生とゼミ生数名と30分程度会話する。募集人数は毎年10名程度。書類・面接をもとに先生と学生とが相談して選考する。応募者数は年度によって変動が大きいので、倍率の目安は存在しない(2023年度は2-3倍程度)
年間予定
<本ゼミ>
Sセメスター、Aセメスター通年で毎週1回開催。
2023年度の本ゼミは毎週金曜4,5限に「演習」として開講予定。
<サブゼミ>
4-7月:リサーチデザイン(フィールドワークの研究計画)
夏休み:フィールドワーク in 東南アジア
9-11月:データ解析、論文執筆、プレゼン準備、成果発表
<その他>
OBOG会や他大学での研究発表会など
内部のホンネ
○魅力
・知識量が多く真面目で頭の回転が速い学生が多い。刺激的な学びの環境である。
・毎週ゼミ後に飲み会があり、先生含めゼミ内の仲が良い。
・先生がゼミだけでなく飲み会にも積極的にいらっしゃって、フレンドリーに接してくださる。
・毎年東南アジアにフィールドワークに行く。
・サブゼミを通じて研究の面白さを実感できる。
・データサイエンスなど社会的に求められている知識・手法も身に付く。
・先輩後輩の垣根も低い。学年関係なく質問しやすい雰囲気があり、白熱した議論を交わせる。
・英語で論文を読み書きすることや発表することに対する苦手意識がなくなる。
・ハードなゼミであることは確かだが、充実した楽しいゼミ生活になることは間違いない。ゼミ生一同、自信をもっておすすめする。
△大変なところ
・ゼミ進度が速く、そのスピード感についていくのがやや大変。
・1セメスターに4回程度発表担当が回ってくる。プレゼンの機会が比較的多い。
・発表担当者以外も予習(教科書、論文)に毎週1-2時間程度割く必要がある。
・英語論文を読むので、英語が苦手な人は若干苦労するかも。ただし、英語の能力よりも根気が大事。
・2Aのミクロ経済学・マクロ経済学・統計の内容は前提知識として扱われる。
・先生や先輩方は、学部生だからと妥協せずに手厳しいコメントを下さる。
新歓日程詳細
12月に学生経友会主催のゼミ体験会に参加する予定。例年は、3月-4月ごろにゼミ説明会を開催する。予定は、Twitter新歓アカウントにて告知する。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事

米山ゼミ
会計学に関連することを学ぶゼミ。
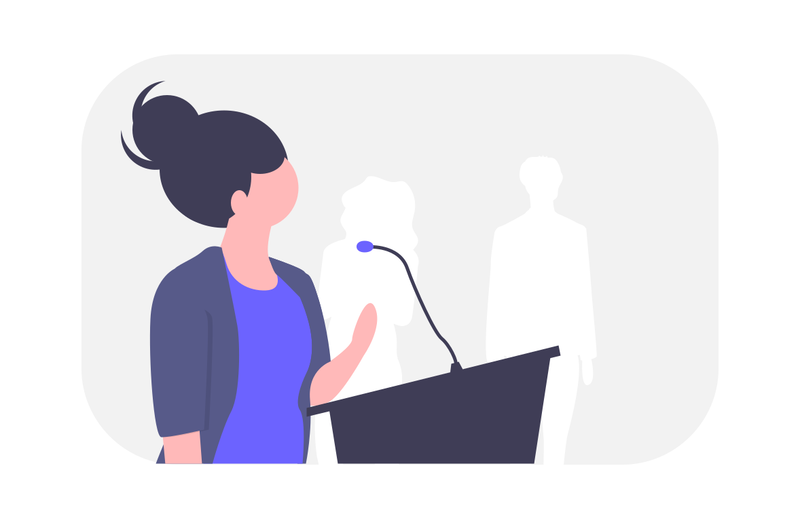
山口慎太郎ゼミ
労働経済学、教育経済学などについて、計量経済学の見地も踏まえて扱う。

植田ゼミ
マクロ経済・国際金融を扱う経済学部のゼミ。

奥井ゼミ
実験経済学を学ぶ経済学部のゼミ




