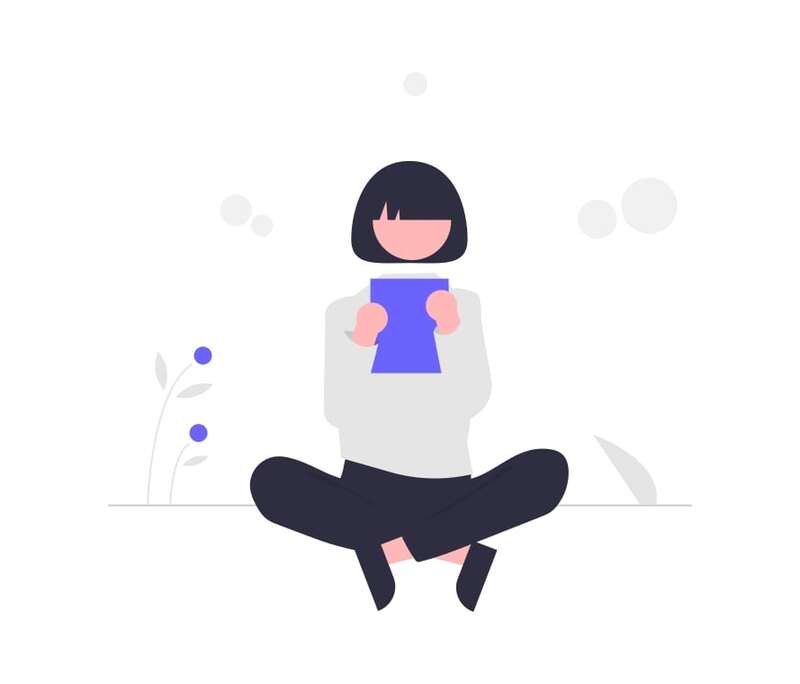
石原ゼミ
ジェンダー
社会保障
経済学部ゼミ
OBOGとの繋がり
教授が優しい
家族
家族やジェンダーといった視点を取り入れつつ社会保障について考えるゼミ。主な活動は輪読と個人研究。
目次
基本情報
| 執行代 | 主に3年生。4年生がサポートをする。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生7名、4年生3名 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週火曜4限(18:00まで延長することもある)。対面開催。 |
| 卒業論文 | あり |
| ゼミ論 | あり |
| サブゼミ | 年度による |
|
2年間の
合計単位数 |
12単位 |
| 公式X |
概要
〈 内容 〉
輪読と、卒業論文執筆のための個人研究を行う。輪読では事前に本を読み、担当者がレジュメを基に発表した後に議論を行う。通年で1つのテーマに沿って輪読を行うことで、ゼミ生が自分で問題意識を持つためのきっかけをつくる。卒論は4年生で執筆する。最大24,000字でテーマは自由。輪読した本や経済に絡めても絡めなくても良い。また、3年生では卒論の前段階としてゼミ論を執筆する。
ゼミの大きなテーマは「福祉国家と福祉社会」。社会保障システムの問題状況を時間軸(歴史的視点)・空間軸(国際比較)の中に位置づけて把握し、今後進むべき方向性を探ることがゼミの課題となる。キーワードとして2021年度と2022年度はジェンダー、2023年度は社会的排除と社会関係資本について扱った。
参考:輪読していた書籍名
〈今年度〉
福澤宏幸(2007)『社会的排除/包摂と社会政策』、法律文化社
ジョン・フィールド(2022)『社会関係資本――現代社会の人脈・信頼・コミュニティ』、明石書店
〈昨年度〉
大沢真理(2022)『企業中心社会を超えて』、岩波現代文庫
大沢真理(2010)『いまこそ考えたい 生活保障のしくみ』、岩波ブックレット
本田由紀(2014)『社会を結びなおす』、岩波ブックレット
経済学の視点だけでなく、地方自治体・家族などの視点を絡めて社会保障について考えたい人におすすめのゼミ。経済理論やデータ分析についての学びを深めたい人には向かない可能性がある。
〈 授業計画 〉
授業が本格的に始まるのは5月から。
Sセメスターは輪読、Aセメスターは個人研究の進捗発表を2回行う。
長期休みには合宿がある。2023年度は愛媛県松山市で開催。観光のほか、市役所や町の会長さんへのインタビューを行うなど、現場の生の声を聞く機会となっている。
Aセメスターには日帰りで行われる福祉や自治体行政の現場の見学がある。
合宿や見学の日程は先生とゼミ生が相談して決める。
〈 先生について 〉
石原 俊時先生 教員紹介
1984年3月に東京大学経済学部経済学科卒業。1995年に経済学博士(東京大学)。2002年に東京大学大学院経済学研究科助教授、2007年に准教授、2018年に教授となる。
主要な研究分野は西洋経済史。東京大学経済学部では、「上級西洋経済史Ⅰ・Ⅱ」、「経済史Ⅰ・Ⅱ」などの授業を担当している。
〈 他ゼミ比較 〉
・他のゼミとはテーマが被っていない。
・コンパの頻度が多い。月に1回の頻度で開催。お酒を飲ませるということはない。コンパには先生も出席してくださるため、先生とコミュニケーションをとれる機会が豊富にある。
・コンパに定期的に参加するOBOGの方もおり、交流する機会がある。
メンバー構成
・人数:3年生7名(1名留学中)、4年生3名。男女比は3:2。
・属性:サークル・部活・地方出身など属性は多様。所属コミュニティとしては、東大むら塾などのサークルに所属する学生などがいる。
・性格:穏やかで、意見を言いやすい雰囲気のゼミである。少人数であるため仲が深まりやすい。石原先生はどんな意見を言っても優しくフィードバックを下さる。
・兼ゼミ先:兼ゼミは可能だが、今年は兼ゼミをしてる人はいない。
・就職先:銀行・商事・IT系など多様。定まった傾向があるわけではない。OBOGの人と会う機会が多い。
活動頻度
毎週火曜4限。18時頃まで延長することが多い。
募集
原則経済学部の3年生が中心。4年生も受け入れているが要相談。募集人数は特に決まっていないが、多くはとらない。
選考については自己紹介と志望理由を書式・枚数自由で提出することが必須である。
年間予定
(2023年度の例)
Sセメスター:輪読
夏休み:合宿
Aセメスター:2回個人研究の進捗状況についてプレゼンをする
2月:OBOG会
内部のホンネ
○魅力
・先生が優しい(ゼミ生も)。どんな意見でも優しく拾ってくれてフィードバックがもらえる。
・経済史の先生なので、話が面白い。
・人数が少ない分、仲が深まりやすい。
・先生がサバティカル前はやんちゃな学生が多かったが、サバティカル後は落ち着いた学生が多い。
・コロナ禍になってからは国内で合宿を行っているが、コロナ前はロシアや韓国など海外にも行っていたため海外の学生との交流も可能だった。(2024年度は韓国に合宿予定)
・学部生の生活の中で論文を形として残せるのは達成感がある。先生のサポートは手厚く、時間をとってフィードバックをしてくれる。
・卒論のテーマ選択が自由。スポーツに関する論文を書いた人もいる。
△大変なところ
・人数が少ない分発表の頻度が多くなる可能性がある。一回の負担は大きくはないが、運動会などと両立する上で大変に感じる人もいるかもしれない。
・延長が多いため、5限に他の授業を入れることはできない。
・卒論が必須である。テーマの選択が自由である分適当なものを見定めるのが難しい。
新歓日程詳細
3月にゼミの説明会が行われる。説明会についての情報はSlackとX(Twitter)にて3月ごろから共有される。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
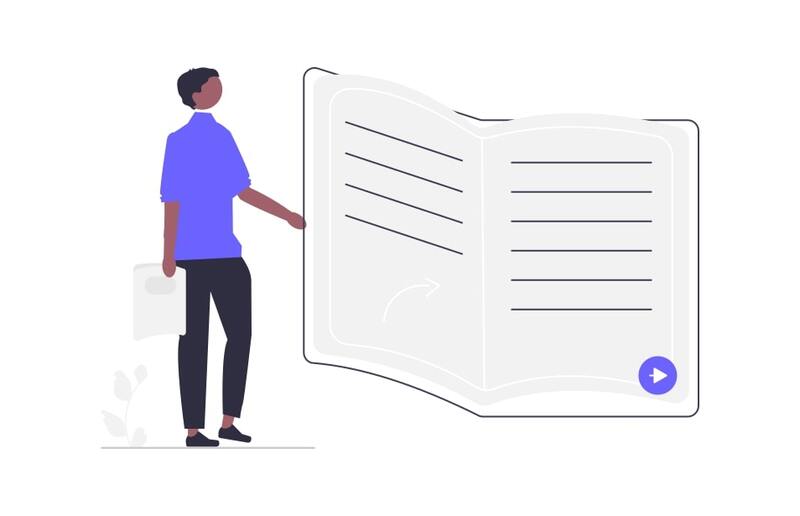
山本ゼミ
日本語・英語での文献講読や議論を通じて資本主義の歴史を探究するゼミ
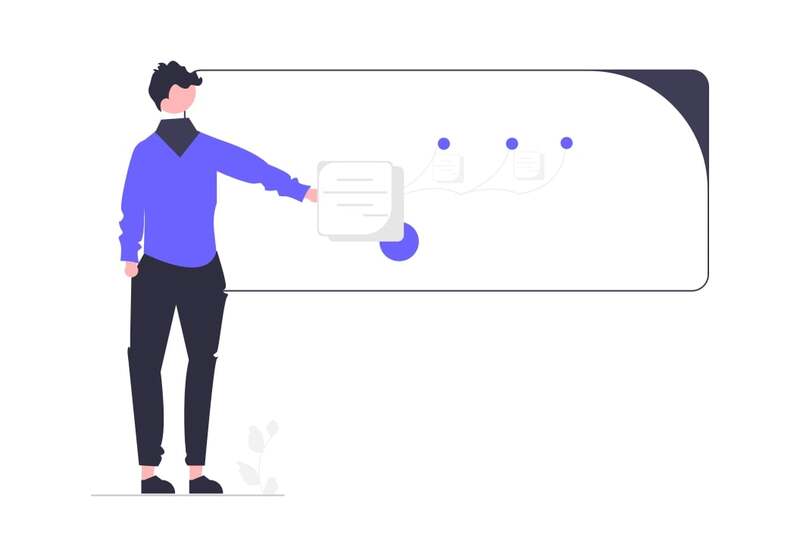
粕谷ゼミ
経営史(日本経営史)・経営学を学ぶゼミ

野原ゼミ
経済学の古典を通して経済学史を学ぶ経済学部のゼミ。

青木ゼミ
マクロ経済学に基づいて身近な現象を分析する力を養う経済学部のゼミ。




