
青木ゼミ
経済学部ゼミ
マクロ
金融
経済理論モデル
インゼミ
マクロ経済学に基づいて身近な現象を分析する力を養う経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長は3A後半~4A前半。 OBOG会や合宿などの企画は3年生が行い、4年生はサポートに回る。 新ゼミ長については現役のゼミ長と副ゼミ長が話し合って決める。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生7名・4年生9名(2023年度) |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週火曜4限 ※延長があり、4,5限(14時55分~18時過ぎ)となることも。 |
| 卒業論文 | あり |
| ゼミ論 | なし |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
16単位 |
| 公式X |
概要
〈内容〉
分野はマクロ経済学であり、特に青木先生のご専門である金融政策に興味のある人が多い。マクロ経済学などの理論を用いて、ゼミ生が身近な経済現象の説明を試みる「ブリーフィング」と、教科書や論文を読みマクロ経済学ついて学ぶ「輪読」の二つが活動の中心となっている。
また、4年生はブリーフィングなどを通じて見つけた興味あるトピックについて卒論を執筆する。
〈授業計画〉
3、4年生が一緒に活動しており、メインは「ブリーフィング」である。
ブリーフィングは、15分の発表→質疑応答→ディスカッション→(2週間後に)追加発表という流れで行われ、各ゼミ生が興味あることについてスライドを用いつつ発表する。例年、経済学理論を援用して、身近な経済現象の説明を試みる学生が多いが、堅苦しくないテーマのものも多く、昨年はマラソンの時間配分に関する分析を行った学生がいた。ブリーフィング後のディスカッションにおいては、このテーマをさらに発展させるにはどうすれば良いか、ゼミ生一同で議論する。また、発表者はその間に先生から1対1でフィードバックを受けることができ、2週間後の追加発表において先生やゼミ生から受けたアドバイスをもとに、さらに発展させた内容を発表する。
基礎知識の獲得を目指し、輪読も行っている。Sセメスターでは先生が執筆中の中級マクロの教科書(和文)を用いている。内容は駒場マクロの復習レベルから始め、その後金融政策などいくつかのトピックについて学ぶ。Aセメスターではゼミ生の関心に応じて金融政策や国際金融といったトピックを選び、複数の論文(和文と英文の双方の場合あり)を輪読する。輪読の内容・形式は毎年異なり、基本的にはゼミ生の希望に沿った形で進められる。
グループワークも必要に応じて行っている。Sセメスターの初めには経済分析演習という形で、マクロ経済にかかわる超長期のデータを整理し、経済学の知識を使って説明することを試みる。3・4年生が合同でブリーフィングに近いことを行うことで、親睦を深めつつ、3年生はここでブリーフィングの練習になる。また、インゼミの準備は3年生がメインで行い、複数人でグループを組んで1つの発表を行う。
また、サブゼミ(※)が例年Aセメスターのみ行われ、単位認定も行われる。そちらでは輪読を行っているが、参加は完全に自由であり、基本的にはゼミ生のみで運営される。2023年度は『金融政策:理論と実践』(白塚重典)を輪読した。
※サブゼミ:ゼミの前後に行われる補習時間のこと。経済学部的にはプロアクティブラーニングセミナー(プロアク)とされる。サブゼミが、プロアクとゼミに認定された場合は単位が認められ、そうではなければ認められない。事前に特定のメンバーが監督者(4年生または院生)となり、受講者の名前・学生証番号も全て登録しておく。
〈青木浩介先生について〉
研究分野
マクロ経済学と金融政策を中心に研究を行っている。近年では,金融市場の不完全性に焦点を当てて,資本移動自由化に伴う経済調整や,資産バブルに関する理論的な研究を行った。金融政策の分野では主に不確実性下の金融政策を分析している。
近年のご研究は、こちらを参照。
平成4年 神戸大学経済学部卒業
平成6年 神戸大学大学院経済学研究科前期課程修了
平成12年 プリンストン大学 Ph.D.
平成23年 東京大学大学院経済学研究科准教授
平成29年 東京大学経済学研究科教授
詳細
〈他ゼミ比較〉
マクロ経済学・金融の分野で分ければ渡辺努ゼミ・中嶋ゼミ・福田ゼミなどと比較されやすいが、自由な発表ができるブリーフィングに魅力を感じて青木ゼミを選んだと話す人が多い。
メンバー構成
・人数:3年生7名、4年生9名(2023年度)。
・属性:全員が経済学部生(他学部性の参加実績はあり)。大多数が兼ゼミしている。留学する人も一定数いる。
・性格:真面目で、それぞれの興味あることに打ち込むゼミ生が多い。
・兼ゼミ先:松井、下津、澤田、佐藤泰裕、北尾ゼミなど
・進路:日銀などの公的金融機関、金融庁、内閣府などの官公庁や、大学院進学が比較的多い。日系大手、外資系などを含めて多様である。
活動頻度
毎週火曜4限。サブゼミが火曜1限(毎年変動有)に開講され、単位認定も行われる。(オンライン下の現在は、メンバーの都合に応じて日時を変更することも。)
募集
原則、経済学部の3・4年生を新規で受け入れている先生がゼミ生の多様性を重じ、兼ゼミを推奨しているため、例年必ず二次募集を行っている。他学部生でも聴講で受講することができ、その際は先生にメールする必要がある。選考は経済学部のスケジュールに準じて行う。
応募に際しては、エッセイ(2000~3000字程度)の提出が必要。興味を持っている経済問題や最近読んだ本について書くことが求められる。
その後、青木先生との1対1の面談となり、そこではエッセイの内容に関連した話を先生に聞かれることが多い。
募集人数は毎年10名程度。選考は先生が行っている。
年間予定
両セメスター共に毎週火曜日の4限(~18時頃)にゼミを行う。
11月:OBOG会
歴代の先輩方が参加し、過去の青木ゼミの活動や社会人生活の実態についてざっくばらんにお話しする。
12月:ゼミ合宿
初日は4年生が卒論の進捗報告会を行い、3年生も含めたディスカッションを通して4年生は卒論のブラッシュアップを行う。後半は観光をする。例年温泉宿に泊まっており、2023年度は湯河原に行った。
1月:藤原インゼミ
年明けに、慶應大学の藤原ゼミとインゼミを行う。お互いに興味ある経済問題について分析して発表しあう。藤原ゼミ生はいつも斬新な切り口から質問してくれ、多くの学びが得られる。日銀の白川元総裁も参加してコメントをくださる。インゼミ後は合同で食事会を行い、親睦を深める。
2月:ソウルインゼミ
ソウル大学にある、経済学専門のサークルの学生と交流するイベント。隔年でソウルに行く年と、東京にソウル大の学生が来る。2023年度はソウルを訪問した。青木ゼミは、藤原インゼミの発表内容を英語で行う。ソウル大学の学生から鋭い質問が飛んでくることも多く、いつも刺激が受けられる。ソウル開催の場合はソウル大学の皆さんと韓国料理や市内観光で盛り上がった。東京開催の年はソウル大学のみなさんをもてなす。
内部のホンネ
○魅力
・先生がとても優しく、教育熱心。複雑な経済モデルや経済事象でも、先生の説明を聞くとすんなりと受け入れられる。
・ゼミ生は優しく真面目な人が多く、居心地がよい。
・経済事象について深く考える人が多く、刺激が得られる。
・留学に挑戦する人や学業に打ち込む人、長期インターンをする人など、様々な興味関心を持った人がいる。
・他大学との交流がある。
△大変なところ
・ブリーフィングのテーマを考えることが意外と大変。良いテーマが思いつかず数週間思い悩むことも...
・他のゼミ生のブリーフィングに対して、意味ある質問・意見を述べることが難しい。数週間かけて準備してきた内容を素早く理解して、さらなる発展に役立つことを言おうといつも苦労している。
・延長が多い。時間割上では火曜4限だが、ブリーフィング内容について議論していると、いつの間にか18時をまわってしまう。
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウントにて告知。(3月頃から稼働開始か)
例年は、12月に駒場で、また3月末~4月頭に本郷でゼミ説明会が行われる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
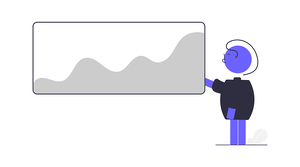
林ゼミ
租税や社会保障などの財政分野を取り扱うゼミ。

市村ゼミ
計量経済学の理論を基礎から発展まで学ぶ自主ゼミ。

佐藤泰裕ゼミ
都市経済学を学ぶ経済学部のゼミ。

西村ゼミ
金融市場・金融政策を扱う経済学部の自主ゼミ。




