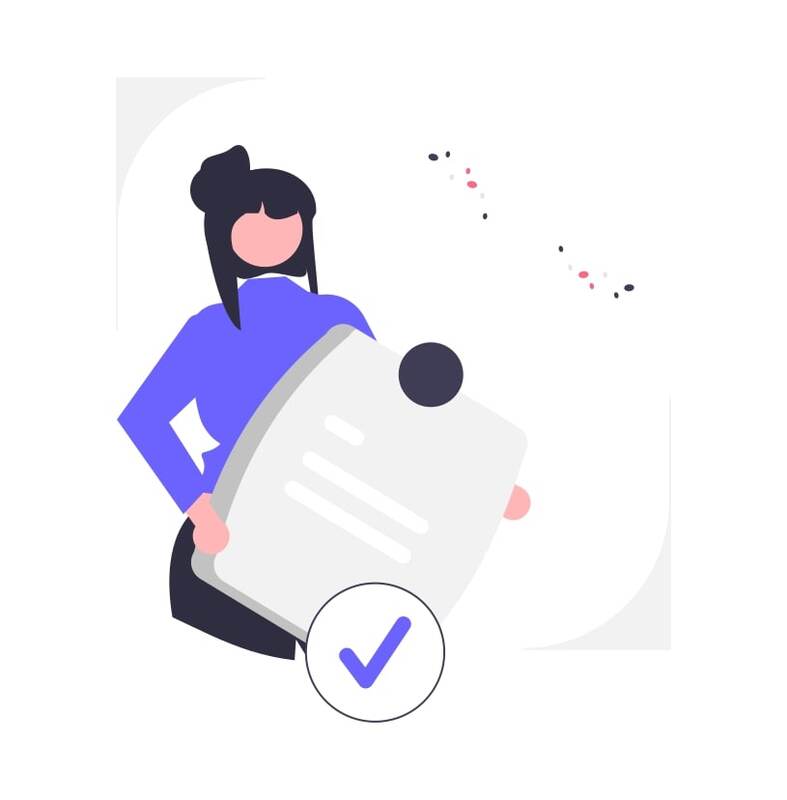
福田ゼミ
経済学部ゼミ
マクロ
金融
計量経済学
マクロ経済学や金融について幅広く学ぶゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長は3A~4S。 合宿係や新歓係などは3年生が行い、4年生はその運営のサポートに回る。 ゼミ長については、皆で話し合って決定する。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生8名、4年生7名 ※年度によって人数の偏りが発生することもある。 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 卒業論文 | なし |
| ゼミ論 | なし |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
12単位 |
| 公式X |
概要
〈 内容 〉
マクロ経済学や金融について幅広く学ぶゼミ。福田ゼミには4つの柱があり、それは「日本語ニュース発表」「海外ニュース発表」「計量発表」「輪読発表」。実際の経済事情や理論までオールラウンドに学ぶことができるのが特徴。
〈 授業計画 〉
○日本語ニュース・海外ニュース発表
日経新聞やThe Wall Street Journalなどから実際の経済ニュースを持ってきて、その事柄を説明するとともに起きた事象を自分なりに経済学的に分析して発表する。発表についてゼミ生からの質問と福田先生からのフィードバックを通じ、相互的なやりとりを介して経済学の本質的理解を目指す。
○計量発表
新世社「コア・テキスト計量経済学」を用いて計量経済学的な分析をゼミ論で活かせるように理解を深める。3Sでは計量経済学の基本的な理論について発表し、3Aでは実際にデータを用いて計量経済学的な分析を行なった結果を発表する。理論については本格的に理解するというよりかは、実際にどのように使うのかを重点的に学ぶ。持出科目の「統計」の復習ができ、「計量経済学」や「数理統計」などの授業の理解につながる。
○輪読発表
経済学の専門書を皆で分担して発表する。2023年度Sセメスターで使っているのは東京大学出版会「地球温暖化と経済発展」で、Aセメスターでは慶應義塾大学出版会「金融政策 理論と実践」であった。
これも日本語ニュース・海外ニュース発表同様ただ発表するだけではなく、ゼミ生からの質問と福田先生からのフィードバックを通じ、相互的なやりとりを介して経済学の本質的理解を目指す。なお、輪読書自体は福田先生が決定するが、希望を伝えておくとそのテーマの輪読にしていただけることもある。
3年生も4年生に混じって、日本語ニュース・海外ニュース発表を両セメスターで担当する。計量発表は基本的には3年生が発表する。輪読発表は2023年度は4年生が担当し徐々に3年生も発表するように移行したが、2024年度ではゼミ生の希望に合わせる予定である。発表の頻度はジャンル関係なく月に1回程度。
〈 福田慎一先生について 〉
1984年に東京大学経済学部経済学科卒業後、イェール大学に進学し1989年博士課程修了(Ph.D)。2021年紫綬褒章受賞。
マクロ経済学、国際金融、金融の3つの分野を中心に研究。マクロ経済学の分野では、貨幣経済モデルの動学的な側面に焦点を当て、金融政策へのインプリケーションを考察したり、東アジアの通貨制度・円の国際化問題を研究したりしている。
福田先生は経済のみならず幅広い分野に造詣の深い先生であり、毎回のゼミで経済分野以外の知見も披露してくださる。例年は「金融」の授業を担当されている。
〈 他ゼミ比較 〉
同じマクロ経済学・金融系の青木ゼミと比較されることが多いが、福田ゼミはマクロ経済学・金融をオールラウンドに学ぶ一方、青木ゼミは金融政策について重点的に学ぶ印象がある。
メンバー構成
- 人数:3年生8名、4年生7名。
- 属性:全員が経済学部生。兼ゼミをしている人も多い。サークルを続けている人や部活動に所属する人などバックグラウンドは多様。理系出身の人もおり、現在のゼミ長もそうである。
- 雰囲気:学ぶ時は学び、遊ぶときは遊ぶイメージが強い。3年生は就活に力を入れる人も多く、就活生どうしの繋がりもできる。ゼミ後にご飯会が開催されることもある。
- 兼ゼミ先:ミクロ、マクロ、経済史、計量経済学など多岐にわたる。
- 就職先:金融、コンサル、官公庁など幅広く存在。伝統あるゼミのため、さまざまな年次・舞台でOB・OGが活躍なされており、2023年度のOB・OG会でも40名ほどの方が参加された。
活動頻度
毎週月曜日15:30〜18:00ごろ。サブゼミはAセメスターに開講され単位認定もある。日時は未定。
発表が定期的にあるのでその準備に各々時間を費やす必要があるが、特に忙しい時期は存在しない。
募集
原則、経済学部の3年生を新規で受け入れており、4年生の募集は無い(院進する前提の4年生の募集は受け付けている)。一次募集と二次募集が存在する。選考は経済学部のスケジュールに準じて行う。
応募に際しては、ゼミで勉強したいことや今まで勉強してきたこと等を含めて3000字程度でまとめる。原稿を提出した者は、その後先生との1対1の面談による選考が数分行われる。
募集人数は毎年8名程度。選考は先生が行っている。倍率は一次募集と二次募集ならして2倍弱前後。
年間予定
9月 夏合宿
11月 OB・OG会
12月 インゼミ
定期的に飲み会・イベントなども予定している。
内部のホンネ
○魅力
・さまざまな切り口から経済事情を捉えることができるので、経済学の面白さを痛感できるのはもちろん、普段の授業では味わえないような知的好奇心がくすぐられる体験ができる。
・ゼミ生の仲は非常に良い。ゼミ後にはだいたい隔週ペースでZoomで話したりする。ゼミ中には見えづらい様々なバックグラウンドを持ったゼミ生のいろんな話を聞くことができる。
・歴史の長いゼミであり、様々な業界にOBOGがおり、話を伺うことができる。
・(教員紹介にも書いたが)福田先生は経済学以外の分野にも造詣が深く、ゼミ中には様々な知的好奇心を刺激する話をして下さる。ゼミの時間はあっと言う間にすぎるように感じる。
△大変なところ
・ゼミ1回における発表人数が多いため、発表が自分に回ってくる頻度が他ゼミに比べて高いかもしれない。ただ発表を準備するのは楽しいのと、1回の量はそこまで多くないので頻度の多さはそこまで気にならないかも。
・先生やゼミ生が鋭い質問をしてくるので、それにしっかり対応することが難しい場合がある。ただ、他のゼミ生も回答を助けてくれることが多いため、共に乗り越えることができる。
新歓日程詳細
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
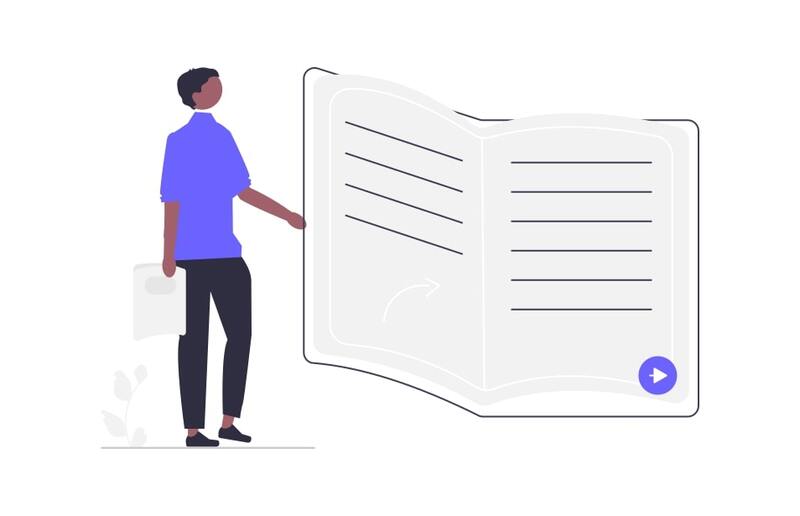
山本ゼミ
日本語・英語での文献講読や議論を通じて資本主義の歴史を探究するゼミ

稲水ゼミ
経営組織論・組織行動論・経営科学を学ぶ経済学部のゼミ。

楡井ゼミ
マクロ経済学を学ぶ経済学部のゼミ。

柳川ゼミ
ビジネスエコノミクスを学ぶ経済学部のゼミ。




