
松井ゼミ
経済学部ゼミ
ミクロ経済学
ゲーム理論
ゲーム理論を学ぶ経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長/副ゼミ長は4S~4Aの1年間。 合宿やOBOG会は3年生が企画・運営し、4年生がサポートする形。 ゼミ長/副ゼミ長はは4年生で相談し、本人に確認を取った上で決定される。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生9名、4年生13名(うち他学部2名) *人数に明確な決まりは無いが、毎年10名前後の3年生が入っている。 *他学部の方も松井先生と別途相談の上で聴講扱いとなるが入ゼミ可能。 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週水曜1,2限。延長は基本的に行われない。 |
| 卒業論文 | あり |
| ゼミ論 | あり |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
16単位 |
| 公式X |
概要
〈 内容 〉
ゲーム理論周辺の特定分野をセメスター毎に学んでいる。各セメスターで何を扱うかはゼミ生全員で決めていく。例えば2023年度のAセメで扱ったテーマは「統計的差別」であり、どうして差別が行われてしまうのか、どのような状況だと差別は発生するのか、といったことを学習した。このように、松井ゼミでは社会問題をゲーム理論の枠組みでモデル化し分析することを行っている。ノーベル賞を受賞した論文を読むことも。
またテーマとは別に、3年生が企画する「経済実験(※1)」がゼミ合宿で行われる。ゼミ生と先生が被験者となり、ミクロ経済学などにおける理論が実際に成り立つか実証するものが多く、過去の例では「公共財」というテーマなどが扱われた。笑いが起こる場面も多々あり、毎度盛り上がる人気のイベントとなっている。
※1:例えば景観保全を考えたとき、風景は誰かが独占できるものではないので、景観維持に貢献していない人でも風景を楽しめる。すると景観維持に関して寄付金を募っても、皆「他のだれかが寄付してくれるだろう。そうすれば風景をただで楽しめる」という意識から寄付をしなくなり、結果として景観維持ができなくなってしまう。このときの景観は「公共財」に当たり、実験ではこのメカニズムを応用した。
〈 授業計画 〉
輪読が中心で、学年混合の5班に分かれて担当範囲をプレゼン形式で発表していく。ゼミ中に班別での議論が頻繁にあり、大抵はゼミ生から出た質問や発表内容に対する先生のツッコミによって議論が始まる。
輪読の内容はセメスター前にゼミ生が話し合って決め、先生がテキストや論文を選ぶ。セメスターを通して1冊の教科書を読む場合もあれば、班毎に複数の論文を読んでいく場合も。
3年生によるゼミ論発表や4年生による卒論発表も行われている。
サブゼミ(※2)はAセメスターの水曜2限に行われる。先生はいないため、内容はゼミ生が主体となって決めることができ、本ゼミよりは易しめの教科書を輪読したり、経済実験が行われたりする。
※2 サブゼミ:経済学部の制度である「プロアクティブラーニングセミナー」の通称。形式上は学生の自主学習会ですが、実際はゼミの延長として関連テーマを扱う場合がほとんどで、参加者を集めた上で学部に届け出ると単位が付く授業として認められます。
〈 松井彰彦先生について 〉
1985年、東京大学経済学部卒業。(理科一類出身)
ノースウエスタン大学J.L.ケロッグビジネススクールにてM.E.D.S博士課程を修了後、東京大学大学院経済学研究科助教授を経て、2002年より東京大学大学院経済学研究科教授。
ゲーム理論と社会的障害に関する研究がご専門。
〈 他ゼミ比較 〉
ミクロ系のゼミで迷う人が割といますが、「雰囲気に惹かれて入った」というゼミ生が多い。メカニズムデザインではないミクロ理論も扱っているところが魅力
メンバー構成
・人数:3年生9名、4年生13名(うち他学部2名)。男女比は4:1程度。
・属性:ほぼ全員経済学部生だが、理系学部出身の学生もいる。所属コミュニティは運動会/運動サークル/音楽系サークルなど様々です。
・性格:
松井先生が「一芸を持つ人を集めた」と言うほど、各々が独自の趣味(クラシックギター・折り紙・競技かるたなど)を持っており、どのゼミ生も話していて面白い。飲み会や遊びの企画もあり、毎度盛り上がっている印象。
ただ勉強への熱意は共通している。ゼミの発表時には参照されていた論文を読んで自主的に発表したり、自ら理解を助ける問題を作ってくる者も珍しくない。またゼミ外で自主的に勉強会が開かれることもしばしばあり、難度の高い教科書に四苦八苦しながらも協力して読み解いていく。オフをそつなく楽しみつつ、ゼミ内外での勉強に真剣に取り組む姿勢は特徴の1つと言えるかもしれない。
ちなみに、松井先生の好みもあってフットサルにも熱を入れており、2018年のゼミ対抗フットサル大会(毎年恒例)では優勝を飾った。フットサル大会前になると、ゼミ後に練習に行くこともある。
・ダブゼミ先:例年ダブゼミする人が多数おり、ダブゼミ先は様々である。神取(ゲーム理論)・大橋(産業組織)・山口(労働経済)・佐藤泰裕(都市経済)・青木(マクロ経済学)・福田(金融)・野原(経済学史)・新宅(経営戦略)ゼミなど。
・主な進路:
大学院・コンサル・日系大手(重工業・鉄道など)。毎年2,3名前後が大学院に進学している。人数の割に院進が多いのは一つの特徴である。
活動頻度
毎週水曜1,2限。学部の制度の都合上Aセメスターの2限がサブゼミ(上記参照)扱いとなるが、時間割は年間を通して変わらない。
募集
選考は経済学部のスケジュールに準じて行われる。原則は経済学部の3年生を新規で受け入れているが、他学部を含め4年生も相談の上で応募可能。例年は1次募集で枠が埋まることが多い。
応募に際しては、エントリーシートと成績表の提出が必要。エントリーシートは「これまで打ち込んできたことと今後の抱負」を計1200文字程度で記入。
エントリーシート提出者は先生との個人面接に臨む。質問内容はオーソドックスで、自己紹介・志望理由・これまで学んできたことなど。
募集人数は毎年10名ほどで、倍率は2~3倍ほど。
年間予定
9月:2泊3日の合宿。主なコンテンツは4年生の卒論発表やミクロ経済学を用いた経済実験、フットサルの練習。先生がフットサル好きなのも手伝い、毎年コートを借りてフットサルをしている。初日と2日目の夜に先生も交えたコンパが行われ、非常に盛り上がる。
12月:OBOG会。20年を超える歴史があるため、様々な先輩に出会うことができる。
内部のホンネ
○魅力
・難しい内容に対しても積極的に議論する雰囲気がある。
・学年混合の班が割り振られており、自然とゼミ生と仲良くなれる。分からない点があると班内ですぐ共有できる。
・どのゼミ生も勉強に対して真面目。
・先生の熱意。鋭い指摘や難しい問いを投げかけてくださり、非常に勉強になる。
・延長がまずない。
~ゼミ生の声~
「思ったよりタフなゼミだな」と思いました。ただ「なぜその結果になるのか」を丁寧に突き詰める人が多く、非常に鍛えられます。またゼミ生も勉強一辺倒では全くなく、多様な趣味を持ち、様々な活動をしています。ゼミ後に昼食を食べに行ったり有志で飲み会を開くなど、縦横の繋がりも強いです!!
△大変なところ
・扱う論文やテキストは難解なものもあり、議論が長引くことがしばしばある。ただ本当に困ったときには、先生や4年が助けてくれる。
・理論を学ぶことへの熱意が求められる。
・論理記号を学ぶのは、最初のうちは少し苦労する。
・先生の問いかけが往々にして難しい(笑)。
・何といっても1限。
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウントにて告知。(3月頃から稼働開始の予定)
例年は12月に駒場で、また3月末~4月頭に本郷でゼミ説明会が行われます。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
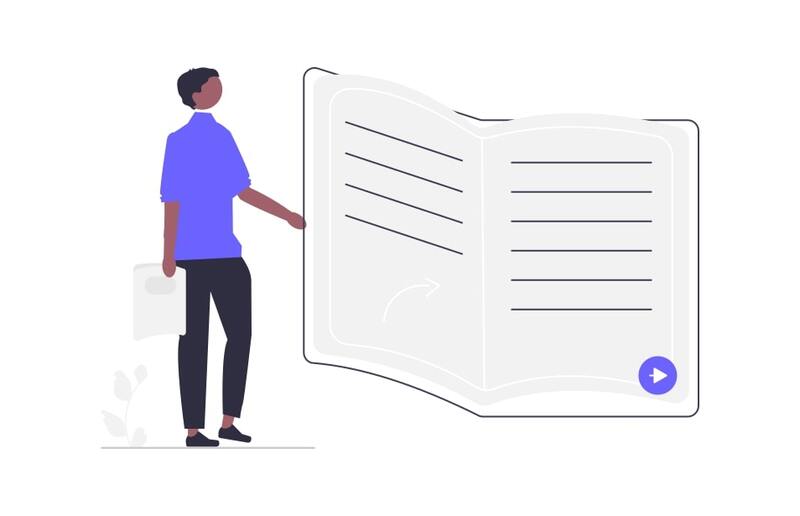
山本ゼミ
日本語・英語での文献講読や議論を通じて資本主義の歴史を探究するゼミ
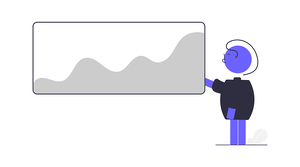
林ゼミ
租税や社会保障などの財政分野を取り扱うゼミ。

澤田ゼミ
開発経済学を学ぶ経済学部のゼミ。
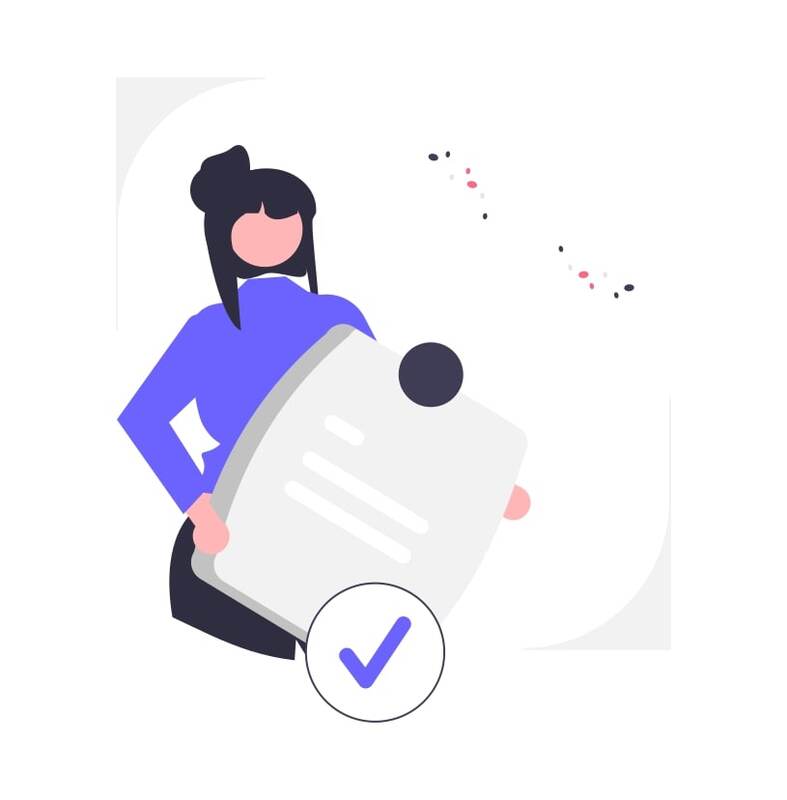
福田ゼミ
マクロ経済学や金融について幅広く学ぶゼミ。




