
中嶋ゼミ
経済学部ゼミ
マクロ
金融
ダブゼミ
マクロ経済学を学ぶ経済学部のゼミ。
創設6年目で学生がゼミの内容を主体的に決定できる。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長は4年生が担当。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生9名 4年生6名 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週木曜4限 ※基本的に延長なし |
| 卒業論文 | なし |
| ゼミ論 | なし |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
12単位 |
| 公式X | |
| 公式メアド |
nakajimazemi.ut[a]gmail.com
([a]を@にしてメールを送信してください) |
概要
<内容>
マクロ経済学の理論的な面について学ぶ創設6年目のゼミ。2023年度はGalíの "Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle" の輪読・発表を行なった。また、景気循環論に関する論文の輪読も行った。
<授業計画>
マクロ経済学に関する教科書をゼミ生で輪読していくスタイルのゼミ。輪読で扱う教科書は駒場マクロやファイナンスの発展といえる内容であり、大学院レベルの高度な理論を扱うこともある。2023年度は年度を通じてGalíの "Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle" というニューケインジアンモデルと金融政策に関する教科書を輪読した。また、Dynareというソフトを用いたマクロ経済モデルの数値計算も行った。
サブゼミも行われており、本ゼミの内容の理解を深めたり、周辺知識を理解するような内容が扱われている。参加は任意だが本ゼミの内容と補完的なので、参加することが強く推奨される。
ゼミ論や卒論が必須ではないため、それらによる負担はない。書きたい場合はもちろん書くことができるし、中嶋先生が全面的にサポートしてくださる。そのため、大学で学んだことをまとめるために卒論を書きたいという人でも大丈夫。実際に、2023年度の4年生も複数人が卒論を執筆した。
〈中嶋智之先生について〉
京都大学教育学部
↓
京都大学大学院経済学研究科(修士)
↓
シカゴ大学Ph.D(経済学)
↓
ブラウン大学助教授
↓
京都大学経済研究所助教授・教授
↓
東京大学大学院経済学研究科教授
中嶋先生は教育学部出身というかなり珍しい経歴をお持ち。本格的に経済学の勉強を始めてから2年でアメリカの名門大学院に博士留学する輝かしいご経歴。日本銀行にも客員研究員として勤めていた経験があるらしい。駒場の「マクロ経済学Ⅱ」を受講した方ならわかると思いますが、本当にきさくで優しい、笑顔の素敵な先生である。また、ゼミ中に学生がわからないところがあれば、丁寧に直感的な説明をしてくださるので、自分一人で学習するよりもずっと多くのことを学ぶことができる。
〈他ゼミ比較〉
他のゼミと比べた特徴として、プロジェクトを進めてゼミ論の発表をするという形態ではなく、主に教科書の輪読を行う点がある。したがって、プロジェクト型の活動も行いたい人はこのゼミで理論面を深めた上で兼ゼミ先でプロジェクトを行うといった学び方をするのがおすすめ。また、実証面よりも理論面を主に扱うため、理論が好きな人におすすめできるゼミである。
メンバー構成
・人数:3年生9名、4年生6名
(応募者次第なので)女子率は年度によって変わりうるが、2023年度は男子のみ、2022年度においては4年生は男子のみ、3年生は女子2名だった。過去の例をみても男子が多い傾向にあるが、人数や男女構成比に関して厳格な規定はない。
・属性:全員が経済学部生。兼ゼミは毎年3割前後。所属コミュニティとしては、バスケ部・テニスサークル・ボウリング部・自転車部など体育会系から折紙サークル・温泉サークル・書道研究会など文化系まで幅広い。
・性格:いろいろなタイプの人がいるが、全体的には真面目な人が多い印象。
・兼ゼミ先:松井ゼミ、高橋ゼミ、尾山ゼミ、大森ゼミ、小島ゼミなど
・就職先:就職先は公的機関(国家公務員含む)やコンサル、IT系など幅広い。毎年変動があるが1~3割程度の学生が経済学研究科に進学する。
活動頻度
毎週木曜4限。
毎回ではないが、日によっては延長がある。
サブゼミも存在し、学生や先生の都合に合わせて曜限を決定する。
募集
募集人数は10名程度。
原則として経済学部の3年生を新規で受け入れているが、4年生や他学部生も受け入れている。例年二次募集まで行われることが多いが、一次募集の人数次第。
選考課題は例年、A4一枚で自己紹介&経済について興味のある事を書いて提出するというもの。
成績は特に重要でないが、それなりに高度な理論を勉強していくことになるため、経済理論を楽しめる人や分からないことがあれば積極的に質問できる人に来てほしいと中嶋先生はおっしゃっていた。
わからないところがあれば上級生や先生がちゃんとフォローするので、たとえ数学が苦手であってもマクロ理論に興味があるなら心配せずに応募してほしい。
年間予定
毎週の本ゼミとサブゼミでの活動がメイン。
夏休みには希望人数次第だが勉強会を開く予定。
ゼミ後のアフターも数回実施した。合宿を開催することも検討中。
内部のホンネ
○魅力
・中嶋先生がとにかく優しく穏やか。笑顔も素敵。
(これはどの他のゼミを比較しても自信を持って言えます)
・取り扱っている教材のわからないところを的確に解説していただける。
・雰囲気が丸い。発表の際も失敗したらどうしよう、といったプレッシャーを感じる事なく落ち着いて発表できる。
・延長がないので授業や予定を入れやすい。
・発表を担当するのは月に1〜2回程度で負担があまりない。
・就職の予定などが入ってしまっても中嶋先生がそういったゼミ生の都合にとても寛容。
△大変なところ
・輪読本は英語であり文章量もあるため発表準備が少し大変。
(筆者も英弱でとても共感できますが、現代の翻訳ツールの便利さや発表頻度のおかげでなんとかなっています。)
・(特別高度な訳ではないが)マクロ経済学Ⅱで取り扱った数式が出てくるため、苦手意識を持っているとやや大変。
・(これは仕方ないことだが、)何度か休んでしまうと発表している内容を理解するのに少し苦労する。
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウントにて告知予定。
例年3月下旬~4月上旬にゼミ説明会が行われる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
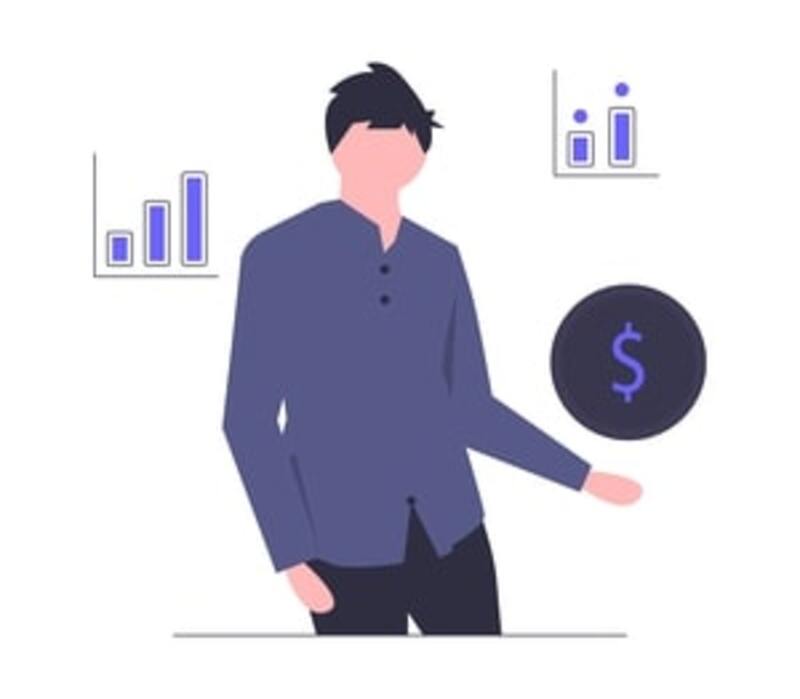
田中万里ゼミ
計量経済学について学ぶ経済学部のゼミ。

古澤ゼミ
英語で国際経済学を学ぶ経済学部のゼミ。

植田ゼミ
マクロ経済・国際金融を扱う経済学部のゼミ。

大橋ゼミ
産業組織論(応用ミクロ)を学ぶ経済学部のゼミ。




