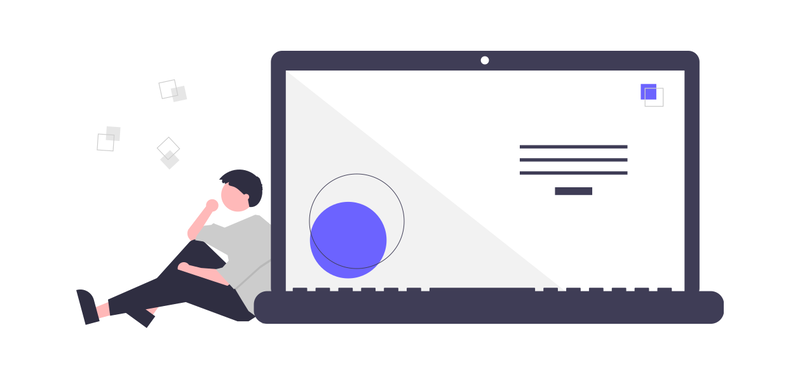
佐藤整尚ゼミ
経済学部ゼミ
データサイエンス
プログラミング
機械学習
深層学習
アプリ開発
プログラミング言語Pythonを使ってのデータ分析やデータマイニングを行う経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | 4年生の間(ゼミ2年目) |
|---|---|
| 人数 | 各学年15名ほどを予定 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週月曜4限 ※延長なし |
| 卒業論文 | なし |
| ゼミ論 | なし |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
8単位 |
| 公式X | |
| 公式サイト | |
| 公式メアド |
sato.seisyo.seminar[a]gmail.com
([a]を@にしてメールを送信してください) |
概要
<内容>
データ分析を通してプログラミングを学ぶ。佐藤整尚先生と、学生時代の先輩、そのお二人で顧問をして下さる。先生方が何か教えるというよりは、自分たちでやりたいことをやるゼミです。
2023年度Sセメスターは、初学者班と経験者班に分かれて輪読と最終課題(kaggle【データ分析コンペ】など)に取り組んだ。初心者班はデータサイエンスの基本を1から学び、経験者班は画像認識やゲームAIなどについての理解を深めた。
Aセメスターでは班を組み替え、班ごとに活動した。
[活動内容(例)]
・ポケモンAIの開発
・仮想通貨自動取引
・楽曲分析
・地価推移予測
扱った教科書は主に以下の通り。
『東京大学のデータサイエンティスト育成講座』
『PythonによるAIプログラミング入門』
その他教材, ネット上の教材も随時利用する。
<補足>
・ゼミの活動内容は毎年先生から与えられるのではなく自分たちで決められるのが特徴。望めばプログラミングまたは金融および統計に関する限り基本的には何でもやらせてもらえる。
・先生方も興味関心のある話題(例えば量子コンピュータや投資)を提供することでやることのヒントをくれる。
・有志でIT系企業との共同活動を行なっている。需要分析や株価予測などに取り組んだ。
・データ分析やエンジニア, アクチュアリー(保険数理士)などに興味がある学生を歓迎している。上記の分野に携わるOBOGも多く、話を聞くことができる。
<授業計画>
2024年度も例年通りSセメスターで基礎を固めてAセメスターで実践に取り組む。
Sセメスターでは、初学者は『東京大学のデータサイエンティスト育成講座』を、経験者は指定の教材から一つを班ごとに輪読する。なお、初学者は理学部のpythonプログラミング入門を受講することを推奨している。
Aセメスターで行う実践は夏休み中にメンバー全体の要望を聞いて決める。不安な基礎を固め直す人もいる。
サブゼミ(※)は「プログラミングのための統計」をメインテーマとし、プログラミングに関連する理論に関して深い理解を目指す。難易度としては、選択必修科目「数理統計」と同程度を想定しており、最終的には統計検定準1級〜1級の取得が狙えるレベルを目指す。
卒論は任意。
※サブゼミ:ゼミの前後に行われる補習時間のこと。経済学部的にはプロアクティブラーニングセミナー(プロアク)とされる。サブゼミが、プロアクとゼミに認定された場合は単位が認められ、そうではなければ認められない。事前に特定のメンバーが監督者(4年生または院生)となり、受講者の名前・学生証番号も全て登録しておく。
〈佐藤整尚先生について〉
平成 3年 3月 東京大学経済学部卒業
平成 5年 3月 東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了
平成 7年 6月 東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程中退
平成 7年 7月 統計数理研究所予測制御研究系助手
平成 12年 12月 博士(工学)取得(東京工業大学)
平成 14年 12月 統計数理研究所予測制御研究系助教授
平成 19年 4月 統計数理研究所データ科学研究系准教授
平成 25年 4月 東京大学大学院経済学研究科准教授
メンバー構成
【人数】:各学年15名ほどを予定。
(※ 極端な比率を避けるため、男女比を調整する場合がある)
セメスターごとに5名ほどの班分けを行うので、そこで親交を深められる。
【兼ゼミ先】:小島、柳川、新谷、植田、山口ゼミなど
ダブゼミをしている人も多い。特に金融工学や計量経済系のゼミとは親和性が高い。
【就職先】:多種多様で、金融からコンサル、ITなど幅広い。傾向としては、SIerやデータサイエンティストなどのIT系専門職か、アクチュアリーなどの金融系専門職が多い。大学院に進学する人も各学年2,3名はいる。
活動頻度
・月4の本ゼミ(延長はほぼなし)
・(任意)月5のサブゼミ(週1程度、日程はゼミ生で調整)
・(任意)共同研究プロジェクト(週1回程度)
・(任意)不定期の勉強会
募集
【参加要件】:他学部履修も可。4年生も、Sセメが就活などで忙しくない場合は歓迎する。
【応募方法】:2024年度の入ゼミ希望者には、志望動機(300字程度)、自己紹介動画(1分程度)、コーディング問題(初心者向け)の提出を求めていた。
【選考】:人数が多い場合は、ESや動画を元に選考を行う場合がある。具体的には、プログラミング経験やモチベーション、Sセメの忙しさなどから判断する。
(※ 極端な比率を避けるため、男女比を調整する場合がある)
年間予定
授業計画に加え、ゼミ合宿がある。
各セメスターに任意参加のイベント/飲み会を実施。
内部のホンネ
○魅力
・高いコミットメントを強制されるわけではないが、皆意識を高くもち勉強をしている。
・上級者が教えてくれるので、プログラミング初心者でも学びやすい環境が整っている。
・初心者でも、一年後にはプログラミングが「武器」に変わっている。
・プログラミング経験者は、Sセメスターで余裕そうにしている人が多い。その分Aセメスターで助け舟を出すことが期待される。
△大変なところ
・Sセメスター、特にS1に頑張らないと一年間の活動がつまらなく意義を感じなくなる可能性がある。最初が肝心。
・輪読したコードなどは、実際に書いてみないと全く身につかない。
・微積や線形、統計のエッセンスが絡んでくる。経済学部生向けの講義で補完することが望まれる。
・先生に引っ張ってもらう形式ではないので、そこでゼミの好みが分かれるかも。何を学びたいか明確にしておく必要がある。
・基本的に学習内容が経済学部の授業と被ることはないので少なく、機械学習に興味がないと厳しい。
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウントにて告知。(3月頃から稼働開始か)
例年は、12月に駒場で、また3月末~4月頭に本郷でゼミ説明会が行われる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
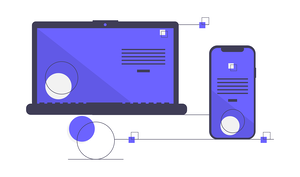
新谷ゼミ
時系列予測や機械学習を学ぶ経済学部のゼミ

佐藤泰裕ゼミ
都市経済学を学ぶ経済学部のゼミ。

米山ゼミ
会計学に関連することを学ぶゼミ。

中嶋ゼミ
マクロ経済学を学ぶ経済学部のゼミ。 創設6年目で学生がゼミの内容を主体的に決定できる。




