
桑嶋ゼミ
経済学部ゼミ
技術経営
イノベーション
経営戦略
OBOG
経営戦略・イノベーションを学ぶ経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長は4S~4A。 ゼミ長・副ゼミ長については前ゼミ長と先生で話し合って決める。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生7名、4年生7名 ※原則1学年7名前後。 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週木曜4限 ※発表会などを除けば、ほぼ延長なし。 |
| 卒業論文 | あり |
| ゼミ論 | あり |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
16単位 |
| 公式X |
概要
〈内容〉
経営戦略やイノベーションについて、輪読を通して幅広く学ぶ。ゼミ論・卒論は個人が自由なテーマで3年・4年時それぞれ執筆する。テーマは必ずしも経済学に絡まないものでもOK。先生がビジネススクールでの指導経験をお持ちなので、そのコネクションを用いて様々な方のお話を伺う機会がある。
〈授業計画〉
両学年ミックスで活動する。両セメスターで輪読を行う。
1年を通して3年生はゼミ論、4年生は卒論を執筆する。輪読の合間合間に論文の中間報告会が入るイメージ。ゼミ論については4名程度でチームを組んで執筆する。
輪読については、本の選定を先生が行うが、ゼミ生側から要望があればそちらを扱うこともある。2020年度Sセメスターでは「戦略の教科書」(ハーバードビジネススクール)、Aセメスターでは「ジョブ理論」(クリステンセン)を扱っている。
また、サブゼミは行われ単位認定も行われるが、そちらは論文の発表前にゼミ生同士の相互確認を行う程度で、輪読などは行わない。
※サブゼミ:ゼミの前後に行われる補習時間のこと。経済学部的にはプロアクティブラーニングセミナー(プロアク)とされる。サブゼミが、プロアクとゼミに認定された場合は単位が認められ、そうではなければ認められない。事前に特定のメンバーが監督者(4年生または院生)となり、受講者の名前・学生証番号も全て登録しておく。
〈他ゼミ比較〉
経営系の新宅ゼミ・高橋ゼミ等と検討して入ってきた学生は多い。新宅ゼミや高橋ゼミは、輪読と論文執筆双方で経営及び企業戦略に関連する分野を扱うイメージだが、桑嶋ゼミは取り扱う範囲が広いこと、論文のテーマが自由で経営分野に限らないことなどが特徴である。
メンバー構成
・人数:3年生7名、4年生7名。女子率は2割程度。
・属性:全員が経済学部生。兼ゼミは原則禁止であるため、全員桑嶋ゼミのみの所属である。
・就職先:人数が少ないので傾向は特にないが、今年の4年生の就職先は証券・コンサル・ベンチャー等である。
活動頻度
毎週木曜4限。サブゼミがあり、単位認定も行われる。
募集
原則、経済学部の3年生を新規で受け入れており、4年生の募集は無い。例年一次・二次募集を行う。選考は経済学部のスケジュールに準じて行う。
応募に際しては、エントリーシートの提出が必要。自己紹介、本ゼミを志望した理由、興味のある研究テーマをA4二枚でまとめる。
エントリーシート提出者は、その後面接を行う。先生は自分のゼミにマッチする生徒であるかどうかを最も重視しているため、主に対話を通して生徒の人柄を見ていく。
募集人数は毎年7名程度。選考は先生とゼミ生で相談して行っている。倍率は低めで、1倍台のことも多い。
年間予定
両セメスター共に毎週木曜日の4限にゼミを行う。
基本的には輪読を行い、合間に卒論とゼミ論の中間報告会がある。具体的な日時は未定だが、2020年度は合計4回中間報告があった。
1月:ゼミ論・卒論発表会
1年間を通して執筆したゼミ論・卒論の発表会を行う。発表会には先生とゼミ生はもちろん、OB/OGも参加し、中には一部上場企業の社長もいらっしゃる。
内部のホンネ
○魅力
・OB/OGが豊富で経営者・ビジネスパーソンと交流の機会がある。直近でいらっしゃったのはアサヒ飲料社長の米女さん。
・ゼミ論・卒論のテーマが自由
・雰囲気は和やかで、ビシバシ議論する感じではない。
△大変なところ
・先生がゼミ論・卒論の報告に対して若干辛口。
・ゼミ公式の飲み会があまりない(人によっては良い?)
・輪読の回では、自分の発表回でなくてもレジュメを毎回作る必要がある。
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウント(上記)にて告知。(3月頃から稼働開始か)
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事

青木ゼミ
マクロ経済学に基づいて身近な現象を分析する力を養う経済学部のゼミ。
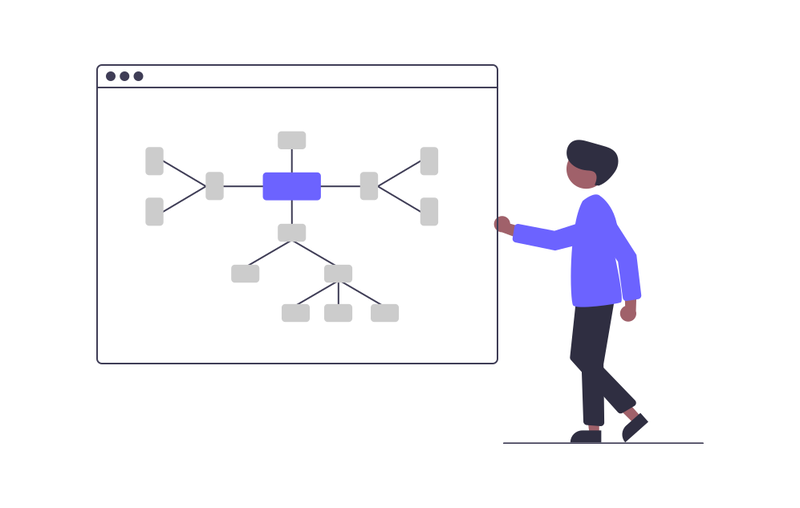
尾山ゼミ
プログラミング言語Pythonを用いて経済理論を学ぶゼミ。

中嶋ゼミ
マクロ経済学を学ぶ経済学部のゼミ。 創設6年目で学生がゼミの内容を主体的に決定できる。
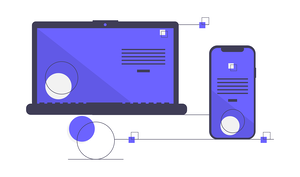
新谷ゼミ
時系列予測や機械学習を学ぶ経済学部のゼミ




