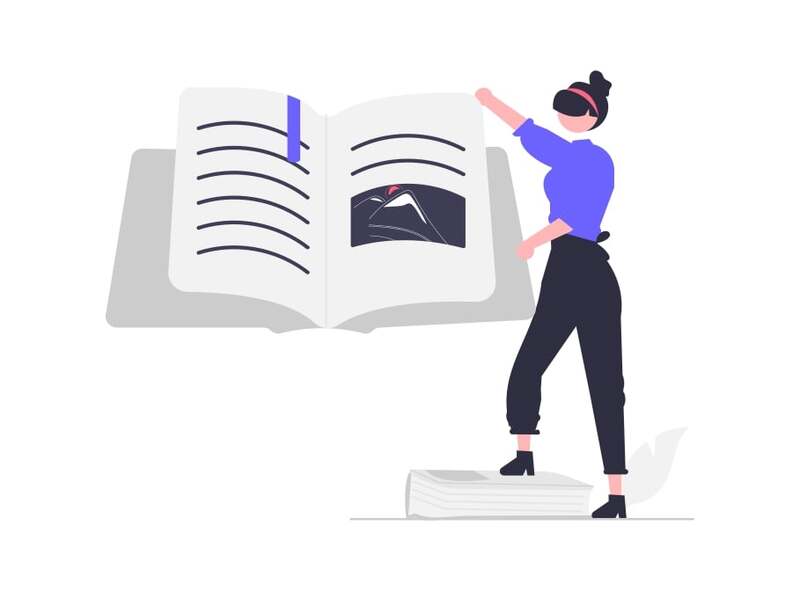
神取ゼミ
経済学部ゼミ
ミクロ
ゲーム理論
メカニズムデザイン
情報の経済学
ゲーム理論・メカニズムデザイン・情報の経済学などについて学ぶ経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミ長は4年生が担当。 OBOG係や合宿係について3年生が行い、4年生はサポートに回る。 ゼミ長については希望者が担当する。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生10名、4年生7名 ※原則1学年7~10名前後。 |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週月曜4限 |
| 卒業論文 | あり |
| ゼミ論 | なし |
| サブゼミ | なし |
|
2年間の
合計単位数 |
8単位 |
| 公式X |
概要
主にゲーム理論・メカニズムデザイン・機械学習に関連した分野を扱う。最先端の研究分野について広く学びが得られる。
2020年度以降は、オークション理論やマッチング理論といったマーケットデザインと呼ばれる分野について学んでいる。近年は、機械学習をマーケットデザインに応用するといった研究も扱っている。論文などの輪読だけでなく、プロジェクトとして理論を現実社会の問題にどう応用するか等を考えるグループ発表も行われている。
2018年度は繰り返しゲームとカルテル、2019年度はインフォメーションデザインを扱った。
〈 授業計画 〉
両学年ミックスで活動する。2021年度では進振り制度におけるDAアルゴリズムの改善やシミュレーション、経済学部のゼミマッチングにおけるDAの活用などについてグループ発表が行われた。2022年度や2023年度は、機械学習を用いて得られたオークションやマッチングのメカニズムを、理論的にも解析することを試みた。4年生は自身の卒論テーマについての発表も行う。
輪読について、本や論文の選定は先生が行う。2021年度Sセメスターでは小島武仁先生が執筆したマッチング理論のテキストを小島ゼミと合同で行った。最新の機械学習に関する論文を読み、そこからゼミ生達でコーディングをする事などもある。
〈 神取道宏先生について 〉
- 1982年東京大学経済学部卒業。
- 1989年スタンフォード大学経済学部博士。
- ペンシルべニア大学経済学部助教授、プリンストン大学経済学部助教授、東京大学経済学部助教授などを経て、1999年より東京大学経済学研究科教授。
- ミクロ経済学・ゲーム理論の世界的研究者であり、2020年度よりゲーム理論の代表的国際学会であるGame Theory Society副会長、東京大学マーケットデザインセンター副センター長。
- 2022年から2024年までgame theory society会長 (詳細:http://www.e.u-tokyo.ac.jp/fservice/faculty/kandori/kandori-j/kandori01-j.html)
メンバー構成
・人数:3年生10名、4年生7名。女子率は2割程度。
・属性:全員が経済学部生だが、他学部生(法学部など)が在籍していたことも。理系出身者、文3出身者など文2以外から経済学部に来ている人も多い。また、兼ゼミしている人も多い。所属コミュニティとしては、例年運動会、音楽系、ゆるめの愛好会まで多岐にわたっている。
・性格:基本的にしっかりと勉強や議論はするが、外向的で明るい学生が多め。
・兼ゼミ先:ミクロ系の松井ゼミや小島ゼミ、経営系の片平ゼミや大木ゼミ、計量系の奥井ゼミや下津ゼミ、入江ゼミ等。
・就職先:特に毎年一貫した傾向がみられるわけではないが、2021卒では官庁や銀行・証券会社など金融系に進む人が多かった印象。院進は4名。2020卒では起業している方もいた。
活動頻度
毎週月曜4限。
募集
原則、経済学部の3年生を新規で受け入れている。例年二次募集が実施されている。
選考は経済学部のスケジュールに準じて行う。
応募に際しては、レポートの提出が必要。現在関心を持っている経済学の内容、大学入学後に読んで感銘を受けた学術書2冊の要約と感想、志望動機や自己PRなどを3000字程度でまとめて提出する。
その後先生との1対1の個人面談が数分行われ、主にレポートに書いた内容について聞かれる。人によって掘り下げられるポイントは様々である。
募集人数は毎年10名程度だが年度によって変動あり。選考は先生が行っている。
年間予定
4月:新入生歓迎会
9月:グループ発表の準備
Sセメで学んだことを生かし、Aセメでのグループ発表の準備を各グループごとに行う。
2月:ゼミ合宿
京都大学の情報系の研究室と繋がりがあり、京都で研究発表を行う。京都観光もできる。
3月:OBOG会
内部のホンネ
○魅力
・最先端の経済学のテーマについて学ぶことができる。
・ゼミ生全員が詰まってしまうようなポイントでも先生が直感的にわかるように配慮しつつ説明をしてくれる。
・厳密な理論の理解と並行して、理論の現実世界への応用についても考えることができる。
・2019年度には学部生ながらEconometrica誌に論文を載せた先輩がいたほか、卒論に関しても特選論文受賞者が安定的に輩出しているので、論文をちゃんと書きたい人にもおすすめなのかもしれない。
△大変なところ
・テキストや論文の内容を正確に理解していくのが難しい。
・発表で思ってもみなかったところで先生や学生からの突っ込みが入るのでそれに丁寧に対応していく必要がある。
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウントにて告知。(12月頃から稼働開始か)
例年は、12月に駒場で、また3月末~4月頭に本郷でゼミ説明会が行われる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事
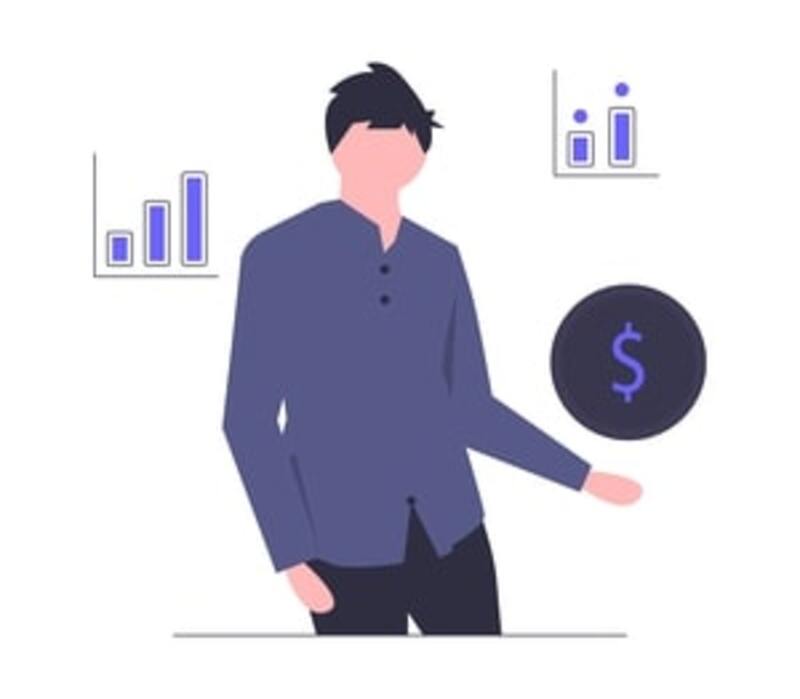
田中万里ゼミ
計量経済学について学ぶ経済学部のゼミ。
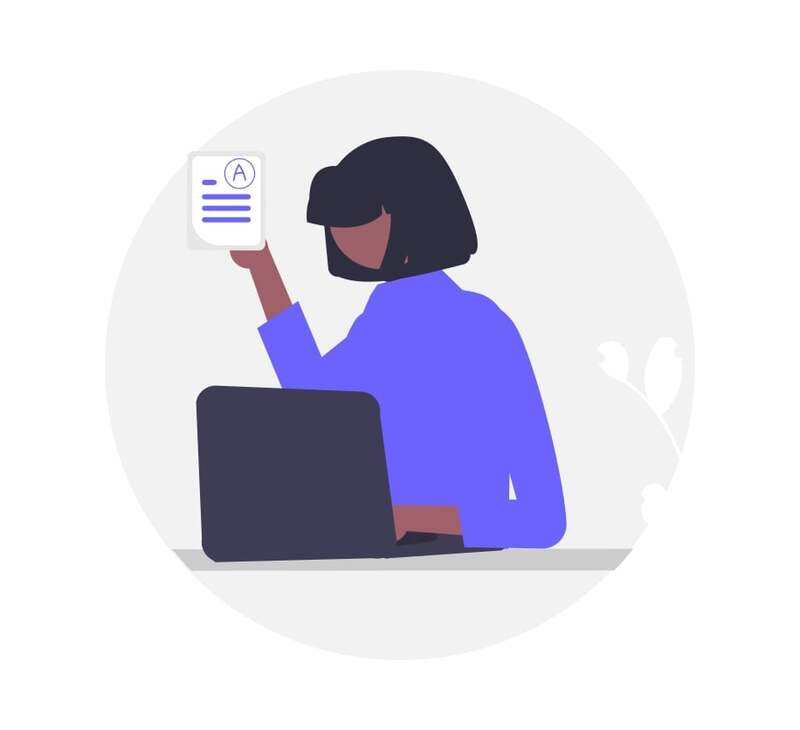
小島ゼミ
マーケットデザイン、マッチング理論について学ぶ経済学部のゼミ。

渡辺努ゼミ
マクロ経済学(金融政策)を学ぶ経済学部のゼミ。

中嶋ゼミ
マクロ経済学を学ぶ経済学部のゼミ。 創設6年目で学生がゼミの内容を主体的に決定できる。




