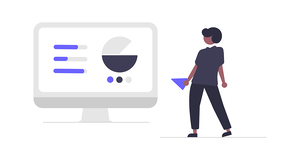
谷本ゼミ
経済学部ゼミ
経済史
近代経済史
単位効率
教授が優しい
就活との両立
基本的には近代経済史を学ぶ経済学部のゼミ。
ただし卒論やゼミ論のテーマは自由。
目次
基本情報
| 執行代 | ゼミの中で執行代といった役割は定められていない。ゼミ説担当とフットサル担当は決まっている。 |
|---|---|
| 人数 | 3年生9名、4年生5名 ※例年来ただけ取ると言われている(もちろん限界はあるが) |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週木曜4限 ※延長が多い(15時~17時半) |
| 卒業論文 | あり |
| ゼミ論 | あり |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
16単位 |
| 公式X |
概要
〈内容〉
近代経済史の範囲内で例年テーマを設けて著書や論文の輪読による学習を行う。その後近代経済史に限らないテーマのゼミ論作成に取り掛かる。卒論の内容とゼミ論の内容は一致しなくてよいので、自分がその時々に研究したい内容について自由に研究することが可能。教授はどんなテーマ(スポーツ、アイドル、化粧品マーケ、経営戦略など)の発表についても優しく聞いてくださり、質問を通して内容を深めたりアドバイスをしてくださる。
サブゼミは学生が自由に研究したい内容を一つ選定し、そのテーマについて研究する。
〈授業計画〉
両学年ミックスで活動する。
Sセメでは輪読を行う。
Aセメでは三年生はゼミ論、四年生は卒論の進捗報告を行う。
さらにAセメではサブゼミが開講される。
Sセメの輪読については、書籍の選定を先生が行う。2020年度Sセメスターでは『知識経済の形成』(ジョエル=モキア)を扱った。
また、サブゼミ(※)が現在は木曜昼(毎年日程調整を行うので心配なし)に行われ、単位認定も行われる。そちらでも輪読を行う。「リブラの正体」(リブラ研究会)を読み、ディスカッションする。3,4年生ともに全員参加。
※サブゼミ:ゼミの前後に行われる補習時間のこと。経済学部的にはプロアクティブラーニングセミナー(プロアク)とされる。サブゼミが、プロアクとゼミに認定された場合は単位が認められ、そうではなければ認められない。事前に特定のメンバーが監督者(4年生または院生)となり、受講者の名前・学生証番号も全て登録しておく。
〈谷本雅之先生について〉
基本情報:
東京大学大学院経済学研究科教授。研究課題は,近代日本の経済発展を「近代工業化」と「在来的経済発展」の複層的発展として描き出すこと。
(詳細:http://www.e.u-tokyo.ac.jp/fservice/faculty/tanimoto/tanimoto.j/tanimoto01.j.html)
ゼミ生視点:
優しい。ゼミ生の発言を受け止めた上で問題となる論点や改善につながりそうなアイデアや知見を教えてくださる。話し好きなイメージがある。対面で会えた際にコロナ関連の世間話をしたところ、ゼミ後にもかかわらず喜んで話してくださった。教授って気難しい方が多いのかなとか発言して詰められたら嫌だなと思っていたが全くそんなことはなかった。とにかく温厚な方。
〈他ゼミ比較〉
他ゼミと迷ってというよりも、自由さや単位効率の良さを目当てに入ってきた学生が多い印象。
メンバー構成
・人数:3年生9名、4年生5名。女子率は1割程度。来たら来ただけ取ると例年言っているそう。
・属性:全員が経済学部生。兼ゼミは現在ほぼいないが、歓迎。所属コミュニティはバラバラで、経友会・テニスサークル・音楽系サークル・自動車部など。
・性格:就活と両立している学生が多く、オンオフの切り替えがうまい学生が多い印象。オフライン活動時はゼミ後にご飯を食べに行ってた(完全任意参加)。
・兼ゼミ先:少数だが、西村ゼミなど。
・就職先:日系IT、飲料メーカー、コンサルなど
活動頻度
毎週木曜4限。サブゼミが木曜昼に開講され、単位認定も行われる。(サブゼミの曜限は毎年日程調整の上で決まる)
募集
経済学部の3、4年生。例年二次募集まであることが多い。選考は経済学部のスケジュールに準じて行う。
応募に際しては、エントリーシートの提出が必要。ゼミの志望理由とこれまでに読んだ経済関連の書籍について。
募集人数は毎年できる限り来ただけ取る。
年間予定
両セメスター共に毎週木曜日の4限にゼミを行う。
夏休み:希望者が多ければゼミ合宿を行う。
Sセメ:輪読を行う
Aセメ:三年生はゼミ論、四年生は卒論の進捗報告を行う
加えてAセメではサブゼミが開講される
内部のホンネ
○魅力
・単位効率が良い。およそ1.5ヶ月に1回の担当で、1回あたり3~5時間の準備で対応可能。サブゼミは2時間で対応可能。
三年生になると就活・サークル・学生団体・授業課題・友人との交流などで意外と忙しい。ゼミ選択後にゼミに割ける時間が限られていることに気づいたが、このゼミに入って本当に良かったと思っている。
・先生がとても優しい。ゼミ生と積極的にコミュニケーションを取ってくださり、よく理解してくださっている。就活で外せない予定がゼミと被った際には事前に相談すれば柔軟に対応していただける。
・卒論、ゼミ論のテーマが自由。自分が研究したいことを自分の好きなタイミングで研究できる。先生は一切否定することなく内容を高めようとしてくださるのでありがたい。
△大変なところ
・延長が多い。時間割上では木曜4限だが、基本的に17:30までゼミがある。
・OBとの交流がない。(最近はOB訪問アプリが充実してきたので、大きな障害にはならない)
・卒論やゼミ論を書きたくない人は嫌かもしれない。(普段の授業期間にゼミ論・卒論を少しずつ進めて進捗報告すること自体を課題とするのでしんどくない。ゼミ論・卒論の進捗と並行して更に課題を課されるゼミはきつそう。)
・テーマ設定や選考プロセスが比較的緩いこともあり、ゼミ内での一体感が薄くなりがち。
・同じ専門分野のゼミ同期と議論したり、専門のディシプリンを極めたりしたい学生には、やや物足りない環境かもしれない。
新歓日程詳細
Twitter新歓アカウントにて告知。(@tanimotosemi21)
例年は、12月に駒場で、また3月末~4月頭に本郷でゼミ説明会が行われる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事

米山ゼミ
会計学に関連することを学ぶゼミ。
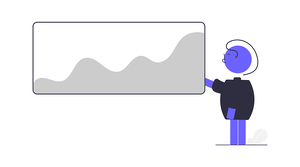
林ゼミ
租税や社会保障などの財政分野を取り扱うゼミ。

植田ゼミ
マクロ経済・国際金融を扱う経済学部のゼミ。

青木ゼミ
マクロ経済学に基づいて身近な現象を分析する力を養う経済学部のゼミ。




