
星ゼミ
経済学部ゼミ
日本経済
経済政策
政策評価
EBPM
日本の経済政策、およびEBPM(証拠に基づく政策形成)を学ぶ経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | 4年生 |
|---|---|
| 人数 | 4年生(2024年進学):8人(うち2人留学中) |
| 参加学年 | 3・4年のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 毎週木曜日4限 |
| 卒業論文 | なし |
| ゼミ論 | あり |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
8単位 |
| 公式X | |
| 公式メアド |
thoshiseminar[a]gmail.com
([a]を@にしてメールを送信してください) |
概要
<内容>
①経済学に関する研究テーマを設定し、共同研究を行う。
②並行して、ゲストスピーカーの講演を通して多角的な視座を育む。
<授業計画>
年間を通して上述した研究を行う。また、研究を進めるにあたって必要となる知識の習得などを目的に、官僚・政治家・外部の有識者をお招きして講演をしていただく。研究については、3人程度の学年混合グループに分かれて、それぞれメンバーの興味関心に沿ったテーマについて研究する。2024年度は「ふるさと納税と税収の再配分」「大阪万博の経済効果について」「最低賃金政策の所得向上に対する有効性」などのテーマを扱った。ゲストスピーカーの講演(2024年度)については、河野太郎元大臣、竹中平蔵元大臣、雨宮正佳元日銀副総裁などをお招きした。
<星岳雄先生について>
主な研究分野は金融論、マクロ経済学、日本経済論。1983年東京大学教養学部卒業後、マサチューセッツ工科大学院に進学。そのまま2019年9月まで、基本的にはアメリカの大学で教鞭を執る。2012年から2019年8月までスタンフォード大学教授。また、1997年から1998年まで、日本銀行金融研究所で客員研究員を務めた。2019年9月より、東京大学大学院経済学研究科 教授(現職)。2021年4月より、東京大学大学院経済学研究科長・経済学部長(2023年3月末日まで)。
<他ゼミ比較>
マクロ系のゼミという扱いをされることが多いが、一般的なマクロ系ゼミのように数式や数学を駆使して研究するよりも、その結果の解釈や考察などに重点を置く。そのため、グループ研究の内容にはよるものの、概して数学的な知識はあまり登場せず、むしろ数式の変形だけでは捉えきれないものを思考することが大事にされている(班員の好みによっては簡単なモデルを立てて分析する場合もある。)。研究テーマの自由度はかなり高く、星先生のご専門と異なる分野のテーマも可能。"
メンバー構成
- 人数:2024年度は4年生8名、3年生8名。女子は16名中4名(うち3年生1名)。
- 属性:2024年度は全員経済学部生。学科は経済学科から金融学科まで幅広い。兼ゼミは可能。ゼミ生の所属コミュニティも、運動会から文化系サークルまで幅広い。
- 性格:研究を複数人のグループで行う関係上、他のメンバーとの協調が求められることもあり、ゼミ生同士の仲は良い。各セメスター終了時には星先生との食事会も開催され、通常のゼミ後も場合によっては希望者で夜ご飯に行く。フットサル大会への参加・ゼミでの遊びなどもあり、プライベートも充実できるゼミ(これらへの参加は希望制)。
- 兼ゼミ先:元重ゼミ、楡井ゼミなど
- 就職先:2024年度は官公庁、政府系金融機関、民間金融機関、コンサル、総合商社など幅広い業界
活動頻度
毎週木曜4限。基本延長はない(あっても5〜10分程度)。ゼミ時間外の負担はグループによるが、一般的な程度。
サブゼミも存在し、「プロアク」として単位認定されている。2024年度はSセメスターのみ、毎週金曜4限に実施した。実施するかどうか、その曜日についても3・4年生で相談して決める。
募集
募集は経済学部のスケジュールに準じて行われる。星先生はゼミ生の多様性を求めており、他学部生の応募も歓迎される(ただし、他学部生に単位は出ない)。
2024年度は二次募集まで実施された。2025年度については、3年生を主に募集するものの、新4年生の参加も可能である。また、2025年度は一次募集のみを行う予定である。
応募に必要な書類は、自己紹介・興味のある経済問題についてA4の紙1枚のエッセイ。書類選考通過者には、提出した資料をもとに星先生・ゼミ生数人と約15分の面接が行われる(いずれも内容は2024年度。2025年度募集も内容を大きく変える予定はない。)
募集人数は6〜8人を予定。
*星先生が2025年度をもってご退官されるため、星ゼミは2025年度が最終開講となります。
年間予定
グループ研究を軸に、ゲスト回を組み合わせる。
各セメスターの研究内容はゼミ生全員から意見を募って決定する。
内部のホンネ
○魅力
・ゲストが豪華
・3年4年の距離が近く、研究でも協調的
・星先生の知見が幅広い
・ゼミ生がみんな優しくかつ優秀で熱意のある人が多い
・ダイバーシティに富んだ人材がいる(部活面でも、就活面でも)
・比較的新しいゼミでゼミ生主導でさまざまな改革が行われており、意見も反映されやすい
・机上の経済理論研究と官僚など政策担当者の実際のリアルな経済政策を両方学べる
△大変なところ
・経済学の講義はないので、研究の必要に応じてキャッチアップ・復習
・星先生はゼミ生に対して真摯に向き合って指摘をなされるので、ゼミ生の前で星先生とやり取りする時はやや緊張するが、多くの学びが得られる
・グループによってはモデル分析をする場合があり、ある程度の数学力と統計、経済の基本的な知識が必要(星先生のアドバイスを都度受けられます)
新歓日程詳細
主にX新歓アカウントにて告知。また、経済学部や経友会のゼミイベントなどには基本的に参加予定。
Xにて質問箱を設置。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事

片平ゼミ
3、4年生対象の、ブランドマーケティングについて学ぶ自主ゼミ。
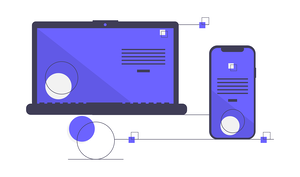
新谷ゼミ
時系列予測や機械学習を学ぶ経済学部のゼミ
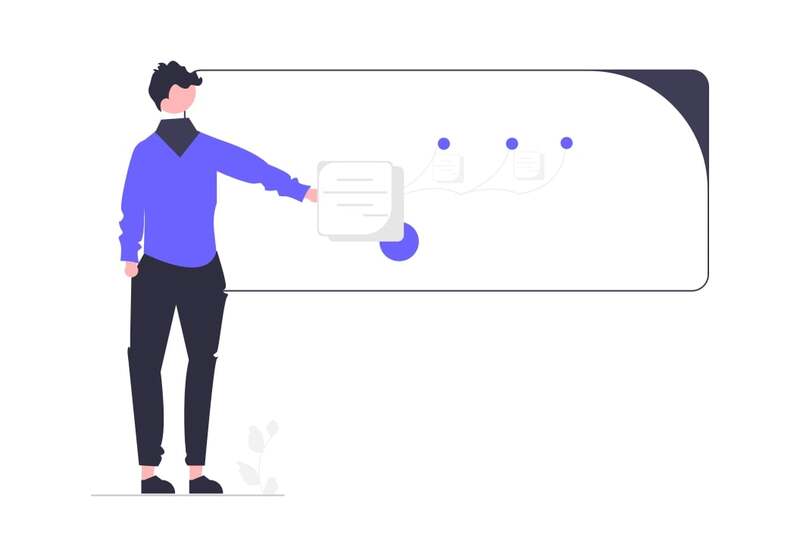
粕谷ゼミ
経営史(日本経営史)・経営学を学ぶゼミ

柳川ゼミ
ビジネスエコノミクスを学ぶ経済学部のゼミ。




