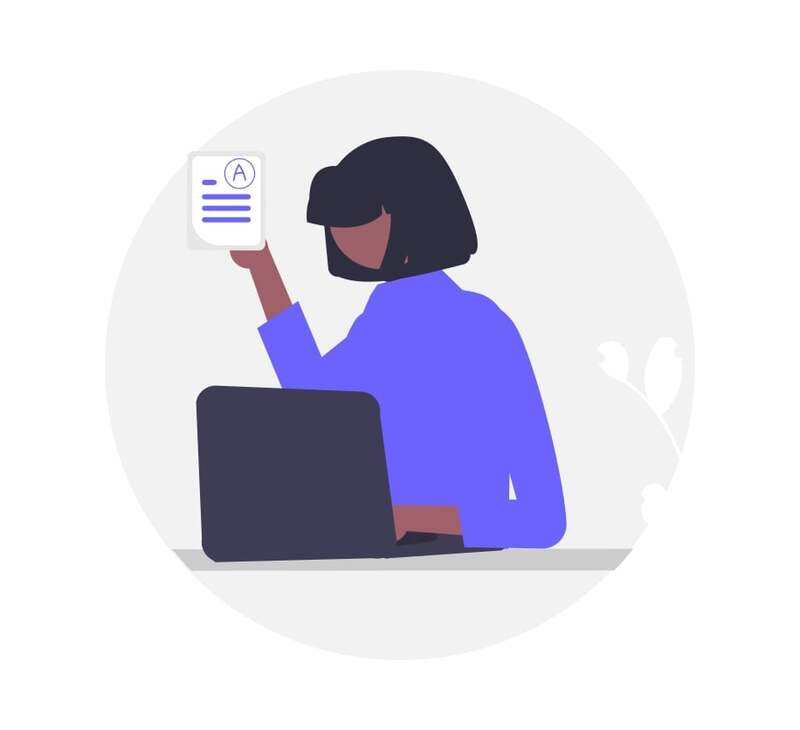
小島ゼミ
経済学部ゼミ
ミクロ
ゲーム理論
マーケットデザイン
マッチング
オークション
マーケットデザイン、マッチング理論について学ぶ経済学部のゼミ。
目次
基本情報
| 執行代 | 四年 |
|---|---|
| 人数 | 2024年度は、3年生14名、4年生9名 |
| 参加学年 | 学部生のみ |
| 選考 | あり |
| 活動頻度 | 火曜4限(基本的に全員参加のサブゼミが火曜5限にある。延長なし) |
| ゼミ論 | なし |
| サブゼミ | あり |
|
2年間の
合計単位数 |
12単位 |
| 公式X | ut_kojima_semi |
概要
〈内容〉
マッチング理論の基礎とその応用について学ぶ。マッチング理論は市場制度を「設計できるもの」として捉えて人やモノ・サービスを効率よく結びつけることを目指す「マーケットデザイン」という分野において頻繁に用いられる基礎的な理論である。ゼミでは最初に基礎的なマッチング理論を学んだのち、学生の興味に応じてプロジェクトを行うことを目指す。
〈授業計画〉
両学年ミックスで活動する。Sセメスターでは基本的なマッチング理論の教科書と論文の輪読を行う。Aセメスターでは、発展的な内容を学びつつプロジェクトなどを行うことを目指す。
〈小島武仁先生について〉
2003年、東京大学経済学部卒業。
2008年、ハーバード大学経済学部博士
イェール大学(博士研究員)、スタンフォード大学(助教授、准教授、教授)などを経て、2020年より東京大学大学院経済学研究科教授、東京大学マーケットデザインセンター(UTMD)センター長。
(詳細:https://sites.google.com/site/fuhitokojimaeconomics/fuhito-kojima )
〈他ゼミ比較〉
マッチング理論において数学やゲーム理論の特別な知識は最初は求められないが、証明や重要な概念について丹念に追う必要がある。
メンバー構成
人数:3年生14名、4年生9名、女子率は3割程度。
属性:ほぼ全員が経済学部生。理科系出身者が3名。7割が兼ゼミ。所属コミュニティとしては、運動会、ダンス、音楽、テニス、学生団体/ディベート/ゼミ系など多様である。
性格:理論の細かい証明や意味合いについて徹底的に突き詰めて議論しようとする気概のある人が多い。ゼミ外の交流として、2024年度は夏合宿を軽井沢で行った。
兼ゼミ先:神取・松井といったミクロ系のゼミだけでなく、市村・下津など計量系、渡辺努などマクロ系のゼミと兼ゼミしている人が多数。稲水・新宅・大橋など経営系のゼミと兼ゼミしている人もいる。トリゼミしている人も少なくない。
就職先:院進希望者が多めだが、民間企業に就職する人や官僚を目指す人もいる。
活動頻度
毎週火曜4限。(基本的に全員参加のサブゼミが火曜5限にある)
募集
経済学部の新3年生を募集している。人数に応じて2次募集も行うが、2022年度は1次募集のみで定員に達した。選考は経済学部のスケジュールに準じて行う。
応募に際しては、エントリーシートの提出が必要。A4で1ページ分、志望動機、アピールポイント、プロジェクト案などを好きにまとめる。文章でも絵でもよい。
その後、先生と15分ほど個人面談が数分行われる。主にエントリーシートで書いた内容について質問される。
毎年の募集人数は10名程度。選考は先生が行っている。倍率は不明。
年間予定
両セメスター共に毎週火曜日の4限にゼミを行う。
内部のホンネ
○魅力
・日本のみならず世界を代表するような教授と、文字通り最先端の研究に触れられる。経済学の最前線に立ち続けている先生だからこそ、経済学のリアルが感じられて面白い。
・優秀な学生が多い。
・先生もかなり積極的に議論に参加していただけるため、かなり濃いゼミとなり、新しい論点や気づきがたくさん得られる。
・積極的に発言する人が多く、みんなで協力して理解しようとする空気感が大きい。
・多様な学生がいて、明るく楽しいゼミになっている。
△大変なところ
・扱う論文が誇張なく最先端なケースが多く、非常にレベルが高い。
・内容の面白さと難しさが表裏一体。
新歓日程詳細
Twitterアカウントにて告知。
12月に駒場で、また3月末~4月頭に本郷でゼミ説明会が行われる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
関連記事

青木ゼミ
マクロ経済学に基づいて身近な現象を分析する力を養う経済学部のゼミ。
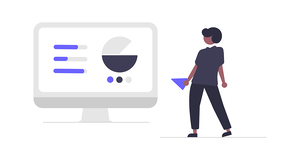
谷本ゼミ
基本的には近代経済史を学ぶ経済学部のゼミ。 ただし卒論やゼミ論のテーマは自由。

古澤ゼミ
英語で国際経済学を学ぶ経済学部のゼミ。

新宅ゼミ
経営戦略を学ぶ経済学部のゼミ。




