教養学部
統合 物質基礎科学コース
2023.4.15
統合自然科学科 物質基礎科学コース
目次
基本情報
| 人数 |
10~20名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ1-2割 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
コース別の情報はなし |
| 公式サイト |
http://www.integrated.c.u-tokyo.ac.jp/admission/courses/course2/ |
学科概要
■どんな学部?
原子、分子、高分子、結晶、新材料、生体を扱っている。様々な階層の物質の物理学あるいは化学を、学生の志向に応じて、深く、且つ広く学び、ミクロからマクロの様々なスケールに渡る物質世界に対する、新しい時代のニーズに対応できる人材を育成。従来の物性物理学、原子核物理学、素粒子物理学、物理化学、有機化学、無機化学などの分野を全てカバーするだけではなく境界領域、領域横断的なところに位置する新しい科目を加えている。物理学的な指向性、化学的な指向性も伸ばしつつ、他の諸学科では決して得ることのできない領域横断的プログラムを学ぶことができる。
■統合物質コースの諸制度
卒業までに必要な単位は76単位以上。
内訳は、度数科目が6単位以上、コース科目から34単位以上、他コース科目から16単位以上(合併科目含む)、卒業研究10単位
■進学定数は?
定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理科(指定科類) | 12 | 8 |
・理1から進学する人が多い。
■内実は?
・興味が多岐にわたっている人が多い。生物と化学と物理と数学の授業を1セメスターでとる人もいる。
・化学、物理に興味を持っている人が比較的多い。融合分野に興味がある人もいる。
・部活に入っている学生は多くない。
・学科の特徴として、授業のカリキュラムを自分で柔軟に組むことができるため、インターンや課外活動で忙しい人もいれば、勉強に集中している人もいる。
■コースの違いは?
本コースは、4コースある統合自然科学科の1コースであり、自然の数理的構造を探求する。様々な数理的概念の理解を深めるとともに、広く自然現象の背後にある数理的構造を学ぶ。「統合自然科学」の名のように、自然科学を統合的に理解しようとする動機のもとで学んだ、高度な数理的考えや手法を様々な分野に生かせる人材の育成を目指す。
※統合自然科学科4コース
・数理:自然の数理的構造の探究
・物質:原子から生体物質まで広く物質の真理を追求
・統合生命科学:生体と生命現象の本質を探究
・認知行動科学:人間・動物などの個体や集団の研究
※スポーツ科学サブコースも存在し、上記の4コースのいずれかに加えて履修することができる。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【物理、化学を自由に学ぶ】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 統合自然科学セミナー | 必修 | 月曜2限 |
(※1)先生1人につき4人程度でわかれて論文を読んだり演習問題を解いたりする。例えば素粒子の論文輪読では、素粒子の授業は、通常4年生や院生が受講するものであるため内容は難しいが、同時に良い刺激にもなるという声もある。。学期の最後には加速器の見学もあった。
セミナーでどんなことをやるのかは先生にもよるが、他の学科では学べないようなことを学べるということはどの先生にも共通している。
・履修が統合自然科学セミナーの一コマを除いて完全に自由。
・前期教養の理系の必修でやったような科目はわかっている前提で進む。
3年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 物質科学セミナーⅠ | 必修 | 水曜1限 |
| 物質科学実験Ⅰ | 必修 | 火、水曜午後 |
(※1)化学系、物理系の実験に分かれている。
・「バイオソフトマターの物理」が特に印象に残った。物理、生物の教授がそれぞれ生物物理について解説する授業で、物理と生物両方の視点からの解説は他の学科では受けられないと思う。
3年生Aセメスター
■【研究室について考え始める時期】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 物質科学セミナーⅡ | 必修 | 水曜1限 |
| 物質科学実験Ⅱ | 必修 | 火、水曜の午後 |
4年生Sセメスター
■【最先端の研究に触れる】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 物質科学セミナーⅢ | 必修 | 金曜2限 |
| 物質科学実験Ⅲ | 必修 | 火、水曜午後 |
・4Sの実験からは、研究室に配属される。学科の学生は一学年50人ほどしかいないが、研究室振り分けの候補として送られてきたエクセルのファイルに、80以上の研究室が載っていた。
・コースを跨いで研究室を選ぶことができる。
・4Sの配属は実験的なものであり、Aセメスターに研究室を変えることもできる。
・4Sでは火曜と水曜に研究室に行く必要があるが、それ以外の時間は研究室によって異なる。
・授業を取る、のんびり過ごす、就活をする、院試の勉強をするなど自由に過ごすことができる。
4年生Aセメスター
coming soon
入る前の想像と実際
・受講することのできる授業の幅が思っていたよりも広かった。前期教養で受けていた総合科目ではわからない、物理、化学、生物それぞれの雰囲気をきちんと味わってから進路を選択できるのが強み。
・「指定されていることだけをやれば力がつく」という学科ではなく、自分でやることを決めて取り組まなければいけないため、モチベーションの維持に苦労している人もいた。
選んだ理由/迷った学科
選んだ理由
・物理と生物のどちらの道に進むか迷っていたが、統合自然科学科では物理と生物を同時に学べるため。
・学生と先生の距離が近い
・研究室の規模が小さい(ほとんどの研究室は5人程度)
・近頃卒業研究でコースの先輩が総長賞を受賞している
(理科二類→物質)
迷った学科
・物理7生物3くらいの気持ちでいたので、物理工学科や理学部物理学科と迷った。
・化学と物理のどちらに進むかで迷っていた同期は多い。
(理科二類→物質)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
5 |
| LINE | 無 |
| Slack | 有 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 無 |
(※1)実験や実習があると8くらい。実習で顔を合わせたり、人数が少なかったりすると仲良くなれる。
(※2)基本的にはSlackで動かしている。学生用のものと学生と先生がいるSlackがある。
(※3)上下のつながりはほとんどない。学科に来たときの歓迎会で上の学年がくることはなかった。
・同期とはTwitterで繋がっており、コミュニティが狭いので、自然と距離が近い。
・先生と学生との繋がりは他の学科よりも強い。授業の間で廊下で話すような機会を作ろうと、学生と距離が縮まるように盛り上げてくれる先生も多い。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 10~20名前後 |
| 成績評価 | 出席、レポート、期末試験 |
・実習、実験を大切にしている。
・コロナ前は試験が多かったが、2021年4月現在は9割くらいの授業がレポート評価。出席を考慮する授業はほとんどないが、授業を受ける人数が少ないため、誰が休んでいて誰が出席しているかはすぐにわかる。
・授業あたりの受講者数が少ないため、大規模講義とは違って質問や議論がしやすい。(例えば、3Aでの物性物理演習は受講者が4人となる年も。)
・成績評価は緩めで、人数が少ないのでわからないところがあったらすぐに聞ける。
研究室・資料
特別な制度・その他
・副専攻:他コース科目を一定以上とると、副専攻認定を受けられる制度。例:主専攻が物質基礎科学コース、副専攻が数理自然科学コース
・サブメジャープログラム:所属コースの主専攻だけではなく、他コースが提供する15単位程度の科目群を副専攻として履修するプログラム。修了生は卒業時に、卒業証書だけではなく、サブメジャー・プログラム修了証ももらえる。
・学融合型プログラム:分野横断的な学習を行うプログラムで、グローバル・エシックス、グローバル・スタディーズ、東アジア教養学、進化認知脳科学、科学技術インタープリターの5種類がある。例えばグローバル・エシックスでは社会・人文科学系の問題のみならず自然科学やテクノロジーに関わる諸問題に対応していくための包括的な価値観や倫理に関わる判断を下す力を身につけることを目的としている。文理の壁を超えてより複眼的知識を身につけたい人は検討してみても良いだろう。詳しくはこちらを参照。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

教養学部
「学際性」「国際性」「先進性」を軸に、深い教養を基盤に従来の枠組み・領域を超えて新しい分野を開拓する人材を育成する学部
関連記事
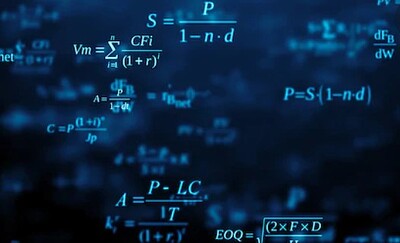
計数工学科
数理工学・物理情報学・認識行動学
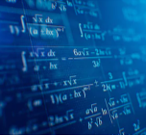
統合 数理自然科学コース
統合自然科学科 数理自然科学コース

数学科





