教養学部
統合 数理自然科学コース
2023.4.15
統合自然科学科 数理自然科学コース
目次
基本情報
| 人数 |
1学年あたり9名程度。3、4年生合わせて17名程度。 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
少人数のため、年によって変わりやすい。 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
院進率は68.6%、就職は21.6%。※院進先は、東大の総合文化研究科が71.4%。※数値はすべて令和元年度のデータ。 |
| 公式サイト |
https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/academics/fas/digs/index.html |
学科概要
■どんなコース?
本コースは、4コースある統合自然科学科の1コースであり、自然の数理的構造を探求する。様々な数理的概念の理解を深めるとともに、広く自然現象の背後にある数理的構造を学ぶ。「統合自然科学」の名のように、自然科学を統合的に理解しようとする動機のもとで学んだ、高度な数理的考えや手法を様々な分野に生かせる人材の育成を目指す。通称は「数理」。
必修は「統合自然科学セミナー」、「数理科学セミナーⅠ・Ⅱ・Ⅲ」、「物質科学実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」または「数理科学演習」(三年生の後期から「物質科学実験」の代わりに履修可能)である。
■統合自然科学科数理科学コースの諸制度
卒業必要単位数は76で、3Sセメスターまでに、卒論を除く全卒業単位を取りきるのはやや難しい。うちコース内の必修科目が17単位、選択必修が17単位。高度教養科目(※)で6単位、他コース科目で16単位が必要。他学部履修はコース主任の承認を得て、卒業単位に10単位まで含められる(詳細はコース便覧を参照のこと)。卒業研究は10単位で、その対象分野は数理に囚われる必要がなく、認知でもスポーツでも構わない。
※ 高度教養科目:後期課程の学生が履修することができる、教養学部内の他学科/コース開講科目。自身の専門分野には直結しないことが多い、学際的内容の概論講義やグループワークが多く、国際研修の一部もこれに該当。前期生でいう「主題科目」に該当し、主題科目と合同開催される例も多いので、前期生が講義にいることも。
■各コースの違い
※統合自然科学科4コース
・数理:自然の数理的構造の探究
・物質:原子から生体物質まで広く物質の真理を追求
・統合生命科学:生体と生命現象の本質を探究
・認知行動科学:人間・動物などの個体や集団の研究
※スポーツ科学サブコースも存在し、上記の4コースのいずれかに加えて履修することができる。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
・週15コマ前後(ただし人によりコマ数は大きく異なる)
・「統合自然科学セミナー」(2単位)が必修。
・週のコマ数は人によってかなり異なる。
・興味が広い人が多いので、取る科目は皆多め。
・2Aセメスター開始直前に、他の3コースと合同で学科ガイダンスが行われる。そこでは、教室に集まって先生や同級生と顔合わせをする。
・この時点で卒業研究のテーマを決めている学生はあまりいない。
3年生Sセメスター
・週15コマ前後(ただし人によりコマ数は大きく異なる)
・「数理科学セミナーⅠ」(2単位)と「物質科学実験 Ⅰ」(3単位)が必修。
「物質科学実験」(週6コマ)では、一年間を通して、実験で化学と物理を学ぶ。
・すでに院進か就職かを決めている人が多い。
3年生Aセメスター
・週15コマ前後(ただし人によりコマ数は大きく異なる)
・「数理科学セミナーⅡ」(2単位)と「物質科学実験 Ⅱ」(3単位)が必修。
・成績が良ければ、3A から「物質科学実験」の代わりに「数理科学演習 Ⅰ」(3単位)を取ることもできる。
・2020年は感染症対策のため、実験はオンラインで行われた。
・院試対策を始める人もちらほら。
4年生Sセメスター
・週15コマ前後(ただし人によりコマ数は大きく異なる)
・3Sセメスター・3Aセメスターとほぼ変わらない。
・「数理科学セミナーⅢ」(2単位)と、「物質科学実験 Ⅲ」(3単位)または「数理科学演習 Ⅱ」(3単位)が必修。
・4年夏に院試があるため、院試の勉強で忙しい。
4年生Aセメスター
・卒業研究開始。
・原則卒業研究は4Sセメスターからで、2,3年生で研究を行うことは原則無い。・4Aは卒業研究で忙しくなると思われる。
・卒業研究では長い論文を書くことはしない。人によっては1ページ程度で終わることもある。コース情報サイトの過去の卒業論文テーマを参照。
・卒論の提出時期は2月頭頃。
入る前の想像と実際
・「理系出身者(特に理一が多い印象。文系出身者はほとんど見られない。」
・「理系出身でないとついていくのはかなり大変だろう。」
・「当コースの学生の雰囲気は学年によって異なる。」
・「物理や数学以外にも、生物から認知まで、学生の興味はさまざまである。優秀な人が多い。」
・「十分に下調べをしていたので、入る前の想像と実際にそれほどの違いはなく、混乱することはなかった。」
選んだ理由/迷った学科
・「統合自然科学科の他コースと迷った。当初は他コースの科目を勉強するつもりだった。」
・「最初から統合自然科学科に行くことは決めていた。」
・「数学に興味があり、進振りの点数も考慮して、数理コースを選んだ。」
・「高い意欲を持ってくる人は興味が多岐にわたっており、興味がひとつに定まらなかった結果、教養学部を選んだという人が多い。」
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| LINEやSlack | 有るがあまり機能しない |
| オフラインでのつながり | 学年による※1 |
| 他コースとの交流 | あまり無い※2 |
※1
・コミュニティ機能が強い学年もあれば弱い学年もある。
・コースのみんなで集まって何かをしようということはあまりない。
・雑談ズームなどが開かれることはあった。また、個人同士で話をすることはある。
・数理コースのメンバー全員で授業を一緒に受けるという機会が少なく、学問の内容を介して話す、ということもあまりない。
※2
・他コースの授業を取ると他コースの学生との交流がある。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実験 | 実験は自分の学年だけで行う。他コースの人も合わせて全体で27名前後で、8名ずつくらいに別れて実験を行う。 必修の実験は物質コースと一緒に行う |
| 成績評価 | 基本的に試験で行う。出席はあまり厳密にとらない。 |
| GPA | 高いGPAを取るインセンティブは少ない。 |
| 他コースとの合同授業 | 「統計力学」などの授業は物理工学科などの学生が履修することもある。 |
・期末レポートが課される授業は普段はほとんどない(コロナ禍では少しある)。
・卒論(卒業研究)は各研究室にて進めるものと思われる。
・ある研究室では毎週一回MTGが行われ、そこで研究の報告がなされる。
研究室・資料
特別な制度・その他
・サブプログラム:所属コースの主専攻だけではなく、他コースが提供する14単位以上の科目群を副専攻として履修するプログラム。修了生は卒業時に、卒業証書だけではなく、サブプログラム修了証ももらえる。サブプログラムはスポーツ科学サブコースを含めて20以上あり、複数のサブプログラムを修了することも可能。
・副専攻:所属コースの主専攻以外のコースの科目群から24単位以上を取得すると、卒業証書だけではなく、副専攻の修了証ももらえる。サブプログラムよりも修了に必要な単位数が多い。
・学融合型プログラム 学問分野を超えて横断的な学習を行うプログラム各種。「グローバルエシックス」、「進化認知脳科学」、「科学技術インタープリター」、「グローバルスタディーズ」、「東アジア教養学」などのプログラムがある。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

教養学部
「学際性」「国際性」「先進性」を軸に、深い教養を基盤に従来の枠組み・領域を超えて新しい分野を開拓する人材を育成する学部
関連記事
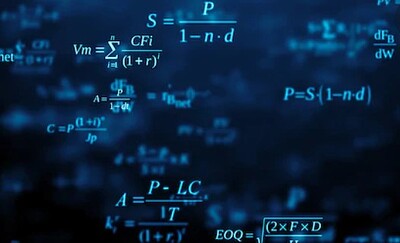
計数工学科
数理工学・物理情報学・認識行動学

天文学科
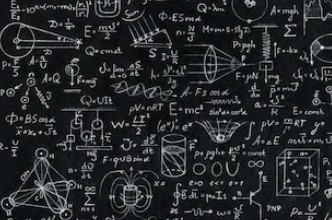
物理学科





