理学部
天文学科
2023.4.15
目次
基本情報
| 人数 |
10名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
少人数学科のため、年によって変動しやすい |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
ほぼ全員が院進し、東大の大学院または附属施設で研究する |
| 公式サイト |
学科概要
将来天文学や他の分野において第一線で活躍できる研究者や教育者の育成、あるいは国際的プロジェクトや学際的プロジェクトの中核となる研究者・教育者を養成を目標としている。国内全体の中でも、学部から天文学の専門教育を行う珍しい学科。教員数やカバーする研究テーマの豊かさは、国内外でトップクラスの水準。
2Aでは理学部の物理学科(理物)・地球惑星物理学科(地惑)と一緒に物理や数学を学ぶことが多い。3年から天文学科の授業が増え、観測実習や実験も行う。必修のコマ数は他の理系学部と比べるとそこまで多くなく、時間割的には余裕がある。10人と人数が少ないため分からないところを同期に相談しやすく、学科全体としてアットホームな雰囲気なのが特徴。観測実習や実験も生徒の人数が少ないため手厚く指導してもらえる。
多くの学生が研究者を目指しており、学部卒で就職するケースはまれ。ほとんど全員が修士課程に進み、半分くらいが博士課程で研究に打ち込む。
学科公式の進学選択パンフレットはこちら
■天文学科の諸制度
卒業までに必要な単位は76.5単位以上で、2Aで18単位以上、3,4年で58.5単位以上取得する。
【内訳】
・2A...必修科目14単位を含む理学部専門科目18単位以上を履修する。
・3,4年...必修科目は研究倫理(0.5単位)のみで、3,4年次のどちらかで履修する。残りの58単位のうち、36単位は選択必修科目(卒論は8単位含む)から、14単位は選択科目から選ぶ必要がある。研究室には3年が終わった春休みで研究室案内があり、希望をとってから4Sセメスターから入ることになる。
他学部専門科目は、あらかじめ科目認定届を提出した上で専門科目58.5単位に含めることができる。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理Ⅰ(指定科類) | 5 | なし |
| 全科類 | 1 | 4 |
天文分野に何かしらの関心を持った人が多く進学する。ほとんどが理一・物理選択者で、自分で意欲的に勉強する人が多い。
■内実は?
・授業で積極的に質問をするような、勉強熱心で真面目な人が多い。自発的にゼミを開いて勉強している人もよくいる。
・学部の勉強に注力する人が多い。運動部やサークルにコミットしたり、インターンをしたりする人も一定数いる。
・5月祭や駒場祭で企画をすることはないが、理学部の1号館10Fに天文学科の控室があり、ゲームをしたりパーティーをしたりなど和気あいあいとした雰囲気である。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【理物、地惑と一緒に物理・数学の授業を受ける】
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 天体物理学実習I | 必修 | 木曜4,5限 |
| 物理数学I (A1) | 必修 | 木曜2,3限 |
| 物理数学II (A2) | 必修 | 木曜2,3限 |
| 物理実験学 | 必修 | 火曜2限 |
| 電磁気学I | 必修 | 月曜2限 |
| 解析力学 (A1) | 必修 | 月曜3,4限 |
| 量子力学I (A2) | 必修 | 月曜3,4限 |
| 情報数学 | 選択 | 金曜3限 |
| 形式言語理論 | 選択 | 金曜4限 |
| 天文地学概論 | 選択 | 金曜4限 |
| 地球惑星物理学概論 | 選択 | 金曜2限 |
| 化学熱力学I | 選択 | 金曜5限 |
| 量子力学I | 選択 | 月曜5限 |
| 無機化学I | 選択 | 金曜4限 |
(※1)天体物理学実習は、学科の10人だけで受ける授業。物理学科の授業で扱っている物理や数学についての問題が出題され、担当者が問題を解いてきて発表する形式だが、授業で扱いきれない問題がレポートになる。
(※2)選択ではあるが、天文学科の人は履修を推奨されている。2Aで唯一の天文学の授業。出席はなく、オムニバスなのでそれぞれの教員(3名ほど)から出されるレポートを提出すればOK。
・平均して週に10コマ程度。
・必修科目(14単位)の他に、選択科目から4単位を履修する。対面授業の場合は全て駒場で受講する。
・多くの授業を理物、地惑と受けるため、受講人数が100人を超えることもある。
3年生Sセメスター
■【実習や実験など天文学科ならではの授業】
授業の例
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 研究倫理 | 必修 | 集中 |
| 銀河天文学 | 選択必修 | 月曜3限 |
| 計算天文学I | 選択必修 | 水曜5限 |
| 基礎天文学実験 | 選択必修 | 集中 |
| 基礎天文学観測 | 選択必修 | 集中 |
| 電磁気学II | 選択 | 月曜2限 |
| 量子力学II | 選択 | 火曜2限 |
(※1)授業の初めの解説を聞いてあとは課題を授業内で進める演習形式。C、C++、Python等を扱う。
(※2)2020年度は例外的に3Aセメスターで行われた。各自都合の良い日時に行って進めるフレキシブルなスタイルで、電子回路実験と光学実験を行う。前期教養の基礎実験があまり好きじゃなかった人も、そこまで身構えなくて大丈夫。
(※3)夏休みからAセメにかけて(集中講義として扱われる)、選択必修科目である「基礎天文学観測」が開講される。7種類ほどある実習の中から希望を出して1人3つ行う。本郷で行うもの、三鷹で行うもの、木曽や西播磨などに泊まりで行うものがある。泊まりの実習は貴重な経験ができて楽しいので、どれかしら行くのはおすすめ。
・平均して週に13コマで、座学が10コマ程度、実験が週に3コマ(ただし、2020年度は実習が3Aセメスターに移動した)。このほかに集中講義として夏休みに実習がある。
・唯一の必修科目である「研究倫理」は、3年生のうちにとる人がほとんど。
・「選択必修科目」とあるが履修の自由度は低く、実際には学科のうちのほとんどが同じ授業を受けている。
・理物、地惑と同じ授業になることが多い。
・2020年度は座学の授業のほとんどがレポートで評価された。
3年生Aセメスター
■【3Sと同様天文に関する授業が中心】
授業の例
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 天体輻射論Ⅰ | 選択必修 | 月曜1限 |
| 天文学ゼミナール | 選択必修 | 水曜3,4限 |
| 太陽恒星物理学 | 選択必修 | 木曜4限 |
| 量子力学III | 選択 | 火曜2限 |
| 生物物理学 | 選択 | 水曜1限 |
| 光学 | 選択 | 金曜1限 |
| Pythonプログラミング入門(A1) | 選択 | 集中 |
(※1)2週間分の授業について感想や質問を書いたレポートを提出しないと、次の2週間のスライドがもらえない。
(※2)二つのグループに分かれて英語の教材を読み進める。割り当てられた箇所を読んできて簡単に発表する。最後の授業では各自興味のある論文を持ってきて英語で発表する。
(※3)オムニバスで、各教員のレポートを提出する。
(※4)物理学科、地球惑星物理学科などと合同。2020年度はレポートのみ。生物をあまり勉強していない人向けなので比較的内容は優しく、レポートもあまり重くない。
(※5)S1セメスター、集中、A1セメスターで同じ授業が開講される。理学部全体の授業で、毎授業課題が出る。本当に基本からやるので自分でPythonを全然勉強してこなかった人におすすめで、天文学科でも取る人は一定数いる。
・平均して週に10コマ程度。
・3Aセメスター終了までで卒業に必要な単位を大体取り切る。
・研究室は3Aが終わった2月上旬に説明があり、3月中旬くらいまでに決める。
4年生Sセメスター
■【研究に打ち込む日々】
授業の例
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 星間物理学Ⅰ | 選択必修 | 木曜2限 |
| 星間物理学Ⅱ | 選択必修 | 金曜4限 |
| 恒星進化論 | 選択必修 | 金曜3限 |
| 宇宙論 | 選択必修 | 木曜3限 |
4年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 天体輻射論Ⅱ | 選択必修 | 火曜3限 |
入る前の想像と実際
・人数が少ない分身構えていたけれど、手厚い指導を受けられた。思ったよりも敷居が高くない。同じ授業をとることが多い理物の方が勉強がハードそうだった。
・女子が少ないのは覚悟していた。
アドバイス
・前期教養の総合科目E「宇宙科学」の授業は天文学科の授業に近い。
・天文について興味を深めておくこと。周りでは自主的に勉強したりしていて、3年生の時点で行きたい研究室が決まっている人もいる。
・前期教養の総合科目F系列に苦手意識があり、基礎統計しか取らなかった。しかし、プログラミングは授業でも頻繁に用いるし、周りもやっているので、もうちょっと勉強していた方がよかった。
選んだ理由/迷った学科
・「高校生からもともと物理系に行きたかった。初年次ゼミナールで宇宙系のものを選び、天文にひかれた。理学部のガイダンスにも行った。他で迷った学科は、理物、地惑。理物では幅広い物理もやる必要があり、地惑よりもっと大きなスケールを扱いたかったのと、地球には興味がなかったので天文を選んだ。」(理一→天文学科)
・「宇宙の話全般を学べ, かつ装置開発にも携われるから。迷った学科は特にない。」
(理二 → 天文学科)
・「科学の中でも宇宙そのものをテーマに研究したかった。航空宇宙は、探査機やロケットの部品について研究するが、天文では銀河や遠くの宇宙についても扱えるから。」(理一→天文学科)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
7(※1) |
| LINE | 有(※2) |
| Slack | 有(※3) |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
(※1)授業で実習や実験が多く、自ずと学生同士の交流が多くなる。
(※2)同期だけではなく、上下ラインもある。テスト前は毎日のようにzoomが開かれており、勉強を教え合う。作業や雑談でzoomを開くこともある。
(※3)授業資料のシェア、研究室の案内、その他有用情報に関するチャンネルがある。
(※4)2020年はコロナで中止になってしまったが、2年生の春休みに3年生が学科旅行に連れていく。控室で先輩と話したり、交流したりすることがあり、すぐに覚えてもらえる。
・2020年度は、女性の助教が理物、天文などの女子学生を集めてお昼にzoomを開き、授業の様子を聞いたり相談に乗ってくれたりしていた。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 変動あり(※1) |
| 成績評価 | 期末試験、レポート(※2) |
(※1)
・座学...理物や地惑と一緒に受ける授業では100名ほど。天文学科の授業では、他の学科の人が履修している場合もあるが、多くて20人くらい。板書が淡々と進む授業。
・実験、実習...天文学科だけで受けるため、少人数。ペアでやることも、個人で進めることもある。また、3S(2020年は3Aに移動)では東大の附属施設で泊まりがけの実習がある。
(※2)
・座学...オフラインでは、試験一発の授業、レポート評価の授業どちらもあった。オンラインではレポートで評価がついた。
・実験、実習...内容や測定結果をまとめたレポートで評価される。
研究室・資料
「天文学教室」とは、本郷キャンパスにある研究室のことを指しており、三鷹やその他東大の附属機関にある研究室と区別している。
〈研究室紹介〉
・天文学専攻(大学院)の指導教員一覧
・戸谷 友則 教授:宇宙物理学
・田村 元秀 教授:系外惑星天文学
・相川 祐理 教授:星間物理学
・柏川 伸成 教授:初期宇宙・銀河天文学
・嶋作 一大 准教授:銀河天文学
・梅田 秀之 准教授:理論天体物理学
・藤井 通子 准教授:理論天体物理学・計算天体物理学
・茂山 俊和 教授:理論天体物理学
・土居 守 教授:銀河天文学
・河野 孝太郎 教授:電波天文学
・宮田 隆志 教授:赤外線天文学
・田中 培生准教授:赤外線天文学
・小林 尚人 准教授:天体物理学
・峰崎岳夫准教授:赤外線天文学
・酒向 重行 准教授:赤外線天文学
・鈴木 建 教授:理論天体物理学
・大内 正己 教授:銀河天文学
・John D. Silverman教授:観測的宇宙論
・郷田 直輝教授:天体物理学
・小久保 英一郎 教授:理論天体物理学
・阪本 成一 教授:電波天文学
・本間 希樹 教授:電波天文学
・深川 美里教授:電波天文学
・都丸 隆行教授:重力波天文学
・本原 顕太郎教授:赤外線天文学
・高遠 徳尚教授:光学赤外線天文学
・原 弘久准教授:太陽・宇宙電磁流体力学
・勝川 行雄准教授:太陽物理学
・奥田 武志准教授:電波天文学
・中村 文隆准教授:理論天文学
・海老沢 研教授:X線天文学
・関本 裕太郎教授:電波天文学
・片坐 宏一准教授:天体物理学
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
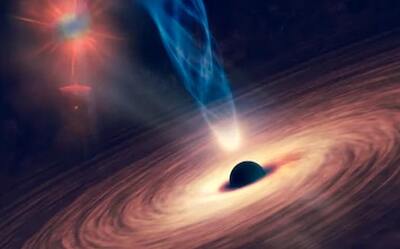
理学部
理学の理念の下に、 豊かで平和な人類の未来社会を切り拓く先端的な理学の教育・研究を推進する学部
関連記事
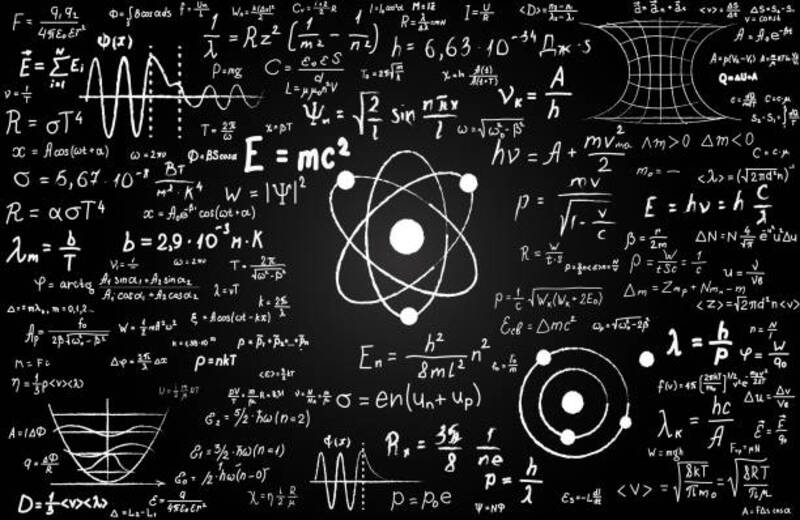
物理工学科
物性物理・量子情報

数学科

学際A 地理・空間コース
教養学科 学際科学科A群





