理学部
地球惑星物理学科
2023.4.15
目次
基本情報
| 人数 |
30名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
年度による変動が大きい |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
1名前後は学部就職、ほぼ全員院進 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
地球惑星科学が対象とする領域は、地殻・マントル・コアから成る固体圏、大気・海洋から成る流体圏、固体圏と流体圏の境界領域に広がる生命圏及びその総体としての地球システム、さらに、太陽系を構成する惑星・衛星から宇宙空間にまで及んでいる。
地球惑星科学専攻においては、広い視野と深い専門知識を併せ持った創造性豊かな研究者を育成すると共に、社会的要請に答えることができる幅広く確かな専門知識を持った研究技術者を養成することを目標として教育を行う。(公式サイトより)
気象予報士の資格を持っている人や、地学オリンピック出場者など、昔からこの道に決めていた人が半分くらいいる印象。先生も生徒も緩い人が多く、授業や課題は基本的に軽い。先生との距離はかなり近い。
■地物の諸制度
地球惑星物理学科においては,教養学部第2学年において別表2に定めるところにより選択必修科目11単位以上を含む理学部第2学年専門科目19単位以上を学修するほか,第3学年及び第4学年において次の専門科目の中から必修科目15.5単位を含めて60.5単位以上を学修しなければならない。
ただし,次に示した専門科目以外の理学部及び他学部専門科目(教養学部第2学年の専門科目及び教職課程科目を除く)であっても,あらかじめ所定の期日までに科目認定届を提出し認められた場合には専門科目60.5単位に含めることができる。
なお、専門科目60.5単位のうち, 30単位以上は次の選択必修科目A群〜C群の中から選ばなければならない。また,この選択必修科目30単位の2単位以上はA群の中から,10単位以上はB群の中から選ばなければならない。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理科一類(指定科類) | 17 | 0 |
| 全科類 | 5 | 10 |
・得点計算で考慮すべき科目
①基礎科目のうち、数理科学と物質科学の系14単位の重率を2とする。(第1~3段階)
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
必修はなし(選択必修13単位より11単位以上)
・理物と共通の必修が多く、物理が重め。
・「解析力学」と「量子力学」は短期間で詰め込まれる形式で大変。
・11コマ〜
・実習はまだない。
・「地球惑星物理学概論」4名の先生がオムニバス形式で、様々な分野の地球惑星系の話が聞ける。
・全部の授業が座学で、駒場で開講される。
・(2019年当時は)多くの授業がテストでの評価だった。
3年生Sセメスター
| 科目 | 開講時限 |
|---|---|
| 地球流体力学I | 月曜1限 |
| 電磁気学II | 月曜2限, 水曜2限, 木曜2限 |
| 地球惑星物理学演習 | 月曜3-4限 |
| 弾性体力学 | 火曜1限 |
| 量子力学II | 火曜2限 |
| 地球惑星物理学基礎演習III | 火曜3-4限 |
| 物理学演習III | 火曜3-4限 |
| 固体地球科学 | 水曜2限 |
| 宇宙空間物理学I | 木曜1限 |
| 統計力学I | 木曜2限 |
| 大気海洋循環学 | 金曜1限 |
| 地球惑星物理学基礎演習IV | 金曜3-4限 |
| 物理学演習IV | 金曜3-4限 |
| 地球惑星物理学観測実習 | 金曜5限 |
| 地球惑星物理学観測実習 | 集中 |
| 地球惑星物理学実験 | 集中 |
| 地球惑星化学実験 | 集中 |
| 臨象理学実習 | 集中 |
| 研究倫理 | 集中 |
・単位のシステムが変わる
・3年以降の必修は研究倫理(集中0.5単位)のみで、他は選択必修がある。
・選択必修A、Bからそれぞれ一定数の単位数(物理系、地球惑星系の科目をそれぞれ)
・物理の基礎を座学で行っていたのに対し、演習が多くなる。
・「計算機演習」プログラミングを行う。
・3Sから実習が始まる。
・科目名の通り、地質調査法、岩石中の鉱物の見方、地球化学に関することを学習する。
・夏休みには「観測実習」という野外調査があり、気象観測や地質調査などを行う。体力的に大変なものもあるので、事前に内容をよく調べておくことが必要。
3年生Aセメスター
| 科目 | 開講時限 |
|---|---|
| 地球流体力学II | 月曜1限 |
| 地球力学 | 月曜2限 |
| 地球惑星物理学実験 | 月曜3-5限, 水曜3-5限, 木曜3-5限 |
| 地球惑星化学実験 | 月曜3-5限 |
| 地球電磁気学 | 火曜1限 |
| 弾性波動論 | 火曜2限 |
| 量子力学III | 火曜2限 |
| 宇宙惑星物質進化学 | 水曜1限 |
| 宇宙空間物理学 | 水曜2限 |
| 気候システム学 | 木曜1限 |
| 大気海洋物質 | 金曜1限 |
| 電磁気学III | 金曜1限 |
| 統計力学II | 金曜2限 |
| 物理演習IV (※) | 金曜3-4限 |
| 地球惑星物理学観測実習 | 集中 |
| 臨象理学実習 | 集中 |
・選択必修の1つである地球惑星物理学実験/地球惑星化学実験は大変そうだった。
4年生Sセメスター
| 科目 | 開講時限 |
|---|---|
| 海洋物理学 | 月曜2限 |
| 気象学 | 月曜3限 |
| 惑星大気学 | 月曜4限 |
| 位置天文学・天文力学 | 月曜5限 |
| 地球惑星内部物質科学 | 火曜2限 |
| 地球惑星物理学特別演習 | 火曜3-4限, 水曜3-4限 |
| 系外惑星 | 水曜1限 |
| 地球物理数値解析 | 水曜2限 |
| 地震物理学 | 木曜2限 |
| 星間物理学I | 木曜2限 |
| 火山・マグマ学 | 金曜1限 |
| 地球惑星システム学基礎論 | 金曜2限 |
| 比較惑星学基礎論 | 金曜3限 |
| 地球惑星物理学特別演習 | 金曜4-5限 |
| 星間物理学II | 金曜4限 |
| 臨象理学実習 | 集中 |
・必修はないが、4年生でしか受講できない選択必修がある。
・選択必修の1つである地球惑星物理学特別演習では、教員が提示したテーマ一覧の中から希望を出し、各教員(複数人の場合もあり)に対し生徒が1~3人ついて論文を読む。
・前半と後半に分かれていて、視野を広げるために違う分野から選ばなければならない。
・研究室の配属は遅く、院試合格後に希望を提出して決まる。
4年生Aセメスター
| 科目 | 開講時限 |
|---|---|
| 大気海洋系物理学 | 月曜2限 |
| 地球惑星物理学特別研究 | 火曜3-4限, 水曜3-4限 |
| 地球物質循環学 | 水曜3限 |
| 地球内部ダイナミクス | 金曜1限 |
| 地球物理データ解析 | 金曜3限 |
| 地球惑星物理学特別研究 | 金曜4-5限 |
・選択必修の1つである地球惑星物理学特別研究は、いわゆる卒業研究のようなもので、教員が提示した研究テーマ一覧から希望を出し、各教員に対し生徒が1,2人ついて研究を行う。
・大学院で希望する研究室を選ぶ人が大半で、各人12分程度のプレゼンをする研究発表会があり、最後にレポートを提出する。
入る前の想像と実際
・地学が学べると思っていたが、結構物理の色が強め。(「地球惑星環境」の方が地学より)
・限られた中でも対面の機会を設けようとしてくれて、
・1人に2人の教授がアドバイザーがついて、面談してくださる。
・教員の方が公式に交流会を開かれることもあり、面倒見が良い。
・オンライン授業への対応がしっかりしていた。
・真面目で意欲的な人が多い。
(理二→地物)
・宇宙・大気海洋・固体地球という広い分野をすべて学ばなければならないと思っていたが、学科開講の授業はもちろん、天文学科や物理学科をはじめとする理学部他学科の授業から好きな授業だけを選ぶことができた。
・宇宙系の授業と物理学科の基礎物理の授業を選んで必要単位を揃えましたが、授業の被らない学科同期もたくさんいた。
・自由度の高さが想像をはるかに超えていました。
(理一→地物)
選んだ理由/迷った学科
・地震や気象についてぼんやりと興味があった。
・地震を調査するとなると、物理も勉強する必要があると考えて、地物を選んだ。
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
8 |
| LINE | 有(※1) |
| Slack | 有(※2) |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有(※2) |
※1 連絡も雑談も基本的にSlackで行われるため、あまり動いていない。
※2 学年による。
・学年によっては学科Zoomが週1回ある。
・自主ゼミが盛んで、そこでも交流があり、それらに参加している人とそうでない人で差は出てしまう。
・対面だった方が仲良くなっていたと思う
・シケタイの制度があり、前期教養よりもしっかりしていた印象。ドライブで過去問の答えや院試の情報も見られる。
・理学部1号館の学科部屋に行けば誰かいる。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 30名前後(※) |
| 成績評価 | レポートメイン |
※ 地物だけの場合の人数。理物と合同だと100人超えのこともある。
・座学か実習のどちらか。
・昨年度・今年度はオンライン授業のためほぼ100%試験評価のものと、レポ・出席で単位が来るものが半々くらい。それ以前は試験がも多かった。
・実験ごとにレポートを書く授業もあるが、殆どは期末レポート1つか、中間レポートと合わせて2つ。
研究室・資料
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
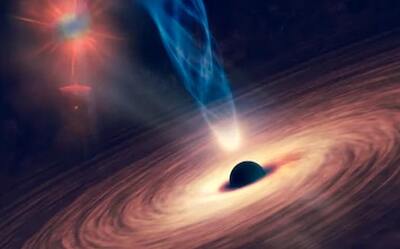
理学部
理学の理念の下に、 豊かで平和な人類の未来社会を切り拓く先端的な理学の教育・研究を推進する学部
関連記事
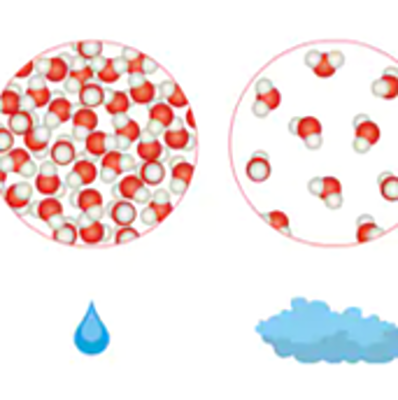
統合 物質基礎科学コース
統合自然科学科 物質基礎科学コース

学際A 地理・空間コース
教養学科 学際科学科A群
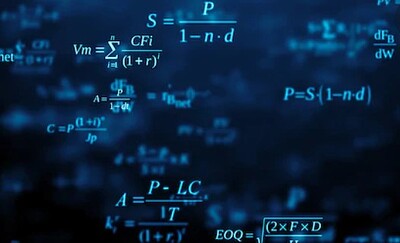
計数工学科
数理工学・物理情報学・認識行動学





