工学部
物理工学科
2025.4.8
物性物理・量子情報
目次
基本情報
| 人数 |
50名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
現在の代は55人中3人が女性で、下の代には女性は0人です。 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
院:就職 = 19:1程度 |
| 公式サイト |
学科概要
■当学科の特徴
・物理学の様々な分野の理論を扱う理学部物理学科や教養学部統合自然学科とは異なり、多数の量子が創り出す世界に理論と実験の両輪で迫っていく。原子内の性質を微細に突き詰めていく素粒子物理学とも異なる。
・2Aで物理学の基本法則とそれを理解するための数学を学び、その後は量子力学や統計物理学などの物理学を学んでいく。
・研究分野は、「物性理論・計算物理」、「先端物質創成」、「量子物性」、「光科学・量子情報・量子計測」の4分野。
・量子情報技術の基礎を学ぶために計数工学科で開講されている計算機科学や情報理論に関する講義の相乗りをすることが多く、SlackやLINEのグループも共同で運用されている。進振り点が高い計数工学科と交流する機会が多いためか、物工にも熱心に勉強・研究を行う生徒が多く、Slack上などで常に活発に議論が交わされている。
■当コースの諸制度
・卒業に必要な履修単位数は95単位。
・内必修単位が47.5単位、限定選択科目を24単位以上履修する必要がある。
※ 限定選択科目:工学部一般に用いられる用語。選択必修のこと。
■時間割
2年生Aセメスター
3年生
4年生
※注意:内容は最新版とは限らないので注意。必修科目、限定選択科目、その他がまとめて書いてある。各セメスター紹介では時間割やコマ数の概要を紹介するが、原則として詳細はシラバスや学科便覧で確認すること。
■進振り前にやっておくべき事は?
・必修授業の多くなる3Sで苦労しないように、有名な教科書を2年生の夏休みに軽く読んでおくべき。特に、「熱力学」と「量子論」に加え、いつの間にか既知の知識として扱われる「解析力学」の3つを抑えておくと良い。熱力学なら田崎 晴明先生、量子論なら清水 明先生の本がおすすめ。(理一→物工)
■進振りの時に気を付けること
・進振りは工学部の一般的な学科コースと同様に、「工学部指定平均点」が用いられる。
■進学後の内実は?
・セメスター制講義が多い。3Sに必修授業が多く存在する。
・3Aセメスター末から4Sセメスターのはじめにかけて研究室振り分け(研振り)が行われる。
・研究室配属は、各教員のプレゼンテーションを聞き最終志望を決定した後に、くじ引きによってランダムに決められる。
・卒業論文/卒業研究は4年生の1年間で取り組む。
(参考) 2016年の優秀卒業論文
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【基礎を固める2A】
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 統計熱力学 | 必修 | 月曜2限 |
| 電磁気学第一 | 必修 | 火曜2限 |
| 量子力学第一 | 必修 | 水曜3限 |
| 数学1D | 必修 | 水曜4限 |
| 数学及力学演習I | 必修 | 木曜3/4限 |
・A1、A2ともに平均15コマ前後が一般的。
・必修「統計熱力学」は、1授業にしてはかなり重い内容で試験も難しく、試験に失敗した人のための救済措置としてのレポートが用意されている。本講義で単位が取れないと卒業できないため、統計力学や熱力学が苦手な人は他の学科を検討した方が良いという声もあるほど。
・限定選択「基礎数理」は、教科書に載っていない根本知識を伝授する名物授業。
・院進する人の割合が高く、2Aのみならず3、4年生の時点でも就活をする人は少ない。
3年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 電磁気学第二 | 必修 | 月曜2限 |
| 物理工学実験法 | 必修 | 月曜/火曜3~5限(隔週) |
| 物理工学基礎演習 | 必修 | 月曜/火曜3~5限(隔週) |
| 統計力学第一 | 必修 | 火曜1限 |
| 量子力学第二 | 必修 | 火曜2限 |
| 数学2D | 必修 | 水曜2限 |
| 固体物理第一 | 必修 | 木曜1限 |
・S1、S2合計で平均20コマ前後が一般的。
・必修「物理工学実験法」と「物理工学基礎演習」は、隔週で交互に行われる。月曜日は量子力学、火曜日は統計力学を扱う。演習の授業では、頻繁に本に載るような有名な問題だけでなく、難しいオリジナルの問題も出される。次の授業までに解いて提出し、さらに答えをクラスで発表すれば加点がもらえる形式。
・限定選択「確率数理工学」は、扱う数学のレベルが高く、数学が好きな人がよく取る。
3年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 物理工学実験第一 | 必修 | 月曜1~5限 |
| 統計力学第二 | 必修 | 火曜3限 |
| 物理実験の基礎 | 必修 | 火曜4限 |
・A1、A2合計で平均15コマ前後が一般的。
・ここからは計数工学科との合同授業は無くなり、物理工学を深く掘り下げていく。
・必修「物理工学実験第一」は、約12週間にわたる授業が3週間ずつ4つのセットに分けられ、本郷キャンパスにある研究室でのレポート作成、柏キャンパスでのプレゼン、本郷での2種類の学生実験をローテーションで行う。
・限定選択「物理工学演習第二」は、3Sの演習授業よりも難易度が上がるため、受講する人が半減すると言われる。
・限定選択「量子物理工学」は、教科書に載っていない内容を独自の視点から3年生にも分かりやすく伝える講義として人気。
4年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 物理工学実験第二 | 必修 | 水曜/木曜3,4限 |
| 物理工学輪講第二 | 必修 | 火曜4限 |
・4Sは、配属された研究室で卒業研究をおこなうための準備をする。
・必修「物理工学実験第二」は個人単位で行う実験である。卒論執筆のための実験をおこなうと、この授業の単位として認められる。
・授業以外では、専ら院試のための勉強をする。
4年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 物理工学輪講第二 | 必修 | 火曜3限 |
・院試が終わり、卒論の執筆に多くの時間を充てる。
入る前の想像と実際
・物理学の応用に興味を持って進学したが、実際にはすぐにインターン先での仕事や自身の起業に活かせるような事はあまり学べなかった。
・前期教養から物理をかなりやっていた人が多くいるだろうと想定していたが、実際にはそれほどいなかった。初期の授業も物理学の知識を根本から再整理する内容で、数学や物理学に長けていなくても十分追いついていけるように設計されていた。
・計数工学科の人たちと深く関わるとは思っていなかった。Twitterなどでの交流を通して、数学系の人たちがどのようなものに興味を持っているのかが分かった。
(理I→物工)
選んだ理由/迷った学科
・他に検討した学科は教養学部統合自然科学と工学部電気電子情報科。進振りの時には物理学の応用に最も興味を持っていたため、物工を選択した。
(理I→物工)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 【7】 |
| LINE | 有 |
| Slack | 有 |
| 学科ドライブ | 有(※1) |
| オフラインのつながり(※2) | 無 |
| 上下のつながり | 有 |
(※1)学年間でGoogle DriveとOneDriveを使い過去問や過去のノートなどの共有を行う。
(※2)コロナ発生以前における授業以外の交流を指す。学科控え室があり、例年はそこで交流を深めることが多かったが、コロナ禍では控え室が使えないためオフラインの繋がりは生まれにくい。
・シケタイ制度、パ長制度あり。
・計数の生徒を中心にTwitterでの発言が活発。
・対面の実験で出席番号の近い人とペアを組む。ここで仲良くなることが多い。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数(※) | 50名前後 |
| 成績評価 | レポートまたはテスト |
※ 計数と合同で授業を受ける2Aは100名前後、物理に興味を持つ計数の生徒もともに参加する3Sでは70名前後、計数の学生のみが授業に参加する3A以降は50人前後で受講する。
・授業は板書中心。
・出席は実験以外では殆ど取られない。
・レポートの重さが極端に分かれているため、レポートの負担を基準に選択必修を選ぶと良い。
研究室・資料
・物理工学科公式サイト
・物理工学科カリキュラム
・物理工学科教員一覧
・物理工学科研究紹介
・物理工学科授業関係日程
■研究室紹介
・詳しくは教員一覧を参照
・香取 秀俊教授は、スカイツリーの上で光格子時計の精度の良さを証明した実験で有名。
・量子コンピュータ関係では、古澤 明教授の研究室が例年人気。
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
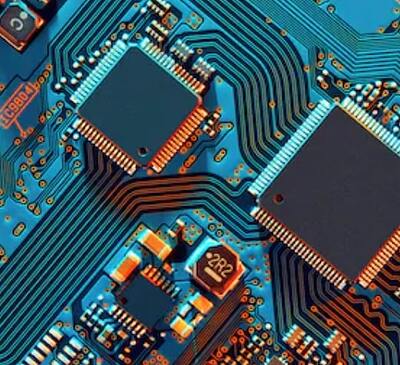
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

システム創成学科C(PSI)
知能社会システム
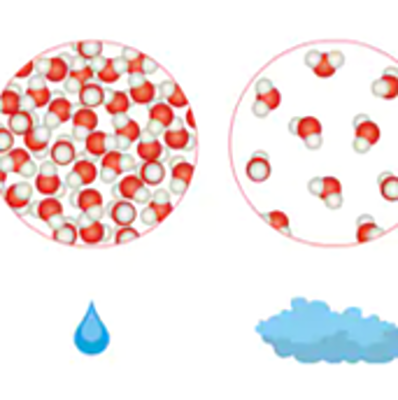
統合 物質基礎科学コース
統合自然科学科 物質基礎科学コース

機械工学科(機械A)
デザイン・エネルギー・ダイナミクス
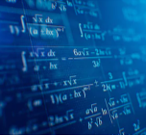
統合 数理自然科学コース
統合自然科学科 数理自然科学コース




