教養学部
統合 統合生命科学コース
2023.4.15
統合自然科学科 統合生命科学コース
目次
基本情報
| 人数 |
20名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ1-2割。 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
就職:院進=3:7 |
| 公式サイト |
http://www.integrated.c.u-tokyo.ac.jp/admission/courses/course3/ |
学科概要
■どんな学部?
教養学部 統合自然科学科 統合生命科学コースは、生命科学を横断的にカバーする学科である。扱っている内容は、分子生物学、細胞生物学、生化学、植物生理学などの「理学」的な基礎研究や、神経科学、内分泌学といった「医学」的な研究、創薬への応用といった「工学」的な研究、物質生産、バイオテクノロジーなど「農学的」な研究など幅広い。さらに特筆すべきこととして生物物理学、数理生物学、生物情報科学、合成生物学など「融合領域」を扱っている研究室が多いのが他学部と異なる特徴である。また、手法も実験と理論の研究室が両方存在する。さらに、履修単位上、統合生命コース以外の授業も履修することが求められており、希望に応じて数理科学や物質科学、認知科学などからの幅広い視野を一流の東京大学の教員から獲得できるのは「学際性」を重んじる教養学部ならではの生命科学の醍醐味だろう。
■pp学科の諸制度
卒業までに必要な単位は76単位。他コースは当然のこと、教養学部内の他学科のみならず、申請次第で他学部の授業を含めることもきる。卒業には卒論提出及び発表が必要。研究室には4Sから入ることになる。4Sと4Aで研究室を変えることも制度上可能であるが、例年変える人はほとんどいない。
卒業単位の内訳は、「高度教養科目」と呼ばれる科目から学科が指定するもののうち6単位以上、統合生命科学コースが開講する科目から34単位以上(内、必修で26単位)、統合自然科学科内の統合生命科学コース以外が開講する授業から16単位以上、卒業研究が10単位、その他特に履修に際しての制限はない自由に履修可能な10単位以上からなるもので、これらを合計して76単位以上になるというわけである。
上記からわかるように、卒業単位数が、生命系の授業に絞られずかなり融通がきくように設定されていることが特徴である。そもそも卒業要件として他コースの授業を一定数取ることが要求されている(卒業単位76単位中16単位以上は、統合自然科内で統合生命科学コース以外が開講する授業を取る必要がある)。その他の単位については、もちろん統合生命科学コースが開講する講義中心で履修を組んでもいい。一方で、生命以外に注力する履修をするのも良いだろう。例えば必修の授業を履修し、かつ複数ある長期期間中の数日単位の集中講義(統合生命科学特論という)など活用すれば、生命系の講義からとることを指定されている必要な単位数34単位以上を簡単にカバーできるため、興味に応じて教養学部内の好きな学科(申請によって他学部も可能)の授業をとって卒業単位を埋めることが可能である。ただし、必修の授業が重なったりする(特に3年からは実験が始まって相当の時間割が埋まる)こととの兼ね合いで物理的に取れる統合生命コース以外の授業数に上限が生まれることに注意。
さて、このように書くと、卒業のためにとる生命系以外の講義についていけるか不安に思うかもしれないが、大体の授業は導入からやってくれるから過度に心配することはない。さらに、実は一つの同じ授業を複数のコースが形式上開講しているというケースが多く、授業の選び方次第で内容は生命系の授業を取っていても申請上は数理系の単位として履修登録することが可能。このような様々な手法はあるものの、独自の制度を活用し、教養学部の真骨頂である学際的な知見を各々養っていくと良いだろう。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
定員20名
第一段階 指定科類 理科11名 全科類 3名
第二段階 指定科類 理科5名 全科類 1名
理I、Ⅱからの進学者が多く、どちらかというと理Ⅱからが多い。また、文系(文Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)からの進学者も数年に一人程度いる。学生の志向は様々で、学部卒業で就職希望の人、院進希望の人、アカデミア志向の人、教員志望の人などが混在している。進学者には、明確にある分野がやりたくて進学する人もいれば、特にそのような軸がなく進学する人もいる。前者に関しては、後期教養の生命科学は越境分野を研究しているユニークな研究室が多いので、これら越境分野・ユニークな研究室に惹かれて進学するというようなケースが多い。また、スポーツ身体科学をやりたくて進学する学生も多い。
■内実は?
学科の特徴として、生命科学の内容を概観でき、かつ特に越境分野の研究に触れられる特徴がある。これは、統合生命科学コースに所属する研究室が非常に幅広い対象をカバーしているのに加え、学際的な研究を行なっている教員が多いためである。
また、学科の様子としてとても自由であることが挙げられる。課題の量もそこまで多いわけではない。また、成績評価ももほとんど試験ではなくレポート中心である。よって、他の学科にありがちな課題、試験だけに追われてしまう多忙な生活ではないので、自分のやりたい軸がある/探したい学生にとっては好きにできるので最適である。(研究室に配属される四年からは忙しさは研究室によって大きく異なる)
また、教員の数が学生よりも非常に多く、かつ柔軟に対応してくれるので、やりたいことがあれば教員にコンタクトを取ると実現できることが多い。
例えば、進振り後早期の頃から研究室に自主的に連絡を取り、研究させてもらっている学生も見受けられる。
一方で、自由であるが故に、やりたいことがない/見つからない場合は、特に何かが学科で手厚くサポートされるわけではないので、行動次第では結果として何も身に付かないということも当然考えられる。
学生の傾向としてはアカデミア志向の学生が比較的多いようである。また、全体の雰囲気としてやりたい分野があって積極的に動いている学生もいる一方で、特にそういうわけでもなく、課題の少なさなどに惹かれて進学する学生もいる。
また、要求・要望科目がないので、理転しやすく、実際にしてくる学生も数年に一人程度いる。授業も生命科学コース以外の様々なコースの人が受けている関係で生命科学を専攻していなかった人向けで展開されていることが多いため、今まで生命科学を深く勉強してこなかった人でも自学習でキャッチアップしやすい。
また、学科の特徴的な授業として、3年生時に週3回で開講される統合生命科学実験がある。この実験を通して、幅広い分野の生命科学実験を体験することができる。
なお、注意すべきこととして、卒業研究で配属される各研究室には、統合生命コースからは各々1名しか定員がないと言うことがある。この配属は、学生への希望調査のもと、希望を最優先に総合的に判断されて教員によって決められる。よって、たまたま同期で同じ研究室の志望が重なっていたら、配属されない可能性がある。例年、自主的な学生同士のコミュニケーションによって、希望のアンケートがとられる前にお互い話し合って被りがないように調整されることが多い。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 細胞生物学Ⅰ,Ⅱ(※1) | 必修 | 木曜2限 |
| 生命科学概論 | 限定選択 | 月曜1限(※2) |
(※1)
ターム制の授業が2つ連続し、セメスターを通し受講する。細胞生物学一般について、担当教員が講義する。なお、タームによって教員が変わる。合計で1セメスターしかないので、教員の専門分野の話に関連した講義が多くなる。よってだんだん内容が専門的になっていきあとで調べてもなかなか出てこない内容になっていくので、レジュメに書き込んでしっかりついていくことが必要である。
(※2)
各教員がオムニバス形式で自分の研究に関して話す。導入は非生命系の人の受講も勘案し、初歩からなされるが、次第に専門的な話になっていく。基本的に統合生命コースの人は本講義の受講を推奨されるが、履修しなくても卒業できる。
本講義は「高度教養科目」と呼ばれる講義の種類の中に位置しているが、同じ「高度教養科目」と言う枠組みのなかで、学科で指定されている数理科学概論や認知脳科学概論...などなどを一定の単位数(例年は6単位以上)履修することで、「高度教養科目」における統合生命科学コースの卒業要件を満たすことが可能である。
3年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 統合生命科学セミナーⅠ | 必修 | 水曜1限 |
2週ごとに英語論文を指定され、輪読形式で学生が和訳しつつ教員から追加説明や質問などがなされる。教員は2週ごとに変わり、教員が論文を指定する。
3年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 統合生命科学セミナーⅡ | 必修 | 水曜1限 |
学生は数名からなるチームに分けられ、チームに対し担当教員が英語論文を指定、チームはこれを読んで他の学生の前でプレゼンし内容を解説する。発表回数は2回ほど割り当てられる。回ごとにチームは編成され、担当教員も変わる。論文は、教員から指定される。発表しない学生は、発表を聞き質問を最低一回することが求められる。
4年生Sセメスター
| 科目 | 区分 |
|---|---|
| 生命科学特別研究(※1) |
(※1)
実質上の卒論のための研究室配属である。内容も卒業研究と変わらない。基本的に、ラボに行く生活になる。この段階で他の授業は履修し終わっているのが理想である。忙しさは、ラボ次第で大きく異なる。しかし、あくまで「卒業研究」ではないので、4Aでラボを変更することも可能である。が、ほとんど変更する人は無い。学生は、3Aに行われる希望調査までに、自分が卒業研究を志望するところを見定める。なお、修士課程に進学する場合、特に希望がなければ同じ研究室に持ち上がりで残る学生が多い(当然院試は受ける必要があり、希望に関わらず成績次第では研究室に残れない場合もある)ので、数年スパンでの環境選びとなり、重要である。先輩などに雰囲気を聞いたり、教員にテーマについて質問する必要があるだろう。特に、現時点においてコースとして研究室ごとの同時説明会などは設けられていない。学生の何倍もの研究室があるから、自分で探していく必要がある。
また、注意すべきこととして、卒業研究で配属される各研究室には、統合生命コースからは各々1名しか定員がないと言うことがある。この配属は、学生への希望調査のもと、希望を最優先に総合的に判断されて教員によって決められる。よって、たまたま同期で同じ研究室の志望が重なっていたら、配属されない可能性がある。例年、自主的な学生同士のコミュニケーションによって、希望のアンケートがとられるまえにお互い話し合って被りがないように調整されることが多い。
さらに本題からそれるが、後期教養学部が接続する総合文化研究科の所属研究室の中には、修士からは学生を受け入れているが、学部生からは受け入れていない研究室などもある。統合生命科学コース進学前に、特定の研究室の配属を計画して逆算し進学する場合は、本当に学部からも受け付けているか確認することが必要である。また、そのような修士からしか学生を取らない研究室は、蓋を開けてみれば定員数が少なかったりして、他大学からの学生との競争率が激しかったりする場合がある。思わぬところで足を掬われないように、事前に連絡をとって定員や募集状態を聞いておくとよい。
・院試について
この時期から院試が始まる。本コースが接続する総合文化研究科の入試時期は8月ごろである。研究をしつつ、だんだんと試験対策に本腰を入れる時期である。ラボによっては院試休みをくれるところもある。詳しく研究室の先輩に聞いてみることをお勧めする。
4年生Aセメスター
| 科目 | 区分 |
|---|---|
| 卒業研究 | 必修 |
卒論執筆のための卒業研究である。ほとんどの学生は4Sからの続きである。卒論を書き、発表することで学位が認定され晴れて卒業となる。
入る前の想像と実際
入る前はどんな学生がいるんだろうと思っていたが、すでに生命に詳しい学生や特定の融合分野に強い興味がある学生がいる一方、生命系は初めてであるという学生も相応にいた。
授業が非常に多くの融合分野をカバーしていて、オムニバス授業でよきせぬ新しい出会いがあり面白かった。
卒研配属の定員一名制度は入るまで知らなかった。
かなり自由な雰囲気である。
履修の関係上、生命系以外の単位も相応取らねばならないので他の分野の考えを知れる機会になって視野が広がった。
授業は割と教員のカバー分野に依存して行われるので、一般的な生物学の知識をつけるには自学する必要がある。
履修を工夫すれば、生命系をあまり取らなくても卒業できるほどの柔軟性があることには驚いた。一定の必修をカバーし、長期期間中の数日単位の集中講義など活用すれば、生命系で必要な単位数の大半をカバーできるため、残りは教養学部内の好きな授業をとることで埋めることができる。
生命実験が始まるとかなり時間割が埋まるので、他のコースの興味ある授業を履修したくても取れない時がある。
生命科学も認知科学・心理学もどっちも学べてお得だと想像した。実際は想像通りだったが、生命の必修と被るため、案外取れる認知の授業は限られていた。
選んだ理由/迷った学科
・ある越境分野に惹かれ、その分野は後期教養でしかやっていなかったから。
・興味のある研究室があったから。
・自由だと噂で聞いたから。
・心理系や数物系など生命系以外の授業を取れるから。
迷った学科は、理学部生物学科、理学部生物化学科、理学部生物情報学科、工学部化学生命工学科、農学部動物生命システム科学科、農学部応用生物工学専修、農学部動物生命システム科学科
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
【数値】5 |
| LINE | 有 |
| Slack | 有 |
| オフラインでのつながり | 中程度。年度による ** |
| 上下のつながり | 中程度。人と年度による |
↑※なども使って、適宜説明を加える。表内に文字を入れ過ぎないように!
・年度による。実験があった学年(コロナ前)はとても繋がりがあったようである。学科の控室というものがあり、実験の待ち時間にそこで談笑していたほか、実験室の前がグラウンドなのでサッカーなどしていたらしい。
・学科LINE/Slackはあるが、あまり動いてはいない
・年度による。2020年度以前の実験があった学年(コロナ前)はとても繋がりがあったようであるが、2021年度はほぼなかった。
・上下の繋がりは人によってはあるが、ない人の方が大半である。特に交流会などはない。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 20~30名前後 |
| 成績評価 | 主に期末レポート |
・期末レポートが一般的。言語科目は試験での評価となる。
・3年から実験が始まる。週三回で、3限から5時-7時くらいまで。早いと3時半くらいに終わることもある。
・3年からセミナー(学科から指定された論文の発表。自分では選べない)が始まる。3Sは毎週英語の論文が出され、それを読むことと当てられた時に訳すこと、質問をすることが求められる。3Aは2回ほど、学科から指定された英語論文を2人ほどのチームで読んで発表する。論文は指定され、選ぶことはできない。
・必修のコース内の授業が他コース・学科・学部に比べて少なく、3年生と4年生を合計して、コース科目はSセメに8コマ、Aセメに10コマのみである。
研究室・資料
特別な制度・その他
・副専攻:所属コース(統合生命科学)の主専攻だけではなく、統合自然科学科内の他コース(認知行動コースなど)が提供する24単位程度の科目群を副専攻として履修するプログラム。修了生は卒業時に、卒業証書に副専攻が記される。
・サブメジャープログラム:所属コース(統合生命科学)の主専攻だけではなく、統合自然科学科内の他コース(認知行動コースなど)および教養学部の他学科(教養学科、学際情報学科)が提供する14単位程度の科目群を履修するプログラム。修了生は卒業時に、卒業証書だけではなく、サブメジャー・プログラム修了証ももらえる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

教養学部
「学際性」「国際性」「先進性」を軸に、深い教養を基盤に従来の枠組み・領域を超えて新しい分野を開拓する人材を育成する学部
関連記事

生物学科
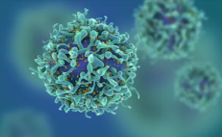
応用生物学専修
【応用生命科学課程】通称「応生(おうせい)」

生物情報科学科

水圏生物科学専修
【応用生物科学課程】通称「水圏(すいけん)」




