理学部
生物学科
2024.1.8
目次
基本情報
| 人数 |
25名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性は3割程度 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
1名前後は学部就職、ほぼ全員院進 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
理学部生物学科、通称「理生(りなま)」。
生命現象の普遍性と多様性を観察し、大腸菌からヒトまで多様な生物現象の理解に取り組んでいく。理生の通称通り、「なまの生き物を丸ごと理解する」という目的で教育・研究を行っている。
授業の多くは理学部2号館で受けるが、実習はそこだけでなく、附属施設である植物園(小石川、日光)や臨海実験所(三崎)等でも行われ、建物の外に出て直接自然に触れることができる。
カリキュラムは、学科全体で共通講義・実習をこなす2Aセメスター、人類学を主として学ぶA(Anthropology)系と、基礎生物学を主として学ぶB(Biology)系と、2コースに分かれる3年次、再び学科全体として「生物科学特別実習Ⅰ~Ⅲ」を通じ卒業研究に励む4年次のように推移していく。
■理生の諸制度
理生では人類学か基礎生物学のどちらかを選ぶため、3年次・4年次の必修科目がそれに応じて大きく異なる。
2年次は専門科目16単位以上の学修が必要。
A系は、必修科目A全て(36.5単位)ならびにその他の専門科目から26単位以上の学修が必要。なお、専門26単位のうち2単位以上は選択必修から選ぶ必要がある。
B系は、必修科目B全て(30.5単位)ならびにその他の専門科目から32単位以上の学修が必要。なお、専門32単位のうち2単位以上は選択必修から実習1単位以上を含むように選ぶ必要がある。
なお、所定の期日までに科目認定届を出して認められた場合は、選択科目以外の理学部及び他学部専門科目についても選択科目にすることができる。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理科(指定科類) | 12 | 0 |
| 全科類 | 2 | 10 |
・得点計算で考慮すべき科目
①要求科目の重率は全て1とする。(第1~3段階)
②総合E「現代生物学」の修得に対し、履修点として2点加点(第1~2段階)
■各コースの違い
3年次よりA系(人類学を学ぶコース)とB系(その他人類学に特化せず基礎生物学を学ぶコース)とに分かれる。
・A系(人類学)
人体解剖などの実習や生化学ゼミ(人体生化学)などの講義、そして猿の観察実習(@長野県地獄谷)などの実習を通じて、人類とその営みを対象とした研究を行っていく。
・B系(基礎生物学)
臨海実験所や日光植物園での実習、古典的実験の追試等で基礎的内容を身につけるSセメスター、それに対してより専門的な内容を扱うAセメスターは、実験やレポートを通じて動植物を広く対象とした研究を行っていく。
■野外実習について
A系
・人類学野外実習(遺跡発掘):3Sセメスター開催@北海道など
・人類学野外実習(霊長類観察):3Aセメスター開催@長野県など
B系
・植物学野外実習Ⅰ:3Sセメスター開催@附属日光植物園
・動物学臨海実習:3Aセメスター開催@附属三浦臨海実験所
共通
・植物科学野外実習Ⅱ:4Sセメスター@西表島など
・植物科学野外実習Ⅲ:3Sセメスター@北八ヶ岳
・特別臨海実習:3Sセメスター@付属三浦臨界実験所
詳細は理学部生物学科ホームページを参照。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■全員で専門科目を受ける2A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 人類生物学 | 専門科目 | A1木曜4-5限 |
| 霊長類学 | 専門科目 | A2木曜4-5限 |
| 骨格人類学実習 | 専門科目 | A金曜4-5限 |
・週15コマ程度。
・多くの学生が受講する講義は15コマ中10コマ程度だが、他セメスターと比べれば履修科目の自由度は高い方である。
・実験はほぼ無い。
・実習や、標本を扱う講義は本郷で行われる。
・新2年生を交えた歓迎会が10月に行われる。それ以外の時期も、理学部2号館のキッチンやラウンジで、先生も交えた懇親会がしばしば行われる。
・学科全体として、A系B系の区別はなく、遺伝学、分子生物学、進化生物学、人類生物学などの基本的な生物学の科目を学んでいく。
・A系に進む学生は、「人類生物学」「霊長類学」「骨格人類学実習」の修得が推奨されている。
・生物化学科、生物情報学科などと同じ授業を受けることも多い。
・A系とB系とのコース選択は、12月末頃に説明があり、1月初めまでに希望を出す。
・基本的にA系とB系は自由選択。人数としてはA系が10名程度でB系が15名程度。
3年生Sセメスター
■A系・B系に分かれる3S
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 形態人類学実習 | A必修 | 集中 |
| 人体解剖学実習 | A必修 | S1月火水木3-5限、金1-4限 |
| 生物科学共通実習 | B必修 | 月火木金3-5限 |
・理学部2号館での、先生・学生交えた懇親会・飲み会は、依然活発になされる。
・4年生は研究室で活動しているため、学科部屋に屯する学生は3年生が中心。参考書やデスクがある。
・年度によるが、五月祭にて生物系に絡めた模擬店などを開くことも。
・AB両系との独自講義のほかに、学科全体に共通の講義(選択必修科目)がある。
・Aセメスターで実施される生物学科開講の「科学英語」について、6月にUTASで履修アンケートが行われ、授業を受けたい先生を選ぶ。人数が偏った場合は抽選。
・AB両系ともに、主に午前中が講義で午後が実習。
A系の場合
・週5で、午後は人体解剖・脳解剖をずっと行うなど、実習がメイン。
・それ以外の授業コマは、午前中に6コマ。
・3年次より、実習が医学部医学科とほぼ同じ。人体解剖と脳解剖、つまり生理学や生化学の実験をする。
・人体解剖学実習の予習と単語テストに追われる。
・人体解剖学実習が6月に終わると、脳解剖実習がスタート。下旬からは医学部と共通ではないA系授業と実習が始まる。
・8月、礼文島へ1週間の発掘実習。海の幸や島巡りも楽しむ。
・9月、2週間ほど人類生物学実習の夏休み集中講義。3Aセメスターに控える人体組織学の予習をする学生もいる。
・選択科目で1週間ほど実習科目を取ることができ、フィールドワーク好きな学生には楽しめそう。
B系の場合
・附属臨海実験所や附属小石川植物園を利用した、動物や植物と直に触れ合う実習がある。
・4月は、器具の取り扱いや基本的な実験方法を学ぶ。
・5月は附属臨海実験所に1週間泊り込み、採集とスケッチを繰り返す。
・6月はダーウィンやシュペーマンなどの古典的実験を追試する。
・7月、実験が一区切りついたらレポートと試験がなされる。
・8月は、日光植物園で野外実習。築100年の長屋で、30名分の食事作ったりする。登山未経験者にはハード。
・秩父や富士山での、希望者だけの泊り込み実習。動物や植物の組織断片のスケッチという宿題で大忙しの学生も。
3年生Aセメスター
■3Sよりさらにハードな3A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 科学英語 | A集中(火1/金2/土3/土4のどれか) | |
| 人類生物学実習 | A必修 | 集中(9-10月) |
| 人体生化学 | A必修 | 集中(月1-2限、水曜1-2限、木曜3-5限) |
| 人体解剖学 | A必修 | A月火水木3-5限、金1-4限 |
| 人類遺伝学実習 | A必修 | A月火水木金1-5限(11月末-12月) |
| 先史学実習 | A必修 | 集中(1月) |
| 人体{生化学/組織学}実習 | A必修 | 月3-5限、木1-2限、金1-4限、集中(1-2月) |
| 人類学野外実習 | A必修 | 集中(10月) |
| 生物科学専門実習Ⅰ | B必修 | A月火木金3-5限 |
| 生物科学専門実習Ⅱ | B必修 | A月火木金3-5限 |
| 生物科学専門実習Ⅲ | B必修 | A月火木金3-5限 |
| 生物科学専門実習Ⅳ | B必修 | A月火木金3-5限 |
・時間割はやや変則的。
・「科学英語」を履修する学生が多い。
・4Sセメスターで2研究室を回る「プレ卒研」がなされる。その研究室希望調査は3Aセメスター末になされる。学生の数に比して研究室数が多いので、ほぼ希望通り。稀に一部研究室に希望が集中した場合は、S1ターム⇔S2タームで入れ替えして対応する。
・1月にはプレ卒研の配属研究室が決まる。先輩の卒研発表を聞いて来年へ向けての勉強を始める。
・3月には、先輩の修論発表会に出向いたり、4年生へ向けて、興味のある研究室に個人的に連絡し、「プレプレ卒研」をしたりする人も。
A系の場合
・授業コマ数は、6コマ程度だった3Sセメスターから8コマ程度に増える。
・医学部と共通の「人体生化学・人体組織学実習」がスタート。Sセメスターより忙しくなる学生が多い。
・「人体生化学」(生化学ゼミ)は予習が大変だが、英語の論文を読む良い訓練になると評判。
・11月には長野県地獄谷で5日間、猿の観察実習に出向く。
・人体組織学実習の期末試験が年末になされる。それが終わると冬休み。
・1月は少人数の集中講義を受ける。
・2月からは「人体生化学実習」にて予習とレポートの日々。ここで基本的な実験操作を学ぶ。2月下旬から春休み。
B系の場合
・Aセメスターから「講義・専門実習Ⅰ~Ⅳ」が始まる。講義も実験もより専門的な内容になっていく。数字が上がるほど実験やレポートの負担が重くなっていく。
・1月は、レポートや試験をこなしつつ、希望者のみ参加の「臨海実習」にて、海産生物の生理をじっくり追求する学生も。
・2月にレポート提出も完了すれば、ついに春休みになる。
4年生Sセメスター
■研究室に配属される4S
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 生物科学特別実習Ⅰ(4-5月) | 必修 | S1月火木3-5限、金3-4限 |
| 生物科学特別実習Ⅱ(6-7月) | 必修 | S2月火木3-5限、金3-4限 |
| 研究倫理 | 必修 | 集中 |
・A系・B系での履修科目の違いは無くなる。
・理学部2号館、附属臨海実験所、附属植物園、総合研究博物館の各研究室に配属される。
・「特別実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」を通じて、最大3つの研究室を回って研究活動に参加する。「特別実習Ⅰ、Ⅱ」の配属先は3Aセメスター末で決めるが、A系B系問わず、生物学科の全研究室から選択できる。
・4-5月は「特別実習Ⅰ」、6-7月は「特別実習Ⅱ」。具体的なテーマが与えられ、研究の進め方や実験技術を修得するとともに、セミナーにも参加し、生物学の文献の読み方を学ぶ。
・「特別実習Ⅲ」の配属先、つまり卒研配属先は7月に決める。
・7月には大学院に出願し、8月には院試を受ける。
4年生Aセメスター
■卒研に追われる4A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 生物科学特別実習Ⅲ(10月-翌1月) | 必修 | A月火木3-5限、金3-4限 |
・11-12月は卒研にひたすら追われる。
・1月には研究成果を発表する卒研発表会が行われる。
・2月には先輩の修論発表会を聴きに行ったり、修士課程の研究をスタートさせたり、中には学会発表にチャレンジする者も。
入る前の想像と実際
・思った以上に一次情報を集めに行くフィールドワークの機会が多い。
・生物が好きで集まっている人が多いので、知識量はかなり求められる。勉強をきちんとやろうと思ったら、相当量の努力が必要になる。
・先生方が質問すれば優しくサポートしてくれる。
・(A系)医学じゃないけど人にまつわる研究ができる。
・リアルな生き物を扱うばかりでは無く、理論系や数理系を扱うことも多い。研究対象は生物でも、自身の強い関心は機械工学、という人も。
(理二→理生)
選んだ理由/迷った学科
・人の骨格や筋肉といった仕組みの研究を本格的にやりたかった。人類について一番学べる場所だと思ったから。
・後期教養の認知や、工学部の機械工学系も迷った。認知だと心理学に近い内容となり、機械工学だと最終的に応用先がロボットなので、やや自身の興味と異なると思い、理生にした。
(理二→理生)
欧米ではバイオ系が一番のトレンドだし、ゲノム解析や遺伝学、DNA系に関心を持っている学生も増えてきている印象。ただ、全体としてはみんな興味がバラけている。マニアックに棘皮動物(ヒトデなど)の研究がしたかった人、1人で西表島でフィールドワーク片付けちゃう人など。
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
7 〜10。年度によって異なる。 |
| LINE | 有 |
| Slack | 年度によって異なる(※) |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | あまりない |
※Slackがある学年では試験や院試の情報交換が行われるが、普段から活発に動くことは無い。
・先生や先輩との距離が近く、キッチンやラウンジがある理学部2号館などで懇親会が頻繁に行われる。地獄鍋などをしたりする。
・仲良いメンバーで学科旅行などが企画されることも。
・学科生同士の繋がりは強く友達も沢山できるが、逆に言えば学科外のコミュニティはあまり広がりづらい。
・クラウド上でシケプリ等は先輩から引き継がれてくる。任意で新たに作る「有能」な人もいる。
・長期インターンなど課外活動に熱心な人もいれば、研究所で朝から晩まで研究している人もいる。
・男女分け隔てなく仲が良い。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 15名前後 |
| 成績評価 | 出席/レポート/期末試験全て |
・座学か実習のどちらか。
・座学では出欠を取る。遅刻はそれほど厳しくない。2Aセメスターを中心に、試験でしっかり点数を取れば出席しなくても何とかなる授業はいくつか。
・実習は参加しないとキャッチアップが結構大変。
・出席やリアペのようなことがあることも。
・特別実習などは、参加したうえで月末にレポートを提出するスタイル。
・(A系の場合)解剖等の授業は3週間くらいごとに「諮問」がある。部位の説明等の口頭試験も行う。月1程度の頻度でペーパーテストも行われ、期末試験もある。
・(A系の場合)医学部と合同で行う授業の場合、完全ミックスというより、学科ごとに番号は振られているので、別々になることが多い。
・実験ごとにレポートを書く授業も多い。
研究室・資料
理生では、学生定員25名前後に比して教員が約50名と非常に多い。
教員一覧
研究室概要(2020年度版)
学科パンフレットが非常に充実している。要参照。
公式 学科紹介動画
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
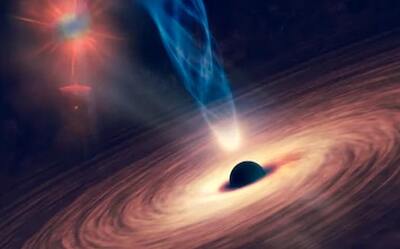
理学部
理学の理念の下に、 豊かで平和な人類の未来社会を切り拓く先端的な理学の教育・研究を推進する学部
関連記事

生物・環境工学専修
【環境資源科学課程】通称「生物環境(せいぶつかんきょう)」

森林生物科学専修 森林環境資源科学専修
【応用生命科学課程】/【環境資源科学課程】 通称「森林(しんりん)」

動物生命システム科学専修
【応用生命科学課程】通称「動シス(どうしす)」

生物素材化学専修
【応用生命科学課程】 通称「素材(そざい)」




