農学部
動物生命システム科学専修
2024.7.24
【応用生命科学課程】通称「動シス(どうしす)」
目次
基本情報
| 人数 |
9名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
少人数学科のため、年によって変動しやすい |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
大多数が院進/就職は学年に1人程度 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな専修?
動物生命システム科学専修(通称:動シス)では、哺乳類を主な研究対象として、分子、細胞から個体レベルまで様々な視点から研究を行っている。さらにこれらの研究を通して、基礎生物学の発展だけではなく、得られた知見を応用した新しいバイオテクノロジーの開発などに取り組んでいる。
3年次は、主として午前中に動シス単独または獣医学専修と合同の授業(座学)があり、午後は6つの研究室それぞれが主催する実習が行われて基礎的な実験手法や研究の基本を学ぶ。研究内容は理学に近いが、獣医学専修の学生が同じ研究室に配属されたり、3年生での必修授業に東大附属牧場での実習があったりと、農学部ならではの実学的な側面も持つ。
学生の人数の割に教員・研究室の数が多いため、希望の研究室にはかなりの確率で進める。ほとんどの人が大学院(応用動物科学専攻)に進学する。
3年次の実習などによって、必然的にどの研究室の教員・先輩とも顔見知りになる。4年生以降は実習でほぼ必ずTAを担当するため、下の代の学生のことも全員覚えられる。同期も少ないため、かなり親密になることが多く、研究室をまたいでの飲み会、ソフトボール大会(獣医と合同)などが開催されることもあり、他の研究室の教員や学生との関わりも多い。実際、実験手法を他の研究室に習いに行くこともある。教員との距離も近いため、4年次の研究室配属に向けて個人的に研究室見学をお願いしやすい環境である。
■学科の諸制度
卒業に必要な単位は76単位。その内訳は下表の通りとなっており、それぞれの区分から必要単位以上を取得しなければ卒業できないため、きちんと計算して履修を組む必要がある。研究室には基本的に3年生の3月頃から入ることになる。
・卒業に必要な単位数
| 区分 | 必要単位数 | 内容 |
|---|---|---|
| ①農学総合科目 | 4単位以上 | ②と併せて14単位以上取得。22単位まで算入可 |
| ②農学基礎科目 | 6単位以上 | |
| ③応用生命科学課程専門科目 | 24単位以上 | 必修10科目20単位を含む |
| ④農学共通科目 | 4単位以上 | 必修1科目2単位(農学リテラシー)+選択必修2単位(環境・生命・技術倫理) |
| ⑤専修専門科目 | 20単位 | 必修10科目20単位を取得 |
| ⑥他課程・他専修専門科目/農学展開科目/課程共通科目/他学部科目 | 合わせて14単位まで算入可 | 農学展開科目は4単位まで/他学部科目は承認が必要 |
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理Ⅱ(指定科類) | 4 | 2 |
| 全科類 | 3 | 0 |
理科Ⅱ類出身者が多い。その他、理科Ⅰ類から年に1人程度、文科からは2年に1人程度が進学してくる。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 環境倫理(※1) | 選択必修 | 月曜5限 |
| 農学リテラシー(※2) | 必修 | W集中 |
(※1) 農学展開科目(卒業までに必ず1単位を取る必要がある)。2Aの「環境倫理」、3Sの「生命倫理」、3Aの「技術倫理」から選択。
(※2) 農学部の学生は全員必修。Wタームに集中講義形式で開催。例年1/23~28前後の4日間。履修登録を忘れずに!
・週12~15コマ前後が一般的。座学が中心。
・動シス主催の授業はほとんどないため、他の専修と合同で農学部の講義を受ける。
3年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 動物細胞生化学I | 必修 | 火曜2限・木曜1限 |
| 動物生命科学基礎 | 必修 | 水曜1限・金曜2限 |
| 放射線動物科学 | 必修 | 月曜1限・水曜2限 |
| 動物生命システム科学実習I | 必修 | 集中 |
| 動物生命システム科学実習II | 必修 | 集中 |
| 動物生命・形態学実習 | 必修 | 集中 |
| 動物生命・牧場実習 | 必修 | 集中 |
3年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 応用遺伝学 | 必修 | 月曜2限・木曜1限 |
| 応用免疫学 | 必修 | 月曜1限・水曜2限 |
| 動物細胞生化学II | 必修 | 火曜1限・木曜2限 |
| 動物行動学 | 必修 | 火曜2限・金曜1限 |
| 動物生命システム科学I | 必修 | 月曜2限・木曜1限 |
| 動物生命システム科学II | 必修 | 火曜1限 |
| 動物生命システム科学実習III | 必修 | 集中 |
| 動物生命システム科学実習IV | 必修 | 集中 |
| 動物生命システム科学実習V | 必修 | 集中 |
| 動物生命システム科学実習VI | 必修 | 集中 |
・3年次の時間割は午前中の講義と午後の実習でほぼ埋まる。
・講義は動シス単独のものと、獣医学専修と合同のものがある。
・実習は動シスの学生のみで行われる。
・「動物生命システム科学実習」は各研究室が持ち回りで担当し、Sセメスターでは基本的な実験手法を、Aセメスターでは研究室ごとに特色のある専門的な実験手法を学ぶ。実習では細胞を扱うものから動物個体を扱うものまで様々な実験を行う。なお、「動物生命システム科学実習」Ⅰ・Ⅱ(基礎実習)及びⅢ・Ⅳ(I専門実習)では、それぞれ一連の実習を扱っており、内容的に区別はない。
・「動物生命・形態学実習」では、実際の動物組織標本を観察しスケッチすることを通して、様々な組織の構造を学ぶ。
・牧場実習(7月初旬)では、獣医学専修の学生と一緒に東大附属牧場を訪問し、ヤギ、ブタ、ウマ、ウシの世話などをする。動シスや獣医の学生・先生と交流を深められる。実習期間は4泊5日程度。
4年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 動物生命システム科学演習 | 必修 | 集中 |
| 卒業論文 | 必修 | 通年随時 |
4年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 動物生命システム科学演習 | 必修 | 集中 |
| 卒業論文 | 必修 | 通年随時 |
・4年次は基本的には研究室に所属し、卒論に向けた研究を行う。
・単位が足りなければここで単位を回収することになるが、大変なのでなるべく3年生まででに取り切っておいた方がよい。
入る前の想像と実際
・「扱うのは動物ばかりなのかと思っていたら細胞レベルでの実験と半々くらいだった。」
・「割りとイメージ通りだった。人数もそこまで多くないため、先生との繋がりも強い方だと思う。」
・「もう少し医学寄りのこともできると思っていたが、やはり農学部色が強い。研究室による。」
・「実習が手厚くて驚いた。」
・「パリピが多い印象だったが、みんな真面目に研究に打ち込んでいた。」
選んだ理由/迷った学科
・「感染症の研究がしたかったから。学生の数に比して教員の数が多いため、色々ことをみっちり教えてもらえると思ったから。(迷った学科:薬学部)」
・「少人数でまったりと研究したかったから。(迷った学科:獣医学専修)」
・「動物(哺乳類)の研究がしたかったから。(迷った学科:理学部生物学科)」
・「1学年の人数が少なく、教員の方が学生に比べて多いくらいだったため、手厚い指導が受けられそうだったから。」
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
7 |
| LINE | 有(※1) |
| Slack | 有(※2) |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
(※1)「ほとんどの代で同期Lineがある。」
(※2)「学生間ではLINEを使い、先生とはSlackで連絡を取っている。」
・「人数が少ないため、代や人によって異なるが、概して仲は悪くないと思う。」
・「3年次の実習でほとんどの先輩(特に4年生・修士1年生)と顔見知りになる。逆に学年が上がってからは、懇親会や実習などで後輩と何度も顔を合わせるため、学年を越えて仲良くなる。」
・「研究室選びに向けて気軽に先輩の意見を聞ける。」
・「コロナ前は飲み会を開くと他の研究室の人も来ることがあったため、つながりは強い方だと思う。」
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 8名前後(※1) |
| 成績評価 | 出席/レポート/期末試験 |
(※1)獣医と合同の授業が多い。
・「動シスだけの授業は人数も少なく、双方向の授業になりやすかったと思う(その中でも睡魔に襲われることはある)。」
・「出席+レポート(または期末試験)での成績評価。動シス単独の授業は人数が少ないため、教員と会話しながら進むことが多く、出席をごまかすことはできない。」
・「オムニバス形式で色々な教員が1回ずつ授業を受け持つ授業では、全講義の中から好きな教員の授業を3つ選び、それぞれについて1本ずつ、計3本レポートを書くというものもある。」
・「3年次の午後の実習では、1研究室が2週間弱ずつ担当する。成績評価は、それぞれの研究室で行った実験についてまとめたレポートに基づき行われる(レポートが課されない研究室もある)。」
・「生徒の反応を求める先生が多い(授業中、当てられることが多い)」
研究室・資料
農学部公式の「教員カタログ」はこちら
(各教員の研究内容が平易に書かれているだけでなく、目指す教育内容や研究室の人材輩出実績など進学選択の意思決定に役立つ情報が盛りだくさん。)
〈研究室紹介〉
・応用免疫学研究室 / 紹介動画
・応用遺伝学研究室 / 紹介動画
・動物細胞制御学研究室 / 紹介動画
・細胞生化学研究室 / 紹介動画
・獣医動物行動学研究室 / 紹介動画
・放射線動物科学研究室 / 紹介動画
・実験資源動物科学研究室 / 紹介動画
特別な制度・その他
・One Earth Guardians 育成プログラム(略称OEGs):農学部の学部生・院生向けプログラム。「100年後の地球に貢献する科学者」を育てることを目指している。OEGs候補生は、企画立案から実行まで行う「実学研修」と「認定科目」とをそれぞれ履修。学部3年生から博士課程まで、様々な学年・専修の学生が参加している。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

農学部
諸科学に関する世界水準の教育・研究を進め、食料・環境をめぐる多様な課題に取り組む専門性豊かな人材を養成する学部
関連記事
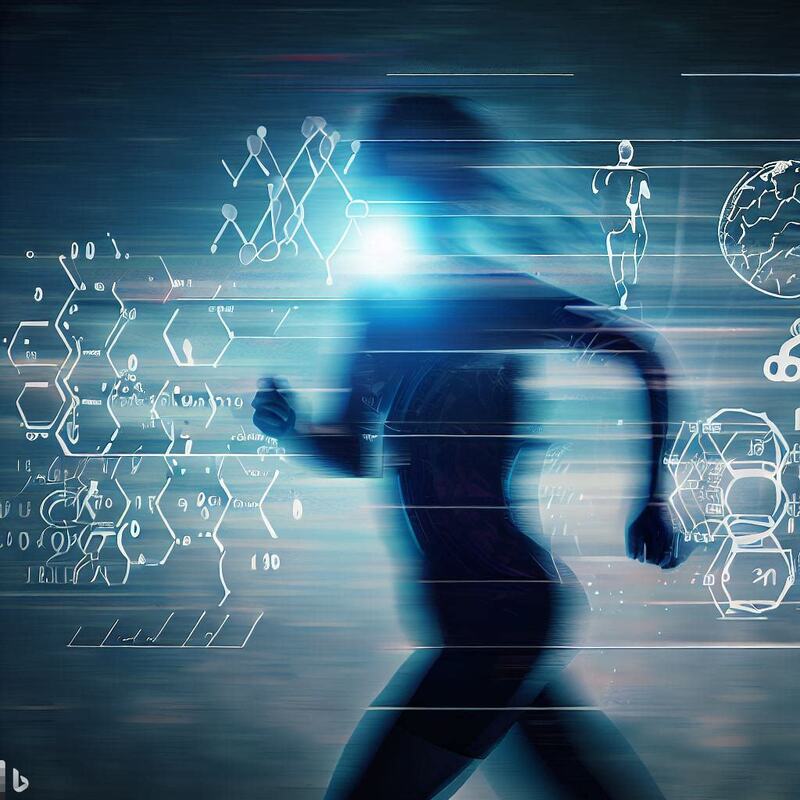
統合 スポーツ科学コース
2023年度の進学選択より正規コースとなった統合自然科学科スポーツ科学コース

農業·資源経済学専修
【環境資源科学課程】通称「農経(のうけい)」

国際開発農学専修
【環境資源科学課程】通称「国農(こくのう)」
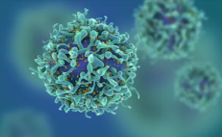
応用生物学専修
【応用生命科学課程】通称「応生(おうせい)」




