教育学部
基礎教育学コース
2023.4.15
総合教育科学専攻 基礎教育学専修
目次
基本情報
| 人数 |
20名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ2ー3割 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
就職:院進=8:2程度 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
・概要とカリキュラム
基礎教育学コース(以下、当コース)は、教育研究の基礎的な部分を哲学・歴史・人間学・臨床哲学といった側面から扱う、教育学部 教育社会科学科(※1) 基礎教育学専修のコース。
※1:教育学部は、全コースともこの学科に所属する。以下、当コース。
カリキュラムの流れは、概論・演習での文献購読やディスカッションを経て、各教員の専攻分野に触れていき、4年次の卒論に収斂させていくようになっている。
・在籍する教員の専攻
教員は教育臨床学、教育人間学、教育哲学、教育史から成る。
■当コースの諸制度
・必要単位数
卒業までに必要な単位は70単位。教育学部は全コースともに卒業論文8単位、必修科目30単位及び選択科目32単位の修得が必要。必修科目の30単位については、当コースの「概論」6単位と「演習」10単位、「特殊講義」4単位、さらに他専修の授業科目8単位(概論4単位以上を含む)、当コース「研究指導」2単位で構成される。
・必修科目の内訳
| 科目名 | 単位数 |
|---|---|
| 基礎教育学概論 | 6 |
| 基礎教育学演習 | 10 |
| 基礎教育学特殊講義 | 4 |
| 教育学部他専修の授業科目 | 8(※) |
| 基礎教育学研究指導 | 2 |
※ 概論4単位以上を含む。
・注意点
なお、当コースは前期教養で言う「情報」「ALESA」のような「特定の必修の授業」は卒論以外に無く、講義題目と授業科目が異なる点に注意が必要。例えば「概論」は、「西洋教育史概説」「教育臨床学概説」「教育哲学概説」「教育人間学概説」「日本教育史概説」で構成される。この時、いずれか3種類の講義を取れば6単位の要件に到達できる。
■進学定数は?
・進振り時点からコースごとに希望を出す。
・コースの定員数は19名で、受け入れ枠としては指定科類枠(文Ⅲ)、全科類枠の区分が存在する。
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅲ(指定科類) | 9 | 4 |
| 全科類 | 3 | 3 |
■卒論は?
・教員6名程度、学生20名程度のコースなので、卒論は基本的に3名程度の少人数個別指導。
・ゼミに所属するわけではなく、卒論を指導してもらいたい教員に希望届を出して指導してもらうスタイル。同じ教員が4-5名指導する場合は、ゼミ形式になることも(教育史の小国先生は「教育史」担当が一人だけなので、人数が多くなりがち)。
・基本的には上手く希望が分かれることが多い。
・動き出し~卒論提出までは、質問事項があれば教員に連絡するケースから、指導学生が一堂に集まるケースまで多様。教員によって内実は異なることが多い。
・卒論の質は学生による。単位を揃えて卒論を出しさえすれば、基本的に卒業は可能。
〈全体的なスケジュール〉
○4S
・構想発表に向けた準備が中心。
○夏休み前
・構想発表(卒論のテーマやアウトラインを発表する会)が行われる。
・「学生が発表→教員がそれに質問・アドバイスする」流れを、指導教員関係なく全員集まって順々に行う。
○夏休み終わり
・卒論に向けて本格的に動き出す。
○11月
・中間発表の場にて、進捗報告を行う。
○1月
・上旬に提出期限がある。
○2月:最終発表(口頭質問)
・卒論の要旨をプレゼンテーション。
・3時間で、20名程度が1日で発表する。
・1-2名の教員から、発表内容について質疑応答を受ける。
■卒業後の進路は?
・民間企業・公務員・教育現場・大学院で大別される。
・民間は、教育と無関係の企業が多い。
・公務員は、国家公務員・地方公務員ともに一定数はいるが、やや少なめ。
・教育現場は、高校教員や中高一貫教教員が多い。有名私立の場合、母校で採用されることが多い。※東大教育学部では、小学校免許を取ることができない。
・大学院は、殆どが「教育学研究科」の「基礎教育学コース」へ進学。
Cf.2014年進路状況調査-教育学部
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■駒場と本郷の両方で持ち出しを受ける2A
| 講義題目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| Philosophical Issues in Education | 特殊講義 | (駒場)A金曜2限 |
| 価値と教育Ⅰ | 演習 | (本郷)A金曜4限 |
| 教育文化論演習 | 演習 | (本郷)A火曜4限 |
| 教育政治学演習 | 演習 | (本郷)A金曜3限 |
| 臨床教育現象学演習 | 演習 | (本郷)A木曜2限 |
※全て取るわけではないので注意!(以下のセメスターも同様)
※対面授業時には、本郷キャンパスと駒場キャンパスで開講される隣あった曜限の科目を履修できないというルールがあるので注意。オンライン時は許容されているが、対面での講義・試験の場合、どちらか一方のみ選択することになる。詳細は[こちら](学生向け情報 | Forstudents (wixsite.com)から確認のこと。
・平均して10コマ前後が一般的か。
・ほとんどの人は教育学部持ち出し科目や他学部・他コース科目を、駒場と本郷で半々程度で受ける。
・教職を取っている学生には本郷開講を多く取る人もいるが、まれ。
・駒場で取れる持ち出し科目の数はそれほど多くない。教育学部便覧 (※) に「総合教育科学科(教育学部全5コースとも当学科に所属) 持出専門科目」として1ページにまとめられるほどの数。ただ、当コースの「特殊講義」に指定される科目がある(上表の通り)。
・教育学部の持ち出し科目だけでなく、他学部履修として、教養学部や文学部の科目(持ち出しOKの科目が大半)を履修する者も多い。
3年生Sセメスター
■授業はバラバラの3S
| 講義題目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 教育人間学概説 | 概論 | S金曜3限(偶数年度) |
| 文化と教育の哲学 | 概論 | S木曜4限 |
| 戦後教育史演習 | 演習 | S月曜2限 |
| 道徳と教育 | 特殊講義 | S金曜4限 |
| 臨床教育現象学概論 | 特殊講義 | S木曜5限 |
| バリア・スタディーズ | 特殊講義 | S金曜5限 |
| 教育思想特論 | 特殊講義 | 7-9月集中 |
・10コマ前後の履修が一般的。
・上表内から選ぶ形なので、人によって履修傾向はバラバラ。全員が同じ授業に揃うことが稀だが、1回の授業で10名程度には会える。
・概論・演習・特殊講義等の必修単位を4年に持ち越さないため、コース科目の履修に勤しむ。
・他学部でも文学部など似た分野の科目を取る人や、ターム制が多い経済学部の授業を取る人もちらほら。
3年生Aセメスター
■卒論の足音が聞こえてくる3A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 教育哲学概説 | 概論 | A木曜4限(偶数年度) |
| 日本教育史概説 | 概論 | A月曜2限(偶数年度) |
| 価値と教育Ⅰ | 演習 | A金曜4限 |
| 教育文化論演習 | 演習 | A火曜4限 |
| 教育政治学演習 | 演習 | A金曜3限 |
| 臨床教育現象学演習 | 演習 | A木曜5限 |
※「価値と教育Ⅰ」~「臨床教育現象学演習」は、2年次の学生も受講できる。
・10コマ前後の履修が一般的。
・上表内から選ぶ形なので、人によって履修傾向はバラバラ。
・概論・演習・特殊講義等の必修単位を4年に持ち越さないため、コース科目の履修に勤しむ。
・他学部履修の傾向は3S同様。文・経済などが多い。
・4年生の卒論口述試験(2月)は原則出席必須。その際に、先輩が何を研究していたのかを知り、自身の卒論テーマについて徐々に考えるようになっていく。
4年生Sセメスター
■卒論に着手する4S
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒論 | 卒論 | ―― |
| 基礎教育学研究指導(※) | 研究指導 | 通年隔週月曜1限 |
※隔週月曜1限とあるが、実際には授業が行われないことが多い。卒論指導は指導教員の裁量に委ねられており、詳細は当ページ上方、「学科概要 ■卒論は?」参照。
・コマ数は、残している必修の数や個々人の興味に依存し、多様。
・指導教員は5月に決める。指導してもらいたい教員に連絡後、コースに希望届を出し、基本的には希望が通る形式。
・1教員当たり2名以下だと個別指導(好きなタイミングで質問する等)、4~5名になるとゼミ形式で指導が進む。
4年生Aセメスター
■卒論執筆・発表準備に追われる4A
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒論 | 卒論 | ―― |
| 基礎教育学研究指導 | 研究指導 | 通年隔週月曜1限 |
・卒論以外で授業を取っている人は少ないが、一定数いる。
・12月前後には、他学部・他コース同様、本格的に卒論に取り組む人が多い。
・1月上旬が提出期限で、2月上旬には口述試験も行われる。
入る前の想像と実際
・イメージ通りだが、ゆるい。
・学問を頑張りたい人は先生からのサポートも厚く頑張れるし、一方単位を取りやすいため部活や就活、課外活動などそれぞれ自分が頑張りたいことにも注力できる環境。
・卒論以外で、「必修科目」が無いことに驚いた。
・放任主義。履修の組み方・卒論ともにそう。
・3,4年次ともにゼミが無く、オンライン化もあって学科懇親会や対面授業も無い。よって自由な所もあるが、学科への帰属意識をやや持ちづらかった。
・体系的に基礎→応用とステップを踏んでいくよりは、教育学に関することを何でもやるイメージに近かった。
・とっつきやすいテーマで、特に東大生は語りやすいテーマなので、「基礎なんかいらない!」と思う人もいるかもしれないが、入ってみるとまだまだ知らないことだらけだった。
・教員免許を取りたい人にとっては、教育学部の認定科目と履修科目が被りがちなので、結構お得。
※比較的他コースに当てはまる内容が多いと思われる。
(文三→基礎教育学コース)
選んだ理由/迷った学科
・自分の研究関心に紐づけて選択した。2Sセメスター時にコースで開講されていた授業を聴講した上で決めた。
・比較教育社会学コースと迷ったが、実証主義的な考え方が合わず、当コースを選択した。
(文三→基礎教育学コース)
一般的には「単位取得の容易さ」を挙げる人が多い。消極的理由に聞こえるが、部活などに全力を傾ける学生も多い。初ゼミの教員に影響され、教育哲学に関心を持つ者もいた。
コース所属教員の著書・論文、卒論などを参考にする者も多い。
Cf. 基礎教育学コース 卒論テーマ
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 5 |
| LINE | 有 |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 少 |
・例年LINEグループはある。
・Slackは、代によるが、「院進希望者」など一部メンバーで作られることも。
・公式の連絡は、事務室からメールで連絡が来る。事務員の方とも仲が良く、お土産渡したりお茶したりすることも。
**
《ビフォーコロナ》
・学科同期同士の飲み会もあり、仲が良い。
・寝泊りできるレベルに整備された学科部屋があり、そこに入り浸る学生も多い。ロッカーもある。先生や事務員の方も交えた懇親会なども。
・3Sセメスターが始まる4月に教育学部棟でコース内の3,4年生で懇親会がなされるが、参加する学生数がそもそも少ない。
**
《アフターコロナ》
・飲み会・学科部屋での交流はあまり活発に行われていない。
・同期のLINEグループ間で、手続きや卒論などのやり取りは行われる。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 40-50名前後(※) |
| 成績評価 | 出席/レポート |
※他専修から受けに来る学生も多いため。
・全体的に出席が重視される。
・グループワーク講義が多く、グループごとに話した内容をまとめて提出することが多い。
・期末試験を課す科目はあまりない。
・レポートが中心なので、シケプリを作る文化自体がそもそもない。
研究室・資料
特別な制度・その他
履修科目の関係上、当コースでは教職に加えて、社会教育主事、学芸員、司書の資格が取りやすい。
※いずれも、コース内外で必要単位を取得することが必要。
・取れる資格一覧
①教員免許状
社会(中学)、地理歴史(高校)、公民(高校)、保健体育の教科について、中学校及び高等学校の一種の教育職員免許状を取得できる。大学院にて、専修免許状を取得可能。
②社会教育主事
教育委員会の社会教育行政専門職員。社会教育・生涯学習施設、体育センターなどで専門職員として働く場合にも重要。
③司書・司書教諭
公立図書室・学校図書室で専門的職務に従事する資格。ただし司書教諭の場合、教員免許状を基礎資格とする。
④学芸員
博物館で資料の収集・保管・展示及び調査研究などの専門的職務に従事するための資格。
⑤社会調査士
社会調査のスキルの取得を証明する、一般社団法人社会調査協会認定の資格である(※取得できるコースに制限あり)。
(※) 学部便覧、または教育学部ページをご参照下さい。
後期課程の便覧は基本的に内定生のみが閲覧可能です。ただし、学部ごとの前期課程生向けガイダンスや学科のサイトで配布されていることもあるようです。また、アドミニ棟に前年度のものが置いてある可能性があります。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

教育学部
教育についての専門的な研究と教育、教育に関する専門職の育成、中等教育教職養成を目指す学部
関連記事

超域 比較文学比較芸術コース
教養学科 超域文化科学分科

地域 ラテンアメリカ研究コース
教養学科 地域文化研究分科
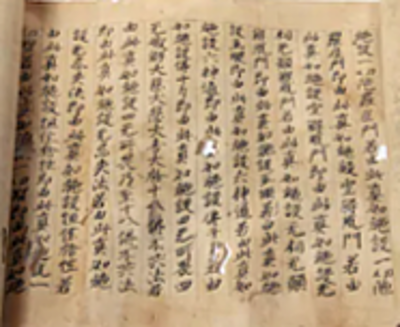
G国文学専修
G群(言語文化_国文学)

A倫理学専修
A群(思想文化_倫理学)




