教養学部
超域 学際言語科学コース、言語態・テクスト文化論コース
2023.10.21
教養学科 超域文化科学分科
目次
基本情報
| 人数 |
学際言語:5~10名(年によって変動あり)/ 言語態・テクスト文化論:2,3名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
少人数のコースなので、年によって異なる。 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
就職:院進=7:3 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんなコース?
学際言語科学コースでは、言語の構造と機能に様々な側面から光をあてつつ、統合的な人間理解をめざす視点からその本質に迫ることを目指した研究・教育を行っている。
言語の多様性とその背後にある普遍性とを捉えようとする視座と、様々な視点から言語を科学的に見据える姿勢を育てる。こうした横断的視座・学際的アプローチを実践するため、2つ以上の実践的な外国語の能力を養い、マルチリンガルな発信型の外国語習得を目指す。同時に、メディアリテラシーを身につけ、言語への理解を軸に、現代の多元的言語生活、文化複合状況の中を生きる力を目指す。
理論研究からフィールド・実験・応用系まで多様なスタッフを擁し、外国語教育から言語工学技術まで、社会での実践に役立つ専門知識を備えたスタッフも充実している。
言語態・テクスト文化論コースでは、言語の問題を根幹にすえて文化事象を捉えなおす立場(テクスト文化論)から、文学作品をはじめとする様々なテクストが社会でいかに受容され、時代とともに変化するのかを批評的に検証する。その際、複数の文化間で恒常的に生じている横断や交錯を念頭におきながら、その現れのさまざまな様態(言語態)に注目している。このような研究を体系的に進めるために、「文化横断論」「批評理論」「メディアとしての言語研究」の学習を軸にカリキュラムが構成されている。
*学際言語コースと言語態・テクスト文化論コースは学部では別コースであるが、大学院では「言語情報科学専攻」に統合される。
学際言語科学コースのガイダンス資料
言語態テクスト文化論コース
■卒業要件単位
学際言語コース
卒業までに必要な単位は76単位。
内訳は、高度教養科目6単位以上、言語科目18単位以上、コース科目30単位以上、卒業論文10単位。
言語態・テクスト文化論コース
卒業までに必要な単位は76単位。
内訳は、高度教養科目6単位以上、言語科目20単位以上、コース科目26単位以上、卒業論文10単位。
両コースとも、サブメジャー・プログラムやその他のサブプログラムにより取得した単位を卒業単位に組み入れることができる。教職課程科目、特設科目科目、他学部の単位も、コース主任の承認を得ることで卒業単位に組み入れることができる。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 文Ⅰ・Ⅱ(指定科類) | 6 | 2 |
| 文Ⅲ(指定科類) | 13 | 9 |
| 全科類 | 5 | 1 |
※超域文化科学分科として進学選択を行い、その後学祭言語科学及び言語態テクスト文化論コースを選択する。随って、この受け入れ数は同分科のものである。
■内実は?
勉強を頑張っている人が多い。両コースとも、言語に関わることならば何でも勉強できるため、各々が自分の興味に合った分野を勉強している。課題は授業によってまちまちだが、大学院生用の授業を取ると重くなる。コースの人数に対して教員数が多く親身に指導していただける。教員数が多く、研究については指導してくださる。学務的には自己管理をする必要がある。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 言語科学への招待(※1) | 必修 | 金曜5限 |
| 基礎言語理論Ⅰ 形の体系 | 必修(A2) | 毎年変動 |
| 言語データ分析基礎 | 必修(A2) | 毎年変動 |
(※1)言語科学への招待:本コース教員が関わる学問諸分野における基本的枠組みを理解する
・言語態・テクスト文化論コースでは、
言語態研究基礎
テクスト文化論基礎
言語態研究演習
テクスト文化論演習
言語文化横断論
メディア文化論
の6つの授業、計12単位が必修であり、そのうち「言語態研究基礎」「テクスト文化論演習」(1つ目と4つ目)がAセメ、残り4つがSセメに開講されている。
両コースともに、2Aで開講される授業のうち、4単位が必修になっている。卒業までに、英語以外の外国語科目を6単位以上取得する必要があるため、2Aからコツコツと外国語の授業を履修しておくと後が楽かもしれない。
しかし、必修以外の授業内容は毎年変わるものがほとんどなので、必要な単位と興味ある授業を見比べながら履修を考える必要がある。
3年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 基礎言語理論Ⅱ 意味の体系 | 必修(S1ターム) | 毎年変動 |
| 基礎言語理論Ⅲ 音の体系 | 必修(S1ターム) | 毎年変動 |
(以下、学際言語コースのみ)
週に12コマほど。一番少ない場合でも10コマ。
必修は2Aの4単位と、3Sの2単位のみであり、そのほかは選択必修となっている。必修は基礎的な部分を学習するが、その他の授業では教員の研究分野が幅広いため、毎年授業内容が変わる。自分の興味関心で授業を自由に履修できる。
3Sの途中や、3Aの前のタイミングで留学を考える人がいる。
3年生Aセメスター
週に10~12コマ。3A以降は必修がなくなるので、人によって時間割は全く異なる。
ほとんどの人は、70単位ほどを3Aまでに取り切る。単位数や授業は自分のスタイルに合わせて調整できる。
4年生Sセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文 | 必修 | なし |
5月、6月に指導教員が決定する。7月、11月に中間発表があり、1月に卒論を提出する。授業をとる人も入れば、就活がある人もいる。
教員の数が学生の数よりも多い。教員と学生が1対1の関係にあるので、相性が重要。
真面目な人が多く、修士や博士までいく人は卒論に真剣に取り組んでいる人が多い。
4年生Aセメスター
| 科目 | 区分 | 開講時限 |
|---|---|---|
| 卒業論文 | 必修 | なし |
引き続き卒業論文に取り組む。
入る前の想像と実際
(学際言語コースのみ)
・進学するまでは、そもそも他に内定生がいるのか不安だったが、同期は思った以上に多かった。
・語学オタクはあまりおらず、進学してはじめてしっかり言語学を勉強する人も多い。
・真面目な人が多いが、各々の興味がばらばらで刺激的。
・大学院生・教員の数が学部生に比べて圧倒的に多い。大学院とのつながりが強く、交流も盛んである。
選んだ理由/迷った学科
■選んだ理由
学際言語
・文理に囚われない「言語学」を学べる。
迷った学科は、文学部言語学研究室と統合自然科学科認知行動科学コース。
学際言語科学コースでは、文学部の言語学と異なり、理系的なアプローチも取れることや、守備範囲が広いことが魅力であった。認知科学との相性も良いコースである。
認知行動科学コースは低次の認知機能を扱う一方、学際言語科学コースは言語という高次のそれを扱える点も魅力であった。(文1→学際言語)
言語態・テクスト文化論
・授業が少人数で楽しい。(文3→言語態)
■迷った学科
学際言語
・文学部G群の言語学専修
教員の数や教員の専門といった理由でこちらに来ている人が多い印象。(文3→学際言語)
・学際科学科B群 総合情報学コース
興味の主軸を言語学におくか、システム全体におくかという点で迷った。
同期、先輩後輩がみな何かしらの部分で言語に関心がある人たちが集まっているので、進学してよかった。(文3→学際言語)
言語態・テクスト文化論
・文学部の現代文芸論
超域の表象文化論コースや比較文学比較芸術コースなどと悩む人が多いよう。そのような人たちはサブメジャーを利用して何に主軸を置きたいかで決定している。(文3→言語態)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
8 |
| LINE | 有 |
| Slack | 有 |
| オフラインでのつながり | 有 |
| 上下のつながり | 有 |
(学際言語コースのみ)
・コミュニティに繋がるのも、繋がらないのも完全に個人の自由である。
・ゼミで同じだったり、コモンルーム(※)と呼ばれるのたまり場にいたりすると個人的な繋がりができる。
※コモンルーム:8号館の3階にある部屋で、学際言語科学コースや言語態・テクスト文化論コースの学生および言語情報科学専攻の大学院生(修士・博士)が利用可能な談話室。PCやプリンター、スキャナー・本棚や辞書があり、学習環境として整っている他、ソファ、冷蔵庫があり交流の場としての機能もある。コモンルームの正面には言語情報科学専攻の専攻図書室があり、言語学・文学に関する豊富な資料を利用できる。
・顔合わせを自主的に行った(コロナ禍であっても変わらず行った)。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 10名~20名前後 |
| 成績評価 | 出席、レポート、期末試験 |
・両コースとも外国語が重視され、授業の内容は教員の研究分野に基づくため多岐にわたる。
・成績評価は、授業によって異なる。レポートが8割~9割で、試験は1割くらい。
・授業は講義形式が多く、講義に並行して、英語の教科書や論文を読みすすめる。
・学部段階で、大学院の授業を履修することもできる。
・大学院との2枚看板の授業を取れば課題は重いが、成長もできる。
・そこまで重い課題や試験はないが、自分で勉強したりゼミに入ったりすることが学びにつながる。
研究室・資料
〈研究分野一覧〉
特別な制度・その他
・大学院の授業を単位として組み込むことができる。
・サブメジャープログラム:所属コースの主専攻だけではなく、他コースが提供する15単位程度の科目群を副専攻として履修するプログラム。修了生は卒業時に、卒業証書だけではなく、サブメジャー・プログラム修了証ももらえる。
・学融合型プログラム:分野横断的な学習を行うプログラムで、グローバル・エシックス、グローバル・スタディーズ、東アジア教養学、進化認知脳科学、科学技術インタープリターの5種類がある。例えばグローバル・エシックスでは社会・人文科学系の問題のみならず自然科学やテクノロジーに関わる諸問題に対応していくための包括的な価値観や倫理に関わる判断を下す力を身につけることを目的としている。文理の壁を超えてより複眼的知識を身につけたい人は検討してみても良いだろう。詳しくはこちらを参照。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部

教養学部
「学際性」「国際性」「先進性」を軸に、深い教養を基盤に従来の枠組み・領域を超えて新しい分野を開拓する人材を育成する学部
関連記事

超域 表象文化論コース
教養学科 超域文化科学分科
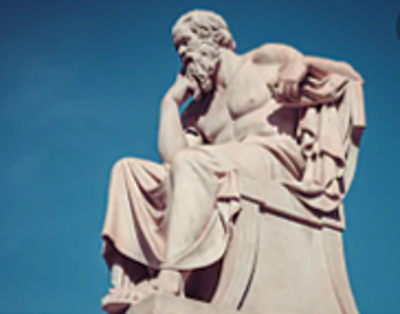
A哲学専修
A群(思想文化_哲学)
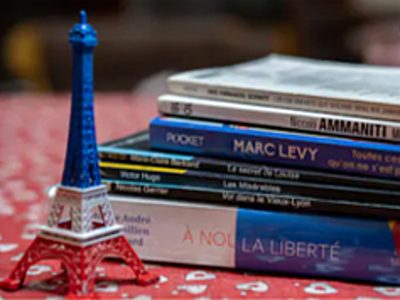
Gフランス語フランス文学専修
G群(言語文化_フランス語フランス文学)

H心理学専修
H群(心理学_心理学)




