文学部
B日本史学専修
2023.4.15
B群(歴史文化_日本史学)
目次
基本情報
| 人数 |
20~25名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ2割程度 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
就活:院進=2:1 |
| 公式サイト |
学科概要
日本史学専修とは
文学部人文学科歴史文化コース日本史学専修では、古文書・記録・史書などの文献史料を正確に読み、内容を批判的に検討し、そこから論点を引き出して歴史像を構成することを目指す。ゼミ(演習)では、文献史料を正確に解読し、優れた先行論文を批判的に検討することが中心となる。講義では、各教員の先端的な研究を学ぶ場となる。
ゼミを決める3Sになるまで、特に多くの学生は進振りの段階で、自分自身が古代・中世・近世・近代のうち何を研究するのかの考えを持つ。各時代ごとに2名(古代のみ1名)ずつ教員がおり(※)、各自ゼミを開講している。自分がテーマに選んだ時代のゼミは、原則2つとも取るのが通例となっている。各セメスターごとに1つのゼミに所属しているのが必修としての最低要件なので、1つのゼミにしか所属しない学生もいる。
※研究室ホームページの項目で、詳しく説明。
なお、院進希望者の場合、3つのゼミに所属するのが一般的。院試で2時代の問題を解く必要があるため、自分がテーマに選んだ時代に加えて、他の時代のゼミも1つ取っておくのが一般的である。
伝統的に、院生が学部生に向けて勉強会などを開催する。それ以外にも、卒論などで助けてくれることもあり、院生と仲良くなっておくと何かとかなり有利になる。院生から学ぶことは、教員から学ぶことに匹敵、もしくはそれ以上とも言われている。
卒業単位
卒業単位が76単位で、うち12単位が卒論。ゼミがセメスターごと2単位、全セメスターで合計8単位が必修。常に1つのゼミは履修しなければならない。選択必修では、「日本史特殊講義○」のうち12単位、「西洋史特殊講義○」のうち4単位、「東洋史特殊講義○」のうち4単位を修得する必要がある。(○にはⅠ、Ⅱ、Ⅲなどが入る)
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
・週14コマ程度が一般的。
・「史学概論」という講義1コマのみ必修。歴史学の理念・概論に近く、西洋史・東洋史・美術史などの専修と合同で受講。火曜2限開講。
・上記の「史学概論」のみ駒場開講で、残りの講義は本郷で開講される。
・事実上の必修となるのが「日本史学特殊講義Ⅰ」であり、これは2Aの学生を対象としている。選択必修のためここで単位を取る必要はないが、大抵の学生はここで修得する。
・その他は、任意の持ち出し科目の履修となる。しかし、日本史学専修は西洋史・東洋史等と比べて持ち出し可(※)となる科目が少ない。
※持ち出し科目:後期課程(3、4年生)になっていない前期課程(1、2年生)の学生が受講した際、後期課程の修得単位数に含めても良いと認められている科目のこと。前期課程学生のテスト処理が面倒と教員が感じている、基礎知識を付けての受講が推奨されている、等、持ち出し不可の理由は様々。教員が「持ち出し可」と認めた科目は、前期課程の学生でも受講することが多い。持ち出し可か否かは、シラバスに記載されるか、教員が明言する。
3年生Sセメスター
・週14〜15コマ程度が一般的。
・選択必修には「日本史学特殊講義○」「西洋史特殊講義○」「東洋史特殊講義○」がある。(○にはⅠ、Ⅱ、Ⅲなどが入る)
・ゼミ活動がスタート。
・特に大学院志望の学生や、教職免許を取ろうとする学生(学科内の1/3程度)はコマ数が多くなって大変。高校教員志望も比較的多い。(進学校では待遇も良い)
・院生が伝統的に勉強会を開催してくれる。院進希望者の参加がほとんどだが、史料読解のスキル等、卒論執筆の際に有利に働くものも多い。また、講師となる院生と仲良くなると卒論等の相談にも乗っていただけるので、その後の進路問わず参加した方が利益が大きい。
3年生Aセメスター
・週14〜15コマ程度が一般的。
・3S同様、選択必修には「日本史学特殊講義○」「西洋史特殊講義○」「東洋史特殊講義○」がある。(○にはⅠ,Ⅱ,Ⅲなどが入る)
・ゼミ生活が活動の中心。
・3S同様、教職を取ろうとする学生は大変。
・3S同様、院生の勉強会が開催されている。
・4年生の間は卒論に専念するため、3年生中に単位を取り切ろうとする学生が多い。
4年生Sセメスター
・ゼミ活動、卒論、院試準備が活動の中心。
4年生Aセメスター
・ゼミ活動、卒論、院試準備が活動の中心。
・院試は1~2月にかけて行われる。1年で1~2名は、専修内の学生も不合格になることがある。
・就活に専念する学生は別にして、院進する学生は、院試に落ちた場合留年することが多い。就活に切り替えるために、院試を前にして内定を持っておく学生は少ない。
入る前の想像と実際
・「日本史を勉強する環境としては素晴らしい。」
・「教員や院生は勿論、本郷の史料編纂所に、日本史関係の史料の多くが貯蔵されている。そのため、日本史をやるなら本郷の方が有利。」
・「更に、各研究室が日本史の史料集を多数所有しているのも大きい。駒場や他学科だと、わざわざ研究室に来て手続きも踏む必要がある。」
・「院生と仲良くなるのは大切だった。勉強会や学科部屋などでのコミュニケーションを通じて、学ぶことが非常に多い。これは、実際に進学してから知った。」
選んだ理由/迷った学科
・「日本史が好きだったから。」(文三→日本史)
・「考古学、国文、または後期教養の超域などでも日本史を扱うことはできる。また、法学部で法制史、経済学部で経済史、工学部建築学科で建築史をやるという道もある。ただ、教員・院生の充実度を見るに、日本史学科が有利。」(文三→日本史)
・点数が底割れすることもある学科なので、法・経済に行けなかった文系の学生が所属することも。
コミュニティとしての機能
・古代・中世・近世・近代それぞれゼミが2つあるが、時代ごとに2ゼミ合同のLINEグループが存在する。各LINEに院生が加入していることも。
・法文2号館に学科部屋があり、院生が勉強している。院生の会話を聞けるので、いろいろな情報を掴めたりする。学部生では、院進志望者の方がいる傾向。
・院生とは勉強会や学科部屋で仲良くなる。その人脈は結構大事。院生の方から学部生に向かって積極的に話に行かれる方は少なめ。一方で教えたい欲が高い方は多いので、学部生の方から話す機会を作ることが大切。
授業スタイル
・ゼミ形式と講義形式が存在。ゼミは「演習」という科目名で開講。
・レポート:試験=6:4程度。
・出席について、とる教員が1/3程度。ゼミは全員顔見知りなので、全出席が当たり前。ただ、来なくても単位を取っていく学生もいる。
・落単などに由来する留年は少ない。
研究室・資料
東大文学部日本史学研究室
日本史学研究室(概要紹介)
○古代
大津透先生
稲田奈津子先生
○中世
高橋典幸先生
三枝暁子先生
○近世
牧原成征先生
村和明先生
○近代
野島(加藤)陽子先生
鈴木淳先生
特別な制度・その他
・近世選択の学生は、近世史の名誉教授がコネを持っている長野県阿智村に、年2回史料調査の手伝いに行ける(任意参加)。史料を手に入れる、地元の人と仲良くなるのはこういうものだと実感できる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
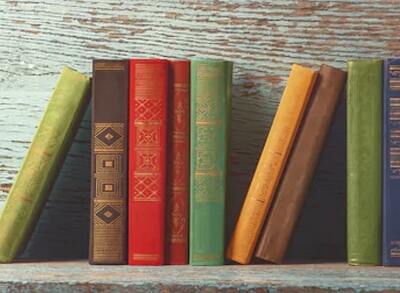
文学部
専門知識や幅広い視野を備え、異なる準拠枠を踏まえ自らの専門を相対化できる、高度な教養人として活躍する若者を育成する学部
関連記事

C東洋史学専修
C群(歴史文化_東洋史学)
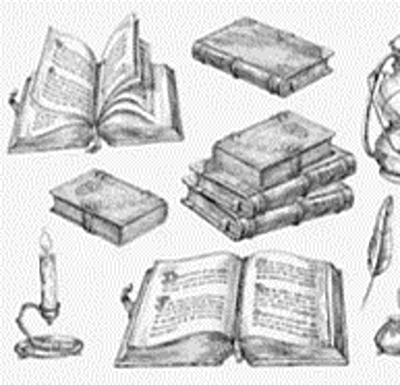
学際A 科学技術論コース
教養学科 学際科学科A群

超域 比較文学比較芸術コース
教養学科 超域文化科学分科

教育実践・政策学コース
総合教育科学専攻 教育社会科学専修




