工学部
都市工学科 都市環境工学コース
2026.2.3
環境共生・国際公共衛生・水・環境バイオ
目次
基本情報
| 人数 |
20名 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ2-3割 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
院進が都市工学科全体で8割程度 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
都市の環境を左右する因子を正しく認識できる専門的知識を持ち、都市環境の施設やシステムの計画・設計・評価を行なえる能力を備えた専門家を育成する。(公式サイトより)
■学科の諸制度
卒業までに必要な単位は94単位。必修以外では、31単位までは、無制限に他学科の授業を含めることができる。研究室には4Sセメスターから入ることになる。
■進学定数は?
・定員数と各科類からの受け入れ数
| 受け入れ枠 | 第一段階 | 第二段階 |
|---|---|---|
| 理Ⅰ(指定科類) | 7 | 3 |
| 理Ⅱ,Ⅲ(指定科類) | 3 | 0 |
| 全科類 | 3 | 3 |
■内実は?
学生の傾向は毎年異なるものの、学問を活動の中心に据える人は少ない印象。部活やサークルなどにエネルギーを割いている人が多い。他の理系学科と同様に授業の拘束時間が長く、長期インターンをしている人はあまりいない。学科全体の合計が少人数のため2コース合同の授業が多いということもあり、学科の中で学生がばらけることは比較的少ない傾向。
授業外で強制される学習はあまり多くない。実験レポートは大変だが、全体の課題の量は理系の他学科と比べると少なめ。単位は比較的取りやすい。
都市環境工学コースには、地球温暖化などの環境問題、インフラの整備、途上国の農業を題材とした都市や社会の持続性の研究などの多様なジャンルがある。
座学の授業では、授業数の関係により都市環境工学コース寄りの内容の授業だけで指定単位数を満たすことはできず、都市計画コース寄りの内容の授業も履修する必要がある。(環境系の内容のみに興味がある人も、計画系の内容についてある程度学ぶことになる。)
■各コースの違い
参考
都市計画コース(略称:計画系)
建築学科、社会基盤学科と合わせて建築系3学科と呼ばれる(建築学科、都市工学科都市計画コース、社会基盤学科の順にスケール大)。建築系3学科の中で、都市工学科は物理的な内容よりも相対的に思想・デザインなどに重きをおいている。
キーワード:developerの都市計画/地域の設計/マネジメント・地区のデザイン
都市環境工学コース(略称:環境系)
建築系3学科とは主軸が異なり、都市問題、地球温暖化などの環境問題、インフラの整備、途上国の農業を題材とした都市や社会の持続性の研究などを扱う。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
| 科目 | 区分 |
|---|---|
| 環境計画基礎演習(※) | 必修 |
(※)週2回4,5限に開講。セメスターが3つに区切られて、テーマを順に取り扱う。テーマは、地球温暖化の根本的な原因/47都道府県のエネルギー消費量と二酸化炭素放出量に係るデータ解析/水俣病におけるターニングポイントと各ステークホルダーの動き の3つがある(内容は変わる可能性有り)。リサーチをしてプレゼンやディスカッションをする、ゼミのような珍しい授業形態。きちんと出席していれば成績は取りやすい。
・週一で駒場の授業があるので通学がやや大変。
・卒業に必要な単位が94単位と多いため、2Aにしっかり単位を取る学生が多数。後期課程において最も大変なセメスターだったという声も。
・座学の授業には、計画系の内容の授業が多め。環境系の内容のみに興味がある人だと座学の授業にあまり興味が湧かない可能性も。2Aは座学が多いため、この傾向が強くなる。
3年生Sセメスター
| 科目 | 区分 |
|---|---|
| 都市工学演習B第一 | 必修 |
| 都市工学実験演習第一 | 必修 |
・実験の授業が週2回3,4,5限にあり、午後全てを使う(授業が長引くことはあまりない)。
・環境に特化した授業は環境系の人だけが取る授業で、興味・目的が明確な人は楽しくなってくる。しかし、環境に特化した授業はテスト評価が比較的多いためテストの負担は増える。
・「都市工学の技術と倫理」という限定選択の授業は、週に2時間連続で設定されている。社会科見学のような内容で、浄水場などを見学した。授業の最後には1泊2日でダムを見に行った。おすすめの授業。(理科二類→都市工学科都市環境工学コース)
3年生Aセメスター
| 科目 | 区分 |
|---|---|
| 都市工学演習B第二 | 必修 |
| 都市工学実験演習第二 | 必修 |
実験の内容が3Sまでと異なる。3Sまでは一回完結式だが、3Aは複数回にわたる実験となる。
セメスターが大まかに2つに区切られる(ex. 浄水について/下水について)。1つのテーマに関して5,6回の実験をして、それらをまとめたレポートを書くため、1テーマあたりのレポートの負担が大きくなる(挿入図を含め1テーマにつき50ページを超える)。
実験の例
・活性汚泥の特性を知るため、沈降性を評価する
・浄水の過程での微生物を計数する
4年生Sセメスター
| 科目 | 区分 |
|---|---|
| 都市工学演習B第三 | 必修 |
| (都市)卒業研究 | 必修 |
5月頭に研究室への配属が決まる。研究室ごとに定員が決まっており、卒論のテーマが提示される。研究室決めに関して、教員は全く口出しせず、決め方も学生が決定する。そのため、研究室決めの方法は毎年異なる。「希望が被れば成績の良い方が枠を獲得するドラフトスタイルで、事前に周りの学生がどの研究室を希望しているのか把握できる」という方法を取る年も。
4年生Aセメスター
単位を取り切っていない学生は単位を取りつつ、基本的には卒論に集中する。環境系では、実験が必要な卒論テーマ(実験系)とパソコン上で完結する卒論テーマ(解析系)がある。
一般に、学科によって解析系か実験系かが決定されることが多いので、学科の中で分かれるのは特徴的である。
入る前の想像と実際
扱う範囲がとても広いので、説明会等ではどうしても抽象的な説明が多くなる。
都市環境工学コースの先輩の話を事前に聞いていたので、あまりイメージとのズレはなかった。
(理科二類→都市工学科都市環境工学コース)
選んだ理由/迷った学科
学部を出て就活するつもりだった。理系学科の中で卒業研究と就活を並行できそうな進学先としては工学部のシステム創成学科・建築学科・社会基盤学科、農学部があった。都市環境工学コースで扱われる内容に興味を持ったため選択した。
(理科二類→都市工学科都市環境工学コース)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) |
【6or7】 |
| LINE | 有(※1) |
| Slack | 無 |
| オフラインでのつながり | 有(※2) |
| 上下のつながり | ほぼ無し(※3) |
(※1)都市工学科全体のグループと環境系のグループがある。学科全体のグループはほぼ動かない。内容は連絡事項が多く、雑談は少ない。たまにオンライン飲み会の日程調整などがある。年にもよるが、2週に1回やりとりがある程度。
(※2)学科の学生が集まる際に使える演習室が用意されていて、時間のある人が集まって遊んでいる。最初は懇親会があったが全体での集まりは少なく、仲が良い人同士で飲み会などが開催される。
(※3)内定決定後の内定者向け学科説明会の後に懇親会が開催されたが、その後基本的に関わることは少ない。研究室配属後に修士課程の人と話す機会があることも。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 18~50名前後(※1) |
| 成績評価 | 出席/レポート/期末試験 (※2) |
(※1)実験や演習は都市環境工学コースの18人で受講する。座学は学科全体で受講することが多く、合計約50人。環境系の内容に特化した選択科目は受講しない人もいるので学生数は変動する。
(※2)環境系に特化している授業はテストが多く、計画系に特化している授業はレポートが多い。出席を取って成績に入れてくれる授業が多い。
研究室・資料
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
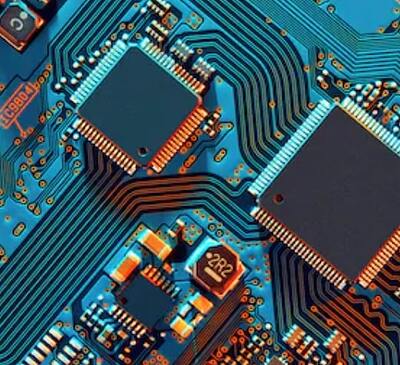
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

木質構造科学専修
【環境資源科学課程】通称「木質(もくしつ)」

国際開発農学専修
【環境資源科学課程】通称「国農(こくのう)」

社会基盤学科
A,B,Cまとめて掲載

建築学科
建築学




