工学部
建築学科
2023.4.15
建築学
目次
基本情報
| 人数 |
60名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ1-2割程度 |
| 要求/要望科目 |
・要望科目 |
| 就活or院進 |
7~8割程度は院進するが、学部卒業も一定数 |
| 公式サイト |
学科概要
工学部建築学科は、「ものづくり」を学ぶ学科である。その学術領域は実に広く、総合的であり、社会との関わり合いも密接となる。例えば、何百年も使い続けられる古建築、高度な災害対策技術、コミュニティ、建具などもその領域に含まれる。歴史や文化を残しながら社会に新しい活力を生み出す「場所」を提供することも、重要な役目となる。建築学科では、人間と空間について様々な現象について多角的な教育が受けられる。「もの」だけでなく、「ひと」を工学的に扱う。
2A・3Sに必修科目が一定数あり、4年生では卒業論文と卒業制作がある一方で、3Aは必修が無く限定選択科目を修得することが多い。卒業に必要な履修単位数については、必修科目が15.5単位、限定選択科目が55単位以上、そして標準選択科目及び選択科目の単位数と合わせて90単位に達するまで修得が必要となる。他学部履修は、必修と限定選択科目以外では最大限履修することができる。
学科では一級建築士を取得しようと考えている学生が多い。試験受験と2年間の実務経験によって資格を取得できる。試験受験資格を得るため、学科内の一級建築士指定科目で一定単位数を取得する必要がある。
五月祭の時は2,3年生のコンペで選ばれた案が翌年の五月祭で採用され、工学部1号館の前にパビリオンを作る。また、卒業制作でも先輩後輩とのかかわりがある。卒業制作には「研究」と「制作」の2種類があるが、「制作」を行う場合(半数程度)は4年生の手伝いとして2,3年生が2人ずつヘルパーについてボランティアをする文化がある。
学科公式の進振りパンフレットについてはこちら
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
・コマ数は週17~20コマ程度が多い。
・全授業が本郷キャンパスで行われ、特に工学部1号館が多い。
・「建築総合演習」という科目では、建築学科の教員に連れられ、ビルの工事現場や建築物の見学を行ったり、ゼネコンの人と話したりする。
・1月から2月は試験期間である一方で、4年生の卒業制作の手伝いにも勤しむ。
・必修科目
「建築設計基礎第一、第二」:「製図」の補助科目。2限が「基礎」、3~5限が「製図」となる。ざっくり建築の歴史を振り返るなど。
「建築設計製図第一、第二」:図面のトレースを行う。1号館の共有スペースの改善計画などを行う。
・必修科目に加えて、一級建築士指定科目のうち2年生で受講できる科目を取る人が多い。
(Cf.「都市建築史概論」「都市計画概論」「環境工学概論」「建築熱環境」「建築構造解析第一」「荷重外力論第一」「建築弾性学」「建築工法概論」「建築構造計画概論」「建築材料科学概論」「建築総合演習」)
3年生Sセメスター
・コマ数は週19~23コマ程度が多い。
・製図関係の科目など、課題が非常に多い科目があるので、それ以外の活動を入れるのは少々厳しい。
・五月祭でパビリオンを出展する。
・必修科目
「建築設計基礎第二」:2Aと似ているが、住宅設計について扱う。
・必修科目に加えて、一級建築士指定科目のうち3年生で受講できる科目を取る人が多い。
(Cf.「製図第三」「製図第四」「計画第一」「計画第二」「日本建築史」「理論第一」「理論第二」「空気環境・水環境」「音環境」「光環境・視環境」「構造解析第二」「荷重外力論第二」「塑性学」「材料科学」「構法計画」「溶接工学」「マネジメント概論」「建築法規(実質必修)」)
3年生Aセメスター
・コマ数は週19~23コマ程度が多い。
・製図関係の科目など、課題が非常に多い科目があるので、それ以外の活動を入れるのは少々厳しい。
・五月祭でパビリオンを出展する。
・研振りが行われる。研振り先の選び方は、学生間での各自の希望を基に話し合うケース。代によって学生間ではジャンケンしたりすることも。また、一部研究室は面接を独自に課す。一部人気が集中する研究室がある(千葉先生等の意匠系や、授業で人気がある権藤先生や加藤先生等)。
・建築史実習が春休みにある。お寺の建築を見に行くみたいな。3泊4日。学科旅行の兼ね合いも強い。(Cf. 2015年建築実習)
・1月から2月は試験期間である一方で、4年生の卒業制作の手伝いにも勤しむ。
・必修科目
「建築設計基礎第二」:2Aと似ているが、住宅設計について扱う。
・必修科目に加えて、一級建築士指定科目のうち3年生で受講できる科目を取る人が多い。
(Cf.「製図第五」「製図第六」「計画第三」「計画第四」「西洋建築史」「理論第四」「環境・設備演習」「建築環境デザイン論」「設備第一」「設備第二」「設備第三」「構造解析第三」「耐震構造」「鉄骨構造」「鉄筋コンクリート構造」「防火工学」「構造演習」「材料計画」「材料演習」「建築施工」「建築法規(実質必修)」「造形第五」「造形第六」)
4年生Sセメスター
・基本的に卒業論文に取り組む。卒論は、研究室で自分が研究したいことを書く場合が多く、場合によっては研究室によっては研究室内のプロジェクトに乗っかって書くことがある。4Sで卒論を書ききり、4Aでは卒業制作に専念できるようにする。
・必修科目に加えて、一級建築士指定科目のうち4年生で受講できる科目を取る人が多い。
(Cf.「製図第七」「近代都市建築史」「日本住宅建築史」「基礎構造」「構法特論」「構造演習」「鉄筋コンクリート構造演習」)
4年生Aセメスター
・基本的に卒業制作に取り組む。1月から2月が忙しさのピークとなる。
・制作は一人でやり切るのは本当に大変なので、4年生の手伝いとして2,3年生2人ずつが各学生にボランティアでつき、4年生は毎回ご飯を奢ってあげる文化がある。
※マッチングは元からの知り合いの場合もある。3年生は、昨年度同じ4年生を手助けした先輩の手伝いをすることが多い。2年生については、大概は10月辺りに行われる歓迎会で4年生から勧誘される。
入る前の想像と実際
・構造計算系の授業がネックだと思っていたが、それらを取らなくても卒業できるのは意外だった。「構造解析論」や「数学及力学演習B」など。一級建築士志望でも、他の分野で単位数をしっかり取り切れば殆ど問題無い。
・建築学科のなかで、自分自身が特に勉強したい分野を自由に選べたのは意外だった。
・設計の授業は全般的に大変。取られる時間と、ち密さの追求という両面で苦労する。後者については、求められるクオリティに対してどこまで足りないか、どれほど時間がかかるか目処がつくので、それに足りていない時に苦しいと感じる。
・「卒業制作」でボランティアにつくシステムを知らなかった。ただ、学科間での縦の繋がりはもっとあると思っていた。
選んだ理由/迷った学科
・「人が集まる場、空間に関心があった。また、勉強のスタイルとしてアウトプットが中心で不足分をインプットするスタイルが向いていると思っていた。駒場で受けた「社会システム工学基礎Ⅰ」で建築学科の先生が登壇していて、学問の幅広さに関心を持った。」
・「後期教養の表象文化論やイスラム建築史も迷ったが、実践的に手を動かす方が好きで、学科長に直接メールしてお話を聞くこともあって建築を選んだ。」
(文二→建築)
コミュニティとしての機能
・学科Slackがあり、授業ごとにチャンネルが作られている。連絡したり動かしたりする人はいるが、コミットしない人も一定数。個人チャンネルを作る学生も一定数。授業中にお互いにプレゼン等のフィードバックをしあうチャンネルもあるが、発言メンバーは一部に限られることが多い。
・先輩後輩がまとめて入ったSlackもある。事務所スタッフ募集の連絡や、パビリオン制作の話、卒業制作の話などが行われる。
・同期や先輩後輩とのつながりは、「卒業制作」で製図室に共にするメンバー間で醸成されることが多い。また、4年生が製図の授業でTAをやっており、それを通じて仲良くなることも。
・パビリオンはコンペで勝った人が中心になって運営を司り、仕切るのは実質4年生となる。
・3年生の春休みに行われる建築史実習で、同期間の仲が良くなる。
・また、製図室が空いているので、製図室が事実上の学科部屋となる。冷蔵庫や寝袋を持ち込む学生も。
・学外のコンペ(住宅メーカー等が公募しているようなもの)に、同期と一緒に応募する人は結構いる。
授業スタイル
・レポートと試験が半々くらい。
・製図の授業は、レポートや試験ではなく、最終的に制作を何か作る。
・成績の付き方は全般的に緩いと思われる。
・リアペが取られることが多いので、出欠は取られている。ただ、授業を切る文化は薄い。幅広く学びたいと思う学生が多いので、意欲的に授業に参加する人が多い。
研究室・資料
特別な制度・その他
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
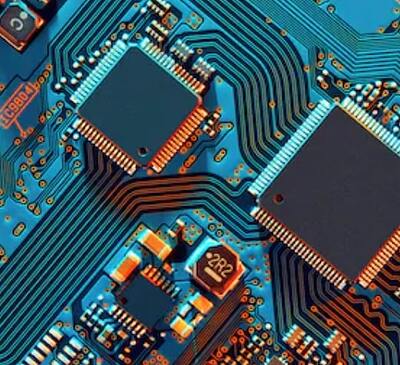
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

都市工学科 都市計画コース
都市と地域の分析・計画・デザイン
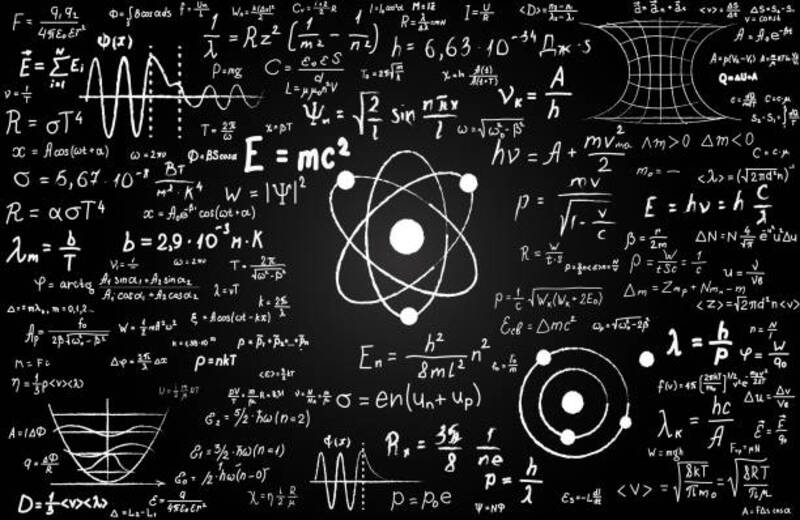
物理工学科
物性物理・量子情報

都市工学科 都市環境工学コース
環境共生・国際公共衛生・水・環境バイオ

生命化学・工学専修
【応用生命科学課程】通称「農二(のうに)」




