工学部
航空宇宙工学科
2023.11.1
航空宇宙学
目次
基本情報
| 人数 |
50名後半 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性はおよそ1割 |
| 要求/要望科目 |
・要求科目 ・要望科目 |
| 就活or院進 |
90%以上院進で、ほぼ東大の院に進む。数名は海外院(米仏など)だが、海外院は博士課程からが多い。 |
| 公式サイト |
学科概要
■どんな学部?
日本の航空・宇宙産業を担う人材が輩出する学科である。航空機やロケット、人工衛星などの宇宙機の機体について学ぶ「航空宇宙システムコース」と、推進機器(エンジン)を学ぶ「航空宇宙推進コース」の2つがある。
ともに、流体、構造・材料、飛行・制御、推進など、さまざまな工学分野をバランスよく学習していく。したがって、学習内容はかなり広範で、他学科で学ぶことも航空宇宙で学ぶことになる。
がっつり理系であってハイレベルであるから、進学者の募集は理科生限定で文科生は志望することができない。
進学者は、3Sまで航空宇宙工学に関する基礎科目をじっくり学ぶ。実験が無く、ほぼ座学の授業が続く。3Aからは2つの専修コース(航空宇宙システムコース、航空宇宙推進コース)に分かれて専門的な内容について実験などを交えて深く学んでいき、4年生の卒業研究や卒業設計に繋げていく。
授業でインプットの機会が多い一方で、新人研修やARLISS(ともに以下、「特別な制度・その他」を参照)等、2,3年生のうちからアウトプットの機会にも恵まれているのが特徴である。
■基本情報
卒業に必要な単位は95単位。必修は27単位(うち卒論10単位)、限定選択(※)は56単位以上の修得が必要。
※限定選択とは、工学部一般に用いられる用語で、要は選択必修のこと。
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
| 科目名 | 区分 | 曜限 (変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 数学及力学演習G | 必修 | 月曜3,4限 |
| 航空宇宙学製図第一 | 必修 | 木曜2限 |
・選択必修含めると、週15コマがデフォルト。「数学及力学演習G」(週2コマ)と「航空宇宙学製図第一」が必修で、残りは選択必修(下に記載)を12単位近く取得する。
・選択必修
「情報システム学第一」「力学第一」「推進学第一」「高速内燃機関」「基礎材料力学」「宇宙工学入門」(各週2コマ)
「計測通論A」「電気工学論第一」「数学1B」「空気力学第一」
”選択”必修だが、ほぼ全員受講する。
・月曜日~木曜日は駒場開講、金曜日は本郷開講、場所は5号館、コムシー、12号館、1号館に分かれる。5号館の511教室や1号館の製図室は、学科生のたまり場になりがち。
・水曜授業の「計測通論A」「電気工学論第一」「数学1B」「空気力学第一」は他学科生と合同だが、他は学科生50名のみが受講する。
・「基礎材料力学」は、3S以降でこれに関連した講義がいくつかあるので、おざなりにやるのは推奨しない。
・「計測通論A」は自習で何とかなると考える人が例年多いとの噂。
・11月~春休みにかけて「新人研修」が金曜5限に行われる。(以下、「特別な制度・その他」の項を参照。)
3年生Sセメスター
| 科目名 | 区分 | 曜限 (変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 航空宇宙学基礎設計 | 必修 | 金曜3,4限 |
| 航空宇宙学製図第二 | 必修 | 水木金で4コマ(※1) |
| 航空宇宙学倫理 | 必修 | 木曜6限(※2) |
(※1)必修の「航空宇宙学製図第二」は週4コマと表記したが、授業は行われていない。必修の「航空宇宙学基礎設計」(週2コマ)で2週間に1回程度出される課題を解くための時間として、この「授業」となる時間は確保されている。つまり、各自が自由に課題を進める時間として4コマ用意されている。
(※2)必修の「航空宇宙学倫理」は木曜6限にあると表記したが、実際にはWeb上にアップされている動画を見る講義であるので、いつでも受講することができる。5回程度の課題を提出するすることで単位が取得できる。
・選択必修含めると、週18コマ前後の履修が一般的。
・授業はすべて座学。
・火曜3,4限に開講で学科生の6割~7割が受講する「宇宙工学演習」(週2コマ)は、ロケットの速度の推定やエンジンの推計が課題に出される授業で、最終課題も比較的重いことで知られる。
・水曜2,3限の「数学2B」は、課題が回を追うごとに非常に厳しくなっていく。序盤は簡単だが、後半は、天才が集まる航空宇宙の学生でもほぼ解けないことも。学科生同士で解き方を教え合うことも多い。この「数学2B」の演習はは機械情報工学科と共通で受講する科目となっている。
・6月に希望調査が行われ、夏休みに3A以降のコース分け(自由選択)が行われる。航空宇宙推進コース、航空宇宙システムコースの2つで、万が一定員に達した場合は前期教養の成績が高い順に希望通りのコースに進める。
3年生Aセメスター
■システム学コース
| 科目名 | 区分 | 曜限 (変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 航空宇宙システム学実験 | 必修 | 木曜3,4限(※1) |
| 航空宇宙システム学製図 | 必修 | 金曜3,4限(※2) |
(※1)システム学コースの人が4年次に配属され得る各研究室で実験を行う。実験内容は各研究室の研究内容と関連するものもある。
(※2)この製図では主に4種類の課題が出される。中でも、最後に提出される「主翼の前桁および金属結合部」の設計・製図が非常に大変であることで有名である。
■推進学コース
| 科目名 | 区分 | 曜限 (変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 航空宇宙推進学実験 | 必修 | 木曜3,4限(※1) |
| 航空宇宙推進学製図 | 必修 | 金曜3,4限(※2) |
(※1)推進学コースの人が4年次に配属され得る各研究室で実験を行う。実験内容は各研究室の研究内容と関連するものもある。
(※2)この製図ではエンジンを設計することになる。推進学コースの教授の多くが製図の際に指導をしてくださる。
・選択必修含めると、週16コマ前後の履修が一般的。
・授業は座学に加えて週2コマ実験が始まる。
・コースごとに必修科目は別授業となる。それ以外にも別授業となる時限もある。
・3年生終わりから研究室決めを始める学生が多い。1~2月に研究室巡りをし、春休み中に研究室選択を行う。
・卒業研究を行う4年次の研究室と、院進後の研究室は、同じでも違っても構わない。
・志望学生が一部研究室に偏った場合は、定員全体の3割が成績で埋まるのが慣例となっているが、残り7割は学生間の話し合いで決定される。欲しい学生などが教員側から特に要請があるわけでは無い。
4年生Sセメスター
・必修として卒論(週7コマ)が課され、研究室で卒業研究を始めていく。
・院試の準備を行う。
4年生Aセメスター
・必修として卒論(週12コマ)が課され、ほぼ卒業研究ばかり。
・11月頃に卒業研究を終え、その後、必修である「計画及製図」と銘打たれた卒業設計(週11コマ)に取り組み始める。システムコースでは航空機やロケット、人工衛星など、推進コースではジェットエンジンを設計する。
入る前の想像と実際
・思った通りみんなマジメ。前期教養でも学部でも、高い成績を取りたがる人が多い。
・教員に、航空宇宙方面で非常に著名な方が多い。いま日本で製造されている人工衛星のほぼすべてにかかわっているだろう方、等々。
・実験をもう少しやると思っていたが、3Sまではほぼ無い。ただ、学ぶべき内容・裾野が非常に広いので、ある程度仕方がないと割り切った方が良い。ピラミッドの基盤を整える座学をしっかりこなし、その後に実験、次いで設計へと繋がっていくイメージ。
・「ロケット好きな人」「人工衛星好きな人」「飛行機が好きな人」の3派閥に分かれる。
・宇宙が好きだが、理論・仕組みよりも実践に関心ある人が多い。
・迷っていそうな学科は、EEIC、理物、物工、計数、機械工など。
※それぞれ、EEIC=工学部電気電子工学科&電子情報工学科、理物=理学部物理学科、物工=工学部物理工学科、計数=工学部計数工学科、機械工=工学部機械工学科
選んだ理由/迷った学科
・「輸送技術関連のものづくりがしたかった。天文系に関心があり、宇宙というものへの憧れもあったと思う。」
・「人工衛星の開発に興味があったのに加え、推進系から人工知能まで幅広い分野の研究室があることが魅力に感じた。」
・「機械工学と迷ったが、部品よりもっと俯瞰した、包括的なかかわり方をしたかった。」
(理一→航空宇宙)
コミュニティとしての機能
・学科内Slackは存在し、活発に動く。わからない問題について聞いたら誰かが答えてくれる。LINEもあるが、あまり動かない。
・先輩後輩の関係はほぼ無い。五月祭の学科主導の展示の運営にかかわる人以外は、学科単位で繋がることはほぼ無い。
・3年生の2,3月に航空宇宙関連施設をめぐる旅行が行われる。参加は任意。教授の方が企画して下さることが一般的。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは... 10 (強いと感じる)↔0 (全くない) |
4~5程度 |
| LINE | 有(※1) |
| Slack | 有 |
| オフラインでのつながり | 有(※2) |
| 上下のつながり | 個人的関係にとどまる(※3) |
(※1)あまり活発ではない。
(※2)年に1~2回程度。パ長の社交性次第。
(※3)過去問の共有はシケ長どうしで行うことが通例。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 30~45名前後 |
| 成績評価 | 試験(+出席) or レポート課題 |
・座学については、課題は割と多めだが、評価は期末試験で決まることが多い。(今年はコロナ禍でレポートが多くなった。)
※コロナ禍においては、レポート評価の方が多くなった。今後がどうなるかは未知数。
・出席を取る科目が多いが、それが成績にどの程度加味されているかは未知数。学生の出席率は、他学科と比べれば全体的に高い。
研究室・資料
特別な制度・その他
・新人研修といい、2Aの11月から3月まで、制御技術やプログラミングを体系的に学べる講義がある。任意参加だが、満員になる年もある。何かしら作品(ロボットなど)を作って発表する。
・航空機制御系の研究室(土屋研)が主導して進めている研究プロジェクトHAPS,自作ロケットの打ち上げを目指す学生団体UTAT,は航空宇宙工学科の学生の多くが参加している。
・小型飛行体や探査車を作るようなコンテスト「ARLISS」に、一部学生はチームを組んで日本代表として参加することがある。開催地はネバダ州ブラックロック砂漠。(例:http://www.aerospace.t.u-tokyo.ac.jp/topics/20161005.html)
・工学系研究科・工学部海外武者修行プログラム
(2020-2021募集要項)
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
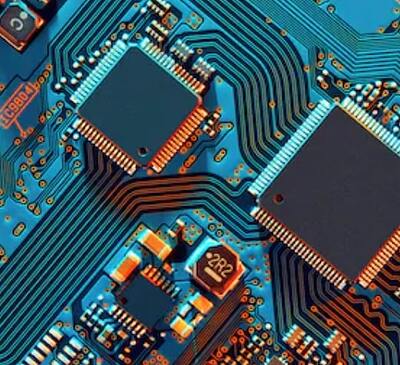
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

システム創成学科C(PSI)
知能社会システム
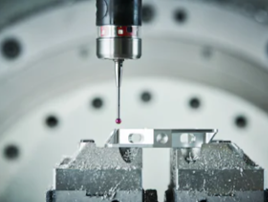
精密工学科
知的機械・バイオメディカル・生産科学

化学システム工学科
環境・エネルギー・医療

電子情報工学科・電気電子工学科(EEIC)
2学科まとめて掲載




