工学部
システム創成学科A(E&E)
2025.6.24
環境・エネルギーシステム
目次
基本情報
| 人数 |
40名程度 |
|---|---|
| ジェンダーバランス |
女性は1-2割程度 |
| 要求/要望科目 |
なし |
| 就活or院進 |
院:就職 = 4:1 |
| 公式サイト |
学科概要
■システム創成学科共通の特徴
・工学部システム創成学科(略して「シス創」)はA~Cの3部門に分かれている。社会系、物理系、情報系の授業がバランスよく存在している。
・限定選択(※)に経済学や経営学を扱う授業があるように工学部の中でも文系寄りで、扱う内容の幅も広い。一般的に第一ターム(S1/A1)に開講科目が固まっていることが多い。
・2Aから4Sにかけて、似通ったテーマを持つ人で少人数グループを作り、調査、プレゼン、ディベート等を行う実践学習形式の授業がある(通称:〇〇プロジェクト)。グループはセメスターごと(orタームごと)に再編される。プロジェクトのテーマは各セメスターの項を参照。→3コース合同のプロジェクト講義は2年A2タームのみであり、次第にコースごとの専門性が高まる。決まったグループでグループワークや実験を行うので、学生間の仲が深まりやすい。
※ 限定選択:工学部一般に用いられる用語。選択必修のこと。
■Aコースの特徴
・エネルギーと環境(※)を軸に、工学的アプローチに加えて政策・経済・国際動向といった社会的側面も踏まえながら、持続可能な未来に向けた課題解決を考える。プログラミングやシミュレーションなどのスキルを活かしながら、エネルギー資源の管理、再生可能エネルギーの導入、環境影響評価、カーボンニュートラルの実現に至るまで、幅広い視点で学ぶことができる。
※E&Eとは、Energy & Environmentの頭文字である。
・E&Eコース公式のInstagram、X、Facebookのアカウントがあり、研究の紹介から学生目線の授業紹介まで、様々な投稿がされている。公式Webサイトにも情報が充実している。
■当コースの諸制度
・卒業に必要な履修単位数は90単位。うち必修科目が20単位(プロジェクト系授業10単位+卒論10単位)、限定選択科目が40単位以上。
・限定選択科目は、基礎的な工学、数学、情報学を扱う基礎科目と、エネルギー工学や資源に関する政策を扱う領域科目に分けられる。
・長期休暇にインターンシップに参加することで1単位が認定される講義がある。
・生徒4人に対しメンターと呼ばれる教員1人がつき、研究・進路相談やキャリア形成について相談できる。また事務所の面倒見も非常に良いと言われている。
■時間割
2年生Aセメスター
※注意:ページ内の汎用にもあるが、当学科全コース科目は黄色のハイライトと共に「創成」、Aコース科目は「E&E」、Bコース科目は「SDM」、Cコース科目は「PSE」と記載されている。
3, 4年生
※注意:必修科目、限定選択科目、その他がまとめて書いてある。そのため、各セメスター紹介でも一部紹介するとはいえ、原則として詳細はシラバスや学科便覧で確認すること。
■進振りの時に気を付けること
・第一段階は工学部の一般的な学科コースと同様、工学部平均を用いて進学振り分けがなされるが、第二段階は要注意。第二段階では、工学部平均と単位数を掛け合わせた値を基準に進学振り分けを行う。そのため、平均が少し低くても単位数を多く取る方が優位になる。
★「システム創成学科 第二段階指定平均点」=「工学部指定平均点」× 取得単位数(上限90単位) (2020年度の場合。次年度以降変わる可能性あり。)
■進学後の内実は?
・ターム制講義が多い。中間試験はあるが、期末試験の負担は他学科と比べて少ない。
・3Aセメスター末から4Sセメスターのはじめにかけて研究室振り分け(研振り)が行われる。配属先は学生間の話し合いによって決められるが、話し合いで決まらない場合は学部(2A〜3A)の成績順で決定されることが多い。
卒業論文リスト
卒業までの流れ
2年生Aセメスター
■【専門分野を決める2A】
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 動機付けプロジェクト | 必修 | 火曜3-5限 |
・A1、A2共に18コマ前後が一般的。
・週3コマ(火曜3-5限)、セメスター開講科目の「動機付けプロジェクト」が必修で合計で2.5単位。A1タームではA~Cのコース別に開講され、Aコースでは教員の研究分野や関連業界の仕事に関するお話を聞く。A2タームではプロジェクトを進めていく。2年次A2タームのみ、テーマの選択肢は全コース共通となっている。その中でAコースの教員が担当するテーマは、JAXAやJAMSTECを見学するものや、CCSに関するグループ研究を行うものなど。動機付けプロジェクトが、コースの研究に触れ、チームワークの力を磨く良い機会となる。
・限定選択では、後の実験などで使う手法の基礎を予め固めておくため、「材料力学」(※1)や「流体力学」、演習科目では「力学演習」や「数理演習」などの受講が推奨される。「地球科学」や「環境・エネルギー概論」では、Aコースの教授陣から資源や海洋、エネルギーに関する様々な研究について学び、興味分野のフロントランナーのお話を聞くことができる。
・他に人気の限定選択の科目として、「プログラミング基礎」(※3)、「システム創成学基礎」、「社会システム工学基礎」など。
・授業以外では、一部外資系企業を視野に入れ就活を始める人がおり、起業をする人もいる。
※1 A1タームで「材料力学1」、A2タームで「材料力学2」、3年次のS2タームで「材料力学3」が開講されるが、内容は連続しており、全て受講することが推奨される。
※2 「プログラミング基礎」や3Sセメスターの「プログラミング応用」ではJavaで文法や数値計算の理論を学ぶ。
3年生Sセメスター
■【相対的に授業が多い3S】
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 基礎プロジェクトA | 必修 | 水曜3-5限 |
・S1、S2共に18コマ前後が一般的。3Sと3Aのどちらかで授業を多く取っておけば良いのだが、3Sで多く取る人が多い。
・週3コマ(水曜3-5限)、セメスター開講科目の「基礎プロジェクト」が必修で合計で2.5単位。ここからはコースごとにテーマは異なってくる。具体例として、大規模な船型試験水槽で浮体の抵抗を計測・分析する実験や、柏キャンパスに行って放射線計測を行う実験など。
・S2ターム開講の「材料力学3」と「数理計画と最適化」
・他に人気の限定選択の科目として、「プログラミング応用」、「経済学基礎」など。
・授業以外では夏季インターンシップが行われる。詳細はページ末尾”特別な制度”に記載。
・3年夏休みに、集中講義「原子炉・ビーム実習」(2単位。必修ではない)がある。東海村キャンパスにて2泊3日で実施され、原子力に関する非常に貴重な実験装置などを見学して演習を行う。参加には3年S2ターム「放射線と環境」の単位取得と放射線業務従事者の登録が必須となる。
3年生Aセメスター
■【研振りを控える3A】
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 応用プロジェクトA | 必修 | 木曜3-5限 |
・個人差が大きいが、3Aは週10〜15コマの人が多い。3Sで多く授業を取っておけば、3Aで空き時間を作る事ができ、他学科の授業の受講や就活などに使える。
・週3コマ(水曜3-5限)、セメスター開講科目の「応用プロジェクト」が必修で合計で2.5単位。扱うテーマの専門性がかなり高まる。「鉱山」「波浪推進船」「原子力」などのテーマから1つ選び、実験や設計を通じて課題に取り組む。学生主体のグループプロジェクトとなる。
・選択必修の科目も専門性が高まる。人気の科目としては「環境エネルギー流体力学1・2」、「数理演習3A」、「流体エネルギー資源の形成と開発」など。
・他学科の授業を覗く事も多くなる。
4年生Sセメスター
■【卒論に勤しむ4S】
| 科目 | 区分 | 開講時限(変更の可能性あり) |
|---|---|---|
| 領域プロジェクトA | 必修 | 火曜/金曜3-5限 |
・必修の「領域プロジェクト(週6コマ)」以外に0〜3コマ程度が一般的。取り残した単位を取るための期間。各自が卒業研究を開始するほか、大学院入試の準備期間にもなる。
・週6コマ(火曜/金曜3-5限)、S1ターム開講科目の「領域プロジェクト」が必修で合計で2.5単位。
4年生Aセメスター
■【引き続き卒論に勤しむ4A】
・院試が終わり、卒論の執筆に多くの時間を充てる。
入る前の想像と実際
・やりたいことが明確に決まっていない人が集まるイメージがあったが、実際入ってみると明確にビジョンを持った人や特定の分野に秀でた人が多くいた。
・ジェネラリストになりたいならそのまま多分野の授業を受講すれば良いが、将来的に特定の分野を専攻したいなら、ある程度分野を決めた状態で入り、目的の達成のために必要な授業は何か考慮する方が確実に得られるものが多い。
(理I→シス創A)
・実験が無いというイメージだったが、実際は少し実験があった(基礎プロジェクト)。(理Ⅱ→シス創A)
・工学部なので女子がほとんどいないと思っていたが、25年度進学の代は約40人中8人が女子だった。
選んだ理由/迷った学科
・元々資源、エネルギーに関する政策立案に興味があったので、文転を考慮していたが、政策を定量的に検証する藤井/小宮山研究室に興味を持ち、そこに入るためにシス創Aを選んだ。(理I→シス創A)
・工学部の中では時間的拘束が緩く、自分のやりたいこと(インターン)に打ち込めそうだったのでシス創Aを選んだ。農学部農業·資源経済学専修と迷った。(理Ⅱ→シス創A)
・宇宙や地学が好きだったので理学部地球惑星環境学科と迷ったが、より社会実装との距離が近そうなこと、カリキュラムが柔軟そうなことからシス創Aを選んだ。(理Ⅰ→シス創A)
コミュニティとしての機能
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ズバリ、学生間のつながりは: 10(強いと感じる)↔0(全くない) | 【7】 |
| LINE | 有 |
| Slack | 有(※1) |
| 学科ドライブ | 有(※2) |
| オフラインでのつながり | 有(※3) |
| 上下のつながり | 有 |
※1 五月祭のための教員との連絡用のチャンネルが存在する。
※2 学年間でGoogle Driveを使い過去問共有などを行う(シケタイ制度、パ長制度はなし)
※3 コース生の7、8割が参加する懇親会などがある。
授業スタイル
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1クラス当たりの人数 | 40~60名前後 |
| 成績評価 | 出席+レポート または 出席+レポート+テスト |
・学科の必修は3-5限で、限定選択も1限は少ない。1限は週0〜1程度が一般的。
・プロジェクト系以外ではあまり実験は行わない。
■成績評価
コロナ禍以前
・出席は紙を回して取る形式と、UTOLの形式が半分ずつ。成績評価は出席+レポートか出席+対面試験かで、前者の割合が高い。
コロナ禍
・大半がUTOLにより出席を取る。一部授業後のレポート提出を出席確認に用いる授業もある。殆どの授業が出席+レポートで評価される。
コロナ禍以後
・出席登録はUTOLによるものが多いが、紙を回して取る形式や授業後の簡単なレポート提出を出席確認にする形式の授業も一定数ある。成績評価は出席+レポートまたは出席+対面試験が多い。工学部の中では試験の数が少ない。
・レポートは、論文を読み自分の考えをまとめていく形式が多い。このコースでは技術と社会の結びつきを重視するため、リアルタイムの政府の発表を元に課題が出されることもある。
研究室・資料
- システム創成学科Aコース公式サイト
- システム創成学科Aコースカリキュラム
- システム創成学科Aコース教員紹介
- システム創成学科Aコース履修モデル
- システム創成学科E&Eコース公式X
- システム創成学科E&Eコース公式Instagram
- システム創成学科E&Eコース公式Facebook
■研究室紹介
(詳細は教員紹介を参照)
◆システム創成学専攻
川畑 友弥 教授: 次世代エネルギー設備の信頼性工学、破壊力学
高橋 淳 教授: 新素材、CFRP、次世代交通・発電の省エネ
辻 健 教授: 物理探査、宇宙探査、CCS
所 千晴 教授: 資源循環、環境修復
福井 勝則 教授: 岩盤力学、地下空間開発論、開発機械学
小林 肇准 教授:バイオエネルギー技術
髙谷 雄太郎 准教授: 資源循環、環境浄化
ドドビバ ジョルジ 准教授: 資源再生工学
羽柴 公博 准教授: 資源開発工学、開発機械学
宝谷 英貴 講師: 海洋波、海洋工学、船舶耐航性能
◆先端エネルギー工学専攻
齋藤 晴彦 准教授: プラズマ核融合、反物質プラズマ、超伝導応用
◆原子力国際専攻
小宮山 涼一 教授: エネルギー安全保障、エネルギー経済モデル
斉藤 拓巳 教授: 放射性廃棄物処分、有害物質の環境動態、核燃料サイクル
藤井 康正 教授: エネルギー・経済・環境システム
島添 健次 准教授: 量子計測、量子イメージング
◆原子力専攻
阿部 弘亨 教授: 材料科学、原子炉材料学、核融合炉材科学
三輪 修一郎 准教授: 原子力システム安全、熱流体工学
◆環境システム学専攻
多部田 茂 教授: 持続可能な海洋利用、海洋利用の環境影響評価
徳永 朋祥 教授: 地球環境変遷と地下環境問題
◆海洋技術環境学専攻
早稲田 卓爾 教授: 海洋流体現象、海洋・波浪モデルと実験・観測
今野 義浩 准教授: 貯留層工学、海底資源開発
平林 紳一郎 准教授: 数値流体力学、海洋乱流、ハイドレート
和田 良太准 教授: 海洋産業システム、海洋工学
小平 翼 講師: 海洋loT、極地海洋、波浪
◆エネルギー・資源フロンティアセンター
加藤 泰浩 教授: 海底鉱物資源、レアメタル・レアアース
安川 和孝 准教授: 海底鉱物資源、気候変動、地球科学分析
・エネルギー・資源フロンティアセンターの加藤教授は政府とのコネクションもあり、最新の政策を議論する授業で人気が高い。それ故に研究室の門も狭いので、授業が受けられる機会があれば是非受けておくべきだ。
(理I→シス創A)
特別な制度・その他
・「夏季インターンシップ」と「海外インターンシップ」の2種類のインターンシップ制度がある。共に1単位ずつ。夏季インターンシップは学部3, 4年生対象で、4月の進学ガイダンス資料で説明がなされる。企業における実習、海外研修など多くの選択肢から選ぶことができる。実施期間は1~4週間程(※)。同じく3,4年生対象の海外インターンシップは学生が主体となり渡航先を決定し、大学、企業等で実践的な研修を行う。実施期間は1~2週間程(※)。
※実施期間は受け入れ先により異なる。
最後まで記事を読んでくださりありがとうございました!
最後に1点、この記事を作成したUT-BASEからお伝えしたいことがあります。
公式LINEにてイベント・プログラム情報や学内情報を発信しています。ぜひ登録してみてください!
2023年度入学者用LINE
2024年度入学者用LINE
2025年度入学者用LINE
所属学部
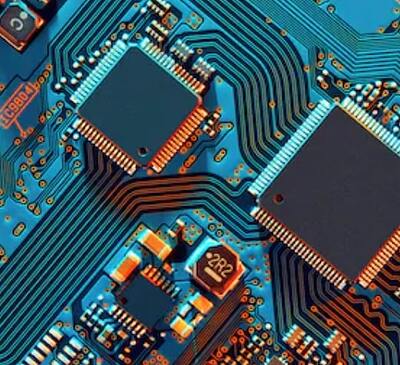
工学部
豊かで体系的な知識を身につけ、諸分野で工学的手法を活用して人類社会の持続と発展に貢献できる指導的人材を養成する学部
関連記事

建築学科
建築学
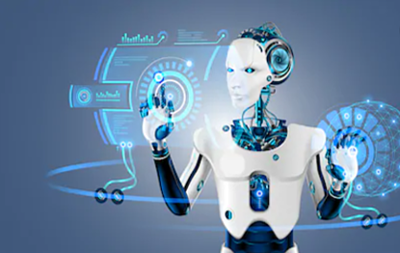
機械情報工学科(機械B)
ロボティクス・知能・ヒューマンインターフェース

フィールド科学専修
【環境資源科学課程】通称「フィ科(ふぃか)」

化学生命工学科
化学生命工学




